【日本書記から】鞆の浦と神話/其の十二
第五段 四神出生章
一書(あるふみ)に曰(い)はく、伊奘諾尊(いざなぎのみこと)、剣(つるぎ)を抜きて軻遇突智(かぐつち)を斬りて、三段(みきだ)に為(な)す。其の一段(ひときだ)は是雷神(いかづちのかみ)と為(な)る。一段は是大山神(おおやまつみのかみ)と為る。一段は是高(たかおかみ)と為る。又曰はく、軻遇突智を斬る時に、其の血を激越(そそ)きて、天八十河中(あまのやそのかはら)に所在(あ)る五百箇磐石(いほついはむら)を染(そ)む。因りて化成(な)る神を、号(なづ)けて磐裂神(いはさくのかみ)と曰(まう)す。次に根裂神(ねさくのかみ)、児(こ)磐筒男神(いはつつのをのかみ)。次に磐筒女神(いはつつのめのかみ)、児経津主神(ふつぬしのかみ)。倉稲魂、此(これ)をば、宇介能美磨(うかのみたま)と云ふ。少童、此をば和多都美(わたつみ)と云ふ。頭辺、此をば摩苦羅陛(まくらへ)と云ふ。脚辺、此をば阿度陛(あとへ)と云ふ。は火なり。音は而善反(のかへし)。、此をば於箇美(おかみ)と云ふ。音は力丁反。吾夫君、此をば阿我儺勢(あがなせ)と云ふ。泉之竈、此をば誉母都俳遇比(よもつへぐい)と云ふ。秉炬、此をば多妃(たひ)と云ふ。不須也凶目汚穢、此をば伊儺之居梅枳枳多儺枳(いなしこめききたなき)と云ふ。醜女、此をば志許売(しこめ)と云ふ。背揮、此をば、志理幣堤爾布倶(しりへでにふく)と云ふ。泉津平坂、此をば、余母都比羅佐可(よもつひらさか)と云ふ。尿、此をば愈磨理(ゆまり)と云ふ。音は乃弔反。絶妻之誓、此をば許等度(ことど)と云ふ。岐神、此をば布那斗能加微(ふなとのかみ)と云ふ。檍、此をば阿波岐(あはき)と云ふ。 <第七>
一書に曰はく、伊奘諾尊、軻遇突智命を斬りて、五段(いつきだ)に為す。此各五(これおのおのいつつ)の山(やまつみ)と化成る。一(ひとつ)は首(かしら)、大山(おおやまつみ)と化成る。二(ふたつ)は身中(むくろ)、中山(なかやまつみ)と化成る。三(みつ)は手、麓山(はやまつみ)と化成る。四(よつ)は腰、正勝山(まさかやまつみ)と化成る。五(いつつ)は足、山(しぎやまつみ)と化成る。是の時に、斬る血激灑(そそ)きて、石礫(いしむら)・樹草(きくさ)に染(そま)る。此(これ)草木・沙石(いさご)の自(おの)づからに火を含(ふふ)む縁(ことのもと)なり。麓は、山の足(ふもと)を麓と曰(い)ふ。此をば簸耶磨(はやま)と云ふ。正勝、此をば麻娑柯(まさか)と云ふ。一に麻佐柯豆(まさかつ)と云ふ。、此をば之伎(しぎ)と云ふ。音(こゑ)は烏含反。 <第八>
一書に曰はく、伊奘諾尊、其の妹(いろも)を見まさむと欲(おもほ)して、乃ち殯斂(もがり)の処に到(いま)す。是の時に、伊奘冉尊(いざなぎのみこと)、猶(なほ)生平(いけりしとき)の如くにして、出(い)で迎へて共に語る。已にして伊奘諾尊に謂(かた)りて曰(のたま)はく、「吾が夫君尊(なせのみこと)、請ふ、吾をな視(み)ましそ」とのたまふ。言訖(のたまふことをは)りて忽然(たちまち)に見えず。時に闇し。伊奘諾尊、乃ち一片之火(ひとつび)を挙(とも)して視(みそなは)す。時に伊奘冉尊、脹満(は)れ太高(たた)へり。上に八色(やくさ)の雷公(いかづち)有り。伊奘諾尊、驚きて走げ還りたまふ。是の時に、雷等皆起(いかづちどもみなた)ちて追ひ来(きた)る。時に、道の辺(ほとり)に大きなる桃の樹有り。故(かれ)、伊奘諾尊、其の樹の下(もと)に隠れて、因りて其の実を採りて、雷に擲(な)げしかば、雷等(ども)、皆退走(しりぞ)きぬ。此桃を用(も)て鬼を避(ふせ)く縁なり。時に伊奘諾尊、乃ち其の杖(みつゑ)を投(なげう)てて曰(のたま)はく、「此より以還(このかた)、雷敢来(えこ)じ」とのたまふ。是を岐神(ふなとのかみ)と謂(まう)す。此、本(もと)の号(な)は来名戸(くなと)の祖神(さへのかみ)と曰(まう)す。八(やくさ)の雷と所謂(い)ふは、首(かしら)に在るは大雷(おほいかづち)と曰(い)ふ。胸に在るは火雷(ほのいかづち)と曰ふ。腹に在るは土雷(つちのいかづち)と曰ふ。背(そびら)に在るは稚雷(わかいかづち)と曰ふ。尻(かくれ)に在るは黒雷(くろいかづち)と曰ふ。手に在るは山雷(やまつち)と曰ふ。足の上に在るは野雷(のつち)と曰ふ。陰(ほと)の上に在るは裂雷(さくいかづち)と曰ふ。 <第九>
<訳>
ある書ではこう伝えられている、伊奘諾尊(いざなぎのみこと)は剣(つるぎ)を抜いて軻遇突智(かぐつち)を斬って、三段にばらした。その内の一段は雷神(いかづちのかみ)と成った。また一段は大山神(おおやまつみのかみ)と成った。そしてまた一段は高(たかおかみ)と成った。また、軻遇突智を斬った時に、その血が流れて、天八十河中(あまのやそのかはら)にあった五百箇磐石(いほついはむら)を染めた。それによって成った神を、名付けて磐裂神(いはさくのかみ)と言う。次に根裂神(ねさくのかみ)、次に磐筒男神(いはつつのをのかみ)、次に磐筒女神(いはつつのめのかみ)、次に経津主神(ふつぬしのかみ)。
倉稲魂、これをうかのみたまと読む。少童、これをわたつみと読む。頭辺、これをまくらへと読む。脚辺、これをあとへと読む。は火のことである。音は而善の反切で読む。、これをおかみと読む。音は力丁の反切で読む。吾夫君、これをあがなせと言う。泉之竈、これをよもつへぐいと読む。秉炬、これをたひと読む。不須也凶目汚穢、これをいなしこめききたなきと読む。醜女、これをしこめと読む。背揮、これをしりへでにふくと読む。泉津平坂、これをよもつひらさかと読む。尿、これをゆまりと読む。音は乃弔の反切で読む。絶妻之誓、これをことどと読む。岐神、これをふなとのかみと読む。檍、これをあはきと読む。<第七>
ある書ではこう伝えられている、伊奘諾尊は軻遇突智命を斬って、五段にばらした。これがそれぞれ五つの山(やまつみ)と成った。一つ目は首で大山(おおやまつみ)と成った。二つ目は身体で中山(なかやまつみ)と成った。三つ目は手で麓山(はやまつみ)と成った。四つ目は腰で正勝山(まさかやまつみ)と成った。五つ目は足で山(しぎやまつみ)と成った
この時、斬った血が流れて、石や礫や樹や草を染めた。これが草木や燐が火の元となった始まりである
麓は、山のふもとのことを言う。これをはやまと読む。正勝、これをまさかと読む。ある書ではまさかつとも読まれる。、これをしぎと読む。音は烏含の反切で読む。<第八>
ある書ではこう伝えられている、伊奘諾尊は妻に会いたいを思って、仮安置していた柩の所に行った。すると伊奘冉尊まだなお生きている時のようで、出迎えて共に語った。そして伊奘諾尊に語って、「我愛しい夫よ、どうかお願いです。もう私を決して見ないで下さい」と言った。そう言い終わると忽然と姿を消した。暗くなって、伊奘諾尊は一つの火を灯して見ようとした。伊奘冉尊は膨れ上がっていた。その上に八色(やくさ)の雷がいた。伊奘諾尊はそれに驚いて走り逃げ帰ろうとした。その時に、雷達が皆起き上がり追ってきた。その時、道の端に大きな桃の樹があった。伊奘諾尊はその樹の下に隠れて、その実を採って雷に投げると、雷達は皆退いていった。これが桃を用いて鬼を防ぐことの始まりである。そして伊奘諾尊は杖投げ打って、「これよりこちら側に、雷は来るな」と言った。これを岐神(ふなとのかみ)と言う。元の名は来名戸(くなと)の祖神(さへのかみ)と言う。八色の雷については、首にいたのは大雷(おほいかづち)、胸にいたのは火雷(ほのいかづち)、腹にいたのは土雷(つちのいかづち)、背にいたのは稚雷(わかいかづち)、尻にいたのは黒雷(くろいかづち)、手にいたのは山雷(やまつち)、足の上にいたのは野雷(のつち)、陰(ほと)の上にいたのは裂雷(さくいかづち)と言う。<第九>
◎雷神(いかづちのかみ)、一書第六の甕速日神(みかのはやひのかみ)。
◎大山神(おおやまつみのかみ)、一書第六の闇山(くらやまつみ)。
◎高(たかおかみ)、一書第六の闇(くらおかみ)。
◎大山(おおやまつみ)、首が頭部のこと。
◎中山(なかやまつみ)、身中は首のない身体のこと、そのことから中山。
◎麓山(はやまつみ)、手が端にあること。
◎正勝山(まさかやまつみ)、腰が斜に細くなっている部分でそこから真坂をあてた。
◎山(しぎやまつみ)、足が最も下の部分で草木が茂っていること、しぎ山という説がある。
また鳥のシギの足が印象深かったことから。
◎沙石(いさご)、燐のこと。
◎殯斂(もがり)、人が死んで葬るまでの間屍を柩におさめて仮に安置すること。
◎生平(いけりしとき)、平常、平生のこと。
◎脹満(は)れ太高(たた)へり、ふくれあがっていた。「たたふ」は潮が満ちてふくれること。
◎杖(みつゑ)、桃の樹の杖でいっそう呪力がある。
◎来名戸(くなと)、「くな」は「来るな」「と」は「道」のことで通行を禁止すること。
◎祖神(さへのかみ)、道祖神のこと。
◎尻(かくれ)、「かくれ」と読むのは書紀特異なもの。
【日本書記から】鞆の浦と神話シリーズ
◎鞆の浦と神話/其の一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052336.html
◎鞆の浦と神話/其の二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052867.html
◎鞆の浦と神話/其の三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053155.html
◎鞆の浦と神話/其の四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053298.html
◎鞆の浦と神話/其の五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053433.html
◎鞆の浦と神話/其の六
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053608.html
◎鞆の浦と神話/其の七
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053772.html
◎鞆の浦と神話/其の八
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053974.html
◎鞆の浦と神話/其の九
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054126.html
◎鞆の浦と神話/其の十
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054282.html
◎鞆の浦と神話/其の十一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054445.html
◎鞆の浦と神話/其の十二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054635.html
◎鞆の浦と神話/其の十三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054887.html
◎鞆の浦と神話/其の十四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055128.html
◎鞆の浦と神話/其の十五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055516.html
日本書紀(上)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
日本書紀(下)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
古事記と日本書紀 (図解雑学)/武光 誠
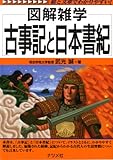
¥1,365
Amazon.co.jp
一書(あるふみ)に曰(い)はく、伊奘諾尊(いざなぎのみこと)、剣(つるぎ)を抜きて軻遇突智(かぐつち)を斬りて、三段(みきだ)に為(な)す。其の一段(ひときだ)は是雷神(いかづちのかみ)と為(な)る。一段は是大山神(おおやまつみのかみ)と為る。一段は是高(たかおかみ)と為る。又曰はく、軻遇突智を斬る時に、其の血を激越(そそ)きて、天八十河中(あまのやそのかはら)に所在(あ)る五百箇磐石(いほついはむら)を染(そ)む。因りて化成(な)る神を、号(なづ)けて磐裂神(いはさくのかみ)と曰(まう)す。次に根裂神(ねさくのかみ)、児(こ)磐筒男神(いはつつのをのかみ)。次に磐筒女神(いはつつのめのかみ)、児経津主神(ふつぬしのかみ)。倉稲魂、此(これ)をば、宇介能美磨(うかのみたま)と云ふ。少童、此をば和多都美(わたつみ)と云ふ。頭辺、此をば摩苦羅陛(まくらへ)と云ふ。脚辺、此をば阿度陛(あとへ)と云ふ。は火なり。音は而善反(のかへし)。、此をば於箇美(おかみ)と云ふ。音は力丁反。吾夫君、此をば阿我儺勢(あがなせ)と云ふ。泉之竈、此をば誉母都俳遇比(よもつへぐい)と云ふ。秉炬、此をば多妃(たひ)と云ふ。不須也凶目汚穢、此をば伊儺之居梅枳枳多儺枳(いなしこめききたなき)と云ふ。醜女、此をば志許売(しこめ)と云ふ。背揮、此をば、志理幣堤爾布倶(しりへでにふく)と云ふ。泉津平坂、此をば、余母都比羅佐可(よもつひらさか)と云ふ。尿、此をば愈磨理(ゆまり)と云ふ。音は乃弔反。絶妻之誓、此をば許等度(ことど)と云ふ。岐神、此をば布那斗能加微(ふなとのかみ)と云ふ。檍、此をば阿波岐(あはき)と云ふ。 <第七>
一書に曰はく、伊奘諾尊、軻遇突智命を斬りて、五段(いつきだ)に為す。此各五(これおのおのいつつ)の山(やまつみ)と化成る。一(ひとつ)は首(かしら)、大山(おおやまつみ)と化成る。二(ふたつ)は身中(むくろ)、中山(なかやまつみ)と化成る。三(みつ)は手、麓山(はやまつみ)と化成る。四(よつ)は腰、正勝山(まさかやまつみ)と化成る。五(いつつ)は足、山(しぎやまつみ)と化成る。是の時に、斬る血激灑(そそ)きて、石礫(いしむら)・樹草(きくさ)に染(そま)る。此(これ)草木・沙石(いさご)の自(おの)づからに火を含(ふふ)む縁(ことのもと)なり。麓は、山の足(ふもと)を麓と曰(い)ふ。此をば簸耶磨(はやま)と云ふ。正勝、此をば麻娑柯(まさか)と云ふ。一に麻佐柯豆(まさかつ)と云ふ。、此をば之伎(しぎ)と云ふ。音(こゑ)は烏含反。 <第八>
一書に曰はく、伊奘諾尊、其の妹(いろも)を見まさむと欲(おもほ)して、乃ち殯斂(もがり)の処に到(いま)す。是の時に、伊奘冉尊(いざなぎのみこと)、猶(なほ)生平(いけりしとき)の如くにして、出(い)で迎へて共に語る。已にして伊奘諾尊に謂(かた)りて曰(のたま)はく、「吾が夫君尊(なせのみこと)、請ふ、吾をな視(み)ましそ」とのたまふ。言訖(のたまふことをは)りて忽然(たちまち)に見えず。時に闇し。伊奘諾尊、乃ち一片之火(ひとつび)を挙(とも)して視(みそなは)す。時に伊奘冉尊、脹満(は)れ太高(たた)へり。上に八色(やくさ)の雷公(いかづち)有り。伊奘諾尊、驚きて走げ還りたまふ。是の時に、雷等皆起(いかづちどもみなた)ちて追ひ来(きた)る。時に、道の辺(ほとり)に大きなる桃の樹有り。故(かれ)、伊奘諾尊、其の樹の下(もと)に隠れて、因りて其の実を採りて、雷に擲(な)げしかば、雷等(ども)、皆退走(しりぞ)きぬ。此桃を用(も)て鬼を避(ふせ)く縁なり。時に伊奘諾尊、乃ち其の杖(みつゑ)を投(なげう)てて曰(のたま)はく、「此より以還(このかた)、雷敢来(えこ)じ」とのたまふ。是を岐神(ふなとのかみ)と謂(まう)す。此、本(もと)の号(な)は来名戸(くなと)の祖神(さへのかみ)と曰(まう)す。八(やくさ)の雷と所謂(い)ふは、首(かしら)に在るは大雷(おほいかづち)と曰(い)ふ。胸に在るは火雷(ほのいかづち)と曰ふ。腹に在るは土雷(つちのいかづち)と曰ふ。背(そびら)に在るは稚雷(わかいかづち)と曰ふ。尻(かくれ)に在るは黒雷(くろいかづち)と曰ふ。手に在るは山雷(やまつち)と曰ふ。足の上に在るは野雷(のつち)と曰ふ。陰(ほと)の上に在るは裂雷(さくいかづち)と曰ふ。 <第九>
<訳>
ある書ではこう伝えられている、伊奘諾尊(いざなぎのみこと)は剣(つるぎ)を抜いて軻遇突智(かぐつち)を斬って、三段にばらした。その内の一段は雷神(いかづちのかみ)と成った。また一段は大山神(おおやまつみのかみ)と成った。そしてまた一段は高(たかおかみ)と成った。また、軻遇突智を斬った時に、その血が流れて、天八十河中(あまのやそのかはら)にあった五百箇磐石(いほついはむら)を染めた。それによって成った神を、名付けて磐裂神(いはさくのかみ)と言う。次に根裂神(ねさくのかみ)、次に磐筒男神(いはつつのをのかみ)、次に磐筒女神(いはつつのめのかみ)、次に経津主神(ふつぬしのかみ)。
倉稲魂、これをうかのみたまと読む。少童、これをわたつみと読む。頭辺、これをまくらへと読む。脚辺、これをあとへと読む。は火のことである。音は而善の反切で読む。、これをおかみと読む。音は力丁の反切で読む。吾夫君、これをあがなせと言う。泉之竈、これをよもつへぐいと読む。秉炬、これをたひと読む。不須也凶目汚穢、これをいなしこめききたなきと読む。醜女、これをしこめと読む。背揮、これをしりへでにふくと読む。泉津平坂、これをよもつひらさかと読む。尿、これをゆまりと読む。音は乃弔の反切で読む。絶妻之誓、これをことどと読む。岐神、これをふなとのかみと読む。檍、これをあはきと読む。<第七>
ある書ではこう伝えられている、伊奘諾尊は軻遇突智命を斬って、五段にばらした。これがそれぞれ五つの山(やまつみ)と成った。一つ目は首で大山(おおやまつみ)と成った。二つ目は身体で中山(なかやまつみ)と成った。三つ目は手で麓山(はやまつみ)と成った。四つ目は腰で正勝山(まさかやまつみ)と成った。五つ目は足で山(しぎやまつみ)と成った
この時、斬った血が流れて、石や礫や樹や草を染めた。これが草木や燐が火の元となった始まりである
麓は、山のふもとのことを言う。これをはやまと読む。正勝、これをまさかと読む。ある書ではまさかつとも読まれる。、これをしぎと読む。音は烏含の反切で読む。<第八>
ある書ではこう伝えられている、伊奘諾尊は妻に会いたいを思って、仮安置していた柩の所に行った。すると伊奘冉尊まだなお生きている時のようで、出迎えて共に語った。そして伊奘諾尊に語って、「我愛しい夫よ、どうかお願いです。もう私を決して見ないで下さい」と言った。そう言い終わると忽然と姿を消した。暗くなって、伊奘諾尊は一つの火を灯して見ようとした。伊奘冉尊は膨れ上がっていた。その上に八色(やくさ)の雷がいた。伊奘諾尊はそれに驚いて走り逃げ帰ろうとした。その時に、雷達が皆起き上がり追ってきた。その時、道の端に大きな桃の樹があった。伊奘諾尊はその樹の下に隠れて、その実を採って雷に投げると、雷達は皆退いていった。これが桃を用いて鬼を防ぐことの始まりである。そして伊奘諾尊は杖投げ打って、「これよりこちら側に、雷は来るな」と言った。これを岐神(ふなとのかみ)と言う。元の名は来名戸(くなと)の祖神(さへのかみ)と言う。八色の雷については、首にいたのは大雷(おほいかづち)、胸にいたのは火雷(ほのいかづち)、腹にいたのは土雷(つちのいかづち)、背にいたのは稚雷(わかいかづち)、尻にいたのは黒雷(くろいかづち)、手にいたのは山雷(やまつち)、足の上にいたのは野雷(のつち)、陰(ほと)の上にいたのは裂雷(さくいかづち)と言う。<第九>
◎雷神(いかづちのかみ)、一書第六の甕速日神(みかのはやひのかみ)。
◎大山神(おおやまつみのかみ)、一書第六の闇山(くらやまつみ)。
◎高(たかおかみ)、一書第六の闇(くらおかみ)。
◎大山(おおやまつみ)、首が頭部のこと。
◎中山(なかやまつみ)、身中は首のない身体のこと、そのことから中山。
◎麓山(はやまつみ)、手が端にあること。
◎正勝山(まさかやまつみ)、腰が斜に細くなっている部分でそこから真坂をあてた。
◎山(しぎやまつみ)、足が最も下の部分で草木が茂っていること、しぎ山という説がある。
また鳥のシギの足が印象深かったことから。
◎沙石(いさご)、燐のこと。
◎殯斂(もがり)、人が死んで葬るまでの間屍を柩におさめて仮に安置すること。
◎生平(いけりしとき)、平常、平生のこと。
◎脹満(は)れ太高(たた)へり、ふくれあがっていた。「たたふ」は潮が満ちてふくれること。
◎杖(みつゑ)、桃の樹の杖でいっそう呪力がある。
◎来名戸(くなと)、「くな」は「来るな」「と」は「道」のことで通行を禁止すること。
◎祖神(さへのかみ)、道祖神のこと。
◎尻(かくれ)、「かくれ」と読むのは書紀特異なもの。
【日本書記から】鞆の浦と神話シリーズ
◎鞆の浦と神話/其の一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052336.html
◎鞆の浦と神話/其の二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052867.html
◎鞆の浦と神話/其の三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053155.html
◎鞆の浦と神話/其の四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053298.html
◎鞆の浦と神話/其の五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053433.html
◎鞆の浦と神話/其の六
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053608.html
◎鞆の浦と神話/其の七
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053772.html
◎鞆の浦と神話/其の八
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053974.html
◎鞆の浦と神話/其の九
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054126.html
◎鞆の浦と神話/其の十
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054282.html
◎鞆の浦と神話/其の十一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054445.html
◎鞆の浦と神話/其の十二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054635.html
◎鞆の浦と神話/其の十三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054887.html
◎鞆の浦と神話/其の十四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055128.html
◎鞆の浦と神話/其の十五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055516.html
日本書紀(上)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
日本書紀(下)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
古事記と日本書紀 (図解雑学)/武光 誠
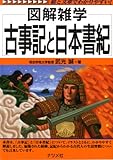
¥1,365
Amazon.co.jp