【日本書記から】鞆の浦と神話/其の十一
第五段 四神出生章 一書その三<第六その二>
書き下し文
時に、伊奘冉尊の曰はく、「愛しき吾(あ)が夫君(なせのみこと)し、如此言(かくのたま)はば、吾(われ)は当に汝(いまし)が治(しら)す国民(ひとくさ)、日(ひとひ)に千頭縊(ちかべくび)り殺さむ」とのたまふ。伊奘諾尊、乃ち報(こた)へて曰はく、「愛しき吾が妹(なにものみこと)し、如此言はば、吾は当に日に千五百頭(ちかべあまりいほかうべ)産ましめむ」とのたまふ。因りて曰はく、「此よりな過ぎそ」とのたまひて、即ち其の杖(みつゑ)を投げたまふ。是を岐神(ふなとのかみ)と謂(まう)す。又其の帯(みおび)を投げたまふ。是を長道磐神(ながちはのかみ)と謂す。又其の衣(みそ)を投げたまふ。是を煩神(わづらひのかみ)と謂す。又其の褌(はかま)を投げたまふ。是を開囓神(あきくひのかみ)と謂す。又其の履(くつ)を投げたまふ。是を道敷神(ちしきのかみ)と謂す。其の泉津平坂にして、或いは、所謂(い)ふ、泉津平坂といふは、復別(またこと)に処所(ところ)有らじ、但(ただ)死(まか)るに臨みて気絶(いきた)ゆる際(きは)、是を謂ふか。所塞(ふさ)がる磐石といふは、是泉門(よみど)に塞(ふたが)ります大神(おほみかみ)を謂ふ。亦の名は道返大神(ちがへしのおほみかみ)といふ。伊奘諾尊、既に還りて、乃ち追ひて悔いて曰はく、「吾前(さき)に不須也凶目き汚穢き処に到る。故、吾が身の濁穢(けがらはしきもの)を滌(あら)ひ去(う)てむ」とのたまひて、則ち往きて筑紫の日向(ひむか)の小戸(をど)の橘の檍原(あはきはら)に至りまして、祓(みそ)ぎ除(はら)へたまふ。遂に身の所汚(きたなきもの)を盪滌(すす)ぎたまはむとして、乃ち興言(ことあげ)して曰はく、「上瀬(かみつせ)は是太(はなはだ)だ疾(はや)し。下瀬(しもつせ)は是太だ弱(ぬる)し」とのたまひて、便ち中瀬(なかつせ)に濯(すす)ぎたまふ。因りて生める神を、号(なづ)けて八十枉津日神(やそまがつひのかみ)と曰す。次に其の枉(まが)れるを矯(なほ)さむとして生める神を、号けて神直日神(かむなほひのかみ)と曰す。次に大直日神(おほなほびのかみ)。又海(わた)の底に沈(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて底津少童命(そこつわたつみのみこと)と曰す。次に底筒男命(そこつつのをのみこと)。又潮の中に潜(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて中津少童命(なかつわたつみのみこと)と曰す。次に中筒男命(なかつつのをのみこと)。又潮の上に浮(う)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて表津少童命(うはつわたつみのみこと)と曰す。次に表筒男命(うはつつのをのみこと)。凡て九(ここのはしら)の神有(いま)す。其の底筒男命・中筒男命・表筒男命は是即ち住吉大神(すみのえのおほみかみ)なり。底津少童命・中津少童命・表津少童命は、是阿雲連等(あづみのむらじら)が所祭(いつきまつ)る神なり。
然して後に、左の眼(みめ)を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて天照大神(あまてらすおほみかみ)と曰す。復右の眼(みめ)を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて月読尊(つくよみのみこと)と曰す。復鼻(みはな)を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて素戔鳴尊(すさのをのみこと)と曰す。凡て三(みはしら)の神ます。已にして伊奘諾尊、三の子(みこ)に勅任(ことよさ)して曰はく、「天照大神は、以て高天原(たかまのはら)を治(しら)すべし。月読尊は、以て滄海原(あをうなはら)の潮の八百重(やほへ)を治すべし。素戔鳴尊は、以て天下(あめのした)を治すべし」とのたまふ。是の時に、素戔鳴尊、年已(としすで)に長(お)いたり。復八握鬚髯(やつかひげ)生(お)ひたり。然れども天下を治さずして、常に啼き泣ち恚恨(ふつく)む。故、伊奘諾尊、問ひて曰はく、「汝は何の故(ゆゑ)にか恒に如此(かく)啼く」とのたまふ。対(こた)へて曰(まう)したまはく、「吾(やつかれ)は母(いろはのみこと)に根国(ねのくに)に従(したが)はむと欲(おも)ひて、只に泣かくのみ」とまうしたまふ。伊奘諾尊悪(にく)みて曰(のたま)はく、「情(こころ)の任(まにま)に行ね」とのたまひて、乃ち逐(やらひや)りき。 <第六>
<訳>
その時に伊奘冉尊は、「愛しい我が夫よ、このようなことを言うのなら、私はあなたが治める国の国民を、一日に千人殺しましょう」と言った。伊奘諾尊はそれに答えて、「愛しい我が妻よ、そのようなことを言うのなら、私は一日に千五百人生もう」と言った。そして、「これよりこちらへ来るな」との言って、杖を投げた。これを岐神(ふなとのかみ)と言う。また帯を投げた。これを長道磐神(ながちはのかみ)と言う。また衣を投げた。これを煩神(わづらひのかみ)と言う。また褌を投げた。これを開囓神(あきくひのかみ)と言う。また履(くつ)を投げた。これを道敷神(ちしきのかみ)と言う。その泉津平坂に(泉津平坂と言うのは別に場所を言うのではなく、死に臨んで生き絶える時の事をいうのか)、塞がっている岩を、泉門(よみど)に塞(ふたが)ります大神(おほみかみ)と言う。別名道返大神(ちがへしのおほみかみ)と言う。
伊奘諾尊は帰って来て、追ったことを悔いて、「私は先ほど醜悪で汚い国に行ってしまった。我が身についた穢れを洗い捨てよう」と言って、すぐに筑紫の日向(ひむか)の小戸(をど)の橘の檍原(あはきはら、地名?)に至って、禊祓いをした。そして身の汚れを濯ごうとして、言葉を発して、「上の瀬は流れがかなり速い。下の瀬は流れがかなり遅い」と言って、中の瀬で濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて八十枉津日神(やそまがつひのかみ)と言う。次にその穢れを直そうとして生んだ神を、名付けて神直日神(かむなほひのかみ)と言う。次に大直日神(おほなほびのかみ)。そして海の底に沈んで濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて底津少童命(そこつわたつみのみこと)と言う。次に底筒男命(そこつつのをのみこと)。また潮の中程に潜って濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて中津少童命(なかつわたつみのみこと)と言う。次に中筒男命(なかつつのをのみこと)。そしてまた潮の上に浮きながら濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて表津少童命(うはつわたつみのみこと)と言う。次に表筒男命(うはつつのをのみこと)。全て合わせて九柱の神である。その底筒男命・中筒男命・表筒男命は住吉大神(すみのえのおほみかみ)である。底津少童命・中津少童命・表津少童命は、阿雲連等(あづみのむらじら)が祭っている神である。
さてその後に、左の眼を洗った。これに因って生んだ神を、名付けて天照大神(あまてらすおほみかみ)と言う。また右の眼を洗った。これに因って生んだ神を、名付けて月読尊(つくよみのみこと)と言う。また鼻を洗った。これに因って生んだ神を、名付けて素戔鳴尊(すさのをのみこと)と言う。全て合わせて三柱の神である。伊奘諾尊、三柱の御子に命令して、「天照大神は、高天原(たかまのはら)を治めよ。月読尊は、青海原の広大な潮の全てを治めよ。素戔鳴尊は、天の下の全土を治めよ」と言った。この時、素戔鳴尊はすでに年老いていた。長く鬚が伸びた老人だった。しかし天の下を全く治めようとせず、常に激しく泣いて怒りを露にしていた。それのことを伊奘諾尊は問いて、「お前はどうして何時もそのように泣いているのだ」と言った。それに答えて、「私は母のいる根国(ねのくに)に行きたいと思って、このように泣いているのです」と言った。伊奘諾尊はそれを憎んで、「好きな世にどことなりと行け」と言って、追放した。 <第六>
◎岐神(ふなとのかみ):道の三叉路に置かれた道祖神。杖は根のついた木を用いていたため、その生成力が霊力を示していて、部落の入り口や岐路に立て邪悪の侵入から防御するために立てられた。
◎長道磐神(ながちはのかみ):長い道の神。帯の形状から。
◎煩神(わづらひのかみ):思うままに行かないことを表す神。衣が纏わりつくことから。
◎褌(はかま):腰と脚を覆う裳の古形。
◎開囓神(あきくひのかみ):「古事記」では冠から生まれた神とされる。冠が開いていることから。
◎道敷神(ちしきのかみ):「ち」は道、「しき」は一面に力を及ぼすこと、履が道を自由に歩行することから。「古事記」では伊奘冉尊の別名。
◎泉門(よみど)に塞(ふたが)ります大神(おほみかみ):冥界との入り口邪霊の侵入を防ぐ神。
◎道返大神(ちがへしのおほみかみ):死者を冥界に返す神。
◎日向(ひむか):日の当たること、もしくは日向国の大隈の地名。
◎小戸(をど):小さな水門。
◎檍原(あはきはら):「檍」はもちのきに当たると言われるが未詳。
◎祓(みそ)ぎ:水に入って身を清浄にすること。
◎興言(ことあげ):言葉を発すること。
◎八十枉津日神(やそまがつひのかみ):「やそ」は多数、「まが」は穢、禍の多いことを表している神。
◎神直日神(かむなほひのかみ):大直日神(おほなほびのかみ)、禍を取り除くため祓い浄めることから。「神」と「大」は美称。
◎底津少童命(そこつわたつみのみこと):中津少童命(なかつわたつみのみこと)、表津少童命(うはつわたつみのみこと)、海を掌る神。生まれた場所によって「底」「中」「表」となっている。
◎底筒男命(そこつつのをのみこと)、中筒男命(なかつつのをのみこと)、表筒男命(うはつつのをのみこと):「筒」は星のこと。古来「粒」を「つづ」「つつ」と呼び、星もそう呼ばれた。この三神はオリオンのカラスキ星で航海の神。
◎住吉大神(すみのえのおほみかみ):摂津住吉大社の祭神。航海を掌る神。
◎阿雲連等(あづみのむらじら):全国の海部を管理する伴造。
◎八握鬚髯(やつかひげ):「八」は数の多いこと。長い鬚を延ばした老人。
【日本書記から】鞆の浦と神話シリーズ
◎鞆の浦と神話/其の一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052336.html
◎鞆の浦と神話/其の二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052867.html
◎鞆の浦と神話/其の三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053155.html
◎鞆の浦と神話/其の四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053298.html
◎鞆の浦と神話/其の五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053433.html
◎鞆の浦と神話/其の六
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053608.html
◎鞆の浦と神話/其の七
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053772.html
◎鞆の浦と神話/其の八
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053974.html
◎鞆の浦と神話/其の九
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054126.html
◎鞆の浦と神話/其の十
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054282.html
◎鞆の浦と神話/其の十一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054445.html
◎鞆の浦と神話/其の十二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054635.html
◎鞆の浦と神話/其の十三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054887.html
◎鞆の浦と神話/其の十四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055128.html
◎鞆の浦と神話/其の十五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055516.html
日本書紀(上)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
日本書紀(下)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
古事記と日本書紀 (図解雑学)/武光 誠
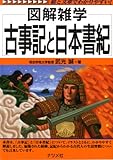
¥1,365
Amazon.co.jp
書き下し文
時に、伊奘冉尊の曰はく、「愛しき吾(あ)が夫君(なせのみこと)し、如此言(かくのたま)はば、吾(われ)は当に汝(いまし)が治(しら)す国民(ひとくさ)、日(ひとひ)に千頭縊(ちかべくび)り殺さむ」とのたまふ。伊奘諾尊、乃ち報(こた)へて曰はく、「愛しき吾が妹(なにものみこと)し、如此言はば、吾は当に日に千五百頭(ちかべあまりいほかうべ)産ましめむ」とのたまふ。因りて曰はく、「此よりな過ぎそ」とのたまひて、即ち其の杖(みつゑ)を投げたまふ。是を岐神(ふなとのかみ)と謂(まう)す。又其の帯(みおび)を投げたまふ。是を長道磐神(ながちはのかみ)と謂す。又其の衣(みそ)を投げたまふ。是を煩神(わづらひのかみ)と謂す。又其の褌(はかま)を投げたまふ。是を開囓神(あきくひのかみ)と謂す。又其の履(くつ)を投げたまふ。是を道敷神(ちしきのかみ)と謂す。其の泉津平坂にして、或いは、所謂(い)ふ、泉津平坂といふは、復別(またこと)に処所(ところ)有らじ、但(ただ)死(まか)るに臨みて気絶(いきた)ゆる際(きは)、是を謂ふか。所塞(ふさ)がる磐石といふは、是泉門(よみど)に塞(ふたが)ります大神(おほみかみ)を謂ふ。亦の名は道返大神(ちがへしのおほみかみ)といふ。伊奘諾尊、既に還りて、乃ち追ひて悔いて曰はく、「吾前(さき)に不須也凶目き汚穢き処に到る。故、吾が身の濁穢(けがらはしきもの)を滌(あら)ひ去(う)てむ」とのたまひて、則ち往きて筑紫の日向(ひむか)の小戸(をど)の橘の檍原(あはきはら)に至りまして、祓(みそ)ぎ除(はら)へたまふ。遂に身の所汚(きたなきもの)を盪滌(すす)ぎたまはむとして、乃ち興言(ことあげ)して曰はく、「上瀬(かみつせ)は是太(はなはだ)だ疾(はや)し。下瀬(しもつせ)は是太だ弱(ぬる)し」とのたまひて、便ち中瀬(なかつせ)に濯(すす)ぎたまふ。因りて生める神を、号(なづ)けて八十枉津日神(やそまがつひのかみ)と曰す。次に其の枉(まが)れるを矯(なほ)さむとして生める神を、号けて神直日神(かむなほひのかみ)と曰す。次に大直日神(おほなほびのかみ)。又海(わた)の底に沈(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて底津少童命(そこつわたつみのみこと)と曰す。次に底筒男命(そこつつのをのみこと)。又潮の中に潜(かづ)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて中津少童命(なかつわたつみのみこと)と曰す。次に中筒男命(なかつつのをのみこと)。又潮の上に浮(う)き濯ぐ。因りて生める神を、号けて表津少童命(うはつわたつみのみこと)と曰す。次に表筒男命(うはつつのをのみこと)。凡て九(ここのはしら)の神有(いま)す。其の底筒男命・中筒男命・表筒男命は是即ち住吉大神(すみのえのおほみかみ)なり。底津少童命・中津少童命・表津少童命は、是阿雲連等(あづみのむらじら)が所祭(いつきまつ)る神なり。
然して後に、左の眼(みめ)を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて天照大神(あまてらすおほみかみ)と曰す。復右の眼(みめ)を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて月読尊(つくよみのみこと)と曰す。復鼻(みはな)を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて素戔鳴尊(すさのをのみこと)と曰す。凡て三(みはしら)の神ます。已にして伊奘諾尊、三の子(みこ)に勅任(ことよさ)して曰はく、「天照大神は、以て高天原(たかまのはら)を治(しら)すべし。月読尊は、以て滄海原(あをうなはら)の潮の八百重(やほへ)を治すべし。素戔鳴尊は、以て天下(あめのした)を治すべし」とのたまふ。是の時に、素戔鳴尊、年已(としすで)に長(お)いたり。復八握鬚髯(やつかひげ)生(お)ひたり。然れども天下を治さずして、常に啼き泣ち恚恨(ふつく)む。故、伊奘諾尊、問ひて曰はく、「汝は何の故(ゆゑ)にか恒に如此(かく)啼く」とのたまふ。対(こた)へて曰(まう)したまはく、「吾(やつかれ)は母(いろはのみこと)に根国(ねのくに)に従(したが)はむと欲(おも)ひて、只に泣かくのみ」とまうしたまふ。伊奘諾尊悪(にく)みて曰(のたま)はく、「情(こころ)の任(まにま)に行ね」とのたまひて、乃ち逐(やらひや)りき。 <第六>
<訳>
その時に伊奘冉尊は、「愛しい我が夫よ、このようなことを言うのなら、私はあなたが治める国の国民を、一日に千人殺しましょう」と言った。伊奘諾尊はそれに答えて、「愛しい我が妻よ、そのようなことを言うのなら、私は一日に千五百人生もう」と言った。そして、「これよりこちらへ来るな」との言って、杖を投げた。これを岐神(ふなとのかみ)と言う。また帯を投げた。これを長道磐神(ながちはのかみ)と言う。また衣を投げた。これを煩神(わづらひのかみ)と言う。また褌を投げた。これを開囓神(あきくひのかみ)と言う。また履(くつ)を投げた。これを道敷神(ちしきのかみ)と言う。その泉津平坂に(泉津平坂と言うのは別に場所を言うのではなく、死に臨んで生き絶える時の事をいうのか)、塞がっている岩を、泉門(よみど)に塞(ふたが)ります大神(おほみかみ)と言う。別名道返大神(ちがへしのおほみかみ)と言う。
伊奘諾尊は帰って来て、追ったことを悔いて、「私は先ほど醜悪で汚い国に行ってしまった。我が身についた穢れを洗い捨てよう」と言って、すぐに筑紫の日向(ひむか)の小戸(をど)の橘の檍原(あはきはら、地名?)に至って、禊祓いをした。そして身の汚れを濯ごうとして、言葉を発して、「上の瀬は流れがかなり速い。下の瀬は流れがかなり遅い」と言って、中の瀬で濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて八十枉津日神(やそまがつひのかみ)と言う。次にその穢れを直そうとして生んだ神を、名付けて神直日神(かむなほひのかみ)と言う。次に大直日神(おほなほびのかみ)。そして海の底に沈んで濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて底津少童命(そこつわたつみのみこと)と言う。次に底筒男命(そこつつのをのみこと)。また潮の中程に潜って濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて中津少童命(なかつわたつみのみこと)と言う。次に中筒男命(なかつつのをのみこと)。そしてまた潮の上に浮きながら濯いだ。これに因って生んだ神を、名付けて表津少童命(うはつわたつみのみこと)と言う。次に表筒男命(うはつつのをのみこと)。全て合わせて九柱の神である。その底筒男命・中筒男命・表筒男命は住吉大神(すみのえのおほみかみ)である。底津少童命・中津少童命・表津少童命は、阿雲連等(あづみのむらじら)が祭っている神である。
さてその後に、左の眼を洗った。これに因って生んだ神を、名付けて天照大神(あまてらすおほみかみ)と言う。また右の眼を洗った。これに因って生んだ神を、名付けて月読尊(つくよみのみこと)と言う。また鼻を洗った。これに因って生んだ神を、名付けて素戔鳴尊(すさのをのみこと)と言う。全て合わせて三柱の神である。伊奘諾尊、三柱の御子に命令して、「天照大神は、高天原(たかまのはら)を治めよ。月読尊は、青海原の広大な潮の全てを治めよ。素戔鳴尊は、天の下の全土を治めよ」と言った。この時、素戔鳴尊はすでに年老いていた。長く鬚が伸びた老人だった。しかし天の下を全く治めようとせず、常に激しく泣いて怒りを露にしていた。それのことを伊奘諾尊は問いて、「お前はどうして何時もそのように泣いているのだ」と言った。それに答えて、「私は母のいる根国(ねのくに)に行きたいと思って、このように泣いているのです」と言った。伊奘諾尊はそれを憎んで、「好きな世にどことなりと行け」と言って、追放した。 <第六>
◎岐神(ふなとのかみ):道の三叉路に置かれた道祖神。杖は根のついた木を用いていたため、その生成力が霊力を示していて、部落の入り口や岐路に立て邪悪の侵入から防御するために立てられた。
◎長道磐神(ながちはのかみ):長い道の神。帯の形状から。
◎煩神(わづらひのかみ):思うままに行かないことを表す神。衣が纏わりつくことから。
◎褌(はかま):腰と脚を覆う裳の古形。
◎開囓神(あきくひのかみ):「古事記」では冠から生まれた神とされる。冠が開いていることから。
◎道敷神(ちしきのかみ):「ち」は道、「しき」は一面に力を及ぼすこと、履が道を自由に歩行することから。「古事記」では伊奘冉尊の別名。
◎泉門(よみど)に塞(ふたが)ります大神(おほみかみ):冥界との入り口邪霊の侵入を防ぐ神。
◎道返大神(ちがへしのおほみかみ):死者を冥界に返す神。
◎日向(ひむか):日の当たること、もしくは日向国の大隈の地名。
◎小戸(をど):小さな水門。
◎檍原(あはきはら):「檍」はもちのきに当たると言われるが未詳。
◎祓(みそ)ぎ:水に入って身を清浄にすること。
◎興言(ことあげ):言葉を発すること。
◎八十枉津日神(やそまがつひのかみ):「やそ」は多数、「まが」は穢、禍の多いことを表している神。
◎神直日神(かむなほひのかみ):大直日神(おほなほびのかみ)、禍を取り除くため祓い浄めることから。「神」と「大」は美称。
◎底津少童命(そこつわたつみのみこと):中津少童命(なかつわたつみのみこと)、表津少童命(うはつわたつみのみこと)、海を掌る神。生まれた場所によって「底」「中」「表」となっている。
◎底筒男命(そこつつのをのみこと)、中筒男命(なかつつのをのみこと)、表筒男命(うはつつのをのみこと):「筒」は星のこと。古来「粒」を「つづ」「つつ」と呼び、星もそう呼ばれた。この三神はオリオンのカラスキ星で航海の神。
◎住吉大神(すみのえのおほみかみ):摂津住吉大社の祭神。航海を掌る神。
◎阿雲連等(あづみのむらじら):全国の海部を管理する伴造。
◎八握鬚髯(やつかひげ):「八」は数の多いこと。長い鬚を延ばした老人。
【日本書記から】鞆の浦と神話シリーズ
◎鞆の浦と神話/其の一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052336.html
◎鞆の浦と神話/其の二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746052867.html
◎鞆の浦と神話/其の三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053155.html
◎鞆の浦と神話/其の四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053298.html
◎鞆の浦と神話/其の五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053433.html
◎鞆の浦と神話/其の六
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053608.html
◎鞆の浦と神話/其の七
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053772.html
◎鞆の浦と神話/其の八
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746053974.html
◎鞆の浦と神話/其の九
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054126.html
◎鞆の浦と神話/其の十
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054282.html
◎鞆の浦と神話/其の十一
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054445.html
◎鞆の浦と神話/其の十二
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054635.html
◎鞆の浦と神話/其の十三
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746054887.html
◎鞆の浦と神話/其の十四
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055128.html
◎鞆の浦と神話/其の十五
http://ameblo.jp/rediscovery/entry-10746055516.html
日本書紀(上)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
日本書紀(下)全現代語訳 (講談社学術文庫)/著者不明

¥1,208
Amazon.co.jp
古事記と日本書紀 (図解雑学)/武光 誠
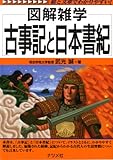
¥1,365
Amazon.co.jp