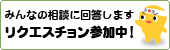小川充オフィシャルブログ
ブログの説明を入力します。
テーマ
月別
カレンダー
最新の記事
このブログのフォロワー
お気に入りブログ
ブックマーク
ブログ内検索
2007-11-05 18:43:38
クラブ・ジャズ入門
テーマ:本ここのところずっと(かれこれ1ヶ月)
ブログでコメントバックができません。
いただいたコメントには全て返事を書いているのですが
いざ打ち込んでコメント投稿完了となり
一瞬表示はされるのです。
しかし、その後すぐに消えてしまうという謎の現象が・・・。
何度やっても同じ繰り返しです。
アメブロの担当者に聞こうかとも考えましたが
皆さんお忙しくて
僕ごときのそんな些細な不具合に構ってられないでしょうから
(以前、メールでとある操作説明を求めた時も
結局返事が返って来なかったのです)
とりあえずこのまま様子を見ることにします。
ですので、しばらくコメントバックができないことを
この場でお詫びしておきます。
さて、今日の本題は
沖野修也さんが書かれた
『クラブ・ジャズ入門』です。

沖野さんにとっては
『DJ選曲術』に次ぐ2冊目の本で
まずはご出版おめでとうございますと
この場を借りてお祝い申し上げます。
クラブ・ジャズという言葉が生まれ
かれこれ15年は経ちます。
今、巷でも
普通にクラブ・ジャズという呼び名が使われますが
でもクラブ・ジャズって一体何?
という人も多いでしょう。
また、ジャズとクラブ・ジャズの違いが
今ひとつよくわからないという人もいると思います。
さらにはよく使われるクロスオーヴァーって?
という疑問もあるでしょう。
そうした事柄に対し
今まできちんとした回答をした書物はありませんでした。
何となくわかっているようで
でも、きちんと言葉で表現できていない
そんな曖昧さがクラブ・シーンにはあったように思います。
音楽とは感覚的なものだから
言葉では伝えられないものがあると。
そうした曖昧さは時にいいこともありますが
でも、きちんと文章で体系化できないと
文化としては未成熟である
というのが僕の持論です。
日本のクラブ・ジャズ草創期から今に至るまで
シーンを牽引し続け
また自身のアーティストとしての
クリエイティヴィティーを絶えず磨き続ける沖野さんが
DJ
アーティスト
プロデューサー
オーガナイザーなど
様々な立場での実体験を通じ
現場に根ざしたリアルな目で
クラブ・ジャズの発生から現在に至る流れを
極めて論理的にかつ判りやすくまとめられたのが
この『クラブ・ジャズ入門』なのです。
DJ/クリエイターの立場にある人が
敢えて自分の関わる音楽界を
客観的に分析し
また感覚ではなく
論理で音楽を解析していくこと
これは非常に意義深いことだと思います。
そもそもDJの資質の一つに
批評性があると思います。
音楽を従来とは違った切り口で紹介し
そしてありきたりの見方では見えなかった
共通項や符号で繋いだり
また時に意外性を伴うプレゼンテーションで
その作品の奥底に潜む本質を開示する。
こうした作業は批評性がないとできないことだと思います。
しかしながらそうした批評性を持ちながらも
DJは感覚でするものと言う人が多く
自らの論理性に蓋をしてしまっている
そんなケースをよく目にします。
そうしたDJやクラブ文化に対し
沖野さんは自ら
DJのさらなる可能性を高める
そんな活動を行っており
それが『DJ選曲術』
そして今回の『クラブ・ジャズ入門』として
発露されたのではないかと思うのです。
最終的に沖野さんは
クラブ・ジャズとはジャンルやスタイルではないと仰ってます。
それは僕も同感です。
クラブ・ジャズとは
既存のジャズを含め
あらゆる音楽ジャンルを越境し
楽しむという態度であると。
そして、譜面や演奏スタイル
ひいては社会的な規制や観念
そうしたものに縛られることなく
自由に創造していくスピリットであると。
僕の『Jazz Next Standard』シリーズもそうですが
最終的に言いたいのはこの部分なのです。
クラブ・ジャズというスタイルを色々と定義づけはするのですが
結局はスタイルではない部分に行き着くのです。
そして、そのスタイルではない部分の有無が
本物とそうではないものを分けるのだと。
本物を見極める目を持つためにも
是非読んでもらいたい本だと思います。