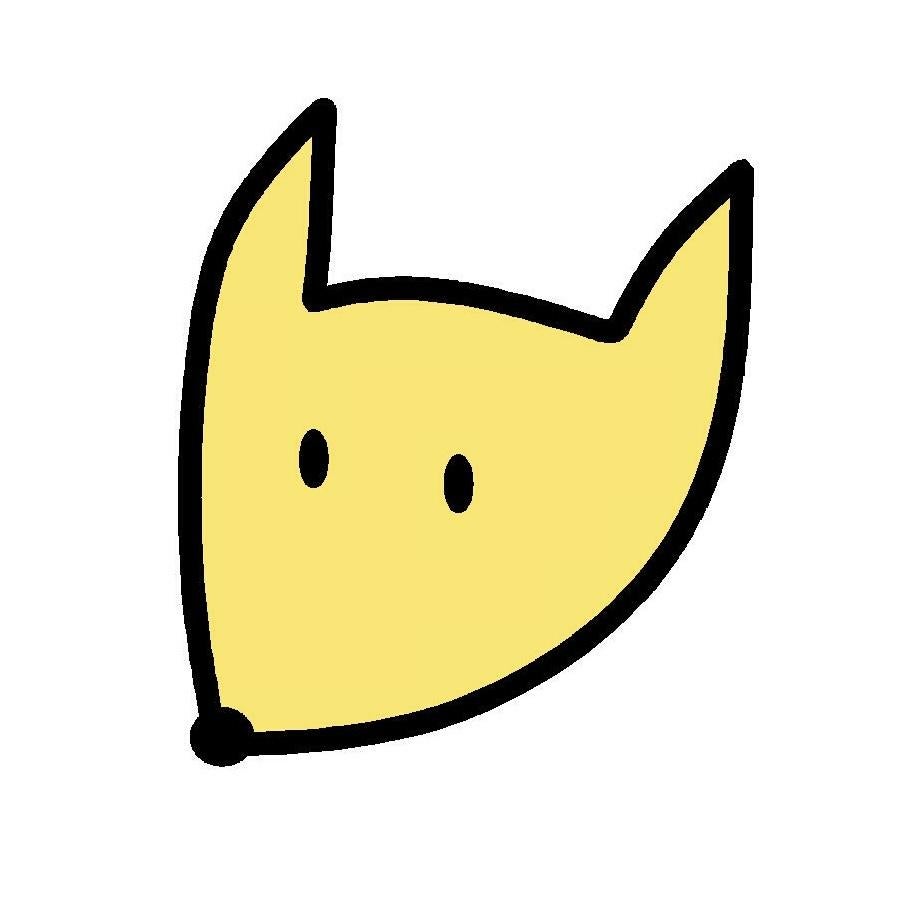うまれたての星 大島真寿美
「これは私たちの漫画だ」
これが少女マンガの変革を生んだものなんだろうな。
“私たち”とは読者であり、作家であり、編集者であるんだが。
押しつけでも、単純な夢物語でもない、
一人ひとりが「自分のためのもの」と思えるものに、
少女マンガがなっていった時代を
フィクションの形で永久保存した。
1970年初頭、少女マンガ雑誌の編集部が舞台。
モデルはマーガレットと別マ。
(そのほか、セブンティーンとかノンノっぽいものも出てくる)
主に7人の人物からの視点が入れ替わり描かれるのだが、
その人物像が本当にリアルで自然。
大島真寿美さんって好きだなあ。
人物を描く筆力なんだろうな。
そのころ、少女マンガだけでなく、
会社における女性の立ち位置も変化し始めていたけど
マンガに比べて動きが鈍い。
そのへんのこともじっくり描かれているから
単なる懐古趣味に陥っていないのはさすがだ。
出てくるマンガ家やそのエピソードは
もちろん実際とは違うのだが、
池田理代子、山本鈴美香、くらもちふさこ、槇村さとる、土田よしことかが
モデルなんだよなあ、とか想像してみる楽しみもある。