夜のミッキーマウス。
それだけでどれ程の想像を刺激される事か。
不思議な事にここでは想像だろうが、妄想だろうが精密な言葉の意味は不必要だ。
寧ろ、不可能と言うべきかもしれない。
その言葉から脳が創り出した何かしらかは、嫌に鮮明に、目の前をうろつく。その瞳は見つめあうほど生気を増すが、その右手の手袋は白いのか黒いのか赤いのかわからない。
そうして、出来上がりつつある、脳内の何かしらかは基本的に淘汰される運命にある。
そこに詩の他人の言葉に対する、暴力を感じる。
それはただの暴力じゃない。
有無も言わさぬ、峻烈な暴力。
読んでしまったが最後、自分の想像で詩には追いつけない。
追いつけそうだし、追いつけるものもある。
けれど、追いつけないものには徹底的に途方に暮れる。
だが、万が一訪れる追い付く瞬間に自身の想像力の身の丈を超える事に気づくだろう。
噛み続けた金属の塊が、次の一噛みで南国の果実に変わるような瞬間。
そこでは、もはや言葉は不要。
詩でしか表現できないものがある。
詩でしか到達できない場所がある。
だから、詩を読むとは暴力に耐える事だ。
だから、私は詩はあまり好きでない。
iPhoneからの投稿
それだけでどれ程の想像を刺激される事か。
不思議な事にここでは想像だろうが、妄想だろうが精密な言葉の意味は不必要だ。
寧ろ、不可能と言うべきかもしれない。
その言葉から脳が創り出した何かしらかは、嫌に鮮明に、目の前をうろつく。その瞳は見つめあうほど生気を増すが、その右手の手袋は白いのか黒いのか赤いのかわからない。
そうして、出来上がりつつある、脳内の何かしらかは基本的に淘汰される運命にある。
そこに詩の他人の言葉に対する、暴力を感じる。
それはただの暴力じゃない。
有無も言わさぬ、峻烈な暴力。
読んでしまったが最後、自分の想像で詩には追いつけない。
追いつけそうだし、追いつけるものもある。
けれど、追いつけないものには徹底的に途方に暮れる。
だが、万が一訪れる追い付く瞬間に自身の想像力の身の丈を超える事に気づくだろう。
噛み続けた金属の塊が、次の一噛みで南国の果実に変わるような瞬間。
そこでは、もはや言葉は不要。
詩でしか表現できないものがある。
詩でしか到達できない場所がある。
だから、詩を読むとは暴力に耐える事だ。
だから、私は詩はあまり好きでない。
iPhoneからの投稿
横尾氏の絵には今一つピンと来るものがないけれど、この人の書く素朴な文章にはとても惹かれる。
彼のみたインドはいかなるものか?知りたくなって読んでみた。
総括してしまうと、
インドと言う国については誰の感想を聞いたところで、『同じ』である。
と気付いた事が最大の成果だと言える。
インドは汚くて、乞食がいっぱいいて、乞食でない人も乞食みたいに汚くて、食事で腹を壊し、
徹底したカースト制が根付き、色とりどりのサリーとはっきりとした目鼻立ちの女性に目移りし、
バイタクの料金交渉で声を荒げ、自分を見つめ、ガンジスを眺め、遺跡では悠久の時の流れを感じ、
荒涼とした大地、花咲き誇る眼前の景色に理想郷を重ねる・・・・・・・。
こういった具合に羅列していけば、していくほど、インドに近づいているのかと言えば、
そうでもないような気がする。
いつも同じ距離感でそこにある。それがインドではないだろうか。
だからこそ、いつも驚きがある。
例えば、最寄りの駅はいつもそこにある。
それは間違いない。
今年の3/11以降の駅は人であふれていた。
人数規制を行い、駅の外まで人の列が長く延びていた。
その場所は確かに最寄りの駅だけれど、
見えてくる光景からそれが最寄りの駅のイメージから遠くかけ離れている。
だからと言って、そこが最寄りの駅じゃないとは思わない。
いつもと同じ場所に同じようにある。けれど、人が、つまりは変化が多い。
インドでは全てがあふれているような気がする。
富も貧困も死も生も、人も、自然も、建物の、車も。
膨大な量が生成するエネルギーがそこにあるだけ。だけ。
少しだけこの本の内容に触れておこう。
横尾氏はスピリチュアルな人物で、自身のうちに抱えるカルマを越えようと、ヨーガを修養したらしい。
しかし、やれどもやれども解き放たれるどころか膨らんでいってしまう。
あるときに禅僧に出会い、『只管打座』(ただ座る事)を知り、禅へと移行していく。
私も道元禅に興味があるものの、どうにも落ち着きがなくて、ただ座っていると言う事が難しい。
だから、ヨーガを行っているという側面も持ち合わせているが、このただ座ることを難しく考えすぎていたのかもしれないと思った。
これは解釈の違いかもしれないが、
道元禅に置いて、座禅すると言う事は『既に悟っている事』を思いだすために、『作法』にはめられた状態を維持することだと思っていた。
けれど、
ただ座るだけ。そこに作法はあるかもしれないが、無視してもいい。とりあえず座っているだけ。
と横尾氏の文章を読んではっとさせられた。
自分は別に悟りたいという思いがあるわけでもないし、道元がみた地平を拝みたい訳でもない。
ただ純粋に、実践してみたかっただけだと思いだした。
こういう思い込みから自由になるのは本当に気持ちが楽になる。
横尾氏の感じたインドは確かに私のインドでもあった。
沢木氏の語ったインドはイメージから1mmもぶれることなく現実のインドであった。
きっとこれから先、見聞きするインドは私が知っているインドだ。
けれど、感じた事思った事の全てが言葉や思い出になるとは限らない。
だから、そうやってひとつひとついつの間にか丁寧にインドを解体していく。
そして、全く新しいインドと出会うのだろう。
・・・・インド大絶賛だな。笑。
インドへ (文春文庫 (297‐1))/横尾 忠則
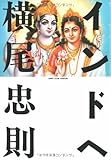
¥650
Amazon.co.jp
彼のみたインドはいかなるものか?知りたくなって読んでみた。
総括してしまうと、
インドと言う国については誰の感想を聞いたところで、『同じ』である。
と気付いた事が最大の成果だと言える。
インドは汚くて、乞食がいっぱいいて、乞食でない人も乞食みたいに汚くて、食事で腹を壊し、
徹底したカースト制が根付き、色とりどりのサリーとはっきりとした目鼻立ちの女性に目移りし、
バイタクの料金交渉で声を荒げ、自分を見つめ、ガンジスを眺め、遺跡では悠久の時の流れを感じ、
荒涼とした大地、花咲き誇る眼前の景色に理想郷を重ねる・・・・・・・。
こういった具合に羅列していけば、していくほど、インドに近づいているのかと言えば、
そうでもないような気がする。
いつも同じ距離感でそこにある。それがインドではないだろうか。
だからこそ、いつも驚きがある。
例えば、最寄りの駅はいつもそこにある。
それは間違いない。
今年の3/11以降の駅は人であふれていた。
人数規制を行い、駅の外まで人の列が長く延びていた。
その場所は確かに最寄りの駅だけれど、
見えてくる光景からそれが最寄りの駅のイメージから遠くかけ離れている。
だからと言って、そこが最寄りの駅じゃないとは思わない。
いつもと同じ場所に同じようにある。けれど、人が、つまりは変化が多い。
インドでは全てがあふれているような気がする。
富も貧困も死も生も、人も、自然も、建物の、車も。
膨大な量が生成するエネルギーがそこにあるだけ。だけ。
少しだけこの本の内容に触れておこう。
横尾氏はスピリチュアルな人物で、自身のうちに抱えるカルマを越えようと、ヨーガを修養したらしい。
しかし、やれどもやれども解き放たれるどころか膨らんでいってしまう。
あるときに禅僧に出会い、『只管打座』(ただ座る事)を知り、禅へと移行していく。
私も道元禅に興味があるものの、どうにも落ち着きがなくて、ただ座っていると言う事が難しい。
だから、ヨーガを行っているという側面も持ち合わせているが、このただ座ることを難しく考えすぎていたのかもしれないと思った。
これは解釈の違いかもしれないが、
道元禅に置いて、座禅すると言う事は『既に悟っている事』を思いだすために、『作法』にはめられた状態を維持することだと思っていた。
けれど、
ただ座るだけ。そこに作法はあるかもしれないが、無視してもいい。とりあえず座っているだけ。
と横尾氏の文章を読んではっとさせられた。
自分は別に悟りたいという思いがあるわけでもないし、道元がみた地平を拝みたい訳でもない。
ただ純粋に、実践してみたかっただけだと思いだした。
こういう思い込みから自由になるのは本当に気持ちが楽になる。
横尾氏の感じたインドは確かに私のインドでもあった。
沢木氏の語ったインドはイメージから1mmもぶれることなく現実のインドであった。
きっとこれから先、見聞きするインドは私が知っているインドだ。
けれど、感じた事思った事の全てが言葉や思い出になるとは限らない。
だから、そうやってひとつひとついつの間にか丁寧にインドを解体していく。
そして、全く新しいインドと出会うのだろう。
・・・・インド大絶賛だな。笑。
インドへ (文春文庫 (297‐1))/横尾 忠則
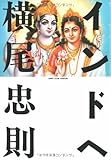
¥650
Amazon.co.jp
今日、ヨガの先生に
『呼吸の仕方上手ですね』って褒められた。
苦手だったから嬉しくてうれしくて。
思わず、
『やったぁ』と叫んだら。
先生が
『「やったぁ」?』といぶかしげな視線を投げかけてきました。笑。
あーうれし。
『呼吸の仕方上手ですね』って褒められた。
苦手だったから嬉しくてうれしくて。
思わず、
『やったぁ』と叫んだら。
先生が
『「やったぁ」?』といぶかしげな視線を投げかけてきました。笑。
あーうれし。
会社の人に水木しげるのDVDを借りて観てみたら、
これが面白い。
なんて自由な人なんだ!と衝撃を受けた。
鬼太郎を楽しんだ記憶もないし、
彼の描く絵はあまり好きではない。
だから、以前流行っていたゲゲゲの女房にも全く惹かれなかった。
まぁ、今はテレビ全般に惹かれていないけれど。
さて本作はと言うと、
なんともまぁ、面白かった。
落ちこぼれも落ちこぼれ。
遅刻なんて当たり前、勉強なん出来やしない。
ただ、絵が好き、妖怪の話が好き、虫が好き。
学校を卒業しても、行く場所がない。
口を聞いてもらって勤めるところ勤めるところ首になるか飽きてしまう。
彼の少年から青年時代を追いかけていくと
本人の気をよそにこちらまで心配になってしまう。
大丈夫なのか?
生きていけるのか?
生活は?
仕事は?
と。
けれど、本人はどこ吹く風。
やがて、赤紙が届いて、入隊する。
しかし、厳しい軍隊でも、彼は自分を崩さない。
だからか、生きては帰ってこれないような激戦地へ送られる。
そこで、左腕を失う事になるが、
それでも、彼の心には曇りがない。
いつでもスカッとしているのだ。
このスカッとした感じはなんなのか、
それはあとがきを読んで画点が行った。
まさに、それ。と膝を打つ感じだ。
生き物の時間と言うのは全部違う。
それは人間も一緒。
だから、みんなが同じように同じような生活をして、
家庭を持ってと言う事は規則正しくて気持ちが悪い。
みんな違う。
その一つの考えで、ずいぶんと心休まる人は多いのではないだろうか。
働いても働いても時間も金もない。
けれど、彼ほどではないのではないだろうか。
大好きな睡眠時間を割いて、
はした金を手にして、出版社が潰れて・・・・・
この現代に疲れた人にこそ読んでほしい活力の書。
人並みという言葉がこの世から消えれば、
もう少し穏やかな気持ちになれそうな気がする。
ほんまにオレはアホやろか/水木 しげる

¥800
Amazon.co.jp
これが面白い。
なんて自由な人なんだ!と衝撃を受けた。
鬼太郎を楽しんだ記憶もないし、
彼の描く絵はあまり好きではない。
だから、以前流行っていたゲゲゲの女房にも全く惹かれなかった。
まぁ、今はテレビ全般に惹かれていないけれど。
さて本作はと言うと、
なんともまぁ、面白かった。
落ちこぼれも落ちこぼれ。
遅刻なんて当たり前、勉強なん出来やしない。
ただ、絵が好き、妖怪の話が好き、虫が好き。
学校を卒業しても、行く場所がない。
口を聞いてもらって勤めるところ勤めるところ首になるか飽きてしまう。
彼の少年から青年時代を追いかけていくと
本人の気をよそにこちらまで心配になってしまう。
大丈夫なのか?
生きていけるのか?
生活は?
仕事は?
と。
けれど、本人はどこ吹く風。
やがて、赤紙が届いて、入隊する。
しかし、厳しい軍隊でも、彼は自分を崩さない。
だからか、生きては帰ってこれないような激戦地へ送られる。
そこで、左腕を失う事になるが、
それでも、彼の心には曇りがない。
いつでもスカッとしているのだ。
このスカッとした感じはなんなのか、
それはあとがきを読んで画点が行った。
まさに、それ。と膝を打つ感じだ。
生き物の時間と言うのは全部違う。
それは人間も一緒。
だから、みんなが同じように同じような生活をして、
家庭を持ってと言う事は規則正しくて気持ちが悪い。
みんな違う。
その一つの考えで、ずいぶんと心休まる人は多いのではないだろうか。
働いても働いても時間も金もない。
けれど、彼ほどではないのではないだろうか。
大好きな睡眠時間を割いて、
はした金を手にして、出版社が潰れて・・・・・
この現代に疲れた人にこそ読んでほしい活力の書。
人並みという言葉がこの世から消えれば、
もう少し穏やかな気持ちになれそうな気がする。
ほんまにオレはアホやろか/水木 しげる

¥800
Amazon.co.jp
この作家の持ち味は何だろう?
独特な言い回しと登場人物、そしてそれらにまつわる恋愛といったところだろうか。
山月記から始まって、藪の中、走れメロス、桜の森の満開の下、そして夢十夜。
古典をアレンジしたこれらの作品は私にとってある登場人物の物語に他ならないような気がする。
原典をすべて読んだ事はないからか、
面白い事に原典を読んでいないものの方が楽しめた。
とはいうものの、走れメロスの章では、終盤の混沌を楽しませていただいた。
完全に自分のものにしてしまっている作者の力量に感嘆してしまうほど。
けれど、もともと彼の作品が嫌いな人にしてみれば、
言語道断だと言われてしまうかもしれない。
新釈 走れメロス 他四篇 (祥伝社文庫 も 10-1)/森見 登美彦

¥590
Amazon.co.jp
独特な言い回しと登場人物、そしてそれらにまつわる恋愛といったところだろうか。
山月記から始まって、藪の中、走れメロス、桜の森の満開の下、そして夢十夜。
古典をアレンジしたこれらの作品は私にとってある登場人物の物語に他ならないような気がする。
原典をすべて読んだ事はないからか、
面白い事に原典を読んでいないものの方が楽しめた。
とはいうものの、走れメロスの章では、終盤の混沌を楽しませていただいた。
完全に自分のものにしてしまっている作者の力量に感嘆してしまうほど。
けれど、もともと彼の作品が嫌いな人にしてみれば、
言語道断だと言われてしまうかもしれない。
新釈 走れメロス 他四篇 (祥伝社文庫 も 10-1)/森見 登美彦

¥590
Amazon.co.jp
ひょんな事から、思い出した。
もしかしたら、10年前に思い出そうとしていたのかもしれない。
大勢で中華料理を食べに行くと、必ずエビチリを頼む人がいる。
理由を聞けば、美味しいから。と答える。
しかし、後ほどその皿を見れば、何となく汚らしい食べ残し。
そんな光景を何度も見ているうちに、
エビチリが好きな人は本当は少ないのでは?と思った。
だいたい、エビチリって何語なの?
本当に中華料理なの?
味が濃い上に、ご飯に合うとも合わない。なんの為のおかずなのが私には理解し難い。
昔、ピーナッツの甘じょっぱいなにものかをご飯と食べた記憶はあるけれど、あのアンバランスな食体験にエビチリは近い。
当然、好みは千差万別。
だから、好みは否定しないが、好みの程度は問いたい。とりあえず、好きな料理ベスト10に入るかどうかから始めよう。
耳をすませば、脳内で会話が聞こえる。
A:エビチリ好き?
B:うん。
A:好きな料理だと何番目?
B:8番目。
A:じゃあ、10位は?
B:お好み焼き。
A:エビチリとお好み焼きどっち?毎日食べるなら?
B:…お好み焼き
A:エビチリは何位?
B:35位くらいかな…
とまぁ、こんなにうまく事は運ばないだろうが、少なくとも今、抱いている好きと言う感覚よりは好きでない可能性が高い。
逆を言えば、私の事をなんとも思っていない女性でさえ、その思考を改め、煮詰め、砂糖を加え、風味付にラム酒でも入れ、隠し味にセロリか勘違いと言う名のスパイスを加えれば、好きだと言う結論に達するかもしれない。
いや、そこまでやれば達してしかるべき事だろう。
私でさえ、そこまでやればなんとかなるのだからエビチリ如きが好きでなくなるのも時間の問題だ。
何となく、皆が頼んでいる事が多い料理だから、慣習的に頼んでいるのではないか?
よくよく考えてみるとそれほど好きではないけれど、上記の状況からエビチリが好きな人が多いように捉えられるから好きと言っておくといった安全地帯に留まっているのではないか?
エビが好きな食べ物の1位に来るのはなんとも思わないけれど、エビチリが1位に来る事は考えにくい。
仮にこれを読んでいる人にエビチリ好きがいたら教えて欲しい。エビチリの魅力を。
いや、そんな事よりも、あの方法でさえ私の事を好きにならない女性がいた場合、私の拠り所は何処になるのか?今晩はそれを考えながら眠りにつこう。
iPhoneからの投稿
もしかしたら、10年前に思い出そうとしていたのかもしれない。
大勢で中華料理を食べに行くと、必ずエビチリを頼む人がいる。
理由を聞けば、美味しいから。と答える。
しかし、後ほどその皿を見れば、何となく汚らしい食べ残し。
そんな光景を何度も見ているうちに、
エビチリが好きな人は本当は少ないのでは?と思った。
だいたい、エビチリって何語なの?
本当に中華料理なの?
味が濃い上に、ご飯に合うとも合わない。なんの為のおかずなのが私には理解し難い。
昔、ピーナッツの甘じょっぱいなにものかをご飯と食べた記憶はあるけれど、あのアンバランスな食体験にエビチリは近い。
当然、好みは千差万別。
だから、好みは否定しないが、好みの程度は問いたい。とりあえず、好きな料理ベスト10に入るかどうかから始めよう。
耳をすませば、脳内で会話が聞こえる。
A:エビチリ好き?
B:うん。
A:好きな料理だと何番目?
B:8番目。
A:じゃあ、10位は?
B:お好み焼き。
A:エビチリとお好み焼きどっち?毎日食べるなら?
B:…お好み焼き
A:エビチリは何位?
B:35位くらいかな…
とまぁ、こんなにうまく事は運ばないだろうが、少なくとも今、抱いている好きと言う感覚よりは好きでない可能性が高い。
逆を言えば、私の事をなんとも思っていない女性でさえ、その思考を改め、煮詰め、砂糖を加え、風味付にラム酒でも入れ、隠し味にセロリか勘違いと言う名のスパイスを加えれば、好きだと言う結論に達するかもしれない。
いや、そこまでやれば達してしかるべき事だろう。
私でさえ、そこまでやればなんとかなるのだからエビチリ如きが好きでなくなるのも時間の問題だ。
何となく、皆が頼んでいる事が多い料理だから、慣習的に頼んでいるのではないか?
よくよく考えてみるとそれほど好きではないけれど、上記の状況からエビチリが好きな人が多いように捉えられるから好きと言っておくといった安全地帯に留まっているのではないか?
エビが好きな食べ物の1位に来るのはなんとも思わないけれど、エビチリが1位に来る事は考えにくい。
仮にこれを読んでいる人にエビチリ好きがいたら教えて欲しい。エビチリの魅力を。
いや、そんな事よりも、あの方法でさえ私の事を好きにならない女性がいた場合、私の拠り所は何処になるのか?今晩はそれを考えながら眠りにつこう。
iPhoneからの投稿
読了!
読めば一度は必ず発狂すると言われる一大奇書。
ミステリーが好きな人ならば一度は耳にする事があるだろう。
ミステリーの三大奇書と言えば、中山英夫の「虚無への供物」、小栗虫太郎の「黒死館殺人事件」、そして本書が挙げられる。
「黒死館~」はどこにも面白さを感じられず、読むのをやめ、「虚無への~」はまぁ、まあまあ、と言ったあやふやな感想しかいだけなかった。
本書も以前は面倒になり読むのをやめてしまったが、先に挙げたキャッチコピーが頭から離れず、また、森博嗣がある本で書いた「ある仮説を持って読み進めて行ったら、恐ろしくなった」という感想が余りにも魅力てき過ぎて、これで最後と挑戦してみた。
読み始め、記憶が蘇る。
退屈で、大袈裟で、前時代的で、長ったらしい印象はすぐに訂正する事になった。
ナニコレ!
オモシロイ!!
言葉の氾濫、洪水。イメージを通り越して、まるで実体験しているかのような錯覚。
面白いのではなくて、面白いと思わされているんじゃないかという疑念。
本筋に対しても、脳が結末を急ぐ。
気持ちではなくて、
この本に限っていえば、脳みそ、もしくは脳髄、更に言えば…。
扱っている題材も凄いが、話の筋道も凄まじい。
この本が書かれた時代背景を推し量るだけでも壮絶な小説なのだが、それはこの小説にして、微細な事に過ぎない。
森博嗣が立てた仮説はわからないけれど、仮説を通して視えてくる物語があるという事になる。
それを鑑みて、視えてきたドグラ・マグラはやはり精神に異常をきたす奇書なのかもしれない。
興味をもって読まれてみたい方は
こちらで無料公開されています。
http://www.aozora.gr.jp/cards/000096/card2093.html
iPhoneからの投稿ドグラ・マグラ (上) (角川文庫)/夢野 久作
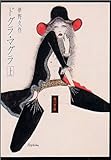
¥540
Amazon.co.jp
ドグラ・マグラ (下) (角川文庫)/夢野 久作

¥620
Amazon.co.jp
読めば一度は必ず発狂すると言われる一大奇書。
ミステリーが好きな人ならば一度は耳にする事があるだろう。
ミステリーの三大奇書と言えば、中山英夫の「虚無への供物」、小栗虫太郎の「黒死館殺人事件」、そして本書が挙げられる。
「黒死館~」はどこにも面白さを感じられず、読むのをやめ、「虚無への~」はまぁ、まあまあ、と言ったあやふやな感想しかいだけなかった。
本書も以前は面倒になり読むのをやめてしまったが、先に挙げたキャッチコピーが頭から離れず、また、森博嗣がある本で書いた「ある仮説を持って読み進めて行ったら、恐ろしくなった」という感想が余りにも魅力てき過ぎて、これで最後と挑戦してみた。
読み始め、記憶が蘇る。
退屈で、大袈裟で、前時代的で、長ったらしい印象はすぐに訂正する事になった。
ナニコレ!
オモシロイ!!
言葉の氾濫、洪水。イメージを通り越して、まるで実体験しているかのような錯覚。
面白いのではなくて、面白いと思わされているんじゃないかという疑念。
本筋に対しても、脳が結末を急ぐ。
気持ちではなくて、
この本に限っていえば、脳みそ、もしくは脳髄、更に言えば…。
扱っている題材も凄いが、話の筋道も凄まじい。
この本が書かれた時代背景を推し量るだけでも壮絶な小説なのだが、それはこの小説にして、微細な事に過ぎない。
森博嗣が立てた仮説はわからないけれど、仮説を通して視えてくる物語があるという事になる。
それを鑑みて、視えてきたドグラ・マグラはやはり精神に異常をきたす奇書なのかもしれない。
興味をもって読まれてみたい方は
こちらで無料公開されています。
http://www.aozora.gr.jp/cards/000096/card2093.html
iPhoneからの投稿ドグラ・マグラ (上) (角川文庫)/夢野 久作
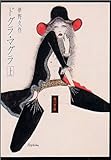
¥540
Amazon.co.jp
ドグラ・マグラ (下) (角川文庫)/夢野 久作

¥620
Amazon.co.jp
ここ最近行き始めた近くのヨガ教室は完全な地下にある。
窓はなく、外の空気も感じない。
けれど、その密閉具合が心地良い。
大好きな外ヨガは「動」
風の音、雑踏、作られていない匂い、マット越しに伝わる大地の感触…。
それら全てに溶けて行くような感覚。
自分が無くなって、有耶無耶になっていくような無境界な状態。
それに対して、
別に対する事ではないけれど、
地下ヨガは「静」。
空気の動きを感じず、圧迫感よりも包まれている安心感に近い。
恐らく、胎児の状態。
動き、呼吸といった個の性質が際立つ。際立つと言う事は孤立ではなくて、個性。
胎児が動くように、個のない状態での個性。
私はここにいる。
けれど、その「ここ」とは世界を認識する前の全て。
色んな事を感じはするけれど、その感じている事を「~である」とは感じない。
今ここで感じている事が、今感じている事でしかない。
数字の0にどんな数字を掛けたところで0にしかならない。
それは掛けられた数字が0になるのではなくて、0でしか表現しようがないということだ。
好き嫌い以前、美醜以前の話。詰めてしまえば、そんなところだろう。
そんな空間で行う、陰ヨガだったからか、始めて最初から最後まで呼吸が途切れる事なくヨガを完遂する事ができた。
密閉された空間。そこにあるのは遮断。
もしかすると、目を塞ぎ、耳栓をして行うヨガはより深く身体の内側にダイブする加速度的な方法なのかもしれない。
そうだ、終わりに口にする、「オーム」と「ナマステ」を調べてから寝る事にしよう。
では、おやすみなさい。
iPhoneからの投稿
窓はなく、外の空気も感じない。
けれど、その密閉具合が心地良い。
大好きな外ヨガは「動」
風の音、雑踏、作られていない匂い、マット越しに伝わる大地の感触…。
それら全てに溶けて行くような感覚。
自分が無くなって、有耶無耶になっていくような無境界な状態。
それに対して、
別に対する事ではないけれど、
地下ヨガは「静」。
空気の動きを感じず、圧迫感よりも包まれている安心感に近い。
恐らく、胎児の状態。
動き、呼吸といった個の性質が際立つ。際立つと言う事は孤立ではなくて、個性。
胎児が動くように、個のない状態での個性。
私はここにいる。
けれど、その「ここ」とは世界を認識する前の全て。
色んな事を感じはするけれど、その感じている事を「~である」とは感じない。
今ここで感じている事が、今感じている事でしかない。
数字の0にどんな数字を掛けたところで0にしかならない。
それは掛けられた数字が0になるのではなくて、0でしか表現しようがないということだ。
好き嫌い以前、美醜以前の話。詰めてしまえば、そんなところだろう。
そんな空間で行う、陰ヨガだったからか、始めて最初から最後まで呼吸が途切れる事なくヨガを完遂する事ができた。
密閉された空間。そこにあるのは遮断。
もしかすると、目を塞ぎ、耳栓をして行うヨガはより深く身体の内側にダイブする加速度的な方法なのかもしれない。
そうだ、終わりに口にする、「オーム」と「ナマステ」を調べてから寝る事にしよう。
では、おやすみなさい。
iPhoneからの投稿
だから、女は駄目なんだ。
何度もその言葉に傷つけられながらも
主人公は婦人警官であり続けようとする。
恐らく、街ですれ違っても、軽く会話をしたところで彼女が警官だとは思わないだろう。
彼女の職責は男社会に裏打ちされ、男の論理で、即ち警察の論理で良いように使われる。
婦人警官という言葉はあるけれど、
警察の中に婦人警官でなければならない理由は殆ど認められていないように見える。
それでも、折れない。折れたかの様に見えても、折り目はつかない。
そうでなければならないのではなく、そうであって欲しいという願望かもしれない。
この小説をそのまま現実と考えてしまうと笑われてしまうかもしれないが、
それでも、現役の婦人警官にエールを送っているように見える。
様々な部署をたらい回しにされ主人公は多く細かく小さく傷が増えて行くように見える。
けれど、それは、磨かれている事に等しい。その時、どんなに深く鋭い傷をおったとしても、それは輝く為に必要な傷なのかもしれない。
けれど、それはだれにもわからない。ただ、若いだけの鈍い光は確かに輝きを増している。
この本では彼女の物語は完結しない。途中から覗き見した彼女のこれからはどうなるのだろう?あれこれと考えて見たくもなるけれど、言葉にするのならば、それは、本書文末の文章に任せる事にしよう。
iPhoneからの投稿
何度もその言葉に傷つけられながらも
主人公は婦人警官であり続けようとする。
恐らく、街ですれ違っても、軽く会話をしたところで彼女が警官だとは思わないだろう。
彼女の職責は男社会に裏打ちされ、男の論理で、即ち警察の論理で良いように使われる。
婦人警官という言葉はあるけれど、
警察の中に婦人警官でなければならない理由は殆ど認められていないように見える。
それでも、折れない。折れたかの様に見えても、折り目はつかない。
そうでなければならないのではなく、そうであって欲しいという願望かもしれない。
この小説をそのまま現実と考えてしまうと笑われてしまうかもしれないが、
それでも、現役の婦人警官にエールを送っているように見える。
様々な部署をたらい回しにされ主人公は多く細かく小さく傷が増えて行くように見える。
けれど、それは、磨かれている事に等しい。その時、どんなに深く鋭い傷をおったとしても、それは輝く為に必要な傷なのかもしれない。
けれど、それはだれにもわからない。ただ、若いだけの鈍い光は確かに輝きを増している。
この本では彼女の物語は完結しない。途中から覗き見した彼女のこれからはどうなるのだろう?あれこれと考えて見たくもなるけれど、言葉にするのならば、それは、本書文末の文章に任せる事にしよう。
iPhoneからの投稿
