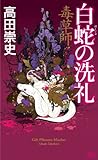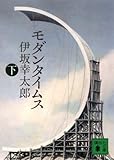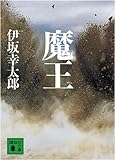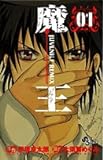なんて気持ちの良い小説なんだろう。
きっと走る事に純粋だからだろう。
主人公の座右の銘、「一つ一つ」。
焦りたい気持ちはある。次を考えて8割程度で抑える作戦もある。
けれど、彼は一つ一つを全力で走れるよう練習に励み、結果、試合での一本一本を走る度に飛躍的に成長して行く。
本作ではそういった地道とも言える積み重ねの上にリレーがある。
個人種目でも白熱するが、リレーには勝らない。
終盤の試合では、主人公の目線と自分とが一つになる。
心拍数は上がり、視野が狭くなる、隣のレーンからくる圧力を感じ、やがて、白線を越える。
今まで、小説として読んでいた物語が、自身と重なる。
勿論、最初から主人公を自分に重ねる人もいるだろうが、仮にこの終盤で主人公と読者の一体化を意図的に行っていたとしたら、鳥肌ものだ。
推理小説でも犯人がわかってしまうよりもわからない方が面白い。どんでん返しが鮮明であればあるほど、それまでの気持ちがリセットされた上で、構築し直し、驚きを新たにする。
これは推理小説ではないけれど、染み込んできた文章と情景が、より鮮明な色彩を帯びて、風を伴った小説体験として露わになる。
その風があまりにも心地よかったから、気持ちの良い小説だと思ったわけではない。むしろ、それは主人公の生き様にある。
ただし、ここではあまり言葉を費やすのは辞めておこう。
最後に思うのは、
果たして、この題名、誰の為なのか?
読者に向けられている言葉だとしたら…と考えるのは穿ち過ぎだろうか?笑。
iPhoneからの投稿
きっと走る事に純粋だからだろう。
主人公の座右の銘、「一つ一つ」。
焦りたい気持ちはある。次を考えて8割程度で抑える作戦もある。
けれど、彼は一つ一つを全力で走れるよう練習に励み、結果、試合での一本一本を走る度に飛躍的に成長して行く。
本作ではそういった地道とも言える積み重ねの上にリレーがある。
個人種目でも白熱するが、リレーには勝らない。
終盤の試合では、主人公の目線と自分とが一つになる。
心拍数は上がり、視野が狭くなる、隣のレーンからくる圧力を感じ、やがて、白線を越える。
今まで、小説として読んでいた物語が、自身と重なる。
勿論、最初から主人公を自分に重ねる人もいるだろうが、仮にこの終盤で主人公と読者の一体化を意図的に行っていたとしたら、鳥肌ものだ。
推理小説でも犯人がわかってしまうよりもわからない方が面白い。どんでん返しが鮮明であればあるほど、それまでの気持ちがリセットされた上で、構築し直し、驚きを新たにする。
これは推理小説ではないけれど、染み込んできた文章と情景が、より鮮明な色彩を帯びて、風を伴った小説体験として露わになる。
その風があまりにも心地よかったから、気持ちの良い小説だと思ったわけではない。むしろ、それは主人公の生き様にある。
ただし、ここではあまり言葉を費やすのは辞めておこう。
最後に思うのは、
果たして、この題名、誰の為なのか?
読者に向けられている言葉だとしたら…と考えるのは穿ち過ぎだろうか?笑。
iPhoneからの投稿