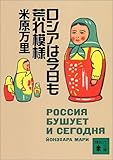安土城の築城に命を掛けた大工の話。
一見してその他の城とは明らかに違う安土城。その城主は言わずとしれた織田信長。
当然、それまでの築城とは全く違う意匠が取り入れられる。
それはつまり大工にしてみれば難題。
が、無理とは言えない。
そこに工夫が産まれる。
この信長と棟梁である岡部又左衛門のやり取りで私は信長に故ジョブズ氏を重ねました。
常人とは違う発想を突きつけ、大工は
如何にそれを形にするか試行錯誤する。
出来ないとは言えない。
どうしたら出来るかを言う。
戸建一つ建てるのに胃がせり上がる思いをしていた私から見ればそのやりとりはまさしく命のやりとりでしかありません。
昨今の建築はものによりけりだけれども、「安易」と言う言葉がよく似合う。一見、悪口の様だがそうではない。
昔は惜しんでいられなかった部分を機械化やシステム化が進んで行くことによって昔よりも技術が進歩してきたということに他ならない。
ただ、ある技術を開発した人間と扱う人間の温度が著しく隔たりがある事が問題なのだと思う。
その温度をまとめるのが本来は棟梁であり、建築家であるはずです。
しかし、歴史は深まり、進歩のスピードは速まり、人は変わらぬままそれらを吸収していかなければならない。
ならば、そのスピードに追いつけさえすれば建築の世界は良い方向に向かうのかと言えばそうではない。
物理的なスピードを超えるものを身につけるしかない。
それは結局、持って生まれた才能でも何でもなく一つ一つの自身の生き様を如何に徹底していくかということではないでしょうか?
岡部又左衛門と息子のやりとりを見ていると子供の育て方に正解はなくとも筋道だけは持たないといけないのかもしれないと思いました。
決して子供を褒めない。
良い仕事も認めない。
反抗的になる息子。
それを同じ土俵で抑え込む父。
けれど、息子は気が付く。気付かされる。自発的であったり、他人から言われたりしながら、己の未熟さを目の当たりにする。
けれど、蓄積された不満はそれで収まらない。
その繰り返しが精神に粘りを生むことになる。
親である覚悟とはかくあるべしかと肌が泡立ちました。
勿論、時代が変われば育て方も変わるでしょうが、芯のある人間の生き様というのは心に響くものがあります。
安土城と言えば有名も有名で、その結末もご存知の方が殆どかも知れません。
けれど、もし、知らない人がいたらWikipediaなどで表面をなぞるのではなく、この小説から立ち上ってくる安土城を想像してみるのも楽しいかもしれません。
iPhoneからの投稿火天の城 (文春文庫)/山本 兼一

¥620
Amazon.co.jp
一見してその他の城とは明らかに違う安土城。その城主は言わずとしれた織田信長。
当然、それまでの築城とは全く違う意匠が取り入れられる。
それはつまり大工にしてみれば難題。
が、無理とは言えない。
そこに工夫が産まれる。
この信長と棟梁である岡部又左衛門のやり取りで私は信長に故ジョブズ氏を重ねました。
常人とは違う発想を突きつけ、大工は
如何にそれを形にするか試行錯誤する。
出来ないとは言えない。
どうしたら出来るかを言う。
戸建一つ建てるのに胃がせり上がる思いをしていた私から見ればそのやりとりはまさしく命のやりとりでしかありません。
昨今の建築はものによりけりだけれども、「安易」と言う言葉がよく似合う。一見、悪口の様だがそうではない。
昔は惜しんでいられなかった部分を機械化やシステム化が進んで行くことによって昔よりも技術が進歩してきたということに他ならない。
ただ、ある技術を開発した人間と扱う人間の温度が著しく隔たりがある事が問題なのだと思う。
その温度をまとめるのが本来は棟梁であり、建築家であるはずです。
しかし、歴史は深まり、進歩のスピードは速まり、人は変わらぬままそれらを吸収していかなければならない。
ならば、そのスピードに追いつけさえすれば建築の世界は良い方向に向かうのかと言えばそうではない。
物理的なスピードを超えるものを身につけるしかない。
それは結局、持って生まれた才能でも何でもなく一つ一つの自身の生き様を如何に徹底していくかということではないでしょうか?
岡部又左衛門と息子のやりとりを見ていると子供の育て方に正解はなくとも筋道だけは持たないといけないのかもしれないと思いました。
決して子供を褒めない。
良い仕事も認めない。
反抗的になる息子。
それを同じ土俵で抑え込む父。
けれど、息子は気が付く。気付かされる。自発的であったり、他人から言われたりしながら、己の未熟さを目の当たりにする。
けれど、蓄積された不満はそれで収まらない。
その繰り返しが精神に粘りを生むことになる。
親である覚悟とはかくあるべしかと肌が泡立ちました。
勿論、時代が変われば育て方も変わるでしょうが、芯のある人間の生き様というのは心に響くものがあります。
安土城と言えば有名も有名で、その結末もご存知の方が殆どかも知れません。
けれど、もし、知らない人がいたらWikipediaなどで表面をなぞるのではなく、この小説から立ち上ってくる安土城を想像してみるのも楽しいかもしれません。
iPhoneからの投稿火天の城 (文春文庫)/山本 兼一

¥620
Amazon.co.jp