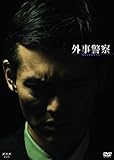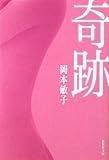「ぬこ」と言う言葉が猫の事を指していると知ったのは最近だ。
慣れというのは不思議なもので、始めは違和感のあったその言葉も、今では猫を見かけると心の中でひっそり「ぬこっ!」と唱える事が増えてきた様にも思える。
この「ぬこ」と言う言葉は不思議なもので、一般化されていないという部分を持つからだろうか、自分が猫に対して、どうしようもなく可愛いという思いを言葉に付加するのにうってつけの様に思えてしまう。
YouTubeなどで猫の動画を観ると、猫でも、猫ちゃんでもなく、時々のニャンコとぬこを使う様になっている。
けれど、その愛らしさは瞬間的なものだと知っている。
だから、私は猫との深い繋がりを感じた事もなければ、苦しさを知る事もない。
以前、動物病院の貼り紙で、「子猫あげます」とあるのを見かけた。
翌日、母親と同じくらいの店長にその事と飼おうかなと言ってみると、
「そんな事、独身の間にしたら結婚できなくなるわよ」と。
つまりは、それ程離れ難く、その魅力は魔性に近い。そんな存在がそばにいたら異性にうつつを抜かしてる暇などなくなってしまうではないか!という事だった。
確かに、とその時首肯した事が正しかったかどうかの証明は未だ叶わない。
さて、横道にそれたがこの作品。
猫との物語であるが、私には命の物語とも読めた。
蟻は殺しても罪には問われない。
けれど、猫ならその行為に対する批判は尽きる事がないだろう。
同じ命。
形とか大きさ、数、感情の有無によって命の質は変わるだろうか?
否、変わらない。
同じ命でも質や価値が変わるというのは、常に言い訳でしかない。
私に言わせれば、菜食主義を豚や牛を殺さずにすむからと勧める事もそれに等しい。
植物なら搾取しても良いのか?と。
調べてみれば、この作者、僧侶だったらしい。
つまりは命を扱う本職だ。
脳髄が痺れる様な描写の数々に動悸が早くなる。嫌な汗でもかくようだ。
しかし、こんな書き方しかなかったのだろうとしか言えない小説だ。
ここにあるのは良し悪しの評価ではなく、生命の事実なのだと思う。
iPhoneからの投稿
猫鳴り (双葉文庫)/沼田 まほかる

¥550
Amazon.co.jp
慣れというのは不思議なもので、始めは違和感のあったその言葉も、今では猫を見かけると心の中でひっそり「ぬこっ!」と唱える事が増えてきた様にも思える。
この「ぬこ」と言う言葉は不思議なもので、一般化されていないという部分を持つからだろうか、自分が猫に対して、どうしようもなく可愛いという思いを言葉に付加するのにうってつけの様に思えてしまう。
YouTubeなどで猫の動画を観ると、猫でも、猫ちゃんでもなく、時々のニャンコとぬこを使う様になっている。
けれど、その愛らしさは瞬間的なものだと知っている。
だから、私は猫との深い繋がりを感じた事もなければ、苦しさを知る事もない。
以前、動物病院の貼り紙で、「子猫あげます」とあるのを見かけた。
翌日、母親と同じくらいの店長にその事と飼おうかなと言ってみると、
「そんな事、独身の間にしたら結婚できなくなるわよ」と。
つまりは、それ程離れ難く、その魅力は魔性に近い。そんな存在がそばにいたら異性にうつつを抜かしてる暇などなくなってしまうではないか!という事だった。
確かに、とその時首肯した事が正しかったかどうかの証明は未だ叶わない。
さて、横道にそれたがこの作品。
猫との物語であるが、私には命の物語とも読めた。
蟻は殺しても罪には問われない。
けれど、猫ならその行為に対する批判は尽きる事がないだろう。
同じ命。
形とか大きさ、数、感情の有無によって命の質は変わるだろうか?
否、変わらない。
同じ命でも質や価値が変わるというのは、常に言い訳でしかない。
私に言わせれば、菜食主義を豚や牛を殺さずにすむからと勧める事もそれに等しい。
植物なら搾取しても良いのか?と。
調べてみれば、この作者、僧侶だったらしい。
つまりは命を扱う本職だ。
脳髄が痺れる様な描写の数々に動悸が早くなる。嫌な汗でもかくようだ。
しかし、こんな書き方しかなかったのだろうとしか言えない小説だ。
ここにあるのは良し悪しの評価ではなく、生命の事実なのだと思う。
iPhoneからの投稿
猫鳴り (双葉文庫)/沼田 まほかる

¥550
Amazon.co.jp