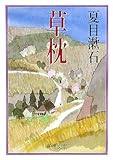知らない事なんて死ぬほどある。
と、思っている以上にあると思っている以上に…。
という、言い回しをいくらしたところで自覚している以上には知らない事はないと思ってしまっている。
そんな自分の無知さに迫る歴史物語。
アイヌは自然と共に生活している、ネイティブアメリカンみたいな存在。独特の文化を持って生きている人々。
その位の認識しかなかったが、これを読んで彼らの虐げられてきた歴史に愕然としてしまった。
北海道は歴史が浅いというものの、それは和人にとっての歴史であって、アイヌの歴史ではない。
当時の感覚を推し量れば、文明を持たない土着民を文明人がある部分では家畜として虐げ、ある部分では人として虐げた。
タバコや酒、そして貨幣と言った新しい価値観を組み込み、和人側に都合の良いようにシステムを作り上げて行く。
歴然とした武力の差でそれを受け入れるしか生き延びていく道がなくなってしまう。
けれど、不満は生まれ、鬱積し、いずれ爆発する。
何とも言えない物語。
無知である事が差別を増長していると気付かされたきつい一冊となった。
蝦夷地別件〈上〉 (新潮文庫)/船戸 与一

¥740
Amazon.co.jp
蝦夷地別件〈中〉 (新潮文庫)/船戸 与一

¥820
Amazon.co.jp
蝦夷地別件〈下〉 (新潮文庫)/船戸 与一

¥860
Amazon.co.jp
と、思っている以上にあると思っている以上に…。
という、言い回しをいくらしたところで自覚している以上には知らない事はないと思ってしまっている。
そんな自分の無知さに迫る歴史物語。
アイヌは自然と共に生活している、ネイティブアメリカンみたいな存在。独特の文化を持って生きている人々。
その位の認識しかなかったが、これを読んで彼らの虐げられてきた歴史に愕然としてしまった。
北海道は歴史が浅いというものの、それは和人にとっての歴史であって、アイヌの歴史ではない。
当時の感覚を推し量れば、文明を持たない土着民を文明人がある部分では家畜として虐げ、ある部分では人として虐げた。
タバコや酒、そして貨幣と言った新しい価値観を組み込み、和人側に都合の良いようにシステムを作り上げて行く。
歴然とした武力の差でそれを受け入れるしか生き延びていく道がなくなってしまう。
けれど、不満は生まれ、鬱積し、いずれ爆発する。
何とも言えない物語。
無知である事が差別を増長していると気付かされたきつい一冊となった。
蝦夷地別件〈上〉 (新潮文庫)/船戸 与一

¥740
Amazon.co.jp
蝦夷地別件〈中〉 (新潮文庫)/船戸 与一

¥820
Amazon.co.jp
蝦夷地別件〈下〉 (新潮文庫)/船戸 与一

¥860
Amazon.co.jp