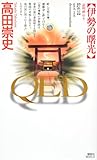久々の『山口雅也』
この作家さんは質の高いミステリーが多く大好きなんですが、
なかなか新作を発売しないんですよね。
『生ける屍の死』なんて、本当最高でした。
お見合いシリーズも同じ作家が書いたとは思えないほど、
ほんわかしていて面白い。
さて、本作。
遊びをテーマに書き連ねた短編集。
この中で、すごろくの話があるのですが、
場所がインドなんです。
読んでいて、もう、インドの事ばかり考えてしまいました。
内容はインドの熱気が冷たく感じる程の終わり方で大変楽しめたのですが、
それよりも心はインド。
バラナシの火葬場やガート、サドゥ、乞食、雑踏、喧騒、人間・・・・・
次に行けるのはいつになるんだろうなと思うと
なかなか行けそうにないのが辛いところです。
でも、行けるとしたら、つぎは南インドへ行ってみたい。
でも、北のダージリンとかダラムサラにも行きたいな。
そうすると、一周することになるのか。
一体何日あればいいのかな。
ん~、二ヵ月。短くて。笑。
そういえば、私はかくれんぼがもの凄く得意で、
みつからない事が多くありました。
あまりにみつからないから飽きてしまう。
探す方も飽きてしまう。
だから、いつからか本気で隠れる事はしなくなりました。
でも、もしも、
見つかるまで出てきてはいけないというルールがあったら、
私はどのくらい行方不明になっていたのでしょうか?
現実的にはその日の夜が限界でしょうが、
それでも、その先を考えるとすこし背筋に冷たいものが走るのは、
恐らく、遊びと言うもがはらんでいる狂気性によるものでしょう。
PLAY プレイ (講談社文庫)/山口 雅也

¥730
Amazon.co.jp
生ける屍の死 (創元推理文庫)/山口 雅也

¥1,260
Amazon.co.jp


にほんブログ村
この作家さんは質の高いミステリーが多く大好きなんですが、
なかなか新作を発売しないんですよね。
『生ける屍の死』なんて、本当最高でした。
お見合いシリーズも同じ作家が書いたとは思えないほど、
ほんわかしていて面白い。
さて、本作。
遊びをテーマに書き連ねた短編集。
この中で、すごろくの話があるのですが、
場所がインドなんです。
読んでいて、もう、インドの事ばかり考えてしまいました。
内容はインドの熱気が冷たく感じる程の終わり方で大変楽しめたのですが、
それよりも心はインド。
バラナシの火葬場やガート、サドゥ、乞食、雑踏、喧騒、人間・・・・・
次に行けるのはいつになるんだろうなと思うと
なかなか行けそうにないのが辛いところです。
でも、行けるとしたら、つぎは南インドへ行ってみたい。
でも、北のダージリンとかダラムサラにも行きたいな。
そうすると、一周することになるのか。
一体何日あればいいのかな。
ん~、二ヵ月。短くて。笑。
そういえば、私はかくれんぼがもの凄く得意で、
みつからない事が多くありました。
あまりにみつからないから飽きてしまう。
探す方も飽きてしまう。
だから、いつからか本気で隠れる事はしなくなりました。
でも、もしも、
見つかるまで出てきてはいけないというルールがあったら、
私はどのくらい行方不明になっていたのでしょうか?
現実的にはその日の夜が限界でしょうが、
それでも、その先を考えるとすこし背筋に冷たいものが走るのは、
恐らく、遊びと言うもがはらんでいる狂気性によるものでしょう。
PLAY プレイ (講談社文庫)/山口 雅也

¥730
Amazon.co.jp
生ける屍の死 (創元推理文庫)/山口 雅也

¥1,260
Amazon.co.jp
にほんブログ村