ジャン・ジュネについて知るところは全くない。
この本のあらすじに書かれていた、
「終身禁固となるところをサルトルらの運動によって特赦を受けた・・・・」
という部分に惹かれて読んでみる事に。
しかし、この本の感想を書くのは難しい。
なぜならその内容自体は泥棒として過ごした彼の半生でしかないからだ。
泥棒としての手腕や功績はこの本では余り重要な要素ではない。
彼の半生、生きてきた軌跡自体でしかない。
放物線や流線型を美しいと感じるようには
彼の人生を美しいとは思わない。
むしろ退屈ですらある。
泥棒である事、父親のいない子供、男色家・・・
思春期ならもの凄い影響をこの本から得られたかもしれないが、
刺激物の多い現代では珍しくもないし、
どんなに悲惨な状況だったとしても、
今の私にこの物語は退屈でしかない。
けれど、読むのをやめようとは思わない。
それは言葉を発する角度が異様だからだ。
その言葉に突き刺さるものもなければ、
感銘を受ける事もない。
だからこそ、余計に彼の言葉の異形さに心奪われる。
言葉は本来意味を持つ。
そして、その意味をつなぎ合わせる事で文章となり、
より複雑化した事象を読み手ないしは聞き手に伝えるものであるはずだ。
ここでは、意図してか意図せずか、
その意味自体はおおよそ空白に近い。
当然、読んで意味もわかり情景も浮かぶ、
けれど、そこで語られる事自体はそれほどなにかしらかを想起させるものではない。
その意味にたどり着くまでの過程に退廃的というには浅はかな美しさがある。
物語としては私は面白いとは思わない。
けれど、何かを説明する際、回りくどさを感じはするものの、
文章として芸術にすがりつくような印象がある。
その回りくどさは、読み手に理解を強要する。
なめまわすような読書体験とでもいえばいいのだろうか。
その結果、甘いも辛いも関係ない。
それは口に放りこんでしまったものの責務だろう。
異様な作家の書いた異様な読書体験は
黒い薔薇の園に迷い込んでしまったような感触を
リアルな手ごたえと共に終えることになる。
恐らくはこの本でしか得る事が出来ない物がある。
ここまで退屈だと吹聴しておきながらも、
人の意見を聞かずにはいられない。
しかして、
迷い込んだ黒薔薇の園から抜け出せたのかどうかも
定かでない者がこの本を他人に勧めていいのかもわからないが。
泥棒日記 (新潮文庫)/ジャン ジュネ

¥740
Amazon.co.jp

にほんブログ村
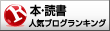
この本のあらすじに書かれていた、
「終身禁固となるところをサルトルらの運動によって特赦を受けた・・・・」
という部分に惹かれて読んでみる事に。
しかし、この本の感想を書くのは難しい。
なぜならその内容自体は泥棒として過ごした彼の半生でしかないからだ。
泥棒としての手腕や功績はこの本では余り重要な要素ではない。
彼の半生、生きてきた軌跡自体でしかない。
放物線や流線型を美しいと感じるようには
彼の人生を美しいとは思わない。
むしろ退屈ですらある。
泥棒である事、父親のいない子供、男色家・・・
思春期ならもの凄い影響をこの本から得られたかもしれないが、
刺激物の多い現代では珍しくもないし、
どんなに悲惨な状況だったとしても、
今の私にこの物語は退屈でしかない。
けれど、読むのをやめようとは思わない。
それは言葉を発する角度が異様だからだ。
その言葉に突き刺さるものもなければ、
感銘を受ける事もない。
だからこそ、余計に彼の言葉の異形さに心奪われる。
言葉は本来意味を持つ。
そして、その意味をつなぎ合わせる事で文章となり、
より複雑化した事象を読み手ないしは聞き手に伝えるものであるはずだ。
ここでは、意図してか意図せずか、
その意味自体はおおよそ空白に近い。
当然、読んで意味もわかり情景も浮かぶ、
けれど、そこで語られる事自体はそれほどなにかしらかを想起させるものではない。
その意味にたどり着くまでの過程に退廃的というには浅はかな美しさがある。
物語としては私は面白いとは思わない。
けれど、何かを説明する際、回りくどさを感じはするものの、
文章として芸術にすがりつくような印象がある。
その回りくどさは、読み手に理解を強要する。
なめまわすような読書体験とでもいえばいいのだろうか。
その結果、甘いも辛いも関係ない。
それは口に放りこんでしまったものの責務だろう。
異様な作家の書いた異様な読書体験は
黒い薔薇の園に迷い込んでしまったような感触を
リアルな手ごたえと共に終えることになる。
恐らくはこの本でしか得る事が出来ない物がある。
ここまで退屈だと吹聴しておきながらも、
人の意見を聞かずにはいられない。
しかして、
迷い込んだ黒薔薇の園から抜け出せたのかどうかも
定かでない者がこの本を他人に勧めていいのかもわからないが。
泥棒日記 (新潮文庫)/ジャン ジュネ

¥740
Amazon.co.jp
にほんブログ村