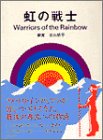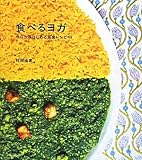本日、念願の山ヨガに行って気ました。
凄く気持ちが良かったし、
脚がガクガクブルブルするほど疲れてしまったけれど、
良い時期に良い経験をさせてもらいました。
にしても、
朝5:30起きは夜行性の私にはかなり辛いかなと思っていたものの、
余程楽しみだったのか、ぱっちりと目が覚めました。
場所は高尾山。
ケーブルカーで昇り、
一時間半程度山を登り、
適度な広場でヨガ。
お昼近かったからか、
登山客が多く、
その広場で皆さんお休みになられるので、
申し訳ないなと思ってしまいました。
なにせ人数が20人くらい。
今までで最大の規模です。
私的には軽いフェス状態。
でも、これで、山でやりたいヨガと言うのは、
人のいない場所でやりたいって事だと気付きました。
次にやる際はキャンプにDVDでも持っていくか、
やはり、そろそろ、自主練を始めるかなんかしないと
やってても楽しめなさそう。
にしても、今日の流れは早かった。
前半と後半でトレーナーが変わって、
後半の先生のスピード感は今までにないものでした。
これには結構衝撃を受けて、
実際教えてもらってる時はゆっくりだけど、
先生方が自分でやってる時ってのは、
どのくらいのスピードでやるんだろう?
と疑問が浮かびました。
そうそう、
あのポーズの順番とかって決まってるのかしら???
なんか、みんなどこも似たような気がする。
いや、似て非なるんですけど実際は。
教え方も人によって当然違うけれど、
どれが良いとか悪いとかってなくて、
それぞれの解釈、身体との会話の深度や幅が違うだけで、
ずいぶんとポーズをとる際の影響が変わってくる。
その影響で、ポーズの限界があからさまに変わるから面白い。
高尾山
人多っ!!!!!
凄く気持ちが良かったし、
脚がガクガクブルブルするほど疲れてしまったけれど、
良い時期に良い経験をさせてもらいました。
にしても、
朝5:30起きは夜行性の私にはかなり辛いかなと思っていたものの、
余程楽しみだったのか、ぱっちりと目が覚めました。
場所は高尾山。
ケーブルカーで昇り、
一時間半程度山を登り、
適度な広場でヨガ。
お昼近かったからか、
登山客が多く、
その広場で皆さんお休みになられるので、
申し訳ないなと思ってしまいました。
なにせ人数が20人くらい。
今までで最大の規模です。
私的には軽いフェス状態。
でも、これで、山でやりたいヨガと言うのは、
人のいない場所でやりたいって事だと気付きました。
次にやる際はキャンプにDVDでも持っていくか、
やはり、そろそろ、自主練を始めるかなんかしないと
やってても楽しめなさそう。
にしても、今日の流れは早かった。
前半と後半でトレーナーが変わって、
後半の先生のスピード感は今までにないものでした。
これには結構衝撃を受けて、
実際教えてもらってる時はゆっくりだけど、
先生方が自分でやってる時ってのは、
どのくらいのスピードでやるんだろう?
と疑問が浮かびました。
そうそう、
あのポーズの順番とかって決まってるのかしら???
なんか、みんなどこも似たような気がする。
いや、似て非なるんですけど実際は。
教え方も人によって当然違うけれど、
どれが良いとか悪いとかってなくて、
それぞれの解釈、身体との会話の深度や幅が違うだけで、
ずいぶんとポーズをとる際の影響が変わってくる。
その影響で、ポーズの限界があからさまに変わるから面白い。
高尾山
人多っ!!!!!