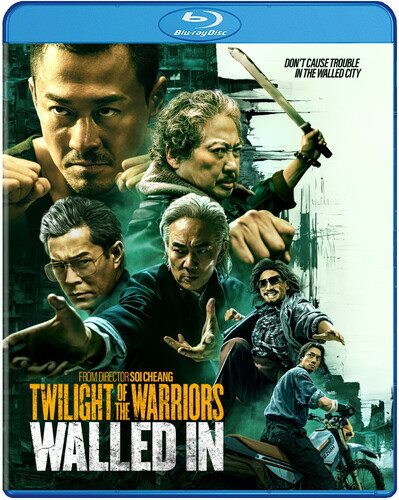久々のアケコンの新作、プロゲーマーのネモ氏監修のM-GAMING A01を購入した。
すでに完成品をレビューしている方らがいるので、詳しい解説は省いて使用感を中心に述べていこうと思う。まずは最も気になるレバーとボタンの感触であるが、これがかなり良い。現在所有しているいずれのフラッグシップとも異なる感触であるが、それらにも負けず劣らずの操作感であり、音もかなり吸収してくれている感じだ。
ロードバイクのフレームと同様、アケコンもレバーやボタンのフィーリングは、その殆どがガワと天板の剛性と素材で決まる。つまり、全く同じ三和電子のレバーを使用していても、ガワによって操作感覚が全く異なってくる訳だ。なので、いくら三和電子を使用していても、ガワがポンコツであれば意味がないのである。
そこで、こちらのA01のガワであるが、まずネモ氏自身が自身の動画で触れているように、完全に大阪の工場で作られた日本製である。天板と底面以外は完全に金属製の一体成形であり、重量と剛性感、そしてもちろん作りの精巧さは申し分ない。重量は3.3Kgほどであり、Obsidian2とほぼ同様である。これ以上軽くても重くてもダメなので、この辺りが理想なのだろう。
天板は金属ではなくアクリル製である。この部分が操作系統の要とも言えるので、非常に重要なパーツであると言えるのだが、前述したようになかなか音を吸収してくれている感じで、個人的にはかなりお気に入りのフィーリングだ。Obsidianや旧Pantheraのように2重構造になってはいない感じなので、若干の空洞感が気にならない事はないのであるが、そこまで気にする人も居ないだろう。
レイアウトに関しては、見ての通りスト6用のボタン配置となっている。ただ、通常の8ボタンとしての使用でも、他のボタンが邪魔になる事もないので、問題になる事はないだろう。ただ、左下のボタンがキックボタンに自然な形で配置されているので、最初は押し間違えがあったのも確かである。
構造上、PSやオプションボタン類が右上側面奥になってしまっているのは若干やりづらい。また、天板上部にかなりのスペースがあるため、机置きにする場合はケーブルの関係もあり、そこそこスペースがないとコードが干渉してしまうだろう。なので、個人的には膝置き前提な作りとなっていると思う。
基板はもちろん最新のBrook基板であるGen-5X使用である。当然多機種対応であり、さらにはUFBとは異なり一度認識したら、あとは自動で対応してくれるため、UFBのSwitchのようにいちいち特定のボタンを押しながらセット必要がないのはとても便利だ。Switchは未だにこれぞという決定的なアケコンがないため、このアケコンの存在は非常に有難いと言える。Switch2発売直前なのも尚更だ。
価格は49500円とまあまあするが、Victrixなどは5万超えだし、NaconのDAIJAも4万円台だ。Obsidaian2も発売当初は5万弱したし、ほぼ同価格でこの性能かつマルチ機種対応であれば、コスパはかなり高いと言えるだろう。個人的にはこれまでの中でも最上位に位置するほどの造りだと思う。