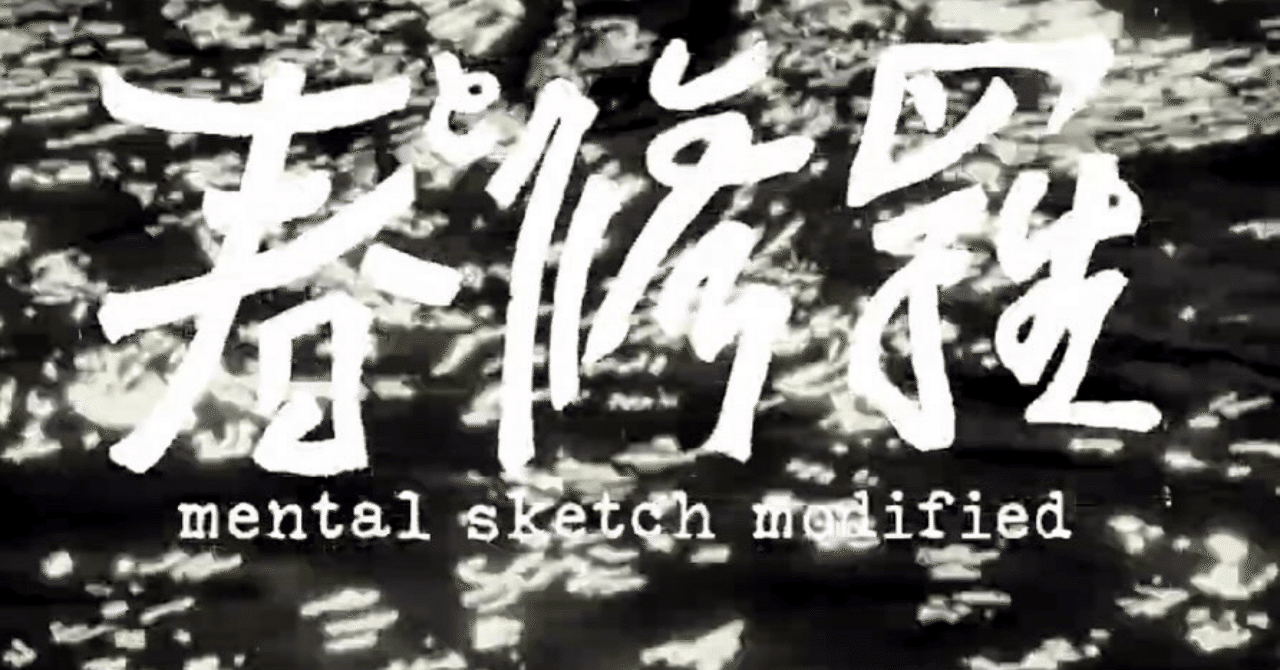10数年前、とある方を講演会の
講師としてお呼びいたしました。
須藤晃さん。
あの尾崎豊を育てた音楽プロデューサーです。
今まで会った方の中で最も眼光が鋭く、
控え室でお会いした時の衝撃は
今でも鮮明に思い出されます。
その眼光よりも印象に残っているのが
須藤さんのお話。
須藤さん曰く、
「人生はボートを漕ぐのと同じだ。
ボートは後ろ向きに漕いで前に進む。
人生もそれと一緒。
一寸先は闇って聞いたことある?
人生はどんなに前を見ても
未来はわからない。
人間っていうのは、
自分のしてきた過去を見ながら、
見えない未来を予測して進むもんなんだ。
ボートの航跡を見て漕ぐようにね。
後ろはネガティブな感じもあるけど、
自分のやってきたことに向き合って
一生懸命やればそれが結果的に
前に進むことになる。」
それまでの自分には全くない考えで、
しかしながら妙に納得しました。
それからは生徒に「前を向け」とか言わなくなり
おりを見ては須藤さんの話を紹介しています。
【須藤晃氏インタビュー記事】※ボートの話は載っていません
ここからは私の勝手な解釈ですが、、、
ボートって一人で漕ぐばかりではないですよね?
二人の時もあれば、
多い時だと9人で力を合わせる競技もあります。
つまり、人生も一人で進むわけではなく、
時には二人、
あるいは何人もの助けを借りながら進む
のだと思います。
漕ぎ手が互いに寄り添い、
そして息を合わせて同じ方向に向かっていく。
波風ある時は特にそれが必要だし、
頼っていいってことなんだと。
「人生は不安定な航海だ」と
シェイクスピアは言いました。
でも隣の人がいれば、
仲間がいればその航海も怖くはないはずです。
生徒にはそんな出会いがあればいいと
常に願っています。