 」について書いて
」について書いてみたいと思います。
花東とは2年前のセンバツで、雄星を擁し
て準優勝した花巻東
 のことです。
のことです。私の地元岩手県では、今では高校野球
においてはトップクラスのチームです

2年前は雄星を軸に、全国制覇を目指し
ましたが残念ながらその夢は叶いません
でした

しかし、このチームのすごいところは
日本一当たり前のことを当たり前に
やることを徹底しようとしてきたところ。
そして、野球の実力も全国の強豪と
肩を並べるほどになったわけです。
確かに、2年前は雄星という超高校級
左腕の存在は大きかったと思います。
でも、野球は一人のスターが存在する
だけで勝てるほど甘いものではありません。
花東の躍進の一因として
「人間力育成」
が開花したということは認めざるを得ません。
現監督の佐々木監督が、
「我々は野球ロボットを養成している訳ではない」
「将来、社会に出て立派に責任を果たせる人間を育成する」
という考えを軸に愚直なまでに、選手
たちに当たり前のことを徹底させました。
「日本一の練習をする」
「日本一のあいさつをする」
「日本一の整理整頓をする」
「日本一の・・・・・・・・・・・・・・」。
野球以前に、一人の人間として、立派に
行動できる「人間力」を身に付けること。
それが、野球にも必ず生きる。
そう佐々木監督は考えたのだと思います。
当たり前のことを当たり前にやるって
非常に難しいことですよね。
疲れること、面倒なこと。
誰でもそう感じることを徹底的にやる
ことで、花東は強く生まれ変わって
いったのだと思います。
確かに子供たちの野球に子供らしさを
失わせるほどの徹底はどうかと思います。
しかし、花東野球は本質を追求している
という部分では非常に参考になります。
人間力が野球人としての能力を引き出し、
また社会で生きていく力となる・・・。
特に少年スポーツにおいては、そのスポ
ーツを楽しみ、その中でよき仲間を作り、
協力・助け合い・思いやりの精神を育む。
子供にとって、社会生活の入口とでもいう
べき少年スポーツでの活動。
その中で子供たちが、大人の偏った価値
観に影響されるのを放ってはおけないと
いう気持ちでこのブログを書いています。
このブログでも今までも再三のごとく書い
てきましたが、偏った価値観を持たない
ためにも、大人はやはり
「自分磨き


 」
」が必要です。
やってみると意外と楽しいものですよ、
自己成長につきあえるってことは

ちなみに今日の明治神宮大会決勝で、
東北代表の光星学院が愛工大名電を
下して優勝しました

よって、来春のセンバツは東北の枠が
1つ増えることになり、花東の出場の
可能性が高くなりました

今年の夏の帝京戦の悔しさをセンバツ
で晴らして欲しいです

エース大谷の復活を期待したいですね










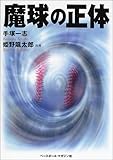




















 」
」








