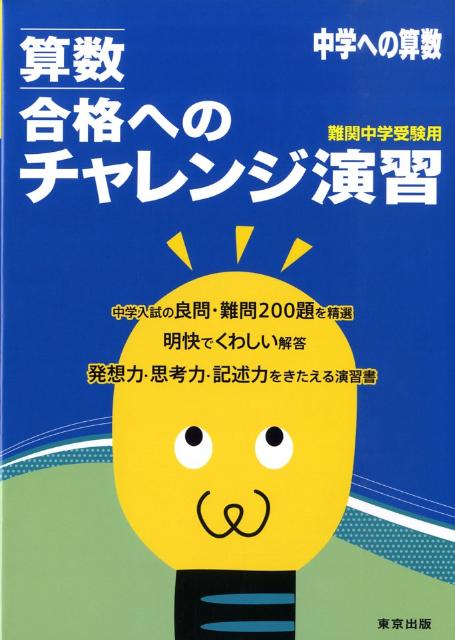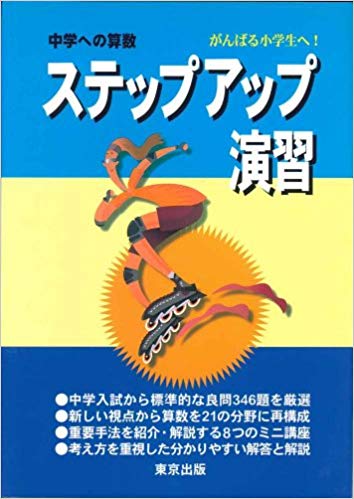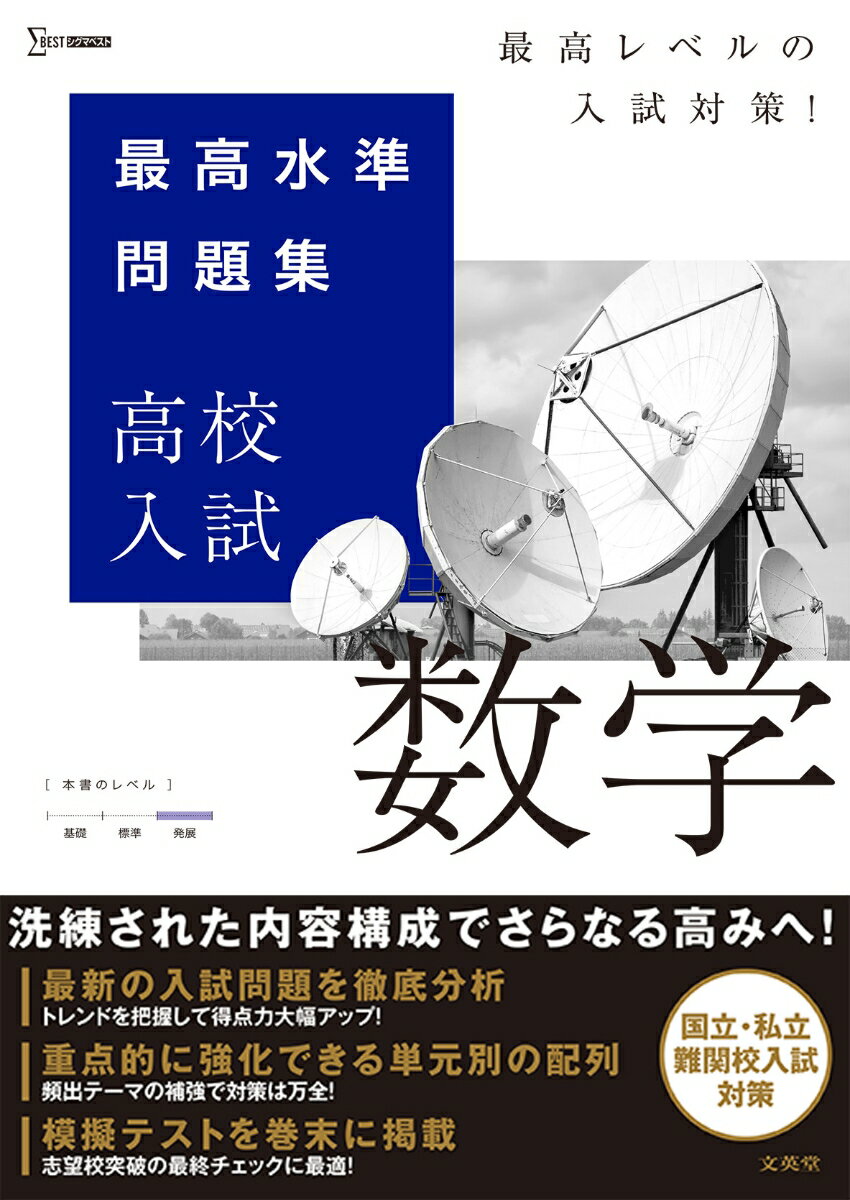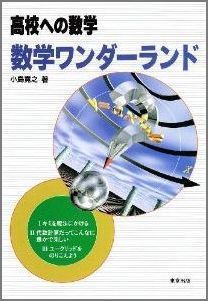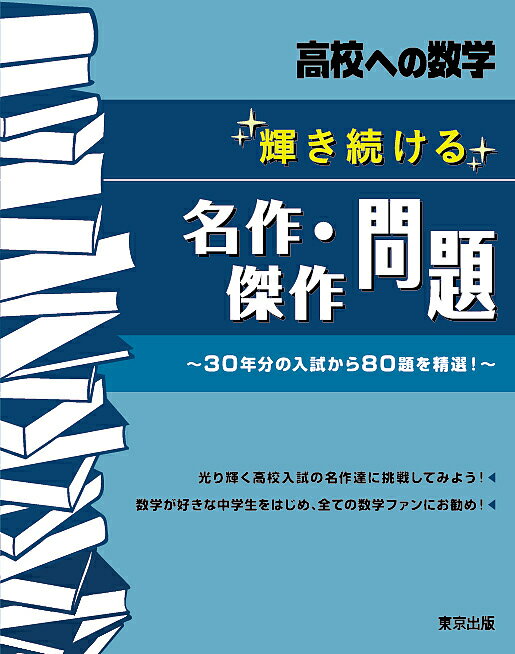次の空欄にあてはまる数を答えなさい。
0、1、2、3、4、5が書かれた6枚のカードがあります。この中から3枚を使って3桁(けた)の整数をつくるとき、できる3桁の整数は全部で[ア]通りあります。このうち、3の倍数であるものは全部で[イ]通りあります。ただし、百の位には、0が書かれたカードは使えません。
(前半について)
ほんの数秒で答えが求められますね。
百の位の数が0以外の5通りあり、そのそれぞれに対して、十の位の数が百の位の数以外の5通りあり、そのそれぞれに対して、一の位の数が百の位の数と十の位の数以外の4通りあるから、3桁の整数は全部で
5×5×4
=100通り
できます。
なお、3桁の整数の個数から2桁の整数(デジタル表示で考え、百の位が0の整数)の個数を引いて、
6×5×4-(1×)5×4
=120-20
=100通り
とすることもできます。
この問題をこの考え方で解くのは面倒なだけですが、あえて余分なものをカウントして、その後でそれを取り除くという考え方は大切です。
(後半について)
まず、カードの数字を3で割った余りで分類します。
(あ)3で割ると1余る数・・・1、4
(い)3で割ると2余る数・・・2、5
(う)3で割り切れる数・・・0、3
3桁の整数が3の倍数となる組み合わせは、(あ)、(い)、(う)のそれぞれのグループから1個ずつ使った場合(P)と(あ)、(い)、(う)の同一のグループから3個使った場合(Q)になりますが、この問題では、(Q)の場合はありえませんね。
まず、使う3つの数の選び方を考えます。
(あ)からどの数字を選ぶかで2通りあり、そのそれぞれに対して、(い)からどの数字を選ぶかで2通りあり、そのそれぞれに対して、(う)からどの数字を選ぶかで2通りあるから、全部で
2×2×2
=8通り
あります。
次に、選んだ3つの数の並べ方を考えると、3×2×1=6通りあります。
したがって、3桁以下の3の倍数(実際には、3桁と2桁の3の倍数)は
8×6
=48通り
あります。
このうち2桁の整数(デジタル表示で考え、百の位が0の整数)が何通りあるか考えます。
まず、使う3つの数の選び方を考えます。
(う)からどの数字を選ぶかで1通り(0を選ぶことに確定していますね)あり、そのそれぞれに対して、(あ)からどの数字を選ぶかで2通りあり、そのそれぞれに対して、(い)からどの数字を選ぶかで2通りあるから、全部で
(1×)2×2
=4通り
あります。
次に、選んだ3つの数の並べ方を考えると、(1×)2×1=2通りあります。
したがって、2桁の3の倍数は
4×2
=8通り
あります。
結局、3桁の3の倍数は
48-8
=40通り
あります。
詳しく説明すると長々しいですが、実際には、2×2×2×3×2×1-2×2×2×1=40通りというようにできるので、解くのに30秒もかからないでしょう。
各位の数の和が3の倍数となるものの組合せを書き出した後その並べ替えを考える地道な解法で解くこともできますが、最難関中学校の受験生であれば、上の解法を当然マスターしておくべきでしょう。
なお、下の灘高校の問題の解説では、地道な解法も紹介しています(メインの(3)の問題が解きやすいので、地道な解法を利用しています)。