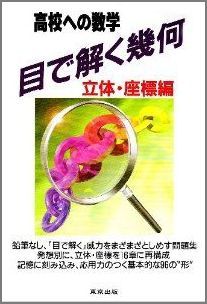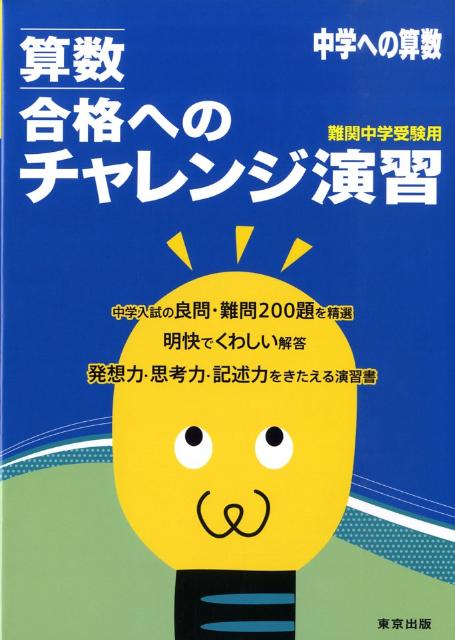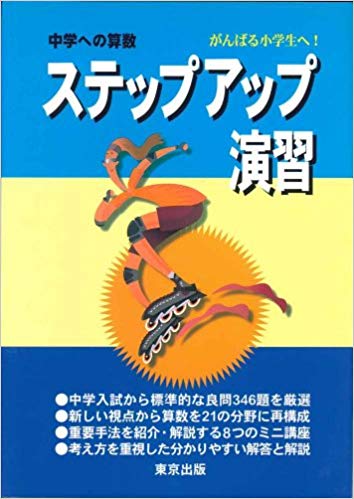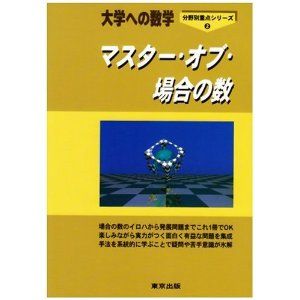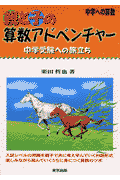図において、△ABCはAC=10、BC=4、∠ACB=90°の直角三角形で、△ABDはAD=BD、∠ADB=90°の直角二等辺三角形である。線分BDと線分ACの交点をE、直線ABと直線CDの交点をFとするとき、次の問に答えよ。
(1)省略
(2)省略
(1)はルート(√)が絡むので省略、(2)は4点A、B、C、Dが同一円周上の点であることと相似を利用すれば簡単に解けますが、小学生には厳しいですし、メインの(4)を解くのに(2)を経由しなくても普通に解けるので省略、(3)は小学生でも簡単に解けます(以下の解説のプロセスで答えがすぐに出せます)が、メインの(4)を解くのにこれを経由しなくても解けるので省略しています。
三角形ABCの面積は4×10×1/2=20となります。
ここで、三角形ABCを辺ABに関して折り返した後、斜めの正方形・直角二等辺三角形の処理(水平な正方形を作出)を行います。
三平方の定理を知らないふりをして解くので一工夫必要ですが、最難関中学校の受験生や算数オリンピックにチャレンジする子などにとっては常識と言えるレベルの処理です(東海中学校2016年算数第8問、灘中学校2023年算数1日目第10問、第28回ジュニア算数オリンピックトライアル問題9(ジュニア算オリ2024年トライアル問題9))し、最難関中学校でなくても同様の処理を要求する問題が普通に出されています(六甲学院中学校2016年A算数第5問)。

三角形ABDの面積は{(4+10)×(4+10)-4×10×2}/4=29となります。
図のように垂直な線を引くと、三角形ABDと三角形ABCは底辺(AB)が共通だから、高さの比(DG:CH)は面積の比と等しくなり、29:20となります。
DGの長さを[29]とすると、三角形ABDが二等辺三角形であることから、AG=GB=[29]となります。
また、CH=[20]となり、2つの直角三角形ABCとCBHは相似(角度に記号をつければわかりますね)で、辺の比(中:小)が10:4=5:2だから、BH=[20]×2/5=[8]となります。
さらに、三角形FDGと三角形FCHのピラミッドう相似(相似比はDG:CH=29:20)に着目すると、HF=([29]-[8])×20/(29-20)=[140/3]となり、BF=[140/3]-[8]=[116/3]となります。
三角形ABCと三角形BCFは、高さが等しく、底辺の比がAB:BF=([29]×2):[116/3]=3:2となるから、面積比も3:2となります。
したがって、三角形BCFの面積は20×2/3=40/3となります。
因みに、仮に三平方の定理を知っていて、ルートの計算ができるとしても、上のように解いたほうが計算が楽になる問題でした。