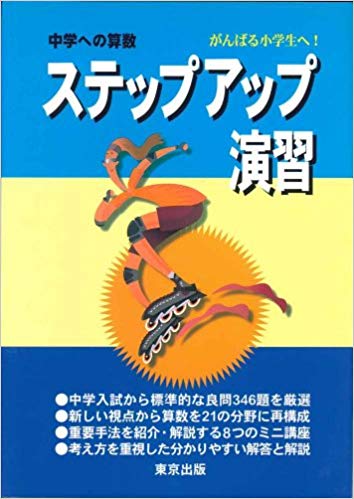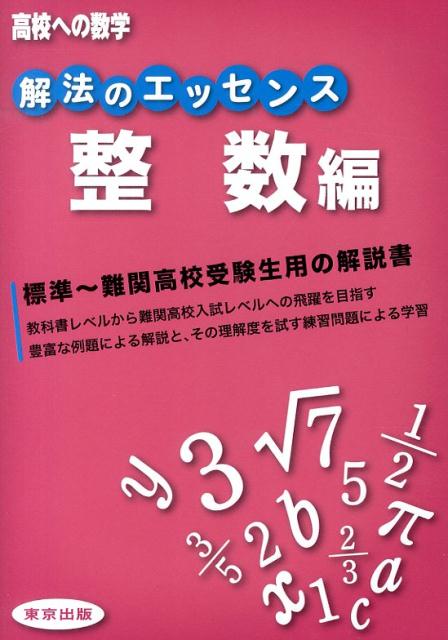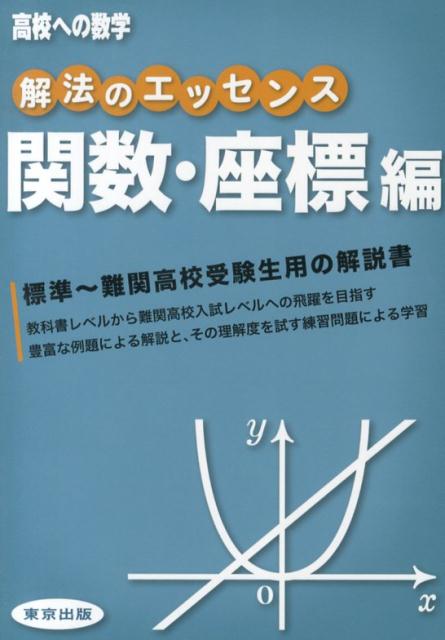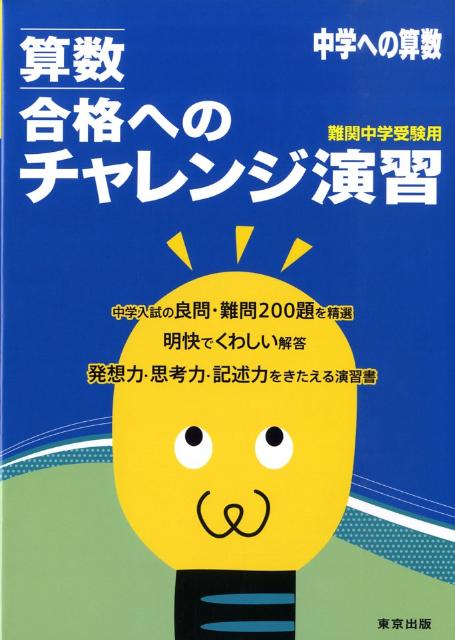47人で動物園に行く計画を立てました。45人以上だと団体料金で入園することができ、全員の入園料が2割引きになります。当日に欠席者が出て、団体料金で入園することができなかったため、予定より全体で672円多くかかりました。欠席者は何人でしたか。また、割引き前の1人あたりの入園料は何円ですか。ただし、この入園料は300円以上1000円以下です。
(式と計算と答え)
条件が足りなさそうな文章題だから、整数条件を利用することを考えるとよいでしょう。
整数条件を利用した後すぐに7パターンを調べつくしてもよかったのですが、少し楽をしようとして、上限と下限をチェックしたら、見事に空振りさせられました。
何も考えずに調べつくせばよかったですね。
因みに、求めた答えの人数では、45人の団体として料金を支払ったほうが得(神戸女学院中学部2008年算数第2問を参照)で、微妙な感じでした。
詳しくは、下記ページで。