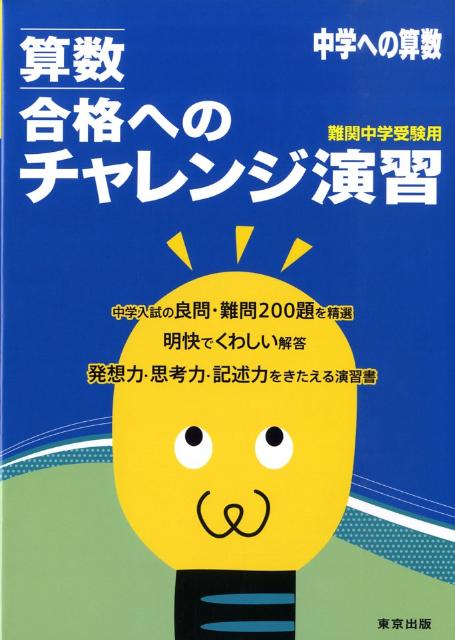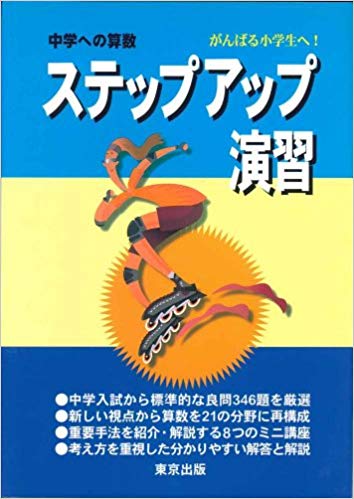7個の数字2、3、4、5、6、7、8から異なる4個の数字を選んで並べ4桁の数ABCDを作り、選ばなかった3個の数字を並べ3桁の数EFGを作ったところ、ABCD÷EFG=9となりました。
(1)このような4桁の数ABCDのうち、A、B、C、Dのいずれかが8であるものはただ1つです。その数を答えなさい。
(2)このような4桁の数ABCDのうち、A、B、C、Dのいずれも8でないものは全部で2個あります。それらの数を答えなさい。
記事のタイトルでは一応覆面算としていますが、数の性質の問題です。
従来1日目に出されたタイプの問題ですが、(2)を処理するのに若干時間がかかるので、2日目に出されたのでしょうね。
ただ、2日目の最後の問題としてはずいぶん軽い問題のような気がします。
答えの個数が明記されているため、指定された個数の答えを見つければ、作業を途中で打ち切ることができますからね。
まず9の倍数判定法を利用(上の2017年の問題と同様の手法ですね)すると、E、F、Gの和がすぐに確定します。
与えられた式を筆算の形にして考えますが、その際、かけ算ではなく引き算で処理するのがポイントです。
9倍する計算において、10倍したものからもとの数を引くという計算の工夫と同じ作業です。
筆算をよく観察すると、A、B、C、D、E、F、Gに関する条件があぶりだせるので、調べる場合が激減します。
詳しくは、下記ページで。