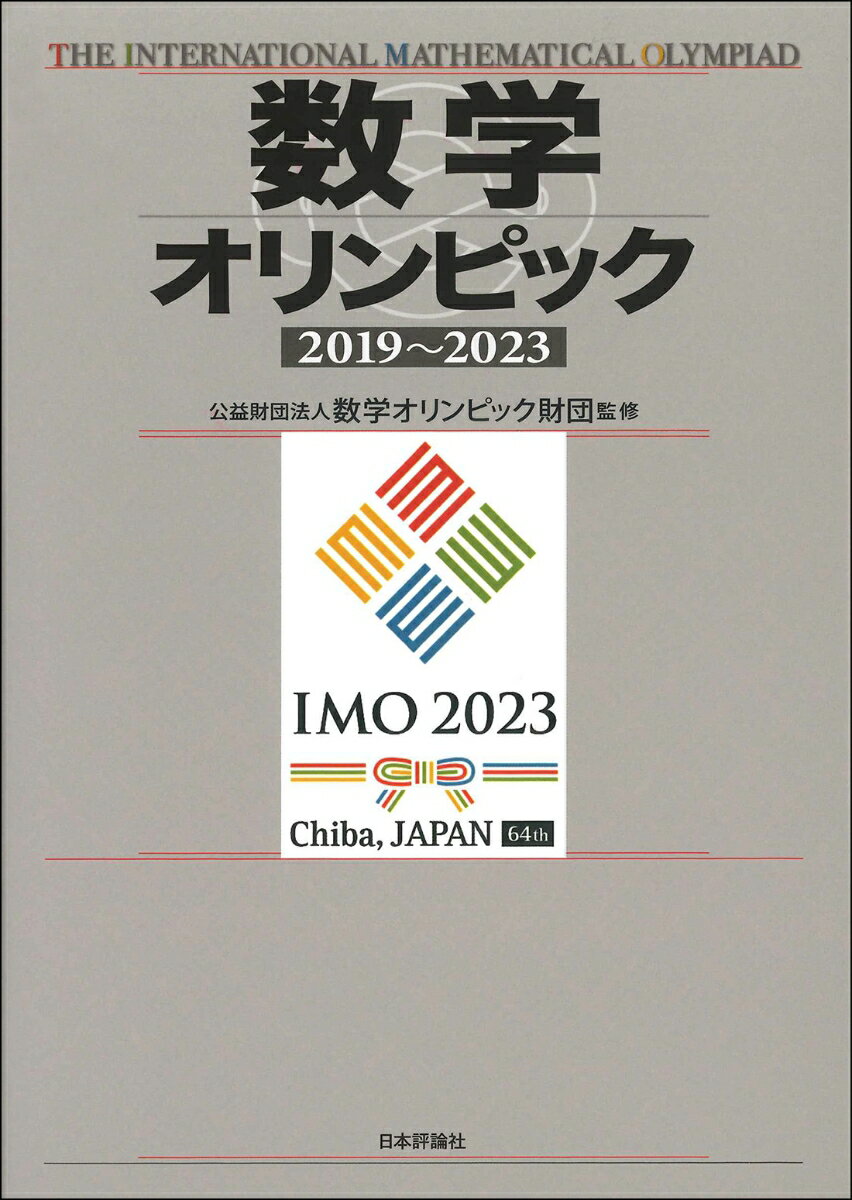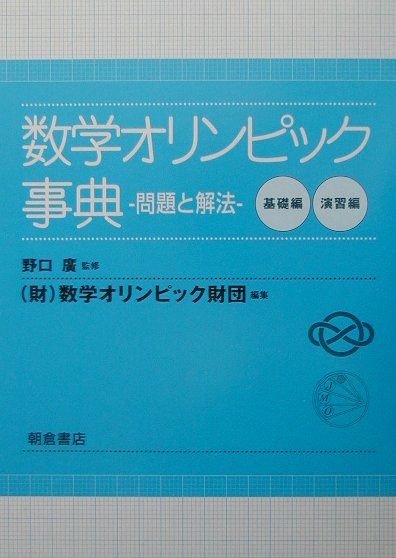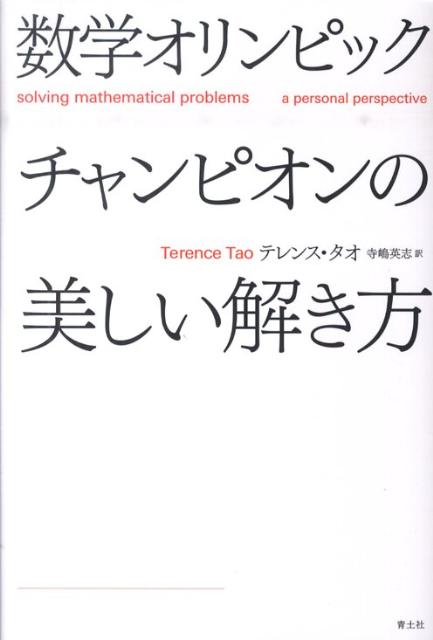今回は、日本数学オリンピック2006年予選第6問を取り上げ、解説します。
簡単な問題ではありませんが、最難関中学校の受験生や算数オリンピックにチャレンジする子であれば、解けるようにしておくべき問題です。
すべての場合の数(2×2×2×2×2×2×2×2×2=512通り)から同じ色のみからなる2×2の正方形ができる場合の数を引いて求めます(余事象の利用)。
赤いマスの2×2の正方形と青いマスの2×2の正方形が同時にできることはありえませんね。
また、赤と青は条件的に同じだから、赤いマスの2×2の正方形ができる場合の数を考え、それを2倍すれば同じ色のみからなる2×2の正方形ができる場合の数が求められますね(条件の対等性の利用)。

赤いマスの2×2の正方形(以下、Sとします)は四隅にできます(上の図の左上のものが一例)。
黄色の部分は2×2×2×2×2=32通りあり、どの四隅にできるかで4通りあるから、Sができる場合は全部で32×4=128通りありそうですが、この中には、(あ)四隅のうち4か所にSができる場合が4回カウントされ、(い)四隅のうち3か所にSができる場合が3回カウントされ、(う)四隅のうち2か所にSができる場合が2回カウントされてしまっているので、それぞれの場合において、3回分、2回分、1回分取り除く必要があります。
(あ)の場合
9マスすべてが赤入りの場合(1通りありますね)だから、1×3=3通り取り除くことになります。
(い)の場合
四隅のうち1か所だけ青色の場合(4通りありますね)だから、4×2=8通り取り除く必要があります。
(う)の場合
Sが斜めに2つ並ぶ場合とSが隣に2つ並ぶ場合があります。
前者は、四隅のうち最も離れた2か所だけが青色の場合(2通りありますね)ですね。
後者は、2×3(3×2)の赤色の長方形が元の正方形の1つの辺のところにできる場合(4通りありますね)で、図の黄緑色のマスが赤色の場合、2つの水色のマスは青色に確定し、黄緑色のマスが青色の場合は、2つの水色のマスは何色でもよく2×2=4通りあり、(1+4)×4=20通りあります。
したがって、(2+20)×1=22通り取り除く必要があります。
(あ)、(い)、(う)より、Sができる場合は全部で
128-(3+8+22)
=95通り
あり、同じ色のみからなる2×2の正方形ができる場合は
95×2
=190通り
あります。
したがって、求める場合は全部で
512-190
=322通り
あります。
なお、上の解説で重複してカウントされてしまっていますと書いてありますが、実際は、わざと重複してカウントして、その後、ダブってカウントされた分を取り除くという手法で解いています。
この手法は、中学入試、高校入試、大学入試、数学オリンピックなどで使える応用性の高いものなので、しっかりマスターしておきましょう。
東京大学2023年理科数学第2問・文科数学第3問、日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)2023年予選第3問、灘高等学校2022年数学第4問などに取り組んでみるとよいでしょう。
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策ならプロ家庭教師のPTへ
算数オリンピック・ジュニア算数オリンピック・キッズBEE対策のお申込み・ご相談