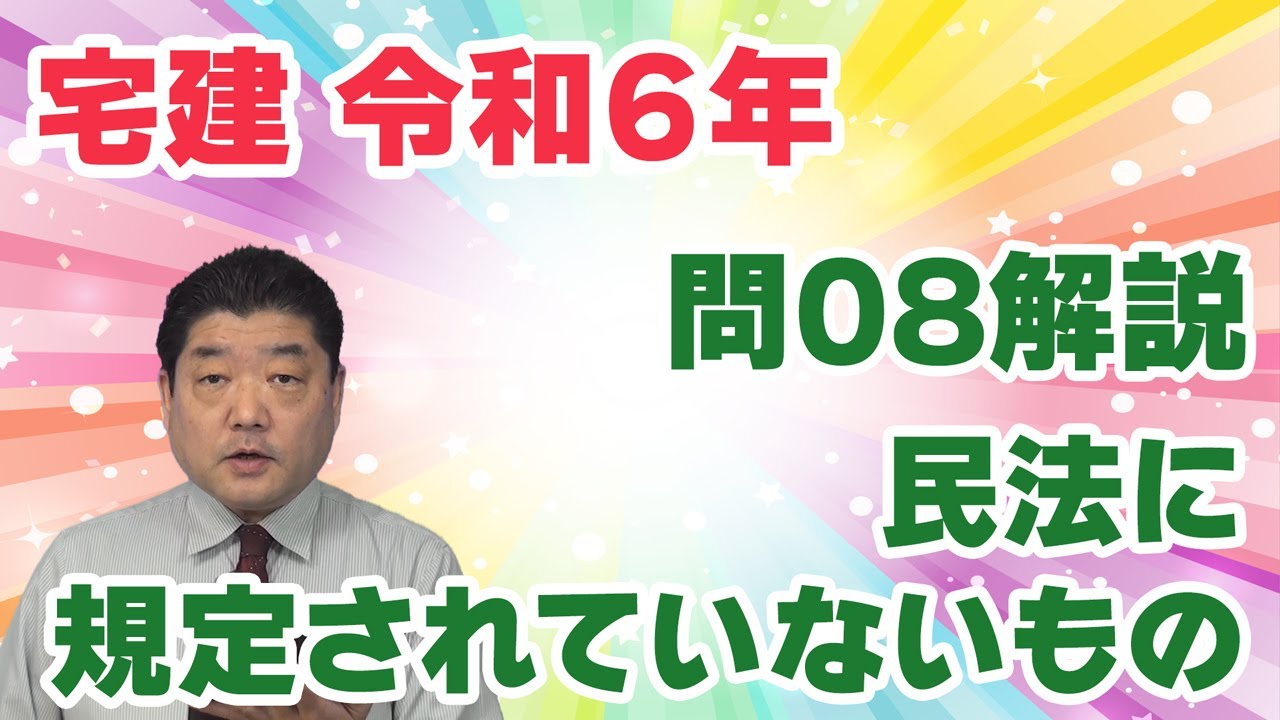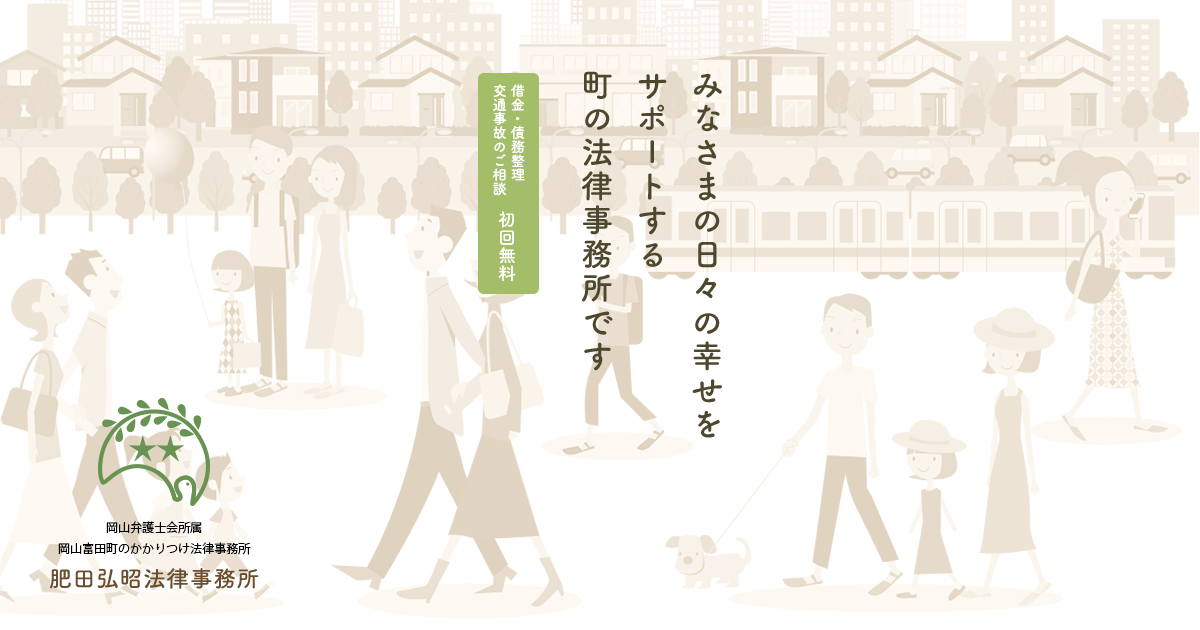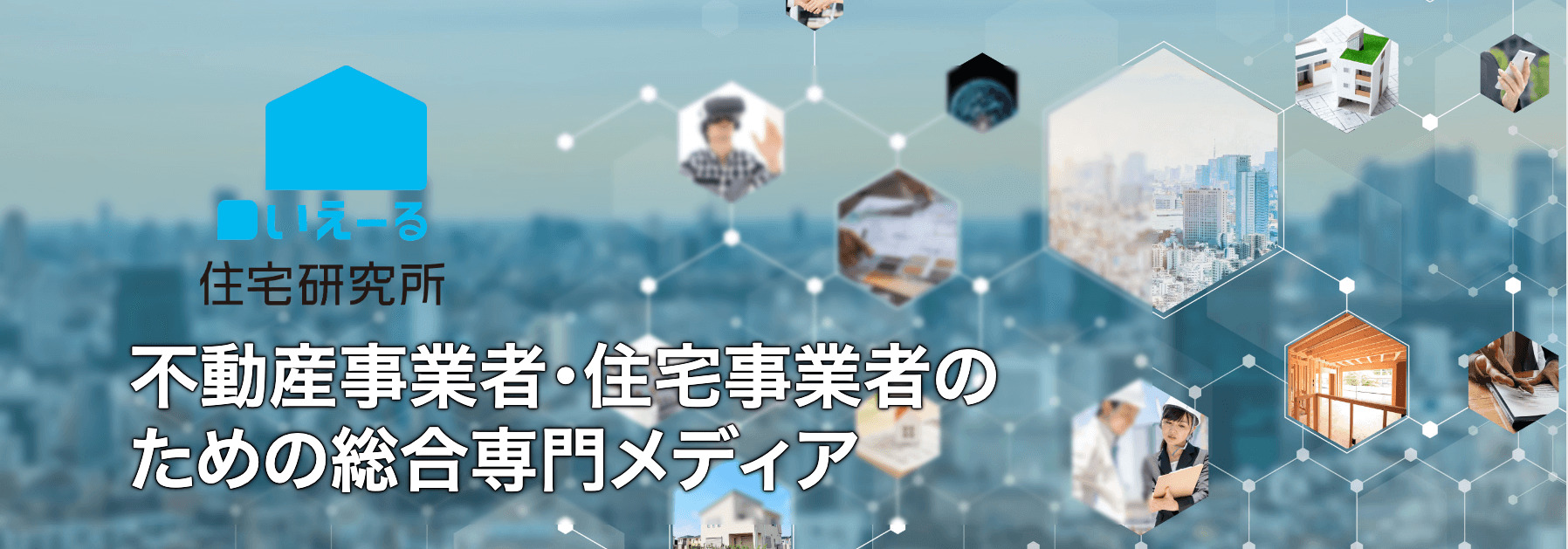※宅建Tシリーズについては序章をご覧ください。24年/25年の使用テキストについてはこちら
A) 個人根保証契約とは
P:「保証」「連帯保証」に続いて、「根保証」ですか~?
S: 宅建35で、Pくんが、上京してきた中学時代の友人Uくんの賃貸の保証人になった例をあげましたが、その時に「民法2020改正資料」 ↓にも触れました。
https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
同資料の17ページの図が ↓です。
P: 根保証=将来発生する不特定の債務を全部保証するって!?
S: 後で紹介する条文(民法第465条の2)のように、「一定の範囲」に限定はされますが。
---実は賃貸の連帯保証人になる契約も、根保証契約なんですよ。
前回の特別編で紹介したように、賃借人に家賃の滞納がなくても、退去時に思わぬ額の請求を受けることもあります。
が、さすがに事情をよく知らないで保証人になったPくんのような「個人」を保護するために、「極度額(きょくどがく)」の設定が、2020年改正で義務づけられました。
条文をあげます。
民法465条の2 ※下線などは筆者
『① 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
② 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
③ 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。』
P:①(1項)に、根保証・個人根保証契約、極度額に含まれる中身などが、書いてありますね。
そして、②によって、極度額を定めない個人根保証契約は無効になると。
③の第446条は、宅建34の「電磁的記録」で条文も紹介してましたね。
『(1) (略)
(2) 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
(3) 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。』
要するに、個人根保証契約は、書面か電磁的記録で=口約束は× と。
S: 宅建36の
A-2) 宅建試験で出題された保証/連帯保証/極度額(2020年10月・問2)
で、宅建過去問(2020年10月・問2)を紹介しましたが、この問題の肢2が個人根保証契約、肢1が書面契約についてでした。
P: 一つ一つの事項は、シンプルなのですが、2020年10月・問2のような形式で出題されると、混乱しますね!
S: 2024年の宅建試験の問8などは、「民法に規定されている=〇」を4肢から選ぶというもので、逆に民法に規定されていない=× を、判別しないといけないので、条文の暗記までは必要ないですが、条文の中身をある程度理解していないと正解できなかったと思います。
それこそ、シンプルだけど、4つの肢にまとめて出題すると難しい問題は、今後も増えそうですね…。
A-2) 身元保証人も「個人根保証契約」だった
S: 前回、新社会人・新大学生むけに、賃貸契約、とくに退去時の原状回復トラブルについて話しまして、保証人(たいていは親御さん)は
お金を請求されるリスクを負う
という話をしました。
P: 個人根保証契約が、「極度額」までになったので少し安心かな?
S: では、Pくんも就職のときに、「身元保証人」として、やはり親御さんに書類にサインしてもらったと思いますが、この「身元保証契約」は、「個人根保証契約」でしょうか?
P: 保証人の側から言えば、わざとではないにしろ問題を起こすかもしれない子どもの損害を、親が保証しますということですから、それこそ「個人根保証契約」では?
S: はい。具体的な根拠は、民法以外の法律によりますが、「個人根保証契約」に該当するので、やはり「極度額」の記載がないと、契約は無効となりました。
P: そういえば、身元保証の期間は限定されているんですか?
S: 上のリンクページにも書いていますが、別の法律で、
『身元保証契約をした時より3年、期間を定めなかった場合は成立の日から5年、5年を超えた期間は5年』とされています。
P:あれ、当ブログのエンジニアZくんシリーズで紹介しているZくんやDくん(21卒エンジニア)も、今年4月で入社5年目に突入か!
最長5年は長いような、あっというまのような…。
S: ちなみに、生成AI(Google gemini)に「身元保証人 極度額 相場」できいたら、
『身元保証人の極度額の相場は、一般的に給与の2~3年分程度とされています。
ただし、法律では特に規定が定められていないため、会社が業種や規模、従業員の業務内容などを総合的に判断して決める必要があります。』(2025年2月8日)
P: 新入社員でも、年収〇百万円ですから、けっこうな額ですね!
S: 犯罪行為(バイトテロ含む)などは別ですが、実際には全額でなく、本人がどれくらい割合で損害賠償しなければならないか? で額も変わります。
5年もたったら、会社の社員教育の問題でしょ! と思いますが。
B)根抵当権
S: 根保証契約の概念が理解できていれば、「根抵当」も理解が早いと思います。
ちょうど、2014年の宅建過去問、問4が、「抵当権」と「根抵当権」の違いでしたので、紹介します。
前提として、
甲土地所有者A
債権者B(抵当権/根抵当権設定者)B
債務者C
そして、AがBとの間で、Cの債務を担保するために、抵当権を設定した場合と根抵当権を設定した場合とで、次の4肢が出題されました。正しいのは1つです。
【肢】 ※分かりやすくするために、「が、」を改行に変更し、[ ]のキーワード付加
① [被担保債権の範囲]
抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならない。
根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
②[第三者への対抗要件]
抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要である。
根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。
③[抵当権の実行]
Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができる。
Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。
④[順位の譲渡]
抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができる。
元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
P: 「抵当権の順位の譲渡」は、この連載ではやってませんが、「元本確定前」というキーワードがあったのと、肢1~3は消去法で×として、肢4が〇ですか?
S: 肢4の詳細は、下記のリンクページをご覧いただくとして、根抵当権の場合は、そもそも元本確定=担保する範囲が確定した後でないと、金額もわからないわけですから、元本確定前にできることは限られています。 ※補足1:元本確定
ちなみに、肢1の「(根抵当権が)BC間のあらゆる範囲の不特定の債権」を担保する」も、根抵当権の条文の知識(下記、参考URL)はなくても、今回とりあげた根保証(家賃保証や身元保証)とおなじように、普通は「ある一定の範囲の取引関係」に限定されるよね? と、Pくんも思ったんでしょう。
P: Sさんによれば、根抵当権は宅建試験であまり頻繁に出題されないので、今回の記事の内容以外は、過去問をやった後に、基本テキストで関連知識を確認する順序でよいのでは? とのことでした。
次回からは、「賃貸借契約(民法/借地借家法)」を予定しています。
【補足1】 根保証の元本確定
生成AI(Google gemini)に「根保証 元本確定とは」できいたところ
『根保証の元本確定とは、根保証契約において、主たる債務の元本が確定する時点を指します。
元本確定すると、その時点で存在する債権を元本として、それ以降の借入は保証の対象外となります。
【元本確定の理由】
根保証契約では、契約時に保証人の責任の範囲が確定していません。
根保証契約では、一定の範囲に属する不特定の債務を担保するため、法律関係が不確定になりがちです。
根保証契約では、保証人がどのような場合に元本が確定し、保証債務から解放されるかを明らかにする必要があります。
【元本確定事由の例】
債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき
主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
主たる債務者又は保証人が死亡したとき』(25年3月22日)
根抵当権については
【写真】
提供:Pixabay(冒頭、中間)、末尾 筆者撮影(東京都の住宅街)
【BGM】
S選曲 三代目 J SOUL BROTHERS 「What Is Your Secret?」
P選曲 Ooochie Koochie(奥田民生×吉川晃司) 「GOLD」