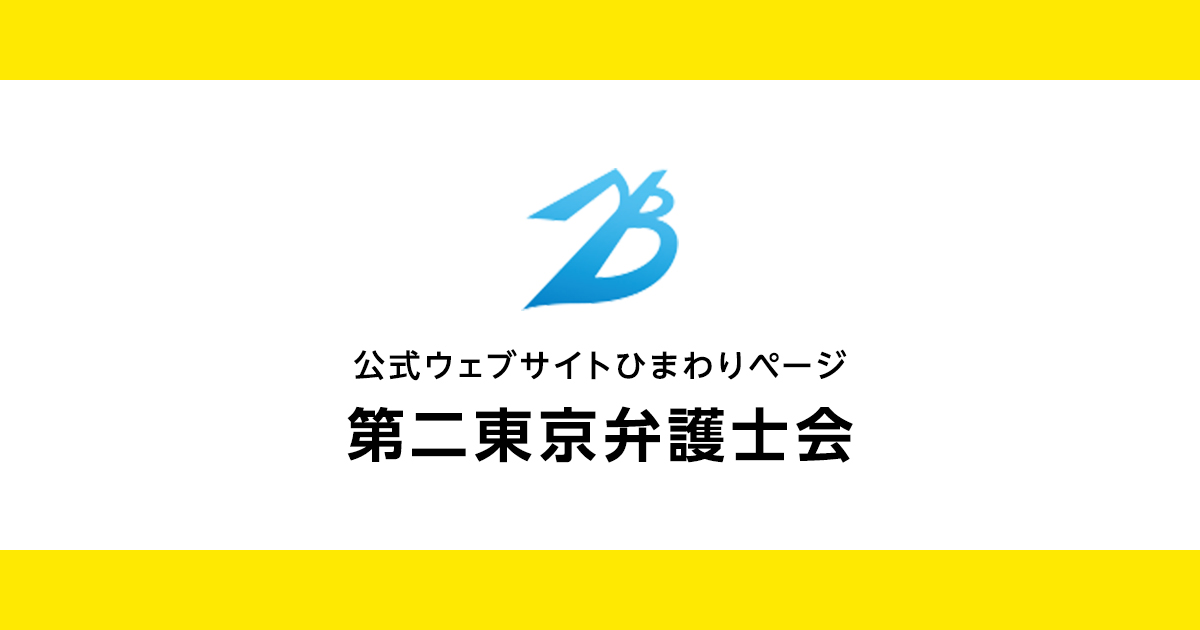※宅建Tシリーズと「基本テキスト」については「序章」をご覧ください。
(A)「 何が」消滅するのか?
P: 前回の「取得時効」に続いて、今回は「消滅時効」についてです。
S:基本テキストでは、
・時間がたつと手に入る「取得時効」
に対して、
・時間がたつと失う「消滅時効」
と説明していました。
P: 「取得時効」は、一定時間、「物」を占有し続けることで、所有権などを取得できましたが、「消滅時効」では「何が?」消滅するのでしょうか?
S:まず、民法の条文で確認してみましょう。
『第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。』
つまり、債権(1.)と、「債権または所有権以外の財産権」(2.)ですね。 ※補足1
宅建試験で出題されるのは、おもに「AがBに対して有する100万円の貸金債権」(1997年・問4)など、お金の貸し借りで生まれる「債権」です。
P: そもそも「債権」が、日ごろあまり使わない言葉なんですが?
S: Pくんが、仮に、友人Qくんに頼まれて1万円を貸したとします。すると、
債権者(お金を貸した人)Pが、
債務者(お金を借りた人)Qに対して有する
1万円の貸金債権(1万円を返してほしいと請求できる権利)
が発生します。Qくんの側からみれば、1万円の債務が発生します。
そして、このPくんのもつ1万円の債権は、先の民法166条の規定により、
・債権者(P)が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
または
・債権者(P)が、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
の早い方の到来で、消滅します。
P: つまり、Qくんは僕に返さなくてもよいと?
S:正式には、(C)で説明する「時効の援用」を、Qくんがすれば、そうなりますね。
(B)消滅時効はいつ開始するか?
それより宅建試験対策で要注意なのは、「権利を行使することができる時」(起算日)は何時か? という点です。
(C)時効の援用
P: もし、ぼくがQくんに「6年前に貸した1万円を返してくれ」と言ったら、どうなりますか?
S: ここも、まず条文を紹介します。
民法第145条
「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」
ちなみに「援用」とは、『 自己の利益のために何らかの事実を主張すること』という意味で、つまりQくんが「Pくんに借りた1万円は、もう消滅時効で返さなくてよいはずだ」と主張をしない限り、時効の効果は発生しません。
P: 上の条文には、「裁判」とありますね。
S: 裁判外でも、主張できます。
この条文の「保証人、物上保証人、第三取得者」は、まだ当ブログで説明していないので、ひとまず「権利の消滅について正当な利益を有する」関係者しか、時効の援用(主張)はできないと、理解しておいてください。
くわしくは ↓
さらに、「時効の利益の放棄」といって、今回のケースではQくんが、「時効の利益を受けない。Pくんに返すよ」と言うこともできます。
ここも条文を紹介すると、
第146条
『時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。』
逆に言えば、時効が完成した後なら、時効の利益を放棄できるわけです。
P: どうして、あらかじめ放棄できないんでしょうか?
S: PくんとQくんの間のお金の貸し借りならあまり問題ないでしょうが、例えばドラマに出てくるような金融業者と借り手とで、もし「あらかじめ放棄ができる」となったら?
P: 当然、最初の貸す段階で「時効の利益を放棄する」旨、一筆書いてもらうでしょうね。
S: それでは消滅時効の制度の意味がなくなるので、時効完成後にQくんが選択できるようにしたわけです。
なお、消滅時効が完成したことをQくんが知らないで、Pくんへ「次の給料日に払う」と言ったあとは、QくんはPくんに対する「時効の援用」ができなくなります。
P: この点は、次回記事「時効の完成猶予/時効の更新」でも触れるそうです。
過去問が気になる方は、先に下記のような2020年12月問5の解説記事をご覧ください。
補足1 そもそも財産権(物権/債権)って? という方は、下記まとめ記事(PDF)が分かりやすいです。
補足2 基本テキストの32~33ページに、「期限」「条件」や、「所有権に消滅時効はない」などの、分かりやすい説明がのっています。
【BGM】
S選曲 Wang Chan 「Dance Hall Days」
P選曲 Dead or Alive 「You Spin Me Round (Like a Record) (Moreno J Remix)」
【写真】上・中:Pixabay 下:撮影筆者(千代田区)