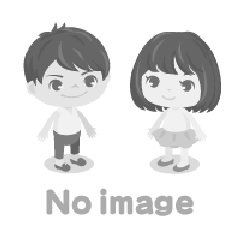少し前までここまで円高が進んだことに対して、「円高になる要因はない」だとか「消去法で円買い」等の意見が主流となっていた。
しかし、僕は円買いの要因は「日本がデフレであること」、「日本の経常収支が大幅に黒字であること」の2つで円高になる説明としては十分だと考えていた。
今でこそこの考えは徐々に浸透してきているように思う。
この「日本が大幅に経常黒字であること」という事実は、公的債務がGDPの約2倍の900兆円以上ある日本が財政破綻しない大きな理由にもなっている。
日本は過去10年以上にわたって大幅な経常黒字を計上している大金持ちの国なのである。今、欧州で懸念されているギリシャは経常赤字国でありこの点で日本とギリシャは大きく違うのである。
みんなが思うように、たしかに今の日本はダメかもしれない。でも、僕たちの先輩が作ってくれた経常黒字構造のおかげで今の日本は支えられているのだ。
この経常収支について今回は書こうと思う。というのも、経常収支は日本の未来を占う上でとても大事だし、同じ経常黒字といっても今と10年前ではその中身が違うからちゃんと認識しておいた方が良い。
● 経常収支とは貿易収支と所得収支の合計(正確にはここにサービス収支、経常移転収支が加わる、があまり大きくないので割愛)
貿易収支というのは、日本国内から海外に製品を輸出して稼いだ金額から海外から輸入して購入した金額を差し引いたもの。簡単に言い換えれば、海外に物を売っていくら稼いだかというもの。
所得収支というのは、海外で働いて得た報酬や海外に投資して得た利子・配当金当の収入の合計。
この合計が経常収支になるのだが、ご存知のように日本は世界のトヨタやソニーを有する製造業立国でありもちろん貿易黒字が大きいと考えられる。
では、ここで日本の貿易収支と所得収支の推移を見てみよう。
Bloombergより筆者作成、単位:10億円
これを見るとわかるように、日本は過去貿易黒字が所得収支を上回るまさに貿易立国だった。しかし2005年に所得収支が貿易収支を上回るとその後は基本的に所得収支が貿易収支を上回っている。日本は確実に変化している。しかし、これは喜ぶべきことでもないし悲しむべきことでもない。なぜなら、国の発展と共に経常収支の中身が変化することはごく当たり前のことだから。変化に合わせて生き方を変えればいいだけの話だ。
では、ここで経常収支の発展モデルを見てみよう。これはクローサーの発展段階説といわれるものである。
1. 未発達の国は輸出する産業もないし海外に投資するお金もないので、貿易収支・所得収支ともに赤字でもちろん経常収支は赤字⇒未成熟な債務国
2. 海外から借金をして徐々に自国産業が発展してくると海外に売る物ができるので貿易収支は黒字になるが、海外からの借金は依然残るので所得収支は赤字。経常収支も赤字。⇒成熟した債務国
3. 国が発展を続けると貿易収支が拡大しいずれ経常収支が黒字に転換する。海外の借金を徐々に返済していくが、所得収支は依然赤字。⇒債務返済国
4. 貿易収支の黒字が安定してくると、海外からの借金が減っていくので所得収支が黒字に転換する。⇒未成熟な債権国
5. 国の発展したため、国内の人件費高騰などを理由に製造業が海外進出していき貿易収支は赤字に転落。これまでの貿易黒字で稼いだお金で海外に資産をたくさん持っているため所得収支の黒字が大きく経常収支は黒字。⇒成熟した債権国
6. 貿易赤字が拡大して経常収支が赤字に転落。海外の資産が減少していき、所得収支も減っていく。⇒債権取崩国
1から6に進むにつれて国は発展している。今の日本は成熟した債権国にあたるので貿易収支よりも所得収支の方が高く推移している。当初政府は2030年頃に貿易収支は赤字に転落すると予想していたが、今回の震災でその時期早まりそうだ。
(上のデータには反映されていないが、2011年4月の貿易収支は赤字に転落している。)
今の日本は貿易立国でもないしトヨタやソニーが支えているわけではない。海外への投資による利子や配当て食っている国なのだ。
僕たちはこの事実をしっかり理解してこれからを生きていかなくてはいけない。
ちなみに日本より先に行くアメリカは貿易収支も所得収支も赤字で完全な債権取崩国である。アメリカの財政赤字は現在の米国内でもとても大きな問題となっているが、いずれ日本も同じ問題に直面するかもしれない。
しかし、日本とアメリカの違いは、アメリカには基軸通貨があるということ。ドルがいくら弱いとはいえ世界はドル中心に回っており、ドル基軸通貨体制が続く限りドルの需要は存在し、アメリカはドルを刷り続けることができる。
しかし、日本円ではそんな芸当はできない。日本の経常収支が赤字になれば日本は執行猶予期間などなく一気に転落するだろう。
そうなる前に、国レベルでも個人レベルでお準備しておく必要があるのは明白だ。
しかし、僕は円買いの要因は「日本がデフレであること」、「日本の経常収支が大幅に黒字であること」の2つで円高になる説明としては十分だと考えていた。
今でこそこの考えは徐々に浸透してきているように思う。
この「日本が大幅に経常黒字であること」という事実は、公的債務がGDPの約2倍の900兆円以上ある日本が財政破綻しない大きな理由にもなっている。
日本は過去10年以上にわたって大幅な経常黒字を計上している大金持ちの国なのである。今、欧州で懸念されているギリシャは経常赤字国でありこの点で日本とギリシャは大きく違うのである。
みんなが思うように、たしかに今の日本はダメかもしれない。でも、僕たちの先輩が作ってくれた経常黒字構造のおかげで今の日本は支えられているのだ。
この経常収支について今回は書こうと思う。というのも、経常収支は日本の未来を占う上でとても大事だし、同じ経常黒字といっても今と10年前ではその中身が違うからちゃんと認識しておいた方が良い。
● 経常収支とは貿易収支と所得収支の合計(正確にはここにサービス収支、経常移転収支が加わる、があまり大きくないので割愛)
貿易収支というのは、日本国内から海外に製品を輸出して稼いだ金額から海外から輸入して購入した金額を差し引いたもの。簡単に言い換えれば、海外に物を売っていくら稼いだかというもの。
所得収支というのは、海外で働いて得た報酬や海外に投資して得た利子・配当金当の収入の合計。
この合計が経常収支になるのだが、ご存知のように日本は世界のトヨタやソニーを有する製造業立国でありもちろん貿易黒字が大きいと考えられる。
では、ここで日本の貿易収支と所得収支の推移を見てみよう。
Bloombergより筆者作成、単位:10億円
これを見るとわかるように、日本は過去貿易黒字が所得収支を上回るまさに貿易立国だった。しかし2005年に所得収支が貿易収支を上回るとその後は基本的に所得収支が貿易収支を上回っている。日本は確実に変化している。しかし、これは喜ぶべきことでもないし悲しむべきことでもない。なぜなら、国の発展と共に経常収支の中身が変化することはごく当たり前のことだから。変化に合わせて生き方を変えればいいだけの話だ。
では、ここで経常収支の発展モデルを見てみよう。これはクローサーの発展段階説といわれるものである。
1. 未発達の国は輸出する産業もないし海外に投資するお金もないので、貿易収支・所得収支ともに赤字でもちろん経常収支は赤字⇒未成熟な債務国
2. 海外から借金をして徐々に自国産業が発展してくると海外に売る物ができるので貿易収支は黒字になるが、海外からの借金は依然残るので所得収支は赤字。経常収支も赤字。⇒成熟した債務国
3. 国が発展を続けると貿易収支が拡大しいずれ経常収支が黒字に転換する。海外の借金を徐々に返済していくが、所得収支は依然赤字。⇒債務返済国
4. 貿易収支の黒字が安定してくると、海外からの借金が減っていくので所得収支が黒字に転換する。⇒未成熟な債権国
5. 国の発展したため、国内の人件費高騰などを理由に製造業が海外進出していき貿易収支は赤字に転落。これまでの貿易黒字で稼いだお金で海外に資産をたくさん持っているため所得収支の黒字が大きく経常収支は黒字。⇒成熟した債権国
6. 貿易赤字が拡大して経常収支が赤字に転落。海外の資産が減少していき、所得収支も減っていく。⇒債権取崩国
1から6に進むにつれて国は発展している。今の日本は成熟した債権国にあたるので貿易収支よりも所得収支の方が高く推移している。当初政府は2030年頃に貿易収支は赤字に転落すると予想していたが、今回の震災でその時期早まりそうだ。
(上のデータには反映されていないが、2011年4月の貿易収支は赤字に転落している。)
今の日本は貿易立国でもないしトヨタやソニーが支えているわけではない。海外への投資による利子や配当て食っている国なのだ。
僕たちはこの事実をしっかり理解してこれからを生きていかなくてはいけない。
ちなみに日本より先に行くアメリカは貿易収支も所得収支も赤字で完全な債権取崩国である。アメリカの財政赤字は現在の米国内でもとても大きな問題となっているが、いずれ日本も同じ問題に直面するかもしれない。
しかし、日本とアメリカの違いは、アメリカには基軸通貨があるということ。ドルがいくら弱いとはいえ世界はドル中心に回っており、ドル基軸通貨体制が続く限りドルの需要は存在し、アメリカはドルを刷り続けることができる。
しかし、日本円ではそんな芸当はできない。日本の経常収支が赤字になれば日本は執行猶予期間などなく一気に転落するだろう。
そうなる前に、国レベルでも個人レベルでお準備しておく必要があるのは明白だ。