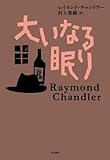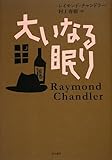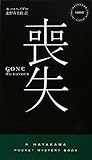『機動戦士ガンダム サンダーボルト 1』
- 2013年最初の記事です。
- 本年もよろしくお願いします。
年末から元日までは娘を連れて実家に行ってきた。
実家の年越しそばと雑煮はどうしても食べずにはいられない・・・。
本年最初は、実家においてあったマンガを読んだ。
一年戦争におけるある局面を描いた漫画。
サンダーボルト宙域に潜むジオンのスナイパー部隊から当該宙域の奪還を図る連邦軍のエースがガンダムを駆る・・・。
画風もプロットもかなりシリアスを追求してる。
『本だけ読んで暮らせたら 2012年のお薦め本』
読むことも、記事を書くことも、更には、よそ様のブログにお邪魔することもメッキリ減った2012年でした。
飽きてきたわけではありません。他に興味のある事が出来たわけでもありません。
気力、持続力の不足です・・・。
・・・気力を振り絞って、この年末記事を記録しておこうと思います。
『作品名』 をクリックすると、紹介記事にリンクします。
<ミステリーとか>
今年もハヤカワ・ポケミスばかりを読んでいたように思います・・・。
そして現在の翻訳ミステリーのトレンドとなっている北欧ミステリーを・・・。
ポケミス『解錠師』 は、年末の各社ランキング本で高評価のようでしたね。結構、渋めの内容だと思うのですが、一般受けするのでしょうか? 初出から1年経たずに文庫もされて驚きました。
『冬の灯台が語るとき』 このポケミスは、雪の夜を舞台にした静かなスウェーデン・ミステリーです。こういう作品に面白味を感じることができるのは、やはり年を取ったのかナと感じてしまいます・・・。
続けてポケミスから2作。しかもどちらもデンマーク産。
『死せる獣 殺人捜査課シモンスン』
に登場する逸脱した主人公がイイです。
『特捜部Q Pからのメッセージ』 は、これまでのQシリーズ3作中の最高傑作です。
北欧産のおもしろミステリーはまだまだあります。アイスランド産の 『湿地』 。
ドイツ産ミステリーからは、 『深い傷』 と 『首切り人の娘』 。
南欧の作家カルロス・ルイス・サフォンの『天使のゲーム』
は前作
ほどの衝撃はなかったけど、それでも物語の王道を行く作品であることには間違いないでしょう。
アメリカ産のものも挙げておきましょう。。。
ボストン・テランの 『暴力の教義』 。ノワールです。相変わらずノワール好きです。ノワールは癖があるんですけど嵌ると・・・。
そして・・・、『真鍮の評決』 と 『大いなる眠り』 を挙げない訳にはいかないですね!
前者は、1990年代から2010年代の現在までで最高のハードボイルド作家=マイクル・コナリー作。
後者は、ハードボイルド小説を確立したレイモンド・チャンドラー作。
どちらも文句なし!テッパン!!
少々変わったモノも挙げておきます。ちくま文庫の短編アンソロジー 『謎の物語』 という作品。 “リドル”という言葉とその意味を教えてもらった作品。内容も印象的なものが多かったです。
さてさて、今年読んだエンターテイメント小説で一番だったのがコレ↓↓↓。
クライマックスから結末に掛けて今年一番の驚きをもたらしてくれた、ジュール・ヴェルヌの『神秘の島』 というSF。
こいつを読んだ時には、古くて一般的には知られていない(?)けど、まだまだこんな面白いのが隠れているんだなーと思わずにはいられませんでした。こんな凄い作品があるってコトを、どうして誰も今まで教えてくれなかったんだって思いましたネ。
<自然科学とか>
この分野からは、『プレートテクトニクスの拒絶と受容』
を挙げます。この本をサイエンスの部類に入れるのはどうかとも思いますが(歴史分野かも?)、それでも驚きの事実を知ることができた内容でした。
それと、過去に何度も読んでるんだけど、今年も読んで新たな発見があった 『ワンダフル・ライフ』 も挙げておきます。
<歴史とか>
高知県の坂本龍馬記念館にしか置いてなくて、一般の書店では購入できないかもしれませんが、『龍馬書簡集 現代語訳付』 がイイです。坂本龍馬の書いた手紙を理解しながら読める喜びを味わうことができます。高知に出かけた際には、是非とも御購入をお勧めします。
今年読んだ全ての本の中で圧倒的にお勧めしたいのがコレ→ 『逝きし世の面影』 。
この国のある一時期に確かに存在した文明、そしてその文明の下に生きたエピュキュリアン日本人の姿を鮮明にイメージさせてくれる本書。
歴史書としてのあるべき姿が本書にある!と思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今年、何時だったか、どの本?あるいは雑誌?だったかは忘れましたが、「書を読むを好むも、甚だしくは解するを求めず」という言葉を見つけました。
ただ読むだけ。何かを得ようとするわけでもなく、他に面白いものを見つけることのできない輩が暇つぶしで本を読む・・・。そんな私には何とも都合の良い言葉に出会い、チョット嬉しくなりました。
私の感想など、私の脳が恣意的に歪めた内容に対してのモノであって、それを自分勝手に解釈し、まったくもって個人的に、安易に、安直に共感もしくは反感しているだけです。
本を読んでの一凡人の感想を披露することに然したる意味などはないでしょう・・・。
それでもこんなブログを書き、公開しているのは、少しでも世間様と繋がっていたいからなのでしょう。
そんな天邪鬼な管理人の当ブログ駄文の数々をご覧いただきました皆様、今年1年ありがとう御座いました。
2013年もお付き合いいただければと存じます。
『ゴリアテ ロリスと電磁兵器』
第一次世界大戦の歴史改変スチームパンク小説3部作の最終巻。
生物の遺伝子操作技術を発展させ、様々な新生物を造り、それらを用いて文明を発展させてきたイギリスを中心とする“ダーウィニスト”陣営。
蒸気動力を用いた機器によって文明を発展させてきたドイツを中心とする“クランカー”陣営。
両陣営による戦争はヨーロッパ外の世界をも巻き込み拡大している・・・。
(2巻で)オスマントルコの革命成功の一翼を担った主人公の2人(イギリス海軍士官候補生デリン・シャープとオーストリア・ハンガリー帝国大公の息子アレック)を乗せたイギリス海軍巨大飛行獣<リヴァイアサン号>はイスタンブールを去り、東京に向かう途上のシベリア上空にいた。
二人の眼前に広がるシベリアの森林。そこは数百km四方に渡って木々が倒れている。この森林でいったい何が起こったのか??
リヴァイアサンには、このシベリアの大地から敵国クランカーの科学者を救出せよとの命令が下る。
ニコラ・テスラというクランカーの科学者による電磁兵器“ゴリアテ”の能力・威力を世界に見せることによって戦争を終結に向かわせたいと考えるアレック。
一方、女であることを隠して入隊し、その正体が周辺に明らかになりつつあるデリンは、旅の終わりを感じながら、そしてアレックへの感情にとまどいながらも、アレックが抱く戦争終結への想いに協力するのであった・・・。
二人を乗せたリヴァイアサンは、東京から大西洋を渡りアメリカ、メキシコへ、そしてまたアメリカへと戦いの舞台を移して行く・・・。
さて、このシリーズ、それぞれ1作が2段組みでだいたい450ページもある。それが3冊。長ーい作品だが、全体のストーリーは極めて単純だ。小中学生向きと云ってもイイかもしれない。まァ、全体の流れは単純であるが、一つひとつの場面に関しては細部にこだわって描いているものだから、これだけの分量になっている。
SFは世界観を大事に、細部にこだわって描いてほしいと思う私には満足のいく作品だった。
作中で描かれる生物兵器や蒸気機関兵器、そして様々なシーンがふんだんな挿絵によって表現されているのも、この物語を盛り上げるのに一役かっていた。なにより、こうした多量の挿絵が、昔読んだジュブナイルSF作品のテイストを思い出させてくれた。1年間楽しませてもらった。
- ベヒモス ―クラーケンと潜水艦―
 ←第2作
←第2作
- リヴァイアサン クジラと蒸気機関
 ←第1作
←第1作
『腕くらべ』
3連休はカミさんの使いで2度外出した以外はもっぱら2階の和室に閉じ籠もって、幾つかの読み掛けの本を摘まんでいた。
本ばかり読んでいた割りに、読み終えた本はコレ1冊・・・。
短く記す。
新橋芸者=駒代を主人公とした物語。壊れゆく明治・大正期の花柳界文化への追憶の物語。滅び逝くモノの哀切の情緒を描いた物語。
一方、春画的風俗小説としての一面も伺える。大正期に描かれた小説としては、なかなかにエロい場面も出てくる。その描写は現代でも通じるように思える。
一見本筋とは関係ないように突然現れる第12章「小夜時雨(さよしぐれ)」が物凄くイイ。
荷風の言いたかったことがこの1章に集約されているんだと思うと、この章を挿入しない訳にはいかなかったのだろう。荷風の心意気が表われている。
布団にくるまって読んだ本作。不思議と作中の雰囲気に同化できるようで、荷風の世界にどっぷりと浸かることができたように思える。
『快楽としてのミステリー』
大量の積読本を抱え、それらの消化も儘ならないのに、読み掛けの本が大量にあるのに、またもや衝動買いしてしまった・・・。
『快楽としてのミステリー』
- 『快楽としてのミステリー』 丸谷才一/著、 ちくま文庫(2012)
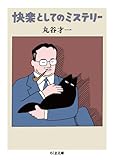
本書に先だって同著者による 『快楽としての読書 日本篇』 と 『快楽としての読書 海外編』 が出ていた。
- 快楽としての読書 日本篇 (ちくま文庫)/筑摩書房
- 快楽としての読書 海外篇 (ちくま文庫)/筑摩書房
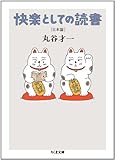

どちらも読んでみたいとは思っていた。とりわけ後者については書店に行くたびに立ち読みしていて、その都度購入を迷っていたが、結局それには至らなかった。どちらかというと純文学作品に関する紹介・書評であり、おおもとの作品をほとんど読んでいない文学音痴の身にとっては丸谷の言い分を充分に理解することは叶わないと感じたからであった。
だが、ミステリーに特化した内容・・・、しかも海外ミステリーが圧倒的に多い・・・、だったら結構読んでるし?・・・著者の云っていることも判るかもしれない???・・・。
ん~っ、じっくり読みたい・・・ってコトで・・・今に至る。。。
著者の丸谷才一はミステリー小説(丸谷本人の言い方としては「探偵小説」)を愛していた。文学作品と分け隔てなく。そもそもがジャンル分けを必要としていない風の態度が見える。
特段嬉しいのは、丸谷がチャンドラーに関して昔から高評価していることが判ることだ。
チャンドラー作品に関わるエッセイが5編載っている。
「フィリップ・マーロウといふ男」 p.103
「角川映画とチャンドラーの奇妙な関係 『プレイバック』」 p.182
「名探偵の前史 『マーロウ最後の事件』」 p.295
「これが文学でなくて何が文学か 『過去ある女 プレイバック』 『湖中の女』」 p.298
「ハードボイルドから社交界小説へ 『ロング・グッドバイ』」 p.301
以前、村上春樹による新訳『ロング・グッドバイ』に関する感想 を書いたときに、清水俊二による旧訳『長いお別れ』との比較はプロの書評家が行うだろう、と予想していたが、それを↑の5編目で丸谷が行っていた。
丸谷は言っている。
村上春樹の新訳によって『The Long Goodbye』はハードボイルドから社交界小説になった、と。
また、こうも言ってる。
清水訳は“マチスモ(男っぽさ)の悲哀”を描いて魅せたが、村上訳ではそれを“普遍的な人生の憂愁”に変じさせた、と。この比較については、さすがプロ!と感じる。
さてさて、本書の第1章では、「ハヤカワ・ポケット・ミステリは遊びの文化」と題して、1989年1月に行われた丸谷才一×向井敏×瀬戸川猛資による鼎談の模様が載っている。
ポケミス・ファンは必読!
他にもイロイロなミステリー作品に関する好意的な論評が載ってる。
で、グレアム・グリーンが読みたくなった。
『現代ミステリ傑作選 18の罪』
海外ミステリの短編が18作。
ローレンス・ブロック、ジェフリー・ディーヴァー、マイクル・コナリーの名前があるのを見て購入してしまった。積読本満載なのに・・・。
コナリーの『マルホランド・ダイブ』は、以前に読んでいた ・・・(^_^;)
『大いなる眠り』
村上春樹訳版チャンドラー作品、フィリップ・マーロウものの第4弾。
これまでの3作については、コチラ⇒ 『ロング・グッドバイ』
『さよなら、愛しい人』
『リトル・シスター』
この作品こそが、探偵フィリップ・マーロウが初めて登場した作品。チャンドラーが描いた長編7作品中の最初を飾る作品だ。
本作、本当に出来がイイ。これぞハードボイルドの典型である。
1939年に登場した探偵フィリップ・マーロウ。
その後に登場する膨大な探偵小説の主人公の原型はこの作品で確立されたとも云われているが、まったくその通りに思える。
死に瀕した大富豪ガイ・スターンウッド老人の依頼を受けた探偵フィリップ・マーロウは、その依頼を完遂するために様々な障害を排除することになる。障害としては、カジノを経営するギャングの親玉であったり、依頼人の美貌の二人の娘であったりするわけであるが、そうした障害に遭った際のマーロウの対応・態度にハードボイルドの典型を見るのである。
ハードボイルドの主人公の存在意義は、ただひたすらに自由である、というところにある。
自由であるために必要なコト、それを追い求める。
自分以外の誰からも束縛されない。
信頼した人間、自分が認めた人間に対しては、どこまでも忠実であろうとする。
それ以上に自分に忠実であろうとする・・・。
四半世紀も前に読んだ作品だが、いま読んでも更に惹かれる。私がミステリーを、本を読み始めるきっかけとなったのがチャンドラーなんだ、と改めて感じさせてくれた。
お薦めです。
バイブルの新訳
今月ハヤカワから出版された3冊を購入してきた。
ゴリアテ ―ロリスと電磁兵器― (新ハヤカワ・SF・シリーズ)/早川書房
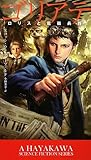
中でも、チャンドラーの『大いなる眠り』は、私にとってのバイブルうちの一つ。
読み掛けの永井荷風『腕くらべ』が終わったら、取り掛かかろう・・・。楽しみ。
『すみだ川』
この文庫には、「深川の唄」 「すみだ川」 「新橋夜話」 が収められている。
「深川の唄」は短編。
「すみだ川」は中編。
「新橋夜話」は短編連作。
先日、オーディオ・ブック で聞いたはいいが、今一つ内容を掴み損ねていた『深川の唄』を文字・文章として吟味することができた。
文字で読んだことのあるものを聞く方がいい。順番が逆ではダメだと思い知った。
『すみだ川』も実にイイ。『深川の唄』もそうだが、作品全体が写実的だ。
もちろん荷風は人物の心情も描写するが、そこは割り合いあっさりしている。
しかしそのあっさり具合がイイ。ほんのりとした侘び・寂びも感じるし、今風の萌えも感じる。
『新橋夜話』もいい。
短編連作の本作では、主に新橋界隈の芸者やその客やパトロンやらの花柳界に居る人達の物語を連ねている。
人情話、色話の類ばかりなのだが、いずれもその筆致は乾いている。花柳界に生きる登場人物たちは、人生に対して何処か諦めた気持ちを持っている。それがハードボイルド風味を醸し出していて私好みとなっている。
こりゃイイ。
『つゆのあとさき』
つゆのあとさき・・・梅雨の後先の僅か数か月の物語。
昭和初期、東京銀座のカッフェーの女店員の奔放な性格・生活と、そんな彼女に振り回される中年以上の男共の弱さ・情けなさ・滑稽さ・間抜けさを対比して描いている。
主人公の女の強さ・自由奔放さが艶っぽく描かれていてイイ。
間抜けな男共の気持ちが何となく判ってしまうところもイイ。
コレまでに読んだ荷風の小説の舞台は常に東京。
銀座、神楽坂、四谷、麹町・・・、荷風の描く東京は魅力的だ。
荷風自身は、江戸期の趣きが消えてゆく明治末から昭和初期の東京の変貌の具合に嘆いているように見受けられる。
しかし、21世紀の東京を知る読者(私)から見れば、当時の東京は充分に魅力的だ。街並みも、そこに暮らす人々も・・・。
私にとっては、荷風の作品は粋だ。
もうしばらく荷風に付き合ってみることにする。。。