王様のブランチ
久しぶりに休日出勤してきた。
平日より遅く出掛けようとしていた、その直前、テレビから聞こえてきた「岸本佐知子」という音声。
著者インタビューを放映するとのことで、家を出る時間をさらに遅らせてテレビを見た。
岸本さん・・・お綺麗ですね。 話している様子も好印象。
「他人の役にたたないことだけを書こう」としているとのこと。そういうトコもイイ。
『あの夏、エデン・ロードで』
仙台への出張で新幹線に乗車する必要があって大宮駅に。乗車までに少々の空き時間があり、駅構内の書店に入った。
そこで目に付いたのが本書。
主人公は少年らしい。
ある夏、少年が生涯にわたって影響される何かを経験する物語・・・・・ビルドゥングス・ロマンかい?
期待して購入。
読み易くて一気に読んだ・・・・・・・・・・・・だが・・・・・・期待外れだった。それも大外れだ。
結末に少しでも救いがあればまだしも、ただ、醜悪さ、おぞましさだけが残った。。。
帯の惹句「早くも2013年イヤミス No.1の圧倒的な声!」に釣られた私が悪いんだろうが・・・、何処のどいつがそんな声あげてんだっつぅーの!(  ̄っ ̄)
少年の成長物語と云えば、古くは 『飛ぶ教室』 、国産のでは 『鉄塔 武蔵野線』 。
そういうのを期待していただけにガッカリだorz。
『なんらかの事情』
前作『ねにもつタイプ』 以来、6年ぶりの著者のエッセイ。
おとぼけの一品が、再び炸裂した。
相変わらずのヘンテコ妄想エッセイだ。
こういうのを読んでいると、こういうのばっかり読んでいたいと思う。
暖かくなったら缶ビール片手に風呂で半身浴しながらのんびりと読んでやろうとも思う。
一つひとつの作品が短いから、寝しなに読むのにも具合がイイから、お気に入りのは何度も読んじゃう。
生産性だとか有用性だとか機能性だとか、そんなもんはどっかへうっちゃっておいて、ただただ毎日グータラしていていいんだと思えてくる危険な内容の本だ。
で、みんなにもお薦めだァ!
↓この著者の他の危険な本↓
『六人目の少女』
- IL SUGGERITORE (2009)
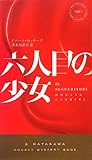
- 『六人目の少女』 ドナート・カッリージ/著、 清水由貴子/訳、 ハヤカワ・ポケット・ミステリ(2013)
犯罪学者ゴラン・ガヴィラが呼び出された森で見つかったのは左腕・・・が5本・・・。
世間を震撼させている5人の少女の連続誘拐事件。やがて左腕は彼女たちのものと判明する。
だが、その森では6本目の腕が発見されていた・・・。当局には6人目の誘拐があったという情報はないにも拘わらず・・・。
しかも6本目の腕は生体から切断されたとの分析結果が得られた・・・。
いったい6人目の少女は? 彼女は生きている??
失踪人捜索のエキスパートであるミーラ・ヴァスケスに、犯罪学者ゴラン・ガヴィラと特別捜査官たちから構成される捜査チームに加わるよう命令が下る。
何としてでも6人目の少女を救いたい。その一心で捜査チームに加わったミーラ。
ミーラとガヴィラと特別捜査官達の懸命の捜査を嘲笑うかのように、犯人は少女たちの遺体を敢えて一人づつ発見させて行く。少女たちの遺体発見現場で見つかる遺留品や状況などから、犯罪学者ガヴィラは犯人のプロファイルや精神状態を推測し、やがて、捜査チームは容疑者を発見した・・・・・かのように見えた。
しかし、別の少女の遺体が発見されるたびに、別の容疑者がまた現れてくる。。。
複数のシリアル・キラーによる犯行!? しかも、その複数の犯人を陰で操るものがいる・・・・・!?
イントロダクションの強烈なインパクト。 プロット・アイデアの新鮮さ。 意外な展開の連続!それが幾つもある。
さらに、家庭に問題を抱ている捜査官、過去の事件において失敗を犯している犯罪学者ゴラン・ガヴィラ、そして、あるトラウマを抱えている主人公ミーラ・ヴァスケス、など、捜査側の人間の置かれた状況も直接的に事件に関わることになり、物語の核心部に影響を与える。
見事な人物設定。キャスト配置。
『羊たちの沈黙』が発表されて以来いくつも描かれたサイコ・サスペンス。かつて乱発され、一時期は飽和状態にあったサイコ・サスペンス。それらとは一線を画す本作。
・・・と思えた。
確かに既往作品とはレベルが違う。『羊たちの沈黙』以来の凄いサイコ・サスペンスだと思う。クライマックスまでは・・・。
クライマックスで、ある主要人物に訪れる転向が安直過ぎるのではないかと私には思えてしまった。意外な真相の開示による大どんでん返しの場面を描くことに注力し過ぎて、その人物が転向する根拠の説明としては説得力に欠けている(強引すぎる)ように思えた。そこがチョイと残念。
しかし、期待するところもある。
不気味なエンディングに垣間見えたフランキーの真のフィナーレとミーラの行く末が今後描かれることに。。。
続編刊行の期待を込めて、お薦めです。
『世界を、こんなふうに見てごらん』
- 50年近くも生きてると、私がマヌケなことを云っていても意見・苦言を言ってくれる人間も少なくなってくる。
- もっとも、大抵の説教・小言は既に聞いてるから、今さら他人の云うことなどに聞く耳を持っちゃいないのだが。
- ハウトゥ本なども紙の無駄使いだと思ってるし。
だが、時には気持ち揺さぶられる言葉に、意見に、考え方に、出会うこともある。
故・日高敏隆博士のエッセイには、素直に首を垂れさせてくれたり、凝り固まった自分の認識や考え方を修正する機会を与えてくれたりする。
「はじめに」と<講演録>を含めて12編のエッセイが載っている。
すべての文章がイイ。
その中でも、「宙(そら)に浮くすすめ」、「イリュージョンなしに世界は見えない」 の2編は格別だ。
優しい言葉で、簡単な文章で語る口調(文調)だが、根源的なコトを云われているような気がする。
お薦めです。
↓日高敏隆博士のサイエンス・エッセイや訳書に関する記事↓
『生物から見た世界』
『セミたちと温暖化』
『ネコはどうしてわがままか』
『人間はどこまで動物か』
『鼻行類』
『春の数え方』
『決着! 恐竜絶滅論争』
6550万年前に地球に衝突した小惑星による環境変動が、恐竜を含む動植物の大量絶滅を招いた・・・。
1980年に発表された恐竜絶滅の原因に関するこの新説は世界の科学界を揺るがした。以来、この説に対する反論がいくつも登場した。しかし、1991年のユカタン半島沖のチチュルブ・クレーターの発見と、その後の小惑星の衝突を裏付ける証拠の数々によって、“小惑星衝突説”は専門家の間では定説とされていた。
だが、いまだに絶滅の原因をめぐって新説が発表されてはマスコミを賑わす状況にあった。衝突説をどうしても受け入れられない学者達がいる・・・。
2010年3月5日に科学雑誌「サイエンス」に発表された論文、
The Chicxulub Impact and Mass Extinction at the Creaceous-Paleogene Boundary,
Science Vol.327, No.5970, p.1214-1218, 5 March 2010.
「白亜紀と古第三紀の境界におけるチチュルブ衝突と大量絶滅」
この論文は、衝突説を支持する41人もの世界中の学者達によって「論争の余地なし」とする決定的なものである。
その41人の中の一人が本書の著者で、本書は、6550万年前の大量絶滅に関して「衝突説」以外に説明できないことをトコトン解説したものだ。
わずか100ページの解説書であるが良くまとまっていて中高生でも判るように書かれている。私でも判る。
科学に対するアプローチの仕方も謙虚で好感が持てる。
『喪失』
- gone (2010)
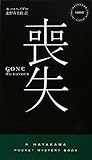
- 『喪失』 モー・ヘイダー/著、 北野寿美枝/訳、 ハヤカワ・ポケット・ミステリ(2012)
2012年のアメリカ探偵作家クラブ賞を東野圭吾・著『容疑者Xの献身』と争い、その『容疑者・・・』を破り、最優秀長編賞を受賞した作品だそうだ。
それにしても最近のポケミスはどれもこれも長い。本作も2段組み480ページもある。分厚い作品は読み始めるのに覚悟がいる・・・。
日・月・火・水曜日の四日間で半分ほど読んでいたが、昨日の出張の往復車中で残り半分を一気に読み終えた。長距離列車の座席での読書は捗る。
買い物帰りの主婦を狙った車の強奪事件。しかし、後部座席には幼い少女が乗っていた・・・。
車の窃盗が目的なら、少女の解放は時間の問題と目されていた。だが、少女の行方は依然不明のまま・・・。
重大犯罪捜査隊の指揮官ジャック・キャフェリー警部は、誘拐事件として扱うことに捜査方針を切り替える。
そして、今回と同じような事件が過去にもあったことが判明し、事件の様相は一変する。
連続少女誘拐事件!?
狡猾な犯人は警察と被害者家族を挑発し、遂には、刑事が警護するセイフティ・ハウスからさえ少女の拉致に成功する。さらわれた少女たちはどこに?? 焦るキャフェリー警部・・・。
キャフェリー警部に過去二件の少女誘拐未遂事件があったことを指摘した潜水捜索隊隊長のフリー・マーリー巡査部長は、その経験と勘から、ある運河を捜索し、その近くにある19世紀に掘られたトンネルに着目する。キャフェリー警部に進言して行った捜索の成果はゼロだった・・・。だが彼女の勘は、何かを見落とししていると告げていた・・・。
キャフェリー警部視点で描かれた章とマーリー巡査部長視点で描かれた章を中心とし、ときおり犯人もしくは被害者家族視点で描かれた章を挟みなが物語は進行する。その進行具合は実にサスペンスフルだ。
キャフェリー警部とマーリー巡査部長、主役二人のキャラ描写も申し分ない。
だが、幾つか引っ掛かる点があった。
一つは犯人の動機。過去のトラウマが原因であるかのように仄めかされているが、そうなの?って思えちゃう。ここまでの事件を起こすには動機が軽い。。。犯人の心理描写の書き込みが足りないように思えた。
二つ目はマーリー巡査部長が抱える秘密。前作に関連するのだろうが、彼女のキャラ設定からして、何故そんなことをした???と思えるようなエピソードが描かれている。なんだか不自然・・・。
まァ、幾つかの欠点は挙げてみたものの、総じて楽しめた作品であることは確か。
『失脚/巫女の死 デュレンマット傑作選』
昨年末のミステリー・ランキング本に挙げられていたのを見て覚えていたヤツ。
作者デュレンマットは、スイスの劇作家・小説家。ついこの前読んだ『ミステリ文学』 でも挙げられていた作家。その4編の作品を集めたもの。
光文社古典新訳文庫ならではのナイス・チョイス作品!
■トンネル
24歳の肥った男が乗ったいつもの列車。列車はトンネルに入った・・・。が、列車はいつになってもトンネルから抜け出さない。列車はトンネル内の下り坂を徐々に速度を上げて行く・・・。
短編ミステリにありがちな結末。つまり物語は決着しない・・・。 リドル。
■失脚
一党独裁国家の政治局幹部が集まった密室での権力闘争劇をデフォルメして描いた物語。
密かにお互いの動向を監視し合い、影では足の引っ張り合いを行っている政治局の幹部たち。
僅かな政治的失言や弱気な態度が、即座に自身の失脚に繋がる会議。そこではグロテスクな駆け引きが行われている・・・。
・・・シニカルな喜劇。
■故障 -まだ可能な物語-
これが一番面白かった。
自動車の突然の故障によって地方の村の引退した裁判官の家に宿泊することになった主人公の男。
その家の近所に住む引退した元検事と、やはり引退した元弁護士らも一緒になって、一夜の晩餐会とゲームとしての裁判が開かれる。
主人公は上司殺しの犯人に仕立て上げられ・・・・・、その結末は喜劇と化す。
読み終った直後は、化かされたようで、ポワワーンとなる。その後、じんわりと、「もしかしたら、こりゃ、なんだかスゲー作品かも!?」と思う・・・。
■巫女の死
ギリシア神話「オイディプス王」の中身が判っていない我が身にはナカナカ理解しにくい内容だった。
浅学・・・orz・・・。
4編どれもが、純文学とも、純エンターテイメントとも云えない内容。
今まで経験したことのない奇妙な読後感を持つ作品。
どこがどう奇妙なのかを具体的に言い表せない語彙力・表現力の無さが情けない・・・。
・・・が、読んでみて、と云いたくなる作品。
ん~、やはり、光文社古典新訳文庫は凄い。
<これまでに読んだ光文社古典新訳文庫>
『梁塵秘抄』 『アウルクリーク橋の出来事/豹の眼』 『ガラスの鍵』 『天来の美酒/消えちゃった』
『種の起源(上)』 『種の起源(下)』 『カフェ古典新約文庫 Vol.1』 『闇の奥』
『愚者(あほ)が出てくる、城塞(おしろ)が見える』 『幼年期の終わり』 『木曜日だった男』 『飛ぶ教室』
『ミステリ文学』
- Le roman policier (2002)

- 『ミステリ文学』 アンドレ・ヴァノンシニ/著、 太田浩一/訳、 (文庫クセジュ965)/白水社(2012)
白水社の【文庫クセジュ】とかいうシリーズの1冊。
近・現代フランス文学研究者でスイスのバーゼル大学教授という肩書を持つ著者によるミステリ小説の歴史変遷の解説や作品・作家の紹介。
E・A・ポーやC・ドイルなどのミステリ創設期の作家、
A・クリスティやG・K・チェスタトンなどの黄金期の作家、
D・ハメットやR・チャンドラーなどのハードボイルド作家、
J・M・ケインやJ・トンプスンなどのノワール作家、
W・アイリッシュやP・ハイスミスなどのサスペンス作家・・・などなどの作家論、作品論がメイン。
これらの前段に「ミステリの骨格」という、ミステリを文学の1ジャンルとして捉えた場合の理論や構造に関する概要が述べられている。
ただ、この章に関しては、原著がアカデミックな調子・用語を使っているせいなのか?訳出された日本語が非常に判りづらい。
作家論・作品論としてもプロの研究者のレポートとしては平凡な内容。
日本のミステリ研究者や書評家による評論の方がはるかに内容が濃いと思う。
『JIN -仁-』
正月のテレビドラマ再放送を見て原作を読みたくなり、古本屋で文庫版全13巻をカミさんと折半してまとめ買いし、一気に読み切った。
TV版の南方仁は本来自分が生きていた平成の時代(あるいは残してきた恋人)に未練を抱いているのに対し、マンガ版の南方仁は積極的に江戸時代(置かれた対場・境遇)に馴染もうとしている。
TV版の橘咲は南方仁という人間自体に惹かれているのに対し、マンガ版の橘咲はどちらかと云うと南方仁がもたらした未来の医療技術に惹かれている度合いが高い。
TV版の坂本龍馬はオーバーアクションだったのに対し、マンガ版の坂本龍馬は一般的な龍馬像に比較的忠実だった。
・・・ように思えた。
マンガとはいえ、なかなか中身の詰まった内容だけに、1巻を読むのにもソコソコの時間は掛かる。
しかし、何もせずただゴロゴロして過ごしている正月休みなので、マンガ全巻一気読みなどといったことも出来る。
そろそろ体を動かし始めなければ・・・。








