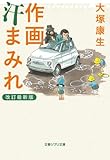『役たたず、』
- GW突入。
- 今年は勤務先オフィースが移転することもあって、飛び石の平日も休業。10連休。何しよう・・・。

- 『役たたず、』 石田千/著、 光文社新書(2013)
今週の初めに読み終った本書。
“役立たず”作家の視点からの風景が綴られたエッセイ。
久しぶりに、次のも読み続けたい! 過去作も読みたい!と思える作家に出会った。 石田千。
取りあげる題材が、モノの観方が、世間に対する感覚が、凄く合う。
文章のテイストが、行間の雰囲気が、言いまわしが、実に心地良い。
たまには純文学??
中学生の娘がブック・オフで買ってきた文庫本。
- 酔って候<新装版> (文春文庫)/文藝春秋
 通勤電車の中でサラリーマンのオッサンが読んでる本だ。。。
通勤電車の中でサラリーマンのオッサンが読んでる本だ。。。
- 阿部一族・舞姫 (新潮文庫)/新潮社
 森鴎外・・・? こんなの読むのか??
森鴎外・・・? こんなの読むのか??
- 斜陽 (新潮文庫)/新潮社
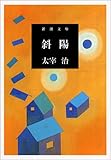 そして太宰・・・。そういや、この前も、『人間失格』を読んでた・・・なんでだ?
そして太宰・・・。そういや、この前も、『人間失格』を読んでた・・・なんでだ?
↑私はどれも読んだことがない。特に、国語の教科書に出てくるような作家のなんて・・・。
今、娘に借りた『黒子のバスケ』を読んでる・・・。・・・奇跡の世代・・・、面白い(*゚.゚)ゞ。
『作画汗まみれ』
「文春ジブリ文庫」だと。
日本のアニメーションの創成期から活躍したアニメーター氏の回顧録と少しの提言。
アニメーションを創る人達の、創作者あるいは職人として個人が持つ苦労と楽しみ、組織人として在るべき立場、それらの併在がもたらす矛盾、矛盾を受け入れつつ好きなことを仕事にし続ける姿、そんなことが良く描かれている。
どの分野でも、パイオニア的存在の一家言には説得力がある。
『知の逆転』
勤務先の同僚から借りて読んだもの。ありがとうございます。
インタビュー集。その相手が凄い。
ジャレド・ダイアモンド
ノーム・チョムスキー
オリバー・サックス
マービン・ミンスキー
トム・レイトン
ジェームズ・ワトソン ・・・っつう、世界的知の巨人たち6人。
J・ダイアモンドは、その著書
を幾つか読んだことがある。最近も最新作が翻訳出版された。
進化生物学などを基礎とした文明論の権威だけあって、非常にバランスの取れた考えに基づいた受け答えをしているように感じた。
N・チョムスキーは、アメリカ人でありながら、アメリカの帝国主義に対する批判を声高に行う過激なオジサン。こういう学者を輩出するアメリカの懐の大きさ・・・。
オリバー・サックスは脳神経科医。この人の著作 も1作品だけだが読んだことある。
若い人に勧める推薦図書を丁寧に挙げてくれるところが好印象。
M・ミンスキーって方の記事には惹かれるところがなかった。。。
本書中で、一番興味を持ったのが、トム・レイトンって方。
MITの応用数学の教授で、ネットワーク・アルゴリズムだとかサイバー・セキュリティーだとかの分野で世界的にも相当のシェアを持つ“誰も知らないインターネット上最大の会社”=アカマイ・テクノロジーズ社を創設した人物。会社設立までの過程がユニークで、その話し方も謙虚。
J・ワトソンは、DNA二重らせん構造の発見者の一人。この人の著作も昔に読んだ覚えがあるが、やけに威張った人って印象しか残っていなかった。このインタビュー記事を読んでもあまり印象は変わらないな。
インタビュアーの吉成さんて方は凄い才媛。今後の活躍に期待。
サイエンス・ライターとして、多くのオモシロ科学本に関わってほしい。
ところで、読み終っても本書タイトルの意味が解らん?
『夜に生きる』
昨日は仙台出張。「はやぶさ」なら大宮から1時間半も掛からずに仙台まで行ってしまう。だから当然日帰り。
で、その仙台では、空き時間を使って、文春文庫の新ブランド「ジブリ文庫」の1作『作画汗まみれ』を購入。
出張のたびにその地の本屋に入らずにはいられない。へんな癖だ。
そういえば、広瀬通りに面した本屋を見付けたんだった。チェーン店ではなさそうだった。いつか入ってみなければ。。。
さて、仙台出張の新幹線の中で読んでたのが、このルヘインの新作。今週の初めから読みだして、新幹線車中で一気に読み進めて、本日読了。
昔からアメリカン・ミステリ小説の一つのカテゴリにギャング・ストーリーがあって、本作もそんな中の一つ。
禁酒法時代のボストンで育った若き無法者が、敵対組織のボスの情婦に惚れて・・・・、抗争や裏切りに巻き込まれて・・・・、刑務所での囚人時代を経て・・・・、出所後は次第に才覚が認められ・・・・、やがてボスに成り上がり・・・・、その後・・・・、という物語。
能書きなど述べる必要の無いくらいのオーソドックスさ。
まあ、ギャング・ストーリーはどれもだいたい似たような話になるが、それでも一流の作家が書くと面白くなる。
使い古されたプロットでも、魅力的な人物と人間関係が描かれていれば充分新たな気持ちで読める。
ストーリーがシンプルなだけに、余計、人物描写で読ませる作品になるのだろう。
ギャング・ストーリーの新たな傑作。
お薦めです。
『ビブリア古書堂の事件手帖4 栞子さんと二つの顔』
人気シリーズの4作目。このシリーズは勤務先の同僚に借りて読んでる。毎度ありがとうございます。
これまでとは違い長編だったこと、江戸川乱歩を扱っていること、本シリーズで最も謎多き人物=篠川智恵子の登場、ってことで、個人的にはシリーズ中で一番面白かった。
『理性の限界 不可能性・不確定性・不完全性』
『理性の限界――不可能性・不確定性・不完全性』 高橋昌一郎/著、 講談社現代新書(2008)
過日読んだ本 との関連で本書を読んだのだが、こちらの方が簡潔。
日本語プロパーの著者が書いたものだから当然読み易い。
序 章: 理性の限界とは何か
第1章: 選択の限界
第2章: 科学の限界
第3章: 知識の限界
アロウの不可能性定理が、囚人のジレンマ、ナッシュ均衡などと関連付けられている箇所はイメージ的に判りやすかった。
2作続けて“不可能、不確定、不完全”に関係する新書を読んでみた。
で、結局、ヒトが持てる知性・知識には限界があるんだったことが何となく判ったりするが、個人的にはそのような「限界」には到底近づくことも出来ない訳だから、日常には全く影響ない。
だが、そのようなことを知ると(知ったつもりになると)、なぜか、大局観と細部に拘る眼、諦念と矜持、それらを併せ持つことが大事なんだなァなんて思っちゃう訳だ。。。
お薦めです。
この著者の他のも読んでみようかな???
『不可能、不確定、不完全』
- 読み終るのに結構な時間が掛かった本書。
- 読んでる最中も良く判らないことだらけで、判らないままに読み続けた。

- 『不可能、不確定、不完全: 「できない」を証明する数学の力』 ジェイムズ・D・スタイン/著、ハヤカワ・ノンフィクション文庫(2012)
そもそもヒトには知ることのできないもの、試みたくてもできないこと、がある。
そういったことを数学的に、つまりはほとんど真理として証明してしまった・・・。
ハイゼンベルクの不確定性原理
ゲーデルの不完全性定理
アローの不可能性定理
↑これらは、現在のところ知られている「できない」、「知り得ない」を証明した原理・定理。
物理学、数学の世界では、今後も、「できない」を証明する可能性がある。あるいは、「「できない」を証明できない」コトなんかも・・・。 ・・・パラドクス???
さて、「できない」が判ったところで、それはいったい何のためなんだ? と思っちゃう。
しかし一方で、そもそもヒトには何かを知りたいという感情が生来的に備わっているんだから、「○○のため」なんてコトにたいした意味はないんだろう、とも思う。
「できる」も「できない」も、「判る」も「判らない」も、とにかく知りたいんだ。。。
著者は、ハイゼルベルクの不確定性原理が証明されたことによってコンピュータやレーザーが開発されたように、答えがないことが判った場合でも、そのような結末によって別の興味深いこと、実用的なモノの発見に繋がることもある、って言ってる。
失敗だったゆえの驚きの展開が待っていることもある、と。
まァ、私の頭では理解できないことだらけだった本書だったが、仕事に関連した事柄もあったので、そこんとこをメモッとこう。
■ニュートンの重力理論はアインシュタインの相対性理論に取って代わられたが、実用的な使用が難しい
相対性理論でなくとも、日常の予測・推定にはニュートンの重力理論で充分な精度の結果が得られる
(p76)。
これは、私個人としても常々感じていること。シナリオ地震動による構造物の振動予測に相対性理論
は必要ないが、ニュートン力学は必須の知識だ。人工衛星などの設計や軌道予測にだって相対性理論
は必要なかろう。
■「ヤング率」で有名なトーマス・ヤングは、エジプト学者としても一流で、ヒエログリフ解読を前進させた。
また、医学部学生の頃、乱視の原因が角膜の湾曲が不規則になることだと診断した。さらに、光が波動
現象であることを示す実験を行ったこともある(p.98-99)。
これも、仕事でよく使う「ヤング率」のヤングさんに関わることで、非常に印象的だった記述。
ヤングさんて、力学屋さんだけじゃなかったんだ・・・。
■“数値解析”についての記述(p.178-179)。解くことのできない方程式の近似解を得ること。
この部分も、私が日常的に仕事で行っていることを端的に述べてくれている箇所。
引き続き ↓↓こちら↓↓ も読書中。こっちはもう少し判り易そう。。。かな?
『地形からみた歴史 古代景観を復原する』

- 『地形からみた歴史 古代景観を復原する』 日下雅義/著、 講談社学術文庫(2012)
地形とか地質とかを分析した内容のモノって、なんか好きだ。その上に“歴史”なんてェ文字が乗ってたもんだから、興味惹かれた。- このテの本では、かつて 『アースダイバー』 という傑作もあったし・・・。
ん~、でもこの本は読みづらかったな。なんでだろう?
文学畑の学者の書いた文章構成や話題の展開の仕方に違和感を感じたからなのか?
単純に相性が良くなかっただけのような気もする・・・。
一文一文、一言一言を追って読むのは途中で断念。
中身は好きな分野なだけに、もう少し時間を置いたら再度挑戦してみようかな?
後半部は、地形図、地質柱状図、地質断面図とそのキャプションを主に見て、文章は飛ばし飛ばしで読んで行くことにした。