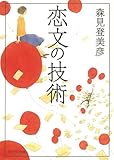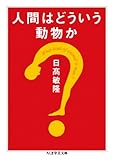『柳生大作戦』
今週はこれを読んでた。
水曜日の仙台出張の新幹線の中でクライマックスを迎えた。
ひさしぶりの荒山ワールド。
朝鮮半島史(東アジア史)と倭国・日本史、壬申の乱と関ヶ原の合戦、これらをリンクさせた物語。
史実、推測・推定、空想、妄想、・・・、これらゴッチャ煮の伝記小説。
いや、伝記小説なんてもんじゃない。登場人物が月面で修業したり、タイムマシンに乗ったりしてるんだから、伝記小説とか時代小説とかの枠をはるかに飛び越えてる・・・。
あらすじだとか、登場人物の魅力だとか、そんなことトヤカク云っても始まらない。とにかく物語は滅茶苦茶だ。だが、エンターテイメントだからそれもアリだ。
・・・・・それしか言えない。。。
参考・引用文献として、山田風太郎、山岡荘八、峰隆一郎や五味康祐などの歴史・伝記小説が挙げられており、アカデミックな歴史書とこれらを同列に扱っている。こんなところにも著者=荒山の立ち位置が伺える。
「あとがき」での歴史学者に対する挑戦もイケテル。これも含めて荒山流エンターテイメントなんだろな。
『人間の性はなぜ奇妙に進化したのか』
ジャレド・ダイアモンドのかなりの前の作品の文庫化。
『文明崩壊』や『銃、病原菌、鉄』にくらべるとやはり面白度は落ちる。
進化論をベースにすれば、大抵のことが説明できそう。。。
ただし、多くの人が納得する説明を行うためには、根気のいる思考実験と閃きが必要だ。
第1回ビブリオバトル
今週火曜日の勤務時間外。社内の若手とそうでもない人に会議室に集まってもらってビブリオバトル をやってみた。
紹介者は4名。ギャラリー2名。全員男。全員がエンジニア。
私が紹介したのは『アースダイバー』
他の3人が紹介したのは、『笑わない数学者』、『なぜ、「これ」は健康にいいのか?』、『恋文の技術』
4名それぞれが自分が持ってきた作品に関して5分きっかりで紹介を行い、各本について3分の質疑応答を行った。
4冊のうちどれが一番「読みたい本」か?、ギャラリーを含めて6名による挙手を行い、チャンプ本を決めた。
結果、
アースダイバー・・・2票
笑わない数学者・・・0票
なぜ「これ」は健康に・・・1票
恋文の技術・・・3票
ということで、第1回のチャンプ本は、『恋文の技術』に決定・・・。
これは、今回参加者のうち、一番の若手が紹介した作品だった。 私もこれに手を挙げた。
なかなかの好評だった。他の若手にもビブリオバトルの噂が出回ってるらしい!?
第2回目もありそう・・・。
『人間はどういう動物か』
最初に関係ない話で恐縮ですが、「ちくま文庫」はリーズナブル、なのに「ちくま学芸文庫」はチト高い・・・と、学芸文庫を購入する度に思うのです。
“学芸”が付いたくらいで何故?
↓本書の構成↓
第一章 人間はどういう動物か
第二章 論理と共生
第三章 そもそも科学とはなにか
あとがき
解説 教養としての科学(絲山秋子)
私の勝手な解釈ではあるが・・・・・、
「利己的遺伝子」と「ミーム」というものを知り、人間は特殊な存在ではなく数多いる動物の一種に過ぎない・・・という考え方を尊重して世の中を眺め、自分の存在や言動を律する。大局観を持ち、自らの行いなどたかが知れていると思っていれば、この世界をシンプルに生きてゆける・・・ような気がする。
日高敏隆センセのエッセイを読むと、いつもそんなことを感じる。本書の第一章からは、いつにも増してそんなことが感じ取れる。
大局観とは「概念」なのだ、とも思う。
HowTo本ではこうした概念を感じることはできないと思う。
音楽や絵画や小説や随筆など、あまり具体的とも云えそうにない漠然とした他人の考え方・観かたに数多く触れていると、そのうちそれらが混ざり合って、いつしかなんとなく自分なりの「概念」が薄ぼんやりと見えてくる・・・?
もちろん、様々な体験をするのが一番なのだろうが、ヒト一人の体験などたかが知れている。
昨日の寺田寅彦の随筆もそうだったが、エライ先生が書いたエッセイを読むと、俺ってバカでもイイじゃん!って思えてくる。
よくよく考えてみると、↑こう思わせてくれるエッセイを、私は「良いエッセイ」と定義している。。。
『柿の種』

- 『柿の種』 寺田寅彦/著、 岩波文庫(1996)、文庫
阪神淡路大震災の翌年に再刷されたのか?
余りにも有名な随筆。だが、この齢まで読まずにきた。
もともとは『柿の種』と『橡の実(とちのみ)』の2作だったのを併せたものらしい。
短いのは2、3行、長くても2ページ程度の短いエッセイ176篇。
大正9年から昭和10年までに書かれたもの。この間に関東大震災を挟んでいる・・・・・。
日常の何気ない出来事や世相や風景や芸術や科学や人付き合いのことや夏目先生のことなどに触れる際に魅せる優しい心情。ときに鋭い観察。そして冷徹な考察。
文理融合の人の書く文章は味がある。
「哲学も科学も寒き嚔(くさめ)哉」 p.164
↑↑この有名な句も、前後のエッセイとの連なりで読むと、何となく意味が解る(・・・ような気がする)。
寺田寅彦随筆集(全5冊)もいずれ読んでみたい。。。
『茶の本』
午後出社の前に昼飯を食おうと寄ったショッピングモール。
その内にある紀伊国屋書店。ん~、文庫の品揃えが少ない・・・・・。
↓その紀伊国屋で購入した岩波文庫。
岡倉天心が英文で書いたものの訳書。
今更感承知で読んでみた。
はしがき、目次、本文、解説などを併せてもわずか100ページの文庫。
型や形式を生み出すに至ったかつての日本人の心性を語った部分は面白かったんだけど、形式だけ、心情だけ、を語る部分はイマイチ理解しづらかったな。
両者の“関連付け”が面白いんだよな。
再読の必要あり。
『掏摸(スリ)』
若き天才スリ師が、「最悪」の男に見込まれ、追い込まれて行く・・・・・。
ノワールの部類に入るのかな?
世の中のルールから逸脱したい。その結果、場合によっては破滅してもしょうがない・・・、なんてフト思うことってある!?
だが、現実はそうもいかない。そんな度胸も無い。
多かれ少なかれ、そんな破滅指向のある輩なら、この小説に惹かれるかもしれない。私は惹かれた。
わずか180ページの短い小説。だが、気持ちをエグられる。
『銃』 も読み直してみるか・・・・・。
『特捜部Q カルテ番号64』
特捜部Qシリーズの第4段。 以前の作品記事はコチラ⇒ 第1作 第2作 第3作
ナイトクラブを経営する一人の女性の失踪事件を契機として、1987年の一時期に集中してコペンハーゲン市内に5人もの行方不明者が存在したことに気が付いた特捜部Qメンバーのアサドとローセ。
その事実に大事件を予感した特捜部Q責任者カール・マーク警部は捜査に着手する・・・・・。
ユーモアとシリアスが程良く混在する本シリーズ。今回もその特徴は失われていない。
しかも今作はデンマーク現代史における最暗部をえぐる問題作でもあり、これまでにも増して読み応え十分である。
さて、このシリーズのもう一つの特徴として、コールドケースの事件を捜査するコペンハーゲン警察特捜部Qメンバー視点のシーンと、事件に最も深く関係する被害者もしくは加害者(被害者と加害者が同一人物であることも)の側からのシーンが交互に描かれる、というのもある。
どちらのシーンでも、登場人物たちの感情の微細な動きまでが理解できるように描かれているから、捜査側メンバーにも、事件関係者(特に被害者)にも、ドップリと感情移入してしまう。まったくもって巧みな描き方だ。作者の力量を感じる。
今作で、特捜部Qメンバー以外で事件に深く関わる人物は二人。
優生思想を抱き、デンマーク国にとって有益とならない人間の排除をあからさまに打ち出す新進政党<明確なる一線>の党首クアト・ヴァズ。
恵まれない生い立ちと境遇ゆえに、凄惨な目に合った過去を持つ老女ニーデ・ローセン。
この2人の人物それぞれの性格と両者の対比が凄く良く描けている。クアト・ヴァズに対しては憎しみが、ニーデ・ローセンに対しては同情が自然に湧き起こる。
そして、シリーズの成熟とともに、特捜部Qメンバー1人一人の性格付けや特徴が明確になってきており、より親近感を覚えやすくなってきている。主人公カール・マークはもとより、今作ではアサドとローセの人間性に強く惹かれているのを感じた。
ミステリとしての出来は前作の方が上回っていたように思えるが、特捜部Qメンバーの描かれ方は今作の方が良かったかな。
今作では、シリーズ全編を通しての謎=カールとかつての同僚達に起こった「アマー島銃撃事件」に関する新たな謎も提示され、次作以降への興味は尽きない。
540ページ2段組みの長~い小説が苦にならずに読めるのだから、お薦めの物語であることは確か。
『機動戦士ガンダム サンダーボルト 2』
ガンダム・ワールド作品。1年戦争時のある局面を描いた作品。
1巻ではスナイパーを前面に出したストーリーだった。
この2巻では、スナイパーという特殊技能を持つキャラの位置付けが変容しつつある!?
そこがちょっと残念。
「スナイパー」を突き詰めてほしい。
さらに引っ掛かったのは、なぜ四肢を切断しないとサイコミュが使えないのか?ってトコ。