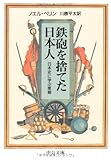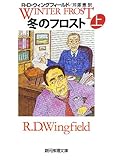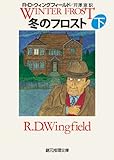『本当はちがうんだ日記』
またまたホムラ・エッセイ。
著者は世間の一般的な感覚とは違う世界で生きてるらしい。
いろいろなトコで、いろいろなコトに、違和感を抱いているらしい。
それでも何とか世間に合わせようとして日々を暮らしているものだから、ちょっとした事にも緊張を強いられているらしい。
↑かようなことを、トボケた調子で、アイロニーを笑いに包んで描いてる。
大甘な1980年代を学生として過ごしてきた者特有の匂いが感じられる。
多かれ少なかれこれを読んでる私にも当てはまるところがあるナと感じながら、ニタニタしながら通勤の車中で読んだ。
2章では「本」をネタにしたエッセイが11篇集められてる。ココを読んでるとニタニタがニヤニヤになる。
そういや、深沢七郎のエッセイにこれと似た題名の『言わなければよかったのに日記』 ってのがあったな。
関係あんのか??
『絶叫委員会』
- 最近続けて読んでるのが穂村弘のエッセイ。
- 『絶叫委員会』 『本当はちがうんだ日記』 『もうおうちへかえりましょう』 と立て続けに読んでる。
- 出張に行くとその土地の書店に入ってみたくなるが、その際に何か購入しようとすると文庫のエッセイが程良い。 最近の2週間でいろいろなところへ行く機会があったので、その都度、穂村弘の文庫エッセイを買って、車中やホテルで摘み読みしてた。

- 『絶叫委員会』 穂村弘/著、 ちくま文庫(2013)
ホムラ・エッセイの面白さについては以前から噂に聞いてた。
「噂に聞いてた」といっても、勤務先の誰かからだとか、ご近所の誰かからというわけではない。おそらくは、どこかの新聞の書評欄で幾つか読んだのをうろ覚えしてたんだと思う。
本書は、偶然に、不合理に、ナンセンスに、真剣に、生まれては消えてゆく言葉たちについての著者の考察。考察といっても、多分に妄想や空想や勝手な思い込みも含まれる。
突然のアクシデントで、日常のルーティンを外れたときに、行動と次の行動の間に、思考から行動への移行の狭間に、そんなときに意図せずに思わず誕生した言葉。
著者は、そんな言葉たちに常にアンテナを張ってるんだ。日常的にメモってるらしい?
詩人て、作家ってスゲー。
エッセイにハマる。
昨年あたりから意識してエッセイ・随筆を読むようにしだしたら、これが結構ハマった(ハマってる)。
ハマった要因・・・、
まず何と言っても、大抵のエッセイ本は薄い。
だいたい200ページくらい。多くても300ページくらいだ。私の好物の翻訳ミステリ作品は最近ますます分厚くなってきていて文庫で500ページくらいの作品が当たり前になってきている。こんなのと比べると読む前に気合を必要としなくてイイ。気軽に読み始められる。
そんでもって、日本語プロパーの著者によるものが多いから文章が読み易い。
翻訳モノを読ませるにあたって、全ての文章から違和感をなくすのはなかなか難しいだろう。日本と外国とでは文化・考え方の違いというものがあって、原著の文章は当然のことながら日本語の言い回しや論理構成と違っているだろう。そういったものを翻訳すれば、通常我々が使う日本語での表現とは異なることもあるだろう。だが、日本人の書くエッセイにはそれがない。
そしてそして内容的にも満足できる。一言でいうとオモシロい(ものが結構ある)。
エッセイってのは、作家の考え、想い、思い、気付き、発見、などを綴ったものだが、やはりプロの書く文章は皆それぞれに巧い。まァ、技巧的に高いってのは当たり前として、重要なのはそんなことではなくて、書き手の視点、感性が独特だから、同じモノ・コトを観たとしても私のような一般人とは捉え方が違うんだ。
半世紀近くも生きてきた私が考えていたこと、感じていたことが、一つのエッセイによって変えられる場合がある。年齢的なモノと、自分を取り巻く環境の均質性もあって、自分の考えを変えさせられることなんて日常ではめったに遭遇しなくなったが、エッセイを読んでいると、たびたび変更を迫られるのだ。そして、それが心地良かったりする。
面白いエッセイの書き手は観察者として巧者なんだ。 そういう人のいうことには聞く耳を持とう。。。と思う。。。
『蔵書の苦しみ』
同じ光文社新書の『読書の腕前』 と同様、本に関するエッセイ。 この著者の場合、著作のほとんどは「本」に関することだけど・・・。
著者は2~3万冊も本を溜め込んだそうだ。そんな自分の溜め込んだ本のこと、蔵書の仕方、蔵書空間の確保、処理・処分方法、はたまた他の人が溜め込んだ本をどうしているのか? に関しての話が羅列されている。
そもそも本を2~3万冊も所有している人間など、超レア・ケースなのだから(?)、そんな大規模な「蔵書の話」など誰が読むのだろう?とも思えるが、実際のところ私が読んだってことは、世の中にはこのテノ話に対する需要があるってことだ!?
電車内で他人が読んでる本だったり、勤務先の同僚が昼休みに読んでる本だったり、とかく自分以外の人間が読んでる本が気になる・・・あるいは、こんな本を読んでるこの人自体のことが気になる・・・と思うのと同じような心理が働いているのだろう?
世の中にはそんな人間が結構居るってことなのか。
「蔵書」に関する他愛のない話が羅列されているだけで、だからって何? って感じの内容で、誰かの役に立つ情報などありはしない。けど、そんな内容だからこそ、のほほ~んとしながら読むエッセイとしての条件に適っていてイイ。
休日や長距離列車での移動中に、肩の力を抜き、ゆったりした気分で読むには最適。
『鉄砲を捨てた日本人』
薄くてすぐ読み終えることのできる本。
ヨーロッパで開発された鉄砲が日本で使われるようになったのは、当然のことながらヨーロッパに比べてかなり遅れた。
だが、伝来した鉄砲のメカニズムと、鉄砲を使うことによる社会的影響の大きさをすぐさま理解した日本人は、その大量生産を成功させた。十六世紀後半の日本は世界最大の鉄砲使用国となった。
戦国時代、世界中で最も鉄砲を生産し、かつ実戦的に使用したのが日本だった。近世初頭、日本は世界でも稀にみる軍事大国だったのだ。
だが・・・、
列島が統一された後、江戸時代を通じて日本は、日本人は、鉄砲の使用を捨てて刀剣の世界に戻った。
同時代のヨーロッパでは、鉄砲の使用拡大によって戦争が頻発していた。植民地支配、ドイツ30年戦争、英蘭戦争、英米戦争、ナポレオン戦争、・・・・・・。
それに反して日本は、江戸期を通して平和な世の中を構築し軍縮を行っていた。
科学技術の進歩、武器の使用という歴史において起こり得ないことが日本では生じていた・・・「鉄砲の放棄」。
ヨーロッパ世界にあっては、武器の進歩=技術の発達、によって経済力が向上した。
同時代の日本は、武器開発を放棄していたにもかかわらず、民生技術が進歩し、経済力が向上していた。
武器の進歩がなかったにもかかわらず技術の発達がみられた国だった・・・。
なぜか・・・?
この「なぜか?」と云うところの分析が本書の“キモ”なのだろうが、著者の分析内容はイマイチ説得力に欠ける。日本人の精神性にあまりにも重きを置き過ぎているような気がする。社会システムや政治・経済・文化状況などの大枠的な観点からの分析が足りないと感じた。
さらに、著者の云う、江戸期日本における軍縮の事実をもって、世界の核軍縮に繋がる希望が見いだせるとは到底思えない。
それでも本書は面白かった。なぜなら、新しいモノの見方を提示してくれたから。
学校の歴史で習った「鉄砲伝来」に対して、「鉄砲放棄」という歴史上ユニークなエピソードを知らせてくれたから・・・・。
歴史を顧みる際、視点をどこに置くのか/どのように据えるのか、あるいは如何に新鮮な視点を用意するのが大事か、ということが良~くわかりました。
お薦めです。
第2回ビブリオバトル
そういや先週火曜日(だったか?)に社内ビブリオバトルの第2回目を実施したんだった。
6人参加。そのうち本の紹介をしたのは3人。5人くらいが丁度良いんだが・・・。
エントリーされたのは、↓この3作品。
結果は、 『七回死んだ男』 1票、 『天空の舟』 1票、 『鉄塔 武蔵野線』
4票
『バッドタイム・ブルース』
先週、『冬のフロスト』を読み終えて、次に読む本を探して入った書店。そこで目に付いたのが本書のカバー・イラスト。
『冬のフロスト』のカバー・イラストとそっくりのタッチの中年オヤジの絵・・・。ジャケ買い。
面白かった。
主人公はデキる刑事。ニック・ベルシー。だが、私生活に問題を抱えている。そもそもはギャンブルで身を崩した。一文無し。住む処も無し。カードも失効。警察上層部にも問題を抱えた刑事としてマークされている。
そんな折、大金持ちの独身男が行方不明との一報が入り、その件の担当になる。行方不明男の身元を調べているうちに、その男に隠し財産があるらしいことが判明してくる・・・。
その金を我がモノにしようと企むニック・ベルシー。
主人公ニック・ベルシーのやってる事はことごとく違法捜査だし、口八丁手八丁で様々な人間をダマクラかして目的を果たして行く。一言で表すと悪徳警官、ってことなのだろうが、それとはチョイと違うような気もする。
知性もあり、行動力もあり、矜持みたいなものも伺えて不思議と魅力的なのだ。
謎を前にすると(自分の身を守るためもあるが)、それを解明しないと気が済まない。所属する警察組織を欺きながら、単身で今は未だ見えない敵に立ち向かわなければならない。そのために知性と行動力を総動員して必死になっている姿に知らず知らずに惹かれている・・・。
担当の行方不明者=大金持ちの独身男の死体を自ら発見し、それを契機にイギリス・ロンドンを舞台にした国際的詐欺事件に関わって行くことになるニック・ベルシー刑事のダークな活躍がスピーディに描かれた本書。なんと、著者のデビュー作だそうだ。
お薦めです。
昇仙峡
3連休のうちの前半2日間は曇りがちだったせいか、連休前に比べればいくらか暑気も和らいだように感じた・・・?
今日は暑いけど・・・(^_^;)
3連休の初日7/13の午前中に甲府に用があって行ってきた。
用件が済んだ後は、大学の地盤工学の先生と地質の専門家の方に昇仙峡に連れて行ってもらった。
昇仙峡(しょうせんきょう)は、甲府市から北に6km行った山中にある花崗岩が侵食されてできた峡谷。
紅葉の頃は大変な賑わいだそうだが、この週末はそうでもなかった。
- ・・・・・と、まァ、景観スポットを専門家の解説付きで見て回る贅沢を半日味わった。
- ↓この本には、昇仙峡のことも載ってるらしい。
- 観光地の自然学―ジオパークでまなぶ/古今書院

『冬のフロスト』
モジュラー型犯罪捜査もののシリーズ第5弾。
関連作品の過去記事はコチラ ⇒ 『夜明けのフロスト』 『フロスト気質』
本作、イギリスでは15年も前に出版されている。 翻訳版はやっとこさ出た。 残りはあと1作。
上下巻で1000ページ近くもある文庫。だが、この1000ページを読んでいる時間が実に楽しかった。
殺人が起こる物語だから楽しいことばかりではないが、そこはまぁフィクションだ・・・。
真冬1月。
主人公フロスト警部は、相変わらず幾つもの事件を抱えてデントン署管内を日夜駆けずり回っている。
7歳と8歳の二人の少女の連続誘拐事件。 “夜の姫”たちを狙った連続殺人。“怪盗枕カバー”の出現。酔っぱらいフーリガンたちによる警察署内での狼藉。
上昇志向の強い女性刑事りズ・モード警部代行、無能な部下モーガン刑事に足を引っ張られながらも、これらの事件捜査全ての指揮をとる。
夜中であろうと早朝であろうと現場捜査に赴き、すべての検死解剖に立ち会い、容疑者たちの取り調べを行う。
さらにその間、事件解決には直接関係の無い内勤を適当にこなす。署内の犯罪統計資料をでっち上げ、捜査に掛かった経費に対する請求書金額の水増しをする・・・。
そして、官僚主義の権化=天敵マレット署長から呼び出され、経費削減、人員削減の条件を突き付けられつつ、事件の早期解決を厳命される・・・。
これだけの過酷な状態に置かれながらも、フロスト警部は下品なジョークをとばしながら飄々と事件に向き合う。
フロスト警部の捜査方法は実にユニークだ。
基本的には聞き込みに基づいて容疑者や状況証拠を見つけ、その後は勘に頼って、容疑者や犯罪現場に対して人海戦術でしらみつぶしに調べる。だが、この捜査方法では直接的な物的証拠が見つからない場合もある。しかもそれが多々ある・・・。
事件発生→ 現場捜査→ 容疑者(らしき人物)の特定→ フロストの思い付きによる人海戦術による聞き込みあるいは証拠品捜索→ 容疑者の取り調べ→ 科学捜査研究所による証拠品分析結果→ 物的証拠不十分→ 容疑者の解放・・・、を幾度となく繰り返すこととなる・・・。
失敗の連続・・・。
そんなフロスト警部だが、部下からの信頼は厚い。彼は捜査過程で生じるミスに対して、部下のであろうと、自分のであろうと、すべての責任を被るからであった。
勘と人海戦術による捜査が徒労に終わる。。。
だが、その捜査の過程で目にしていたこと、気に留めていたことが、後々になって・・・・・。
事件解決は往々に、そんなふうに迎えることになる。。。
結末は“現場第一主義によるルーティンワークの結実”、とでも受け取ると、一般サラリーマン読者には嬉しい。
お薦めです。