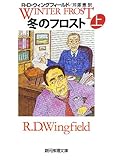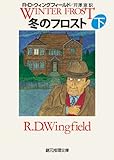『冬のフロスト』
モジュラー型犯罪捜査もののシリーズ第5弾。
関連作品の過去記事はコチラ ⇒ 『夜明けのフロスト』 『フロスト気質』
本作、イギリスでは15年も前に出版されている。 翻訳版はやっとこさ出た。 残りはあと1作。
上下巻で1000ページ近くもある文庫。だが、この1000ページを読んでいる時間が実に楽しかった。
殺人が起こる物語だから楽しいことばかりではないが、そこはまぁフィクションだ・・・。
真冬1月。
主人公フロスト警部は、相変わらず幾つもの事件を抱えてデントン署管内を日夜駆けずり回っている。
7歳と8歳の二人の少女の連続誘拐事件。 “夜の姫”たちを狙った連続殺人。“怪盗枕カバー”の出現。酔っぱらいフーリガンたちによる警察署内での狼藉。
上昇志向の強い女性刑事りズ・モード警部代行、無能な部下モーガン刑事に足を引っ張られながらも、これらの事件捜査全ての指揮をとる。
夜中であろうと早朝であろうと現場捜査に赴き、すべての検死解剖に立ち会い、容疑者たちの取り調べを行う。
さらにその間、事件解決には直接関係の無い内勤を適当にこなす。署内の犯罪統計資料をでっち上げ、捜査に掛かった経費に対する請求書金額の水増しをする・・・。
そして、官僚主義の権化=天敵マレット署長から呼び出され、経費削減、人員削減の条件を突き付けられつつ、事件の早期解決を厳命される・・・。
これだけの過酷な状態に置かれながらも、フロスト警部は下品なジョークをとばしながら飄々と事件に向き合う。
フロスト警部の捜査方法は実にユニークだ。
基本的には聞き込みに基づいて容疑者や状況証拠を見つけ、その後は勘に頼って、容疑者や犯罪現場に対して人海戦術でしらみつぶしに調べる。だが、この捜査方法では直接的な物的証拠が見つからない場合もある。しかもそれが多々ある・・・。
事件発生→ 現場捜査→ 容疑者(らしき人物)の特定→ フロストの思い付きによる人海戦術による聞き込みあるいは証拠品捜索→ 容疑者の取り調べ→ 科学捜査研究所による証拠品分析結果→ 物的証拠不十分→ 容疑者の解放・・・、を幾度となく繰り返すこととなる・・・。
失敗の連続・・・。
そんなフロスト警部だが、部下からの信頼は厚い。彼は捜査過程で生じるミスに対して、部下のであろうと、自分のであろうと、すべての責任を被るからであった。
勘と人海戦術による捜査が徒労に終わる。。。
だが、その捜査の過程で目にしていたこと、気に留めていたことが、後々になって・・・・・。
事件解決は往々に、そんなふうに迎えることになる。。。
結末は“現場第一主義によるルーティンワークの結実”、とでも受け取ると、一般サラリーマン読者には嬉しい。
お薦めです。