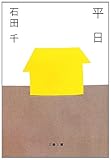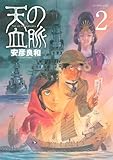『ビブリオバトル』
会社帰り、有楽町の三省堂書店に寄るのが日課となりつつある・・・・・。
目的の本があって寄るわけではないが、ただ何となく店内をぶらつき、タマタマ目に付いた本を立ち読みしたりする。そんなことを毎日繰り返してると、何回かに一度は、ツイ予定外の本を購入してしまうこともある。
本書もそんな中の1冊。だが、そんな本が思わぬ拾い物であったりすることもある・・・・・。
ビブリオバトルとは・・・・・、
何人かが、それぞれ自分のお気に入りの本を持ち寄って、一人5分間でその本をプレゼンする。プレゼン後に、2~3分掛けてその本や紹介した人についての質疑応答を行う。全員のプレゼンと質疑応答が済んだら、参加者全員の投票で、一番読みたいと思った本=「チャンプ本」を決める。
・・・・・ただ、これだけ。
これだけのことだが、結構なコミュニケーションになるらしい。
本書には、ビブリオバトル誕生の経緯やその後の発展・拡散、ビブリオバトルを使ったインフォーマルコミュニケーションによる各種効能、などなどが書かれてる。
公式サイトはコチラ⇒ http://www.bibliobattle.jp/
・・・で、仲間内でやってみようかと思い、何人かにメールを配信し、参加者を募っている。
どうなることやら・・・。
『言わなければよかったのに日記』
ずっと気になっている本がある。いつかは読もうと思っている本がある。いつでも読めるさと思ってる本がある。大長編小説だったり、専門書の場合はそんなふうに思わない。薄い文庫だったり、軽めのエッセイだったりするから、そんなふうに思える。
年々そういう本が増えていく。読めないままの本が増えていく・・・。
これもいつでも読めると思いつつ、ズット積み残してきてた本。
だが先日、角田光代の書いた短いエッセイ に押されて、突発的に読んでみた。
『楢山節考』で文壇にデビューした著者が、その2年後に書いたエッセイ集。
自分の無知さ、無教養さを何のテライも無く率直に語る著者のあっけらかんとした言い分が気持ちイイ。
他人との付き合いの中で、知らず知らずのうちにどこかしらカッコつけちゃうことのある我が身を振り返ると、そんなこと自体がカッコ悪ッ!と思わされる。
軽薄な文章のようにも感じる。けど、そんな文章が幾つも重ねられると、その語り方こそが実直さなんだと思えてくる。著者深沢の何事もひけらかさない自然さが感じられるようになる。
この著者が付き合ってたという作家たち、正宗白鳥や武田泰淳の作品も読んでみたくなる。
以前読んだ深沢作品⇒ 『生きているのはひまつぶし』
『人間和声』
以前、光文社古典新訳文庫で出された短編
がなかなか面白かったので、今月出された長編の方も読んでみた。
結構な時間を掛けて読んではみたが、プロットについても、感想さえも巧く表現できない。
怪奇小説? 幻想小説?
なんだかなーと思いつつ、ワケも判らず読んでしまった。
タイトルも中身も意味不明で無茶苦茶なんだけど、だが結局、終いまで読んでしまった。
4人しか出てこない登場人物。
その中で、健気で残酷な少女がイイ、ってことだけが強烈な印象として残ってる。
『橘花抄』
黒田長政を藩祖とする筑前黒田藩(福岡藩)の重臣=立花重根(しげもと)。
重根の弟で、宮本武蔵創始の二天流五世=立花峯均(みねひら)。
父の自害で孤独となり、重根に引き取られた18歳の少女=卯乃(うの)。
この3人を主人公とした清新清冽な時代小説の傑作!
謗られようとも負けようとも、そこに気高く潔い誠心があれば、ヒトは精神の充足を感じる・・・。
ハムロが描く人物達はホント、ヤバい! カッコ良過ぎ。
すがすがしい読後感。
480ページが短く感じられるくらい一気に読んだ。
『屋上がえり』
有楽町駅のメトロとJRの乗り換え口に三省堂がある。交通会館。
先週、三省堂有楽町店に初めて入った。通勤経路上にある書店。今後、かなりお世話になるだろう。文庫新書売り場は2階とのこと。
1階から2階に上る階段にはたくさんの人達が並んでいた。何事かと思いつつ上ると、そこでは人気作家:小路幸也のサイン会が行われていた。新刊が出たらしい!?
髭づらのオジサン作家を横目に見ながら、ちくま文庫の棚を捜す。作家名五十音順に並べられている。石田・・・の名前を捜す。今の私には、小路より石田だ・・・・。
あった!
地元の本屋には置いてなかった本書・・・。
都内各所のビルの屋上に上り、観た風景、屋上に居る人々を肴にして、湧き出る想いを綴ったエッセイ。
作家ってのは、屋上に上ったくらいのことでも「想い」が湧き出ちゃうのが凄いんだよね。その想いを洒落た小粋な文章にできちゃうのがさらに凄いんだよナ。そんな能力が、才能が羨ましいんだよな。
『平日』
- 連休明けから勤務先のオフィースが移転した。長距離通勤になり、朝も早くに自宅を出なければならない。
- だが、これを機に、30年以上も続けてきた夜型生活を朝型生活に変えたいと思ってる。
- フレックスタイム制を活用してた出社時間を、ほぼ定時出社に変更する。通勤経路が長距離となったことと併せて、これまでより2時間近く早く家を出ることになった。
- 今度の通勤経路と時間帯は電車が混んでる。未だ体が慣れていないせいで、今週は通勤するだけでヘトヘト。 で、休日の今日も結局朝寝坊してしまって、朝型生活を目指した心意気は早くも崩壊した・・・。
長くなった通勤時間では、さぞや本もたくさん読めるだろうと思っていたが、眠いのと混雑とでそれほどでもない。むしろこれまでよりも読める分量は減った。新しい状況に慣れて、ペースを掴むまでにはもう少し掛かりそうだ・・・。
さて、新しい通勤経路で最初に読んでるのが石田千。
『役たたず、』 を読んで以来、石田千の書いたものを探してる。
最もポピュラーなのは新潮文庫の『月と菓子パン』っていうやつかと思ってGW中に幾つかの書店で探したが、どこの書店にも見当たらなかった。
だが、あるショッピングモール内の書店にはこの『平日』が置いてあったので購入しておいた。
その後も別のを捜してるが、新通勤経路中の乗換駅に近接した書店に『屋上がえり』というのがあったので、『平日』を読み終えた後はそっちを読んでる。
市の図書館からは『踏切趣味』と『踏切みやげ』という単行本を2冊借りてる。
「平日」の東京各所の風景や人の様子を活写したエッセイ。
火曜日の上野、金曜日の大手町、木曜日の早稲田、金曜日の羽田、水曜日の吉祥寺、師走金曜日の泉岳寺、水曜日の十条、火曜日の平和島、木曜日の円山町、月曜日の柴又、そして水曜日のハトバス観光。
風景や人々の仕種に対する切り取り方が独特で、そんでもってそれらの描写の仕方に軽やかなリズムがある。
その場所場所に漂ってくる匂いや、聞こえてくる音や、そこに吹いている風の強弱に対する感覚や、人々が纏う雰囲気などを、簡潔ながらも直感でイメージし易い文章で綴る。
一見どこも同じように見える東京の各所だが、作家の眼を通してみると、土地によって細かな佇まいが違うんだってことに気付かされる。
酒好き、銭湯好きの女流作家。 そんなトコにもシンパシーが・・・。
あらためて良い作家に出会ったと思う。
『赤く微笑む春』
- BLODLAGE (2010)

- 『赤く微笑む春』 ヨハン・テオリン/著、 三角和代/訳、 ハヤカワ・ポケット・ミステリ(2013)
エーランド島ミステリ4部作のうちの3作目。
過去2作、「秋」、「冬」と来て、今回は「春」。 前作の記事はコチラ ⇒ 1作目
2作目
エーランド島に暮らす3者の視点で綴られている。
ペール・メルネルという普通の会社員の視点。
エーランド島の石切り場近くのコテージを相続し、そこに暮らし始めた。離婚したかつての妻との間に双子の兄妹がいる。だが娘は重い病気に罹っていて、島の対岸の本土の町カルマルの病院に入院している。
さらに、ほとんど付き合いを絶っていた、かつては傲慢だったが今は脳梗塞を患った父親からの電話によって、ある事件に巻き込まれることになる。父親の別荘が放火され、そこからは二人の焼死体が発見されたのだった・・・。
ヴァンデラ・ラーションという主婦の視点。
エーランド島の石切り場の近くに念願の別荘を購入した。
彼女には社会的に注目されたいという野心を持つ夫がいる。気難しい夫からの一時的な逃避も兼ねて、島の平原をランニングするのが彼女の日課となって行く。
父親と二人の貧しい子供時代を過ごしたこの島で彼女は、平原に突き出した石灰岩の窪みにコインや宝石を置き、エルフに願い事をしていた。そして、今また、エルフを感じるためにこの岩を訪れるのだった。
イェルロフ・ダービットソンという80歳を過ぎた老人の視点。
死期が近づいていることを感じ、養護施設を出て自宅に戻ったイェルロフは、島の春を眺め、亡くなった妻の日記を読んで日々を過ごしている。
自宅の近くに暮らし始めたメルネル家やラーション家を気にしながらも、心穏やかに毎日を過ごすことに努めている。
父親の暗い過去を探りはじめるペール。
秘密の子供時代を回想するヴェンデラ。
日記に書かれた自分の知らなかった妻の想いに馳せるイェルロフ。
エルフとトロールの伝説に彩られたエーランド島の春は、3人に過去への追想を強い、切ない記憶を呼び覚まさせる・・・。
450ページの物語はラスト・シーンを除けば実に静かに進む。
登場人物たちの行動や会話や心の動きは、読者である我々が普段行っていることと何ら変わらない。子供の病気や老いた親への想い。夫婦間の気持ちのすれ違いや諍い。その間も、仕事や家事の手間に時間が割かれる。それらによって感情の起伏が上下する。
彼らの慰みはエーランド島に訪れた春の息吹と伝説に彩られた土地が持つ雰囲気だ。淡々と粛々と描かれた文章によって、読者にもそうした空気感が伝わる。また、ときおり挿し込まれるファンタジーも、この物語に独特の色を帯びさせている。
作中の時期は4月から5月に掛けて。この時期にぴったり。じっくりユックリ、噛みしめて読むのにお薦めの物語です。
中公文庫
GW後半。
本日はカミさんと娘の買い物に付き合わされてとんでもない目に合う。5時間・・・・。
その間、私は書店で暇をつぶし、購入した文庫を90ページほど読み、ショッピングモール内をぶらつき、また書店に入り、本を物色する。
そこで貰ったムックがコレ↓
中公文庫が出版されて40年だそうだ。
中公文庫と云えば、谷崎の『陰翳礼讃』 だろう。 『文章読本』 もあった。
このムックにはいろんな人がいろんなことを云ってるエッセイが載ってる。中でも書店員さん達のエッセイが特にイイ。中公文庫の印象について、古風で静かな佇まい、と云っている方がいて、おもわず私も頷いてしまう。
地味だが、どこか拘った本を出す、そういった姿勢が感じられるのが中公文庫だ。
均質化してきているように思える出版業界だが、まだまだ独自の路線を行く出版社があるのは嬉しい。
もう少し中央公論新社の本を贔屓にしなければ・・・。
『古寺巡礼』
連休の暇に任せて棚の本の並べ替えをしている際に手にした本書。1994年4月発行ってコトだから、20年ほど前に読んだのか?
著者の和辻が二十歳代の頃に見聞した奈良近辺の寺々に対する印象を想像力と知識も重ねて綴ったエッセイ。初版は和辻30歳の時だそうだ。
ホント、昔の人は精神も知識の習得も早熟だったんだナと思う。何と私の幼稚なことか・・・・・
・・・って、今、このブログ内検索したら、2005年にも記事にしてました (^_^;) ま、いっか。
おんなじようなコト書いてら。
『天の血脈 2巻』
- 朝寝坊して起きた日の午後は家事を少々。
- 外壁に埋め込まれた壊れたままのポストに替えて、ポール式のポストを組み立て、その足元を埋め込むために穴掘りと根固めを行う。
- 慣れないことをすると疲れる。腰が痛い・・・・・・・・・
安彦氏が相当気合を入れて描いているらしい、近代史と古代史を繋ぐ歴画の第2弾。 1巻の記事はコチラ
四世紀の那津(ナノツ。今の博多)。
海人族の長の跡取りイサナが水先案内するのは、百済の救援、高句麗との戦いに向かう、神功皇后率いるヤマトの船団。
1903年=明治36年、日露戦争開戦半年前の満州。
好太王碑の研究調査団の一員、一校生の安積亮らはロシア軍に捕らわれる。だが、張作霖らによって救出された安積らは、その後もロシア人と日本人のハーフである華(ハナ)の機転によって日本行の船に乗ることができた・・・。
日本海上の船で安積とイサナが出会う... 展開が全く読めない。。。