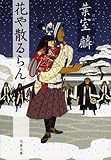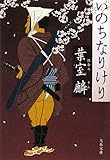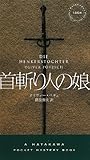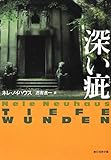『華竜の宮』
2010年日本SF大賞受賞作品の文庫化。
噂に違わぬ面白さ。
ホット・プルームの上昇に伴う地球環境の大変動により250mも海面上昇が生じ、多くの陸地が没した未来。
生き残った人類は、リソースを生命科学と地球環境学に集中させてこれらを発達させた。特に、遺伝子を自由にコントロールできるようになった生命科学は、情報通信科学とも融合し、オリジナルの脳内に人工脳までをも付随させることが可能となっている・・・。
25世紀。
人類は、主に陸上民と海上民に2分される生活形態を採るようになっていた・・・。
いずれの人々も、激変した地球環境の下で生き残るために、身体や頭脳、遺伝子に人工的な改変を加えざるを得ない。特に海上民は、水中・水上での長時間の活動が可能なように、陸上民以上に体の改変を行っている。海上民は常に双子として誕生する。一人はヒトとして、もう一人は魚船(うおぶね)と呼ばれるモノとして・・・。
主人公は日本国の外交官=青澄・N・セイジ。
そして青澄の脳にアクセスして彼の活動や思考をサポートし、本作の語りを担当するのが、青澄のパートナーである人口知性体のマキ。
陸上民を統べる組織である日本国外務省本省や日本が所属する国家連合体の特殊公館の統括官から疎まれながらも、多くの無国籍な海上民や現場の職員達から信頼される青澄。
海上民の立場を理解し、陸上民との間に生じがちなトラブルを解決することの出来る人物として、知る人ぞ知る存在となっている。。。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本国政府と無国籍海上民との間の対立を解消すべく、アジア海域の海上民の女性長ツキソメとの交渉を果たそうと奔走する青澄。海上民たちとの信頼関係を背景として、彼はツキソメとの会談に臨む。会談を果たし、御互いを認め合う両者。
そんな折、かつての中国を中心とした汎ア連合体は、海賊退治と称してアジア海域の海上民たちの虐殺を開始した。
汎ア連合体政治院の上級委員ツェン・リーは、海上民出身というコトから、国家の意思に反して、弟のタイフォンと協力して海上民の保護を画策する・・・。そして彼は青澄の力に目を付ける・・・。
新たな地球的規模のカタストロフィーが予測されだす中で、青澄はツキソメやツェン・リー、そしてパートナー:マキと協働して、人類救済計画の一翼を担う決心をする。絶望的状況下での人類の知性を信じて・・・。
ん~、スケールの大きなサイエンス・フィクションだ。今作だけでは終わらないスケール感がある。
背景設定がしっかりしているから、この世界を舞台にした物語が幾らでも作れそうだ。今後の作品も物凄く期待できる。
ブルーム・テクトニクスが題材に使われている本は以前にもいくつか読んでいる。
一応ノンフィクションらしき作品としては『日本列島は沈没するか?』
SF小説では『ハイドゥナン』
地球科学って面白いよね。
そして、この作家の作品も実は結構読んでる・・・。
↑ この『魚船・獣船』は短編集。
その中で表題作となっている「魚船・獣船」は、『華竜の宮』と同一設定世界での物語となっている。
先に『華竜の宮』を読んでから、短編の方を読んだ方が、より楽しめると思う。
荷風いろいろ
今日午前中は親戚の法事で実家近くの寺へ。天台宗の寺。長年この寺に来ているが、ここの坊さんは念仏も説教も一向に上手くならない・・・。
まァ、それはともかくとして、法事を終え、帰りの電車ではワザワザ一つ前の駅で降りてBOOK OFFの大型店に寄って来た。
この店で荷風作品を幾つか仕入れてきた。
『すみだ川 新橋夜話』 『腕くらべ』 『江戸芸術論』 『荷風随筆集(上)』 『荷風随筆集(下)』 の5作。
そうそう、読み終えた『つゆのあとさき』の記事をアップしとかなきゃ。。。
『深川の唄』『鐘の声』
永井荷風作品のオーディオ・ブック。
『深川の唄』は、電車に乗ってぶらりと出かけた際に見かけた明治期東京に暮らす人々の様子が描かれた作品。東京市内に敷かれていた電気鉄道の車内で見掛けられた人々の服装や態度や会話。到着地深川の街の風景や人々の様子。それらが荷風の心象風景も含めて描かれている。
荷風は、若い女性に対しては好意的に、中年女性には厳しい視線をもって描いている。エロオヤジ目線である。
『鐘の声』は、荷風の自宅に聞こえてくる増上寺の鐘の音について綴ったエッセイ。
オーディオ・ブックなるものを初めて試してみた。
連休中の深夜、ネットサーフィンをしていて衝動的にiTunesで購入した。
オーディオ・ブックにも様々な種類があるが、最初に目に付いたのが荷風作品のラインナップで、以前読んだ『墨東奇譚』 が好印象だったこともあって迷わず本作を選んだ。 イヤ、300円と安かったからか・・・。
散歩中に、二回繰り返して聞いてみたが、内容が頭に入りにくいと感じた。
朗読する声優さんの声は実に聞き取りやすく語りも上手だ。けど、ある言葉を聞いた時に、その言葉はどのような文字で書かれているのか?が気になってしまう。
また、聞いた言葉が記憶に残らない。数秒前に聞いた文章を忘れている。ところどころ断片的には覚えていても、連続した物語として記憶が出来ない。
私の脳の癖として、文字を見た方が、活字を読んだほうが物事を理解し易くなっているような気がした。
同じ作品を文字で読んでみたくなった。
散歩帰りにブックオフに寄ってみたが、同一題名の作品は見当たらなかった。
代わりに『つゆのあとさき』という作品を105円で購入してきた。
論文『吉野ヶ里墳丘墓の構築技術のルーツと伝播』
鬼塚克忠, 原裕 : 吉野ヶ里墳丘墓の構築技術のルーツと伝播, 土木学会論文集C(地圏工学), Vol.68, No.4, p621-632, 2012.
土木学会論文集C(地圏工学)に掲載されていた論文。
吉野ヶ里の墳丘墓がどのように構築されたのか? 土をどのように積み、固めたのか? それらの工法についてが、長江下流域や山東半島に構築された墳墓との調査比較を通して述べられている。
当然、工学的観点からの論考がなされているが、歴史学的調査や考古学的調査の結果をもふんだんに取り入れた考察となっている。
吉野ヶ里墳丘墓の構築技術は、朝鮮半島経由ではなく、長江下流域もしくは山東半島から直接、九州北部に伝播したとする結論が述べられている。
歴史好き、考古学好きの人たちが読んでもかなり面白い読み物となっていると思う。
巻末に挙げられている参考文献は、考古学関係の本ばかりだ。。。
土木学会のジャーナル、特に物理化学的・技術的な課題や問題に関する題材を多く取り上げている「地圏工学分野」にこのような内容の論文が載るのは珍しいので、メモとして当ブログに残しておくことにした。
それにしても、この論文がジャーナルに掲載されたってコトは、ピアレビューを経ているというコトだ。
工学者や技術者ばかりの学会の人材の中で、この論文の査読にあたった方達はいったいどのような人たちだったのだろう? 気になる・・・。
『紳士の黙約』
サンディエゴのサーファー探偵ブーン・ダニエルズが活躍するシリーズの第2弾。
『夜明けのパトロール』 の続編。
前作では、主人公のブーンとその仲間たち=“ドーン・パトロール”と呼ばれる地元で一目置かれたサーファー達の人物紹介と、ハードボイルド小説の主人公ブーンの葛藤と活躍がストレートに描かれた。
本作は前作に比べるとミステリー色(推理小説っぽさ)が強まっている。
地元サンディエゴで知らぬ者はいない伝説のサーファー=ケリー・クーヒオ(K2)が、地元のサーフ・ギャングを名乗る少年に殺された。
K2を敬愛してやまない地元の人々からは、逮捕された少年を厳罰に処すべき、との声が高まっている。
もちろんブーン達、ドーン・パトロールの面々も同様の考えだった・・・。
だが、少年の弁護士の依頼で、事件の周辺を調べ始めたブーンは、何か釈然としないものを感じ始める。挙動の定まらない少年の言動、少年の生育されてきた環境、少年の父親、そして白人至上主義組織との接点・・・。
ドーン・パトロールの仲間たちからは、弁護側の手先となったと思われているブーンは次第に孤立し始める。
さらに、浮気調査を依頼されていたブーンは、その調査対象者が殺された事件にも巻き込まれることになる・・・。
2つの事件に重なる謎。それらが交錯しだしてからは、推理小説としての主人公ブーンの新たな魅力が描かれる。ハードボイルド小説の主人公とは異なる新たな一面だ。
だがクライマックスでは、本来のブーンらしさ=ハードボイルド小説の主人公らしさ=自らの掟に従うストイックな男、が戻る。
ハードボイルド小説の主人公ブーンの活躍はもちろんのこと、ブーンの仲間たちも加わった大団円は爽快だ。
お薦めです。
『古代出雲の原像をさぐる 加茂岩倉遺跡』
「出雲展」 を一緒に見に行った先輩が、会場で購入したものを借りて読んだ。
銅鐸が一カ所から39個も出土した加茂岩倉遺跡に関することを中心に、弥生時代の出雲地方がどのような邦であったかを推定(ときに想像)し、素人にも判るように記した内容の本。
「遺跡を学ぶ」というシリーズの53巻。
日本にある遺跡一つひとつについて、それぞれ1冊にまとめたシリーズの中の1冊。
マイナーな本かもしれないが、内容は充実している。写真や図表もふんだんに使われていて理解しやすい。
遺跡がワンサカ出てくる地方ってのは魅力的だ。
出雲地方には、未だ足を踏み入れたことがない。
いつか行かねば。
島根で何かの学会でも開催してくれないかな・・・。
『花や散るらん』
直木賞作家となった葉室の時代小説。 『いのちなりけり』 の続編。
浅野長矩による吉良上野介への刃傷事件、そして赤穂浪士の吉良邸討ち入り事件の原因については、“幕府に対する朝廷の暗躍”という観点から解釈した、葉室による新たな創作となっている(と思う)。
この点はなかなか面白かった。
だが、超有名史劇である「忠臣蔵」を持って来て、その舞台の中で、前作で魅力を発揮したハムロのオリジナル・キャラクター達がどのような矜持を魅せてくれるのかという期待は惜しくも外れた。
登場人物の多さ、プロットの複雑さ、その割にはページ数を凝縮したコト、これらが相俟って、主人公=蔵人と咲弥の魅力が、他の登場人物たちに分散してしまったように思える。
後半からクライマックスに掛けては展開を急ぎ過ぎ。ヒトに対しても、プロットに対しても、もっとジックリと書き込んで欲しかった。
『風渡る』の二の舞い・・・って感じ? 次に期待。
過去の葉室作品に関する記事はコチラ ↓↓↓
『首斬り人の娘』
11月4日記事で紹介した作品に続き、これもドイツ産のミステリ。 歴史ミステリ。
17世紀ドイツ。凄惨を極めた宗教戦争が終わってからおよそ10年後。中世から抜け出そうとしている時代。
バイエルン地方の小さな街ショーンガウで起こった子供3人の連続怪死事件。
子供達を魔術で殺したとして投獄された産婆。
その産婆の自白を引き出すため、街の有力者たちの命を受けて彼女を拷問しなければならないショーンガウの処刑吏=首斬り人のクィズル。
だが、クィズルとその娘マクダレーナ、そして街の若き医師ジーモンは、産婆の無実を確信していた・・・。
子供達を取り上げてくれた産婆に恩を感じているクィズル。クィズルの娘マグダレーナに恋するジーモン。二人は事件の真相を探り始める・・・。
主人公である首斬り人クィズルのキャラクターが秀逸。
人々から忌み嫌われる処刑吏という世襲の低身分でありながら、当時の呪術的医術とは一線を画した科学的医学に長けた型破りの大男。
そんな主人公が、魔女、俗信・迷信、伝説、が蔓延る世の中で起きた連続殺人事件に対して、合理的・科学的解釈に基づく真相究明を果たすことができるのか? 真犯人を暴くことはできるのか?
・・・まァ、できるのだが、その過程が実にスリリング、かつユーモラス、時にシリアスに描かれている。ところどころに魅せるアクションシーンも程良いスパイスとして効いている。
もう単純に面白い。単純な面白さは大事。
お薦めです。
4部作とのこと。続編の翻訳出版も期待。
古事記1300年、出雲大社大遷宮 特別展「出雲 ー聖地の至宝ー」
いま、上野の東京国立博物館では出雲大社の歴史と宝物が展示されている。
昼休みとその前後の時間を使って見に行って来た。上野公園は勤務先から近くて良い・・・。
ちなみに上野公園内の別の美術館で同時期に開催されているツタンカーメン展は、平日の昼にも拘らず入場には40分待ち、とのアナウンスが流れていた。
それに比べて出雲展は実に空いていた・・・。
古事記に描かれる神話の舞台として、出雲は重要な地位を占めている。
古事記が成立した年は一応712年ってことになっている。古事記が世にお目見えしてから1300年ってこともあって、このような展示会が行われているんだそうだ。
メインの展示物は、出雲大社に伝わる宝物や境内から出土した遺物。そのなかでも、高層建築物であった古代出雲大社の神殿を支えたとされ、大木3本を併せて直径3mもの太さの柱とされた宇豆柱(うづばしら)。
それと、荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡などから出土した銅鐸、銅剣、銅矛。
空いていることもあって、およそ1時間もあれば充分に見て回れる。
古代史好きの方にはお薦めの展示会です。
『深い傷』
ドイツ産ミステリ。 500ページに及ぶ長~い物語。
主席警部オリヴァー・フォン・ボーデンシュタインとその部下である警部ピア・キルヒホフの二人を中心としたホーフハイム刑事警察署の刑事たちによる捜査モノ。
警察小説のシリーズとして、本作は第三作目にあたるらしい。
今後、第四作が訳出され、この2作の日本での評判を見て、全作品を訳出する予定らしい・・・。
80歳過ぎの老人3人が連続して射殺された・・・。 犯人が残したメッセージは“16145”。
最初の犠牲者は、かつて合衆国大統領顧問を務めた人物で、著名なユダヤ人であった。だが、司法解剖の結果、この人物が実はナチスの武装親衛隊員であったことが判明する。
三人の犠牲者との繋がりが見いだせる女性実業家ヴェーラ・カルテンゼー・・・。
オリヴァー達捜査班は、彼女こそが事件のカギを握る人物として、マークを始める・・・。
ナチス・ドイツ時代の暗い血塗られた歴史と、それらが現代に及ぼす影響。過去と現在の人間関係、名門貴族の家族とその周辺の人々における愛憎。それらが複雑に錯綜する中で生じた連続殺人事件。
緻密なプロットが構築され、読者をミスリードに誘いつつも、展開の巧みさで膨大なページ数を一気に読ませる。
個性的な二人の主人公、オリヴァーとピア、もなかなか良いキャラクター。