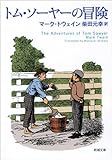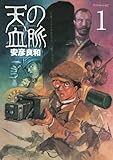榛名富士は登山者が少ない。。。
三連休の中日に榛名富士に登ってきた。
大抵の人はロープウェイで頂上まで行く。
そんなところを娘と二人、徒歩で登ってきた。
ビジター・センター前の駐車場に車を停め、事前に調べていたWEBに載っていた案内板を探し当て、そこから頂上目指して登り始めた。
登山道は、熊笹が生茂った地面に一筋刻まれただけの、人一人が通れるだけの細いもの。
登りの際には二人組のサラリーマン風の男性たちと、降りの際にはアベックとすれ違っただけ。それほど登山者がいなかった・・・。
頂上までは約1時間程度だったが、その間4、5回水飲みと汗拭きのための休息を入れた。
なんだかんだで結構しんどかった。
ゴールデン・ウィークに妙義山 、今回は榛名山、・・・ときたら、次は赤城山だな。
『伏(ふせ) 贋作・里見八犬伝』
アラ・フィフの私は、小学生のとき、NHKで放送されていた「新・八犬伝」を夢中になって観ていた。
鳥山明のドラゴンボールを初めて読んだとき、「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の玉と同じじゃねーか、って思った。
数年前には、馬琴の原作(の現代語訳版)を読んでみようかなと思った。
数日前、贔屓のブログにあった本書の紹介をみて、衝動的に“読みたい!”って思った。
で、他の本をうっちゃって本書を読んでみた。
このところ江戸で頻発する残虐な人殺し。それは、伏(ふせ)と呼ばれる犬の血が流れる異形のモノの仕業であった。幕府は伏に賞金を懸けて取締りを強化している。
山で狩猟をして暮らしていた14歳の少女・浜路(はまじ)は、祖父の死を切っ掛けに、江戸に居る兄・道節の元に転がり込み、兄と共に伏狩りを始める・・・。
浜路・道節の兄妹と伏達との戦い、その戦いの中にあって時折魅られる浜路と伏達との不可思議な交流。
そんなプロットが縦糸となり、そこに、瓦版の読売りである滝沢冥土の描く『贋作・里見八犬伝』や、伏の一人である信乃の語る『伏の森』の物語が横糸となって絡む。
歴史と伝奇と現代風物語がごった煮されたエンターテイメント。
一気読みでした。
2012ハヤカワ文庫の100冊フェア
ハヤカワ文庫の秋のフェアが行われてますね。
早川書房のWEBから、フェア開催書店で配布中の小冊子PDF版がダウンロード できます。
既読本は 35/100でした。
他の出版社に比べれば、ハヤカワ文庫の既読率は高いと思うのですが、それでもこんな程度・・・。
まだまだ読みたい本がワンサカある。
『暴力の教義』
- The Creed of Vaiolence (2009)
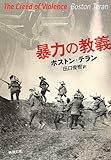
- 『暴力の教義』 ボストン・テラン/著、 田口俊樹/訳、 新潮文庫(2012)
久しぶり。ボストン・テランの新作。
これまでの作品は文春文庫から出ていたが、今作は新潮文庫から。
過去作品の記事はコチラ ⇒ 『神は銃弾』 『凶器の貴公子』 『音もなく少女は』
1910年。メキシコ革命前夜。動乱のテキサスとメキシコ。
主人公は二人。父と息子。
生れながらの犯罪者である父親。自らを、どこにでもいる月並みな人殺しと称する男。
息子は犯罪捜査局の捜査官。
偶然が15年ぶりに二人を巡り合わせた。
息子は、一瞬でその男が父親であると見抜いた。父は息子とは判らない・・・。
そんな二人が、メキシコの武器密輸組織に対する囮捜査を行う。父親は免責特権との引き換えのために・・・。
前作『音もなく少女は』が3人の女達=母娘の関係を描いたのに対し、今作は父と息子の関係が描かれている。その関係は、硝煙とオイルと血の匂いに包まれている。
本作では、悪党=父親が魅力的だ。
この世の全てに無関心でいることによって強さを体現してきた彼の哀れさがクライマックスで描かれる。
その哀れさを表出するシーンのために350ページが、読者にとってはそこまでを読むに至った時間が費やされた。
私にとっては決して無駄な時間ではなかった・・・。 お薦めです。
るろうに剣心 『追憶編』、『星霜編』
先週末は、チョット遅い夏休みをとった。
その際に観たアニメ。 Youtubeで・・・。
『追憶編』は、剣心の左頬の十字傷がどうしてできたのかが判る物語。 悲しい物語。
『星霜編』は、剣心の左頬の十字傷が消失する物語。 切ない物語。
良く出来てる。
実写映画版も観てみたい・・・。
『トム・ソーヤーの冒険』
云わずと知れた古典。小学校夏休みの読書感想文の課題本にでもなりそうな本書。
何を今さらオッサンが・・・とも思うが、新訳が出たのを切っ掛けに何十年かぶりに読んでみた。
大昔にジュブナイル版を、何年か前に英語学習用の版を読んだ。今回でおそらく3回目。
板塀のペンキ塗り場面、殺人事件の目撃場面、迷い込んだ洞窟からの脱出場面など、有名な個所はところどころ覚えているもんだ。
新訳だけあって、非常に読み易い。
次は、未だ読んだことのない『ハックルベリー・フィンの冒険』を読んでみよう。
『ハック・・・』の方は、ずいぶん前にブックオフで岩波文庫(上)(下)を購入してあって、いつかは読まねばと思ってたんだけど、先に『トム・ソーヤー』を読んでからにしようと思って先延ばしになっていた。
そうそう、新潮文庫とともに、光文社文庫でも同時期に新訳が出たんだけど、1876年初版で使われたイラストが表紙となっている新潮社文庫の方を選んでみた。
ほんとは岩波文庫版で読みたかった・・・。
『天の血脈 1巻』
日露戦争前夜。
満州と朝鮮との国境付近の集安で発見された好太王碑の調査隊の一員として彼の地に赴いた一高生、安積亮。
調査中の彼らを襲撃する馬賊、そしてロシア陸軍。
否応なしに国家間の謀略に巻き込まれる安積・・・。
近代史と古代史を繋ぐ謎の物語の開幕。
本作の著者は、ガンダムの作者(作画者)として圧倒的に有名だ。
しかし、もともとこの作家は、アレクサンドロス、ジャンヌダルク、イエス、古事記など、歴史に興味を持ち、それらを題材にした作品が多い。
本作もそうした歴史(近代史?)を題材とした作品なのだろう。
1巻を読んだだけでは先の展開は全く予想つかない。それだけに次巻以降もすっごく楽しみ。
『ビブリア古書堂の事件手帖3 栞子さんと消えない絆』
通勤の往復で読めるお手軽ラノベ・ミステリー。
大人気ですな。どの書店でも平積み状態。
私は同僚から借りて読んだ。。。
そこそこ安定した面白さ。
プロローグ 『王さまのみみはロバのみみ』(ポプラ社)Ⅰ
第一話 ロバート・F・ヤング『タンポポ娘』(集英社文庫)
第二話 『タヌキとワニと犬が出てくる、絵本みたいなの』
第三話 宮澤賢治『春と修羅』(關根書店)
エピローグ 『王さまのみみはロバのみみ』(ポプラ社)Ⅱ
ロバート・F・ヤング著『タンポポ娘』はいつか読まねば、と思いました。
『歴史を考えるヒント』
2001年に新潮選書として出た本書は、「新潮選書」の中で一番売れているらしい。
その文庫版。
「日本史」の中で使われている言葉には、現代人が使う日常用語とは“意味”が大きく異なるものがある。
ある言葉が使われた当時、それがどのような意味を持っていたのか? それを良~く考え、これまでの解釈を改めてみると、そこにはコレまでに考えられていた歴史とは違うものが見えてくる・・・。
近代以前の日本社会は「農本主義」的であったとの解釈が主流だと思われているが、 中世以降の社会には「重商主義」的な一面を併せ持っていたこととか、
江戸時代以前から、かなり成熟した商業・金融の発展があったこととか、
・・・などなど、いくつかの具体例が挙げられている。
巻末には、左・右のイデオロギーを絡めた歴史観の違いを踏まえた本書の「解説」が載っている。
とかく、歴史にはイデオロギーが付き物(憑き物)だが、イデオロギーはどうでもイイ。
中身が面白ければそれでいい。モノの観方を変えてくれるのであればなおイイ。
本書には、モノの見方を変えるための説得力がある(と思う)。