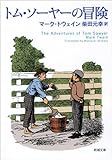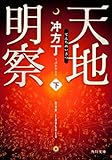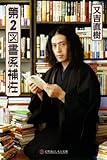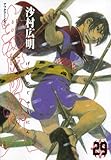『もっとも美しい数学 ゲーム理論』
はっきり言って面白くない。ブックオフ105円本でよかった。
まったく数式が出てこないってのもどうなの?
簡単な数式がある事でより判りやすくなることだってあるはず。
ゲーム理論の簡単な概要を知るためには、別の本を読むべき! と思った。
2012年夏 新潮文庫の100冊
100冊をみると、古典や名作と云われる作品よりも、現代作家による今風の作品の割合が多い。
現代作に読みたいと思うものがない・・・。
『100年の難問はなぜ解けたのか』と『トム・ソーヤーの冒険』の新訳版は読みたい。
2冊買うと “Yonda?ブックカバー” がもらえるそうだ。
『ベヒモス クラーケンと潜水艦』
十日以上もほっぽっておいた当ブログ。
この間、長谷川時雨の『旧聞日本橋』と、ウエスターフェルドの『ベヒモス』を読み終えていたのだが、記事を書くのが面倒になってた。
- 旧聞日本橋 (岩波文庫)/岩波書店

・・・が、休日の本日、なんだかその気になったので、取り敢えず『ベヒモス』の方について書いておこう。。。
- で、いきなり脱線するが、今読んでる『最も美しい数学 ゲーム理論』という本の中で、著者がトーマス・ホッブスの『リヴァイアサン』のことに少しだけ触れている(p222)。
- もっとも美しい数学 ゲーム理論 (文春文庫)

↑コレとちょうど並行して読んでたのが『ベヒモス』と云うSF。
まったく異なる内容の2冊の本の間に出てきた「ホッブス」という偶然性・・・。
スコット・ウエスターフェルドは自著SF作品に、『リヴァイアサン』、『ベヒモス』という、ホッブスの政治哲学書と同じ題名を付けてる。
ホッブスの政治哲学書を意識して題名を決めたのか? だとしたら、ホッブスを読まないと、このSFの面白さの本当のところは判らないのか? などと恐れていたら、3作目の題名が『ゴリアテ』だってことなので、どうやら3作品とも単純に旧約聖書に出てくる巨大獣(巨人)の名前から採ったらしい、ということが判明・・・。
ホッブスとは関係なさそうだ・・・、な~んだ。ホッ!
・・・って話。
すみません(^_^;)
↓ここからがメイン。
第一次世界大戦時代の歴史改変であり、スチームパンクでもある物語の第2弾。
オスマン帝国を自らの陣営に加えたい<ダーウィニスト>イギリスと<クランカー>ドイツは、帝国の首都イスタンブールにて、その覇権を争っている。
急速に親ドイツ化しつつあるオスマン帝国に向かうイギリス海軍の巨大飛行獣<リヴァイアサン>。
主人公=暗殺されたオーストリア大公の息子アレックは、<リヴァイアサン>を脱出し、オスマン帝国スルタンに反抗する革命軍に参加することとなり、
もう一人の主人公=<リヴァイアサン>の士官候補生デリン・シャープは、密命を帯びてイスタンブールに侵入する・・・。
イスタンブールを舞台に物語は急展開する・・・。
物語の世界観と主人公たちの人となりを構築するための書き込みにページを費やさざるを得なかった第1弾に比べれば、この第2弾のプロットは格段に面白くなっている。スピード感も増し、冒険譚らしい内容になっている。
第3弾も楽しみ。
またまた蛇足だが、本書のめずらしい「あとがき」について触れておこう。
「作者あとがき」と「訳者あとがき」がある。
「作者あとがき」は普通なんだが、その後の「訳者あとがき」が笑える。
原著には存在しない副題に対し、訳者はいらないと主張したにも拘らず、編集部に押し切られて付けたそうだ。
訳者の編集部に対する愚痴が載ってるんだ・・・(^_^)
小説の内容から云えば、訳者の言い分に軍配が上がる。。。
『天地明察』
週末は見舞いに行った。その往復車中と宿泊先での寝床で上巻を、本日の出張の行き帰りの車中と帰宅してからの風呂で下巻を読んだ。
下巻クライマックス以降は、読むのを辞められずに湯船に1時間半近くも浸かってしまった。
評判の本作であるから、内容について今更記すことはしない。
概要を知りたい人は、こちら↓のyone1868さんのブログ が参考になるので、ご覧あれ。
ここでは、私自身の無知を曝け出しつつ、思ったことだけを書いておこう。
江戸幕府四代将軍の治世なんて、学校で習う日本史では欠落していたのではなかろうか。私が覚えていなかっただけなのかもしれないが・・・。
関孝和の名前は知っていても、渋川春海は知らなかった。
保科正之の来歴や業績なんて知らなかった。
この時代に改暦事業があったなんて知らなかった。
小説に影響されて歴史上の人物や歴史そのものに興味を覚える・・・。そんな切っ掛けとなる物語の一つと云えるのではないかと思った。
今さらですが、もちろんお薦めです。
『特捜部Q Pからのメッセージ』
このシリーズの翻訳ペース、異常に速い。もう第3作が訳された・・・。
早速読んでみた。
未解決事件を扱う「特捜部Q」の捜査官カール・マーク警部補とその助手でシリア人のアサド。そしてローセ。
この3人が今回解明するのは、「助けて・・・」と書かれたボトルメールの謎。
手紙の文末には、Pの頭文字で始まるサイン。10年以上も経過した手紙の損傷は激しく、解読は困難を極める。だが、どうやらPは誘拐され、監禁されていたらしい・・・。
しかし、過去の記録に該当する事件は見当たらない・・・。
にしても、前2作にも増して、抜群の面白さだ!
話の展開は意外性の連続だし、しかもそれが程良いテンポで繰り出されるし、そんでもって登場人物たちの感情の動きの描きようも実に巧い。
だから物語にのめり込める!
560ページ2段組みの物語だが、決して長くは感じない。
このシリーズ、どんどん面白くなってきてる。
しかも、シリーズ中に仕掛けられた謎自体もまだまだ解かれておらず、この先のシリーズ自体の展開も見逃せない。
お薦めです。
前2作はコチラ ⇒ 『特捜部Q 檻の中の女』 『特捜部Q キジ殺し』
『死せる獣 殺人捜査課シモンスン』
翻訳ミステリに関する記事が随分と久しぶりになった。
デンマーク産ミステリの初モノ。
小児性愛者5人の惨たらしいリンチ死体が発見される。
5人の死体は小学校体育館の天井から幾何学的な配列でぶら下げられていた。
被害者たちは当然の報いを受けたとする犯人擁護の世論はデンマーク国内を席巻する。
ネット、大手新聞社を使い世論を誘導する犯人。その戦略は巧みである・・・。
殺人捜査課を率いる警部補シモンスンには、早期解決のプレッシャーが圧し掛かる・・・。
本作、キャラクターの描き分けが実に巧い。
シモンスンを筆頭に、殺人捜査課の面々が緻密に個性的に描かれている。捜査課のすべてのメンバーが立っている。
プロットもアイデアも見事だ。
本作のプロット面での最大の特徴は、事件解決に至る捜査過程にある。
シモンスンは、犯人の特定と狙いを明らかにするために非合法な仕掛けを計画する。
その捜査方法に関して、捜査課の面々に疑問や反発も生じるのだが、結局、シモンスンは主張を押し通すことになる。
合法的な捜査過程を経た証拠以外は裁判に認められないとするヤワな主人公が出てくる作品とは一線を画す。シモンスンは犯人逮捕のための手段を選ばない。
正義だとか不正だとかを超えた範囲の、感情的とも云える捜査・・・。そんな捜査方法を採る主人公・・・・・私は好みだ。
お薦めです。
そうそう、今日から読み始めたのも、またまたデンマーク産ミステリだ。『特捜部Q』シリーズの第3弾、「Pからのメッセージ」。
最近のスウェーデンやデンマークのミステリが翻訳される風潮、イイね!
『快楽主義の哲学』
ブックオフの105円本。
50年近く前の作品だが今でも読める!
澁澤の文章は簡潔で読み易い。
飲み会後の帰宅の車中で読んでも書いてある事はそれなりに理解できる。
ギリシャの哲学者エピクロスが云うところの「快楽主義」はイイ。
「エピキュリアン」って云うんだ・・・。
過日読んだ『逝きし世の面影』で語られる江戸期の日本人は、まさにこのエピキュリアンじゃないかと思える。
『風渡る』
キリシタン大名黒田官兵衛とイエズス会の日本人修道士ジョアン(架空の人物)の2人を主人公とした物語。
一応、本能寺の変を演出した人物としての官兵衛が描かれている。
・・・が、登場人物の多さ、歴史的背景の複雑さ、物語中の経過時間の長さ、これらがネックとなってしまい、焦点がボケていた(ように思う)。
コレまでに私が読んだ葉室作品中では、最もムムム・・・?な作品だった。
ハムロにしては面白くなかったナ、と思いながら巻末の解説を読んだら、そこには本作の続編『風の王国』があるとの情報。
いずれ、そっちも読んでみるか。
『逝きし世の面影』
結構長い時間かけて読んだな・・・。
幕末・明治初期に日本に訪れた外国人たちによる数々の観察記を精読した著者が、自らの考察もふんだんに加えて、ある時期この国に存在し、今は滅び去った江戸文明を語る・・・。
一度は読んでおくべき、と云われる名著の一つ。誰が言っていたのかは忘れたが・・・。
「ある文明の幻影」と題した第一章、そのイントロで著者が語る。
“日本近代の文明、徳川文明とか江戸文明とか俗称される、一回限りの有機的な個性としての文明が滅んだ”
“文化は滅びないし、ある民族の特性も滅びはしない。それはただ変容するだけだ。滅びるのは文明である”
簡潔さと美しさが一体となった文章。イントロ部だけではない。全編が↑こんな調子で描かれている。
さらに、場合によっては、その語りは熱を帯びることもある。
そんな文章・語りによって、江戸文明とその時代に生きた日本人の残影が照らしだされる。
第 一 章 ある文明の幻影
第 二 章 陽気な人びと
第 三 章 簡素とゆたかさ
第 四 章 親和と礼節
第 五 章 雑多と充溢
第 六 章 労働と身体
第 七 章 自由と身分
第 八 章 裸体と性
第 九 章 女の位相
第 十 章 子どもの楽園
第十一章 風景とコスモス
第十二章 生類とコスモス
第十三章 信仰と祭
第十四章 心の垣根
江戸文明の頃の日本人は、お気楽・朗らかでありながらも、自然に対する諦観を併せ持つ人々だった・・・。
この「自然」には死生観も含まれる。
現代の日本人の中にも結構多く認められると思うし、私自身そういう人間に憧れる。
まったくもって噂に違わぬ名著。 お薦めです。
『無限の住人』29巻
休日はショッピングモールへの買い物の運転手にされる。
食料品、日用品を買うだけに、どうしてあんなに時間が掛かるのか?まったくもって理解不能のカミさんの行動に付き合っていられない私は、隙あらば書店に逃げ込む。
本日は何時にも増して立ち読み時間が多かった・・・。
純文学読みのお笑い芸人、又吉氏による『第2図書係補佐』はナカナカに面白かった。
採り上げている本の紹介は文末の僅か数行なのだが、そこに至るまでのエピソードの語りが上手い。
久しぶりに大島弓子の『グーグーだって猫である』も読んだ。文庫版の4巻。
家に猫をおくだけでなく、野良猫の面倒まで見るようになった著者。。。愛猫家の話に惹かれる・・・。
- グーグーだって猫である(4) (角川文庫 お 25-4)/大島 弓子

購入したのは、↓沙村画伯の『無限の住人』29巻-
- 26巻以降を本棚から引っ張り出してきて、4巻を一気に読んだ。
- 剣劇のエグい場面、グロい場面が満載。そんな場面に嫌悪感を持つ人もいるかもしれないが(我が家のカミさんなど・・・)、その画力、描写力は凄い。
- ただ強い剣だけを求めるという考え、公儀に歯向かう者は問答無用で滅するという考え、肉親の仇を取るためにはどんな事も厭わなという考え、それぞれの単純な考えに基づいて命のやり取りをする者たちの剥き出しの姿が潔く描かれている(と思う)。