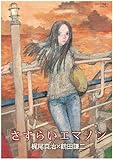『オランダ宿の娘』
単行本は、ミステリ・ワールド・シリーズとして出された。 なんだって、ワールド・・・。
この単行本、ちょうど葉室を読み始めて、「この作家は面白い!」と思い始めた頃に出たんだ。
文庫化されるのを待ってました。
江戸時代、日本との貿易を行っていた数少ない国、オランダ。
普段は長崎の出島を拠点としているオランダ人商館長が、年に一度、江戸参府を行った際に常宿としていた「長崎屋」。その長崎屋の姉妹を中心に、シーボルト事件に関わった人間たちの悲喜愛憎を描いた物語。
いつものハムロ作品とは少~し風味が違う。
剣劇とは無縁。
ストイックな漢(もののふ)が主人公という訳でもないから、猛々しさや勇猛さといった要素はない。
だが、日蘭の文化・心の架け橋たらんとする姉妹二人の凛々しさと儚さが今作には流れている。
そして何より、葉室麟の作品はいつも優しい。
過去の葉室作品に関する記事はコチラ ⇒ 『銀漢の賦』
『いのちなりけり』
『秋月記』
『乾山晩愁』
『実朝の首』
『ミステリアス・ショーケース』
昨年、ハヤカワ・ポケットミステリーで活躍した作家たちの短編を集めたもの。
新世代作家たちだけでなく、ベニオフやトマス・H・クックのも載っている。
日本オリジナル編集のアンソロジー。
1. 「ぼくがしようとしてきたこと」 デイヴィッド・ゴードン/著、 青木千鶴/訳
2. 「クイーンズのヴァンパイア」 デイヴィッド・ゴードン/著、 青木千鶴/訳
3. 「この場所と黄海の間」 ニック・ピゾラット/著、 東野さやか/訳
4. 「彼の両手がずっと待っていたもの」 トム・フランクリン&ベス・アン・フェンリイ/著、 伏見威蕃/訳
5. 「悪魔がオレホヴォにやってくる」 デイヴィッド・ベニオフ/著、 田口俊樹/訳
6. 「四人目の空席」 スティーヴ・ハミルトン/著、 越前敏弥/訳
7. 「彼女がくれたもの」 トマス・H・クック/著、 府川由美恵/訳
8. 「ライラックの香り」 ダグ・アリン/著、 富永和子/訳
技巧派ゴードンの2作品はどちらもユニーク。
ピゾラットの作品はロードノベルの一種で、結末が物凄く現実的。リアル過ぎてやるせなくなる。
トム・フランクリン&ベス・アン・フェンリイ(この2人は夫婦)の作品は、1927年のミシシッピ川の大洪水後の崩壊した村を捜索する2人の男と、彼らが村で出会った赤ん坊と女を描いた物語。地味なヒーローが描かれたハードボイルド。8作品中では最も後味のイイ作品だった。
この中で、ベニオフの作品だけはかつて読んだことがあるはずだが、まったく覚えていなかった。
古参のロシア兵士2人と新兵が、真冬のチェチェンで雪中行軍している。軍事的な要所となりそうな1件の家を捜索し、そこに隠れていた老婆を発見する。古参兵たちは、未だ他人を殺めたことのない新兵に、老婆を家の外に連れ出して殺せと命じる。新兵は、家から離れた地へ老婆を連れ出す。老婆を逃がしてやるのか、それとも・・・・・。
これまた結末の描き方がメチャめちゃリアル。ノワールだ。
ハミルトンのはゴルフ場での殺人を題材にした作品。この8作の中では最もオーソドックスなミステリー。
クックの作品は、いつもの彼の作風とはチョッと違ってる。
深夜のバーで出会った女と一夜を過ごした、と云う話を友人に聞かせている作家の一人語り。短編ならではオチ。
ダグ・アリンという作家のは初読み。
南北戦争末期、戦争によって引き起こされた中年夫婦の悲哀と無常さ、それでも、寄り添って生き続けて行こうとする姿を描いた作品。この結末には気持ちが揺さぶられる。
8作品とも、ハズレなし!
このアンソロジーはホント充実している。 お薦め。 お買い得です。
『たいした問題じゃないが -イギリス・コラム傑作選-』
いきなりどうでも良いことだが、コラムとエッセイの違いは? 良く判らん???
A・G・ガードナー
E・V・ルーカス
ロバート・リンド
A・A・ミルン といった、1900年代前半に活躍した4人のエッセイスト/コラムニストの選集。
全210ページに、32編のエッセイ。
ルーカスの作品には、おそらく逆説的な意味合いを持たせている? と採れる作品があったが、私には理解できないのが幾つかあった。
A・A・ミルンの書いたものが最も好みだったかな。
ミルンの本職はジャーナリストだけど、日本では「クマのプーさん」の作者として有名な人。
4人の中では、彼のエッセイが一番軽くてユーモラス。洒落も効いてる。
『現代落語論』
この本、年度末の忙しい時に読んだんだった。
記事にするのを忘れてた。
昨日の記事は長かったので、今日のは短めに。
談志が最初に書いた本らしい。
文章上手い! 読み易い。
初めての本でここまで書けるものなのか!?
50年近く前に書かれたものだが、主張していること、考えていることに古さを全く感じない。
短すぎる!? ・・ってか、細かい中身、忘れちゃったんだ・・・。
だから、読んだら直ぐ記事にしなきゃいけないんだよな。
『プレートテクトニクスの拒絶と受容』
これもずっと読みたかったヤツ。
偶然にも勤務先の先輩が持っているを見て借りた。
地震、火山、造山運動など、地球上の地質現象の原因を、地球の表面を覆う100km程度の厚さの十数枚のプレート(板状の岩盤)の運動によって説明するのがプレートテクトニクス。
昨年3月11日の地震もあって、プレートテクトニクスに関係する情報は最近でもかなりの量が流れている。
おそらく、21世紀初頭の地震大国日本に暮らす人々のうちの多くは,プレートテクトニクスによる地震発生の説明を受け入れていることだろう。
だが、かつて、このプレートテクトニクスを地質学に携わる日本の学者達の一部(時期によっては相当な多数)は拒絶してきた、という歴史がある。
欧米の地質学者達が、この説発表当初の1960年代から、地質学に生じた一種のパラダイムシフトを受け入れてきたにも拘わらず、何故、日本の地質学者達は、1986年頃までの間、長年にわたってこれを拒絶してきたのか? そして、その後どのような過程を経て受容されてきたのか、その歴史を記述したのが本書である。
日本の地質学者たち(の一部)に拒絶されてきた理由としては、いろいろな要因が挙げられている。
マルクス主義の影響だとか、地学団体研究会「地団研」という地質学会の中に誕生した集団や研究室内のヒエラルキーだとか、日本の地質学が独自に構築してきた日本列島形成に関する学説(地向斜造山論)を守るためだとか、地質学は歴史法則主義的に理解されるべきだとの主張だとか・・・。
科学的な整合性の優劣を議論するよりも、科学の外にある事柄による理由からの拒絶だった・・・。
そうした理由が本当なら、私からしてみれば、それらは一種の宗教とか集団マインドコントロールとも受け取れるようなものだ。当時の雰囲気や匂いを知らない、今頃になって聞きかじった者が尤もらしく云えることではないかもしれないが、プレートテクトニクス否定論者たちが何を言っているのか殆んどわからない、理由とも云えないような理由ばかりだ。
要は、科学的な理由によるものではない、イデオロギーが優先されたとしか思えないようなことばかりだ。
一方、地球物理学者たちは、プレートテクトニクスをいち早く受け入れた。現実主義にのっとった、物理・化学的メカニズムを重視する学者たちだ。
本書には、当時の地質学者と地球物理学者の考え方の違いも描かれている。
科学と云えども、純粋に真理を追求できる部門はごくごく限られている。少なからず政治や社会状況から影響を受ける。
本書はそうしたことの極端な事例を紹介している。
原子力発電の可否や地震・津波災害を巡って論争の続く昨今、こうした本を読んでおくのもイイかもしれない。
さて、ここからは蛇足記事。
私がプレートテクトニクスを知ったのは、中学生か高校生の頃に創刊された科学雑誌Newtonによってだった。プレートテクトニクスという地球のダイナミックな動きの仕組みについて書かれた記事をワクワクしながら読んだことを覚えている。
初代編集長の竹内均(竹内は、早々にプレートテクトニクスを受け入れた地球物理学畑の学者だった)らによって世間一般にも広められたのだ。
雑誌Newtonが創刊されたのが1981年だそうだから、地質学者の中からプレートテクトニクス否定論者が実質上消滅した1986年以前、すでに世間一般にはプレートテクトニクスは知られていたことになる。
つまり、世間の一般人よりも、地質学者の方がプレートテクトニクスを受け入れるのが遅れた、ということになる。こうした事実には驚かされる。
私は1986年以前に大学に入り、地質学などの講義も受けたが、そういえばプレートテクトニクスの説明を聞いた覚えがないことに、今になって思い至った。当時の大学の地質学の講義ではプレートテクトニクスは教えていなかったのか?
『ぼくは上陸している』
進化生物学、古生物学を土台にした著者による科学エッセイ。
著者は、あの傑作『ワンダフル・ライフ』をものしたグールド。2002年に亡くなった。
生物学の世界で云うところの「進化 : Evolution」 という言葉は、一般の世界で用いられている意味とは異なることを述べている。
一般用語または科学の世界でも天文学などでは、「一定方向の展開」という意味で使われるのに対し、生物学では、「変異」とほぼ同義。
生物学の「進化」には、あらかじめ定められた方向性などなく、予測できない結果に変化する。・・・複雑系。・・・創発。
●リンネの分類法
晴天の平日は花見に
会社、休んじゃった。 で、自転車乗って花見に。
氷川神社参道入口
鳥居の下をくぐって真っ直ぐ行くと氷川神社、そして大宮公園(左下)、サッカー場(右下)。


平日の大宮公園はスッゲー混んでた。屋台が数十軒も出ていて、繁盛していた。たぶん。
自転車でぶらぶらしながらも、目的地はちゃんと決めてた。
芝園団地内にある BE BOOKS 。 この書店で澁澤龍彦フェア が行われているってことで行ってきた。
このBE BOOKSの近くには卒業した高校があり、30年ぶりぐらいで訪れたが、学校の近くの雰囲気はあまり変わっていなかった。
で、BE BOOKS、ここまで澁澤作品が揃った平台は初めて見た。こんなにあるんだネぇー、って感心しちゃった。
2作を購入。
澁澤初心者にお薦めされていたのがコレ↓
それと、幻想小説っぽい、コレ↓
レジで「ブログを見て来ました」と云ったら、「楽しんでいただけると嬉しいです」と御丁寧な言葉をかけてくれました。
途中で昼食を取って、復路には、卒業した中学校の桜を見て帰ってきた。
なでしこJAPAN監督の佐々木さんを称える記念碑が建ってた。
往復48.22km。 久しぶりで疲れた。。。
『第六ポンプ』
SFの短編集。
『ねじまき少女』 と同一設定の近未来世界が舞台となっている2つの作品「カロリーマン」と「イエローカードマン」を読みたくて借りた。
その2作、短編小説としてまァまァではあるが、特段ではなかった。
しかも、長編『ねじまき少女』を読んいない人には、なかなか理解できない話ではないだろうか?と思う。
長編を読んでいて、物語が展開されている作品の世界観が判っていないと面白くないだろう。
この本を単独で読んで、はたして作品を楽しむことはできるのだろうか?
『さすらいエマノン』
梶尾真治原作の小説を、鶴田謙二がマンガ化した。
生命進化30億年以上の記憶を受け継いでいる少女、エマノンの旅の物語。
1作目だけでなく、2作目も出たことがうれしい。1作目が出たのはもう4年も前のことだ。 1作目の記事はコチラ。
最初70ページ弱はカラー・ページだ。その彩色の具合がすごくイイ。
文字によるセリフや説明を極力抑えている。
絵の構成と展開、そして、コマとコマの間の余韻 == 本来ならもう一つか二つのコマが描かれていたであろうところを敢えて描いていない隙間、でもってストーリーの展開が判る(想像できる)ようになっている。
原作のある物語をマンガでリライトするにあたって、作家が工夫したんだろうナ~ってことが想像できる。
鶴田画伯スゲー!
『氷川清話』
明治政府の御意見番、勝海舟翁のインタビュー集みたいなもの。
明治中期の新聞などに載った海舟の言説を集めて編集したものらしい。
かつての敵、西郷南洲(隆盛)のことはメチャクチャ誉めているが、伊藤博文などは大した輩ではない!様なコトを言い放つなど、好き勝手なコト言い放題。
だが、自ら、江戸っ子の心意気を語るように、何につけ、その言いっぷりは潔い。
良し悪しは判らないが、言ってることが終始一貫している。
ますます海舟ファンになってしまう。
それにしても、明治中期の政治も、現在の政治と大して変わらず、僅か数か月で内閣が変わったり、何かと政党が分裂したり衆合したり、が繰り返されているのが判る。
私には、明治期の内閣は長期政権でしっかりとした政治を行っていた、という勝手なイメージがあったものだから、こうしたコトを読むと、いつになってもヤッテルコトは変わらんし、それでも何とかなってきたんだ、・・・ってことは現在のダメダメだと思われている政治も歴史の上ではいつも通りなんだ、日本の政治なんてのゎ今も昔も離合集散が常態なんだ・・・、という一種の安心感が芽生えるから不思議だ。
以前読んだ 『それからの海舟』 も面白かったが、コレはもっと面白れぇ!
お薦めです。
本書は、 「閑人@濫読日記」さんの記事 に押されて読みました。ありがとうございました。