『快楽としてのミステリー』
大量の積読本を抱え、それらの消化も儘ならないのに、読み掛けの本が大量にあるのに、またもや衝動買いしてしまった・・・。
『快楽としてのミステリー』
- 『快楽としてのミステリー』 丸谷才一/著、 ちくま文庫(2012)
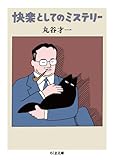
本書に先だって同著者による 『快楽としての読書 日本篇』 と 『快楽としての読書 海外編』 が出ていた。
- 快楽としての読書 日本篇 (ちくま文庫)/筑摩書房
- 快楽としての読書 海外篇 (ちくま文庫)/筑摩書房
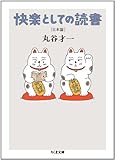

どちらも読んでみたいとは思っていた。とりわけ後者については書店に行くたびに立ち読みしていて、その都度購入を迷っていたが、結局それには至らなかった。どちらかというと純文学作品に関する紹介・書評であり、おおもとの作品をほとんど読んでいない文学音痴の身にとっては丸谷の言い分を充分に理解することは叶わないと感じたからであった。
だが、ミステリーに特化した内容・・・、しかも海外ミステリーが圧倒的に多い・・・、だったら結構読んでるし?・・・著者の云っていることも判るかもしれない???・・・。
ん~っ、じっくり読みたい・・・ってコトで・・・今に至る。。。
著者の丸谷才一はミステリー小説(丸谷本人の言い方としては「探偵小説」)を愛していた。文学作品と分け隔てなく。そもそもがジャンル分けを必要としていない風の態度が見える。
特段嬉しいのは、丸谷がチャンドラーに関して昔から高評価していることが判ることだ。
チャンドラー作品に関わるエッセイが5編載っている。
「フィリップ・マーロウといふ男」 p.103
「角川映画とチャンドラーの奇妙な関係 『プレイバック』」 p.182
「名探偵の前史 『マーロウ最後の事件』」 p.295
「これが文学でなくて何が文学か 『過去ある女 プレイバック』 『湖中の女』」 p.298
「ハードボイルドから社交界小説へ 『ロング・グッドバイ』」 p.301
以前、村上春樹による新訳『ロング・グッドバイ』に関する感想 を書いたときに、清水俊二による旧訳『長いお別れ』との比較はプロの書評家が行うだろう、と予想していたが、それを↑の5編目で丸谷が行っていた。
丸谷は言っている。
村上春樹の新訳によって『The Long Goodbye』はハードボイルドから社交界小説になった、と。
また、こうも言ってる。
清水訳は“マチスモ(男っぽさ)の悲哀”を描いて魅せたが、村上訳ではそれを“普遍的な人生の憂愁”に変じさせた、と。この比較については、さすがプロ!と感じる。
さてさて、本書の第1章では、「ハヤカワ・ポケット・ミステリは遊びの文化」と題して、1989年1月に行われた丸谷才一×向井敏×瀬戸川猛資による鼎談の模様が載っている。
ポケミス・ファンは必読!
他にもイロイロなミステリー作品に関する好意的な論評が載ってる。
で、グレアム・グリーンが読みたくなった。