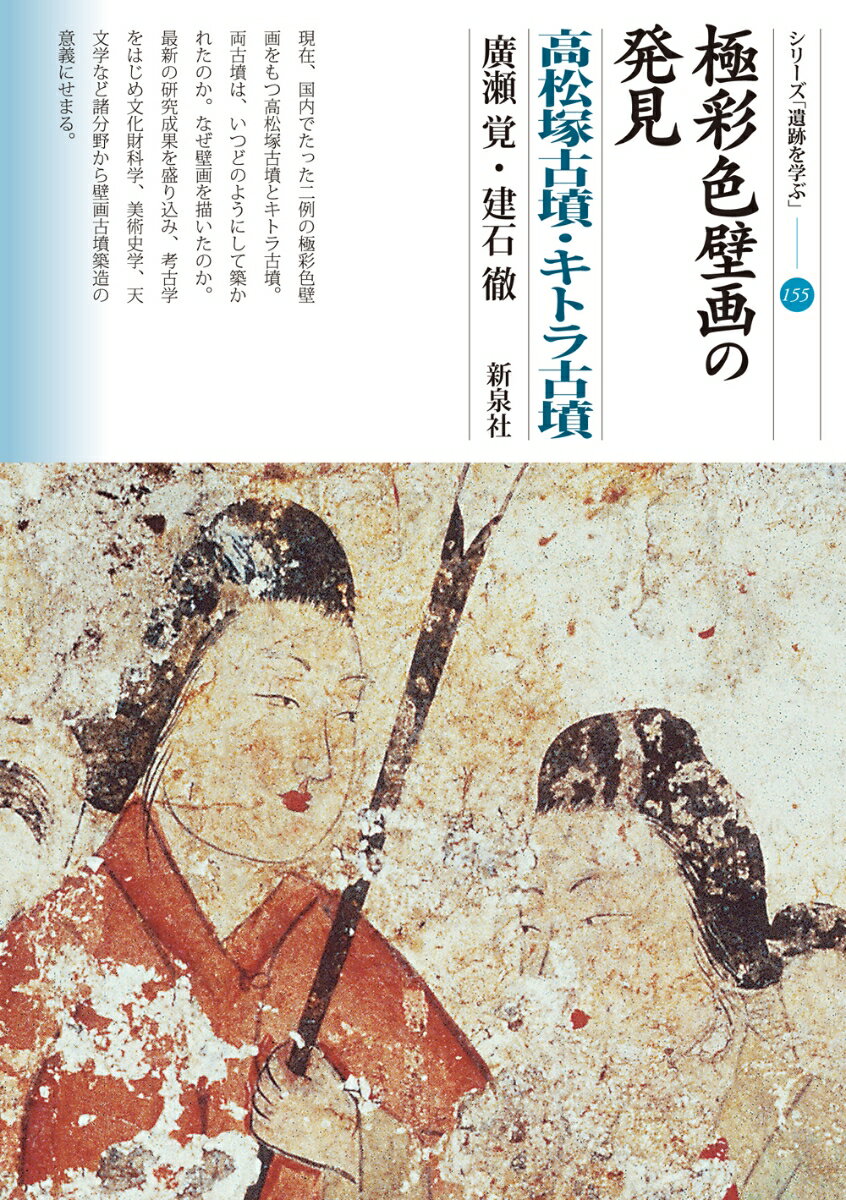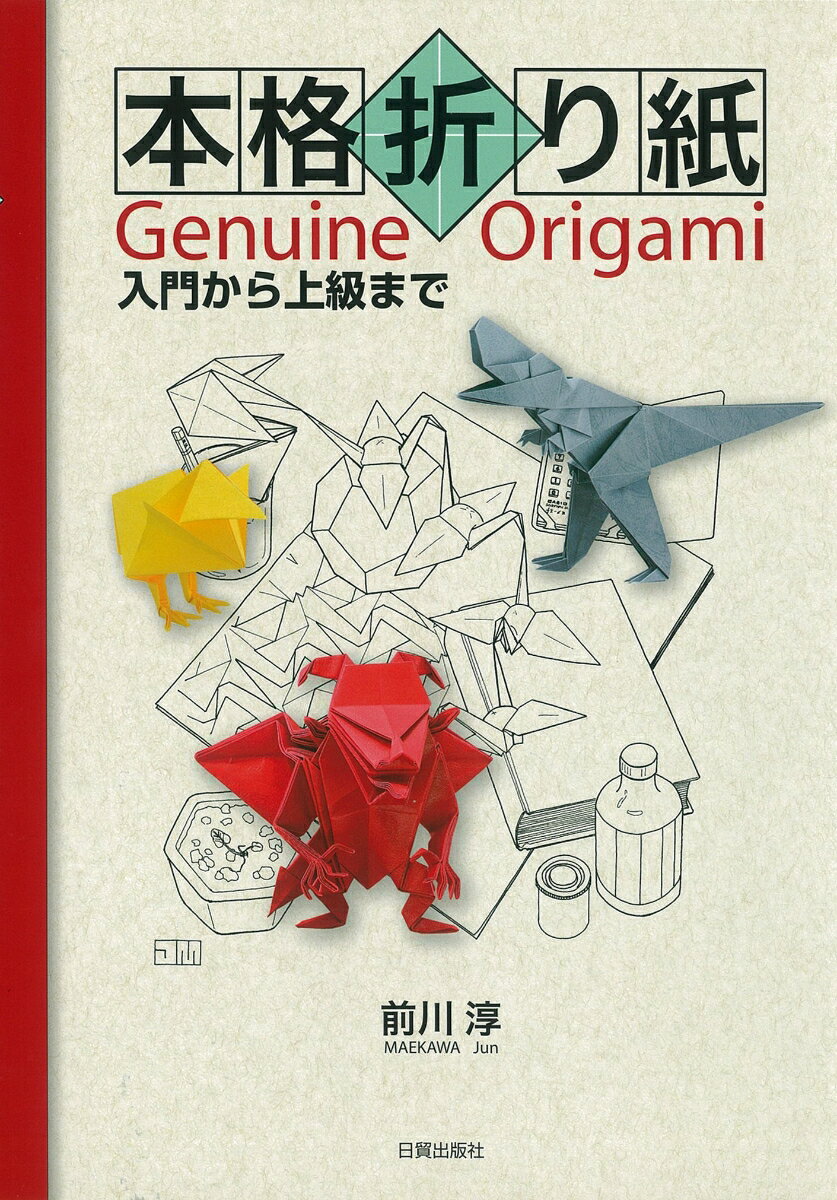先日、NHKニュース「ほっと関西」でも紹介されていた、大東市の北欧ランチに行ってきました。

場所は大東市の「morineki」エリア。最寄りはJR学研都市線の四条畷駅ですが、駅からだと少し歩きます。
着いてみると、広い芝生があったり、建物もゆったり並んでいたりして、「お、ここいいな…」という雰囲気。ずいぶんしゃれた所だなと思ったのですが、元々ここには公営住宅があり、老朽化に伴う建て替え事業の一環で、住宅と市民の憩いの場とをセットで整備した場所なんだそうです。
北欧ランチは「Keitto Ruokala」へ
北欧ランチが食べられるのは、morinekiエリア内の「Keitto Ruokala」というレストラン。
ランチメニューが3種類ある中で、私が注文したのは、ニュースで紹介されていた「北欧ぜいたくランチ」。今日のメインは北欧といえばこれ!のミートボールブラウンソースに、鯛のソテーが加わったプレート。パンにスープ、ドリンク、デザートも付いて1900円でした。
注文は今ドキのQRコードから。スープは3種類から選べますが、私は根菜ポタージュ・クルトン添え。ドリンクはホットコーヒーを選びました。

サラダから、いきなりびっくり
注文を終えると、ほどなくサラダが来ましたが、その内容にびっくり。中にはスモークサーモンに加えてイクラやら小エビやら、キウイまで入っていました。
トッピングも薄くそいで干したゴボウでしょうか。なんだか、いきなり胃袋を掴まれます。おなかが空いていた私は、メインが来るまでに全部平らげてしまいました(笑)
パンは北欧といえばこれ!としか説明できませんが、黒パン。朝早くから万博へ行き、何とか10時前にすべり込んで食べた、北欧館のモーニングを思い出しました。


メイン登場
そしていよいよメインが。スープとお揃いの色の、少し深みのある皿に、付け合わせの椎茸とともにやってきました。
ミートボールは、豚肉の味がしっかりと感じられ、ブラウンソースとのバランスも良し。余談ですがこのブラウンソース、パンにつけて食べるとこれまた美味なんですよね。
こんなこともあろうかと、サラダとスープからの勢いでパンまで平らげず、一切れ残しておいて正解でした(!)

とまあいろいろ感心していると、あっという間にデザート。紅茶のアイス、クッキーなど4種あり、最後まで贅沢気分が味わえました。

「食器」も素敵
さて、私が特に嬉しかったのは、料理自体もそうですが「食器」。
北欧といえば食器も有名ですが、揃いの青い皿は「iittala」、コーヒーカップは「Arabia」と、お店側のこだわりを感じます。
ニュース映像を見たとき、すでに『これは北欧の食器だな?』とピンときてはいましたが、実際に使ってみて、特にコーヒーカップのしっかりした重量感には、ちょっと驚かされました。
コーヒーは量がたっぷりあって、ゆっくりおしゃべりしたい人には最高。ふと店内を見渡してみると、平日の昼12時前にもかかわらず、すでに20人近くお客さんがいて、小さいお子さんを連れたママさん、中年女性のグループが多かったです。
食事を終えた後は、同じエリア内のショップをうろうろしましたが、Arabiaの食器はショップ「Keitto Asua」でも売られていました。素敵ですね。

今日のもう1つの目的、セムラ!
最後になりましたが、今日のもう1つの目的は、ベーカリーカフェ「Keitto Leipa」で売られている「セムラ」。
北欧館でも人気だったこのスイーツ、作っていたのはこのお店だったという情報は、万博閉幕後すぐ把握できていたのですが、なかなか来る機会がなく(大東市にあるのに「四条畷」という名前の駅は、大阪市中心部からは若干遠いですし、駅からも歩くとなかなか距離ありますからね・・・)、今回ついでにと思いテイクアウトしました。

ちなみにKeitto Leipaにはイートインエリアもあり、セムラは店内で食べることもできるようです。
セムラはちょっと前に流行ったクリームパン「マリトッツォ」にも似た見た目ですが、生地にカルダモンが練り込んであったり、中には生クリームのほかにアーモンドペーストも挟み込まれていたりと、若干サッパリ目のお味。
家族の分もテイクアウトし、帰宅後は万博と今日の余韻にしばし浸りました。