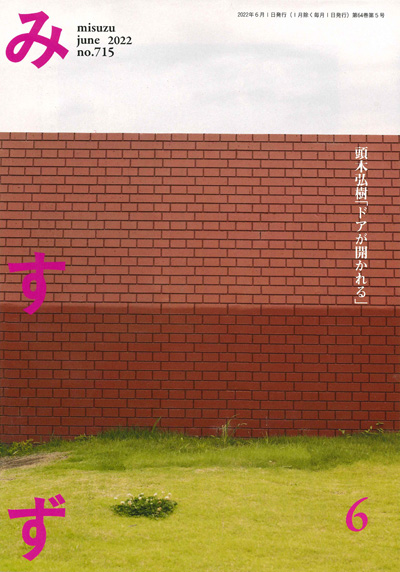「咬んだり刺したりするカフカの『変身』」
という連載をさせていただいています。
隔月連載で、
第1回が2020年8月号
第2回が2020年10月号
第3回が2020年12月号
第4回が2021年4月号
第5回が2021年6月号
第6回が2021年8月号
第7回が2021年10月号
第8回が2021年12月号
第9回が2022年4月号
———————————————————————
今回の「原文」「英訳」「邦訳」
連載中でスローリーリーディングした箇所の
「原文」「英訳」「邦訳」です。
英訳は最も普及している David Wyllie 訳(2002年)、
邦訳は青空文庫の原田義人訳(1960年)です。
(私の新訳は連載のほうに掲載してあります)
※長いので、別にして、このブログのひとつ前のブログに載せました。こちらご覧いただけますと幸いです。
———————————————————————
『変身』の翻訳で解釈が分かれる箇所について、
連載の校正をしてくださっている
岡上容士(おかのうえ・ひろし)さんが、
文章を書いてくださっています。
今回は第10回の分です。
「変身」において
翻訳の解釈が分かれている箇所
(連載の第10回で取り扱われている範囲で)
岡上容士(おかのうえ・ひろし)
※詳しく見ていくと、このほかにもまだあるかもしれませんが、私が気がついたものにとどめています。
※多くの箇所で私なりの考えを記していますが、異論もあるかもしれませんし、それ以前に私の考えの誤りもあるかもしれません。ご意見がおありでしたら、頭木さんを通じてご連絡いただけましたら幸いです。
※最初にドイツ語の原文をあげ、次に邦訳(青空文庫の原田義人〔よしと〕訳)をあげ、そのあとに説明を入れています。なお邦訳に関しては、必要と思われる場合には、原田訳以外の訳もあげています。
※ほかにも、文の一部分や、個々の単語に対して、邦訳の訳語をあげている場合があります。この場合には、『変身』の邦訳はたくさんありますので、同じ意味の事柄が訳によって違った形で表現されていることが少なくありません(たとえば「ふとん」「布団」「蒲団」)。ですが、説明を簡潔にするため、このような場合には全部の訳語をあげず、1つ(たとえば「ふとん」)か2つくらいで代表させるようにしています。
※邦訳に出ている語の中で読みにくいと思われるものには、ルビを入れています。
※高橋義孝訳と中井正文訳は何度か改訂されていますが、一番新しい訳のみを示しています。
※英訳に関しては、今回は、特に示す必要はないと思われた若干の箇所では省略してあります。
※「接続法第Ⅱ式」という語法が出てきますが、「ドイツ語の接続法とはどのようなものか」といったことから説明していますと非常に長くなりますし、ここのテーマからも外れてきます。ですから、ドイツ語の接続法に関してはご存知であることを前提とします。ご存知でない方でご興味がおありの方は、お手数ですが、ドイツ語の参考書などをご参照下さい。
○Es schien leider, daß er keine eigentlichen Zähne hatte, –womit sollte er gleich den Schlüssel fassen? – aber dafür waren die Kiefer freilich sehr stark; mit ihrer Hilfe brachte er auch wirklich den Schlüssel in Bewegung und achtete nicht darauf, daß er sich zweifellos irgendeinen Schaden zufügte, denn eine braune Flüssigkeit kam ihm aus dem Mund, floß über den Schlüssel und tropfte auf den Boden.
残念なことに、歯らしいものがないようだった――なんですぐ鍵をつかんだらいいのだろうか――。ところが、そのかわり顎(あご)はむろんひどく頑丈(がんじょう)で、その助けを借りて実際に鍵を動かすことができたが、疑いもなく身体のどこかを傷つけてしまったことには気づかなかった。傷ついたというのは、褐色(かっしょく)の液体が口から流れ出し、鍵の上を流れて床へしたたり落ちたのだった。(原田義人〔よしと〕訳)
残念なことにはちゃんとした歯が彼にはないようであった。――では鍵を何ではさんだらよいのだろうか。無論歯の代りに顎が非常に強力であった。実際に彼は顎を使って鍵を動かしはじめ、そのさい明らかにどこか傷つけたが、それも気にかけなかった。茶色の液体が口から流れ出て、鍵を伝わり、床にしたたり落ちたのである。(神品〔こうしな〕友子訳)
残念ながら、本来の歯といえるようなものが彼にはないらしく――いったい何でもって鍵をつかめばよいというのか?――、しかしその代わりに、もちろん、顎が上下とも非常に頑丈だった。それに、その顎を使ってみると実際に鍵が動き、明らかにどこかを傷つけてしまったものの――というのも、茶褐色の液体が口から流れ出して、鍵を伝い、床に滴(したた)っていたのだ――、そんなことに構いはしなかった。(浅井健二郎訳)
womit sollte er gleich den Schlüssel fassen? のsollteは、一見過去形のようでもありますが――sollenは過去形も接続法第Ⅱ式も同形ですが、この作品の地の文(小説の語り手の文章)は過去形で書かれていますから――、これらの訳では現在形として訳しています。これはなぜかと言いますと、この文を「体験話法」とみなしているからです。体験話法に関しては、次の題名の頭木さんのブログで詳しく記してありますので、ご興味がおありでしたらご覧下さい。
「咬んだり刺したりするカフカの『変身』」6回目!月刊『みすず』8月号が刊行されました
もっとも、ここのwomit sollte er gleich den Schlüssel fassen? は、体験話法ともそうでないとも解せますが、この点に関しては、終わりの方の「ドイツ語の体験話法に関しての補足」で別に記します。
achtete nicht darauf, のdarの部分は、あとのdaß以下の内容を受けています。邦訳では原田訳のように、「...に気づかなかった」という感じで訳しているものもかなり多いのですが、auf ... achten という言い方は、「...に気づく」という意味とはちょっと違いますし、これほどの状態になっていながら気がつかなかったというのはちょっと不自然な感じがします。神品訳や浅井訳のように訳した方がよいのではないかと、私は思います。
○»Hören Sie nur«, sagte der Prokurist im Nebenzimmer, »er dreht den Schlüssel um.« Das war für Gregor eine große Aufmunterung; aber alle hätten ihm zurufen sollen, auch der Vater und die Mutter: ›Frisch, Gregor‹, hätten sie rufen sollen, ›immer nur heran, fest an das Schloß heran!‹
「さあ、あの音が聞こえませんか」と、隣室の支配人がいった。「鍵を廻(まわ)していますよ」
その言葉は、グレゴールにとっては大いに元気づけになった。だが、みんなが彼に声援してくれたっていいはずなのだ。父親も母親もそうだ。「グレゴール、しっかり。頑張って! 鍵にしっかりとつかまれよ」と、両親も叫んでくれたっていいはずだ。(原田訳)
「ほら、お聞きなさい」と隣室で支配人が言った、「鍵を回していますよ」 それはグレーゴルを大いに元気づける言葉だった。しかし、できるなら、みんながかれに声援を送ってほしかった。父と母にも「しっかり、グレーゴル、それ、こっちだ、鍵にしっかりつかまれ!」と大声で励ましてもらいたかった。(高本研一訳)
aber alle hätten以下は、動詞が過去形の接続法になっているにもかかわらず、原田訳では現在形のように訳しています。これも、前項のwomit sollte er gleich den Schlüssel fassen? と同じく、このaber alle hätten以下を「体験話法」とみなしているからです。体験話法に関しては、頭木さんのブログをご覧下さい(前項にリンクがあります)。
ここのaber alle hätten以下も、体験話法ともそうでないとも解せますし、体験話法と解した場合には、ある問題が出てきますが、これらの点に関しては、終わりの方の「ドイツ語の体験話法に関しての補足」で別に記します。
最初のHören Sie nurですが、原田訳のように疑問文として訳している訳と、高本訳のように命令文として訳している訳とがあり、英訳でも同じように解釈が分かれています。ただ、邦訳でも英訳でも、命令文として訳しているものの方がだいぶ多いですが。
nurはここでは強調のために使われていますが、疑問文でも命令文でも使われますから、決め手にはなりませんね。
私の感じでは、疑問文なのでしたら »Hören Sie nur?«, sagte der Prokurist im Nebenzimmer, »Er dreht den Schlüssel um.« となるのではないかと思います。
もっとも、命令文なら命令文で、文末に!を入れるのが原則ですから、»Hören Sie nur!«, sagte der Prokurist im Nebenzimmer, »Er dreht den Schlüssel um.« となるのが正当なのですが、höreやsiehe――hörenやsehenの、duに対する命令形。必ずしも「聞きなさい」「見なさい」という意味になるとは限らず、「ねえ」とか「ほら」などのように相手の注意を軽く促す感じの意味になることもあります――は、次のように、文の冒頭に置かれて、必ずしも!をつけずに使われることがあります。
hör mal, du mußt etwas sorgfältiger mit dem Buch umgehen
ねえ君、その本はもう少し気をつけて扱ってくれたまえ(郁文堂独和辞典)
Siehe, ich stehe vor der Thür(=Tür) und klopfe an. (新訳聖書「ヨハネ黙示録」、第3章第20節。ドイツ語訳の1つ)
見よ、わたしは戸の外に立って、たたいている。(日本聖書協会訳)
このHören Sie nurもこの種の使い方と考えることは無理でしょうか。
いずれにしましても、私としては命令文と解したいと思いますが、疑問文と解しても誤訳とは言えないと思います。
それから、グレーゴルが想定している、ほかの人たちの掛け声は、口語的な表現になっていて訳しにくいですが、解釈が分かれる箇所ではありませんので、ここでは取り上げません。ただ、英訳ではいろいろな訳し方のヴァリエーションがあって面白いですから、一番最後に付録としてあげておきます。ご興味がおありの方はご覧下さい。
○Und in der Vorstellung, daß alle seine Bemühungen mit Spannung verfolgten, verbiß er sich mit allem, was er an Kraft aufbringen konnte, besinnungslos in den Schlüssel. Je nach dem Fortschreiten der Drehung des Schlüssels umtanzte er das Schloß; hielt sich jetzt nur noch mit dem Munde aufrecht, und je nach Bedarf hing er sich an den Schlüssel oder drückte ihn dann wieder nieder mit der ganzen Last seines Körpers. Der hellere Klang des endlich zurückschnappenden Schlosses erweckte Gregor förmlich.
そして、みんなが自分の努力を緊張して見守っているのだ、と思い描きながら、できるだけの力を振りしぼって気が遠くなるほど鍵にかみついた。鍵の回転が進行するにつれ、彼は鍵穴のまわりを踊るようにして廻っていった。今はただ口だけで身体をまっすぐに立てていた。そして、必要に応じて鍵にぶらさがったり、つぎにまた自分の身体の重みを全部かけてそれを押し下げたりした。とうとう開いた鍵のぱちりという澄んだ音が、夢中だったグレゴールをはっきり目ざませた。(原田訳)
そしてみんながかれの努力をはらはらしながら見守っているのだと想像しながら、しぼれるだけの力をふりしぼって気も遠くなるほど鍵に噛(か)みついた。鍵が回るにつれて、かれも鍵の回りを踊るように回った。いまはもう口だけで身体をまっすぐに支えていた。そして必要に応じて鍵にぶらさがったり、全身の重みを鍵にかけて押し下げたりした。とうとうパチンと音を立てて鍵が開いたが、その澄んだ響きでグレーゴルははっきり目が覚めた。(高本訳)
①... ; hielt sich jetzt nur noch mit dem Munde aufrecht, und je nach Bedarf hing er sich an den Schlüssel oder drückte ihn dann wieder nieder mit der ganzen Last seines Körpers. ここの描写は必ずしも明確ではなく、訳でも解釈がいろいろに分かれています。一応私なりの解釈を記しますが、絶対に正しいとは言い切れません。
まず、hielt sich jetzt nur noch mit dem Munde aufrecht, ですが、ここだけを単独で読みますと、鍵をかんだりはしておらずに、口の部分でドアに身をもたせかけていたとも解せないことはありませんし、かなりの邦訳では「立っていた」とか「体を立てていた」というようにも訳しています。しかし、やはり前後の彼の動きから考えますと、ここで唐突に立ったりするのはちょっと不自然かなと、私は思います。
これは、グレーゴルが鍵を口にくわえて身を(回転はしながらも)固定している状態を言っているのではないでしょうか。回転しているわけですから、彼は上下左右いろいろな位置にいるわけであり、必ずしも鍵にぶら下がった状態だけとは限らないと思います。ですから、高本訳などのように訳した方がよくはありませんでしょうか。
次に、und je nach Bedarf hing er sich an den Schlüsselですが、英訳では、hing(hängen) ... sich an ... を「ぶら下がる」とは解さずに、(cling to ... やhang onto ... や hang on to ... を使って)「...にしがみつく」と解しているものが、案外多くあります。ですが邦訳では、ある訳が「鍵につかまって体を支えたり」と、このようにも解せる訳をしている以外はすべて、「ぶら下がっている」と解しています。このあとが oder ではなく und となっているのでしたら、「しがみついて、さらに体重をかけて押し下げた」とも言えないことはないかもしれませんが、そうはなっていませんし、私はやはり、「ぶら下がっている」と解したいと思います。さらには、このあとのdrückte ihn dann wieder nieder mit der ganzen Last seines Körpersと対比させる形で、グレーゴルが鍵の上にいたり下にいたりしたことを言っているのではないかとも思います。
それから、そのdrückte ihn dann wieder nieder mit der ganzen Last seines Körpers ですが、一部の邦訳では、前の und je nach Bedarf hing er sich an den Schlüssel とこれを、同じ動作の言い換えのように訳しています。確かに、oderには「あるいは」のほかに「すなわち」という意味もありますから、このような解釈も考えられうるかもしれません。ですが、ぶら下がった状態でこの動作をしたのであれば、「押す」と言うよりも、「引っ張る」という感じになりますから、drückteよりも zog(ziehenの過去形) などを使うのではないでしょうか。さらには、ここには dann wieder(それからまた)という語がありますから、前の表現の言い換えとは、やはりちょっと考えにくいのではないでしょうか。ここではやはり、グレーゴルは鍵の上にいて――hielt sich jetzt nur noch mit dem Munde aufrechtと関連づけますと、逆立ちをしているような感じで――、体重をかけて鍵を下へ押していたのではないかと、私は思います。
ただ、こう考えますと一応は辻褄が合いますが、ぶら下がっているのも、上から押しているのも、「鍵を下に下げる」という、同じことをしているではないかということになってきますね。je nach Bedarf という語は文字通り、「必要に応じて」ですし、邦訳も文字通りそう訳しているだけか、またはあえて訳していないかですが、同じ姿勢ばかりですとやはり疲れますので、時々変えたということを言っているのかもしれません。あるいは、Bedarf は日本の独和辞典ではおおむね、「必要」とか「需要」とかいった意味しか載せていませんが、ドイツの辞典には Gewünschtes とか Verlangen とかいった語義も出ており、「彼の[その時々の]望み次第で」とも言えないこともないかもしれませんが、ちょっと強引な解釈でしょうか。
あるいはもしかして、ここは鍵を「[鍵穴に]押し込む」ということかなとも考えてみましたし、一部の邦訳や、あえてdownを入れずに訳している一部の英訳のように、そう解している訳もあります。ですが、niederの基本的な意味は「下へ」ですし、「押し込む」でしたらやはり、[drückte ... ] hinein とするのが自然かなと思います。
②Der hellere Klang des endlich zurückschnappenden Schlosses erweckte Gregor förmlich. では、多くの邦訳が、hellere(hellの比較級。erが比較級の語尾であり、最後のeは形容詞が単数1格の男性名詞を修飾し、かつその前に定冠詞がある場合の、変化〔弱変化〕の語尾ですね)が比較級であることと、zurückとを、特に訳出していません。
hellerと比較級になっているのは、いわゆる「絶対比較級」(ほかと特に比較するのではなく、「かなり...な」という意味になります)かと私は思いますし、zurückに関しては、私は鍵の構造は詳しく知りませんが、はまっていた部分が外れて、パチンと(掛けられていない状態に)戻るということかなと思います。
ですが、こうした箇所まで訳出しますと、かえって読者に細かい疑問が生じてしまったりする場合もありますので、あえて訳出しなくてもよいかもしれませんね。
ただ、一応ご参考までに、hellerの比較級部分を訳出している訳は、
とうとう錠がぱちんとはねあいて、一段と澄んだその音に、グレゴールは目がさめたようだった。(辻瑆〔ひかる〕訳)…しかし、「一段と」ですと普通の比較級のようになりますので、ちょっと感じが違うと思います。
ついに錠前のなかのバネがはね返るややかん高い音に、グレーゴルはふとわれに返った。(高安国世訳)…しかし、「やや」では絶対比較級の訳語としては弱く、これもちょっと感じが違うと思います。
ついに錠がかちりと開いて、ひときわ澄んだその音で、グレゴール(のちの訳では、グレーゴル)は目が覚める思いがした。(城山良彦訳)…「ひときわ」は、逆にちょっと強すぎる感じがします。
ようやく鍵が外れるパチンという大きな澄んだ音が聞こえたとき、その音はグレーゴルを文字通りよみがえらせた。(野村廣之訳)…この訳が一番妥当かなと思います。
また、zurückを訳出している訳は、上記の高安訳のほかに、
ついにパチンと鳴ってはね返った鍵の、その高い音が、グレーゴルを本式にめざめさせた。(川村二郎訳)
ついに錠がカチリと返る澄んだ音が響いて、それでグレーゴルは文字通り我に返ったのだった。(浅井訳)
なお、ついでながら、最後のförmlich は、「中途半端にではなく本格的に」というニュアンスかと思われますが、明確に訳出していない邦訳もありますし、上記の諸訳以外では、「しっかり」「すっかり」「たしかに」「はっと」「まさしく」などと訳されています。
○Da er die Türe auf diese Weise öffnen mußte, war sie eigentlich schon recht weit geöffnet, und er selbst noch nicht zu sehen. Er mußte sich erst langsam um den einen Türflügel herumdrehen, und zwar sehr vorsichtig, wenn er nicht gerade vor dem Eintritt ins Zimmer plump auf den Rücken fallen wollte.
彼はこんなふうにしてドアを開けなければならなかったので、ほんとうはドアがもうかなり開いたのに、彼自身の姿はまだ外からは見えなかった。まずゆっくりとドア板のまわりを伝わって廻っていかなければならなかった。しかも、部屋へ入る前にどさりと仰向(あおむ)けに落ちまいと思うならば、用心してやらなければならなかった。(原田訳)
ドアを開くのにもこんなふうにしなければならなかったので、ドアが内側にすっかり開かれても、彼の姿はドアのうしろになっていて最初は外からは見えなかった。彼はまずゆっくりとドアの開かれたほうの翼板(よくばん)を伝って前にまわらなければならなかった。しかもごく慎重にやらなければ、部屋にはいる直前、ぶざまにどさりとあおむけに倒れる心配があった。(高橋義孝訳)
こんな調子でドアをあけなければならないのだから、いよいよちゃんと大きくドアがあけられても、かんじんの彼の姿はまだみえなかった。一方のドアの翼板をまわって、彼はやっとのろのろ前の方にまわりこんでこなければならない。しかも、みんなのいる部屋へ入ろうとするとたんにどさりと仰向けにたおれるようなみっともない真似(まね)をしたくないばっかりに、念には念を入れて慎重に。(山下肇〔はじめ〕訳)
こんなふうにしてドアを開けるしかなかったので、両開きのドアの一枚がすでにかなり大きく外に開けられていても、まだ誰も彼自身の姿を見ることはできなかった。彼はとりあえず、もう一枚のまだ開けられていないドアにつかまりながら、のろのろ巡(めぐ)らなければならず、しかも、隣室へ入ったとたんに仰向けに倒れるようなぶざまな姿だけはさらしたくなかったので、慎重に行なわなければならなかった。(山下肇・萬里〔ばんり〕訳)
当時のこのようなドアは両開きで、そのうちの一枚は通常、留め金で固定されていたようです(三原弟平〔おとひら〕『カフカ「変身」注釈』p.89)。それで、Er mußte sich erst langsam um den einen Türflügel herumdrehen,と書かれていますが、グレーゴルはどちらのドアの後ろにいて、そこから隣の部屋に入るべく、回り込んだのでしょうか。
頭木さんと私は、固定された方のドアではないかと思いました。有力な根拠の1つは、このあとの方で、次の文が出てくることです。
Gregor trat nun gar nicht in das Zimmer, sondern lehnte sich von innen an den festgeriegelten Türflügel, so daß sein Leib nur zur Hälfte und darüber der seitlich geneigte Kopf zu sehen war, mit dem er zu den anderen hinüberlugte.
グレゴールはむこうの部屋へは入っていかず、しっかりかけ金をかけてあるドア板に内側からよりかかっていたので、彼の身体は半分しか見えず、その上にのっている斜めにかしげた頭が見えるのだった。(原田訳)
この点も含めて、ここに関しては、今回の連載で頭木さんが詳しく論じておられますから、そちらをご覧下さい。私の方では、邦訳や英訳がおおよそどのようになっているかを示すだけにとどめておきます。
この点に関しては、邦訳では解釈が大きく分かれており、おおよそ次の5つのパターンがあります。
(a)開いた方と、はっきり言葉を足している(高橋訳、城山訳、立川〔たつかわ〕洋三訳、三原訳)。
(b)開いていない方と、はっきり言葉を足している(山下肇・萬里訳のみ)。
(c)明確に言ってはいないが、同じ「ドア」という表現をしていることなどから、開いた方と解しているのではないかと思われる。
(d)これも明確に言ってはいないが、「一方」とか「片方」とか表現していることなどから、開いていない方と解しているのではないかと思われる。
(e)文字通りあいまいで、どちらとも解せる。
上記の(a)〜(d)までは、上に訳例を1つずつあげてあります。
英訳でもいろいろなパターンがありますが、この部分を
aroundかround [theが入ることも] one [half, leaf, panel, section, wingなどが入ることも] of the [doubleが入ることも] doorかdoors
と訳しているものが多く、これは邦訳の(d)と同じパターンですが、上記のような書き方ですとちょっとわかりにくいかもしれませんので、5つだけ具体例を示しておきます。
around the one wing of the door (Stanley Corngold訳とKatja Pelzer訳)、around the one section of the door (Karen Reppin訳)、around one leaf of the double door (Stanley Appelbaum訳)、around one of the double doors (David Wyllie訳)、round one half of the door (Michael Hofmann訳)
中には、はっきりopenと入れてある訳や、上記の[theが入ることも]という部分にthisやhisが入っていて、前との関係から「開いた方」とみなしていると判断できるものもあります。
around the open panel of the double door (Charles Daudert 訳)、round his leaf of the door (J. A. Underwood訳)、round this wing of the door (Malcolm Pasley訳とRichard Stokes訳)
英訳で唯一、明確に開いていない方とみなしているのはPhilipp Strazny訳で、前後も入れて記しますと、
Since he had to open the door in this manner, he was still not in view when the door was already quite far ajar. He still had to pivot around the other door leaf, very carefully, because he did not want to enter the room by clumsily falling on his back.
となっています。ただ、これですと、when the door was already quite far ajarのthe doorは、the door leafとした方がよいですね。
○Er war noch mit jener schwierigen Bewegung beschäftigt und hatte nicht Zeit, auf anderes zu achten, da hörte er schon den Prokuristen ein lautes »Oh!« ausstoßen – es klang, wie wenn der Wind saust – und nun sah er ihn auch, wie er, der der Nächste an der Türe war, die Hand gegen den offenen Mund drückte und langsam zurückwich, als vertreibe ihn eine unsichtbare, gleichmäßig fortwirkende Kraft.
彼はまだその困難な動作にかかりきりになっていて、ほかのことに注意を向けるひまがなかったが、そのとき早くも支配人が声高く「おお!」と叫ぶのを聞いた――まるで風がさわぐときのように響いた――。そこで支配人の姿も見たが、ドアのいちばん近くにいた支配人はぽかりと開けた口に手をあてて、まるで目に見えない一定の強さを保った力に追い払われるように、ゆっくりとあとしざりしていった。(原田訳)
このむずかしい作業にかかりきって、ほかのことをかえりみる暇(ひま)などはなかったが、そのとき早くも支配人の、「おお!」と大声に叫ぶ声――まるで、風のふきすさぶようなひびきだった――が耳をうった。と、そこで彼の目にも支配人の姿が見えたが、ドアのいちばん近くにいたその支配人は、あんぐりとあけた口に手をあてて、なにか一様に作用しつづける、目に見えない力に追いたてられてでもいるように、ゆっくりとあとずさりしてゆくのだった。(辻訳)
この困難な動作に彼は熱中し、ほかのことに気に配るどころでないのに、もう支配人の「おっ」という大声が耳に入ってきた。――それはまるで風がざわざわというように響いた。――それからドアの彼のすぐそばに居た支配人が、手で開いた口をおさえ、まるで均等に働きつづけている見えない力に追い払われるかのように、あとずさりしているのが見えた。(神品訳)
順番が前後しますが、そしてこちらの方は、解釈の違いではなくて訳し方の違いなのですが、まずはwie er, ... について見てみます。このwieは、品詞としては接続詞ですが、ここでは関係代名詞に近い用法であり、前のihnの具体的な動作を描写しています。つまり、文法的に正確には、「...し、...していたihn」と訳すことになります(参考例として、Ich blickte dem Wagen nach, wie er durch den staubenden Sand dahinzog. 私は砂ぼこりの中を走り去る車を見送った〔小学館独和大辞典〕)。しかし、ここでそのように訳しますとihnにかかる部分がだいぶ長くなりますので、原田訳や辻訳のようにこのund nun sah er ihn auch, でいったん切るような感じで訳した方がわかりやすいと思われますし、ほかの邦訳も大部分がこう訳しています。
神品訳のように訳している訳も、ほかに4つほどありますが、いずれも直訳的に「...し、...していたihn」とは訳しておらず、「支配人が...し、...していくの(または、さま)が見えた」という感じで訳しています。つまり、「...支配人が、...口に手をやり、...あとずさりしていくさまが見えた(Gregorをうけている方のerは訳出せず)」(菊池武弘訳)、「...グレゴールは、...支配人が...その口に片手を押しあて、...後ずさりしてゆくのが目に入った」(三原訳)、「...支配人が、片手で...口を押さえたまま、...後ずさりしていくのをグレーゴルは見た」(野村訳)、「...支配人が...口に手をあてて...後退(あとずさ)りしていくのが見えた(Gregorをうけている方のerは訳出せず)」(多和田葉子訳)と訳しています。ですが、いずれもihnを省いた形で訳してはいますが、実質的にはwie er, ... をihnにかける形で訳していると言ってよいと思います。
次に、wie er, ... の前の、und nun sah er ihn auchですが、auchはどの語にかかっているのでしょうか。
(a)邦訳では、auchを訳出していない訳も多いのですが、訳出している訳はおおむね、ihn(あるいはsah ... ihnと考えてもよいと思います)にかかっていると考えて、原田訳のような感じで訳しています。つまり、グレーゴルは支配人の声を聞いただけでなく、支配人の姿も見た、ということになりますね。
(b)ですが、辻訳、真鍋宏史訳、川島隆訳は、auchはerにかかっていると考えて、「グレーゴルも支配人を見た」という感じで訳しています。また、菊池訳(対訳書)では、巻末の翻訳では上記のとおりauchを訳出していませんが、原文と対比させている逐語訳では、auchをerにかけて訳しています。つまり、これらの解釈では、支配人がこんな叫び声を上げたのは、当然支配人がグレーゴルの姿を見たからだが、グレーゴルの方も支配人を見た、ということになりますね。
英訳では、邦訳と同様にauchを訳出していないものも多いですし、文末にtooやas well を置いてあるものはどの語にかかっているのか不明確ですので参考にはならず、どちらにかかっているのかを明確にして訳しているものは、解釈がほぼ半々に分かれています。
ここに関しては、どちらが正しいのかは、私には断定できません。
(a)説に有利な考え方としましては、(b)説のように言いたいのであれば、und nun sah auch er ihn, と書くのではないかと思われることがあげられます。ですが、この点に関しては、会話に精通している知人の意見では、この語順はドイツ人には耳への響きの点から不自然と感じられるので、こうは言わないとのことでした。それから、auchが「...のことをしただけでなく、...のこともした」というニュアンスで使われることは確かにあるということもあげられます。ご参考までに、この例を1つあげておきます。
Don Gonzalo hörte ihr(=der Amme) zu; mitunter gab er auch diese oder jene Antwort, und doch waren seine eigentlichen Gedanken schon weit hinausgegangen über alles, was die Amme vorbrachte. (Werner Bergengruen: Die Krone)
ドン・ゴンサロは彼女の言うことを聞いてやった。ときどきあれこれの返事もしてやったが、しかし彼の本来の思いはすでに遠く、乳母の口にする一切のことを越えていたのである。(義則〔よしのり〕孝夫訳)
この場合、「彼も、(乳母だけに話させていたわけではなく)返事をすることはあった」のようにも訳せないことはありませんが、やはり「聞いてやっただけでなく、返事もしてやった」のように訳した方が自然ですね。
(b)説に有利な考え方としましては、auchは必ずしもそれがかかる語の直前や直後に置かれないことも少なくないことや、(a)説のように考えると、上記のwie er, ... に関する説明からもおわかりのように、このauchはihnだけではなく、ひいてはwie以下の内容にもかかってくることになり、重い感じになってしまうような気がすることがあげられます。後者のようなことを意識したのかどうかはわかりませんが、wie以下をihnにかける感じで訳している5つの邦訳はどれも、auchを訳出していません。
しかしながら結局は、どちらに解しても言っている内容自体は大きくは変わりませんから、読者の好みでよいのではないでしょうか。
ここでちょっと余談的になりますが、auchに関する興味深い例を1つ、見てみましょう。
今回の「変身」でのこの文では、auch がどちらの語にかかっていると考えても、意味が大きく変わってくることはありませんが、中にはどちらの語にかかっていると考えるかによって、意味が正反対になってくることもあります。以下にあげる文章は、ある短編小説の冒頭からちょっとだけあとの部分であり、捕虜たちが食事のパンを受け取ろうとしている場面が描かれています。
„Du bist Brotholer“, sagte einer und stieß Norbert in den Rücken.
„Ich weiß, aber laßt mich vorher die Hände waschen.“
„Ich nehm das Brot auch so!“ rief einer von oben. (Hans Bender: Der Brotholer)
「おまえがパンを取りに行くんだぞ」と、だれかが言ってそしてノルベルトの背中を突いた。
「わかっているよ、だがそのまえに手を洗わせてくれ」
「おれもそうやってパンを受け取るんだ!」と、だれかが上から(上段の板張りの寝床から)叫んだ。(榎本〔えのもと〕重男訳〔『ひとりで学べるドイツ語』に収録〕)
榎本訳ではこうなっていますが、この so を「そのままで」と解して、前の auch と結びつけて考え、「おれはそのままでも(つまり、手を洗わなくても)パンを取りに行くぞ!」と解する考え方もあります(小川超〔ちょう〕による教科書版の注釈)。
このあとを見ても、„Ich nehm das Brot auch so!“ と言った人がこう言ったあとでどうしたのかは書かれておらず、どちらが正しいかを判断する決め手はありません。
さらに言いますと、このセリフを「俺(おれ)はパンもこうして貰(もら)うからな。」としている邦訳も実はあるのですが、このように「パンも」とつなげると意味が通らないのではないかと、私は思います。
○Es war inzwischen viel heller geworden; klar stand auf der anderen Straßenseite ein Ausschnitt des gegenüberliegenden, endlosen, grauschwarzen Hauses – es war ein Krankenhaus – mit seinen hart die Front durchbrechenden regelmäßigen Fenstern; der Regen fiel noch nieder, aber nur mit großen, einzeln sichtbaren und förmlich auch einzelnweise auf die Erde hinuntergeworfenen Tropfen.
そのあいだに、あたりは前よりもずっと明るくなっていた。通りのむこう側には、向かい合って立っている限りなく長い黒灰色(こくかいしょく)の建物の一部分が、はっきりと見えていた――病院なのだ――。その建物の前面は規則正しく並んだ窓によってぽかりぽかりと孔(あな)をあけられていた。雨はまだ降っていたが、一つ一つ見わけることのできるほどの大きな雨粒で、地上に落ちるしずくも一つ一つはっきりと見えた。
mit seinen hart die Front durchbrechenden regelmäßigen Fensternの中のhartですが、邦訳ではこれを訳していないものが少なくありませんが、英訳ではわりあいきちんと訳しています。
「荒々しく」という感じでもよいかもしれませんが、あとの「規則正しい」と今一つ合わないような感じもしますので、建物の正面をくり抜いて規則正しく窓が作られている様子を、「冷厳に」という感じで表現したのではないかと、私は思います。
邦訳でこれを訳しているものについてだけ、どのように訳しているかを示しておきます。
... 、その正面には、きつくえぐられた窓の穴が、規則正しく並んでいた。(辻訳)
...――その建物の前面の壁がきちっとくりぬかれて、同じ窓がずらりと並んでいる。(高本訳)
... 、その前面の壁に非情な穴をうがちながら、一様な窓が規則正しく並んでいた。(高安訳)
... 、正面の壁を規則的な窓が冷たく穴を開けていた。(神品訳)
... 、前面の壁にはくっきりと切りとられた同じ形の窓が並んでいた。(川崎芳隆訳)
前の壁面をぐいとえぐった窓が規則正しく連なっていた。(川村訳)
... 、そのファサードには容赦なく打ちぬかれた窓が規則ただしくつづいていた。(三原訳)
... 、窓が厳(いかめ)しく張り出して整列していた。(多和田訳)
...――建物の正面にきっちりと規則的に開けられた窓がはっきりと見えた。(田中一郎訳)
英訳では、hartに該当する語だけを示しますと、abruptly、harshly、relentlessly、sharply、startlingly、starklyが使われており、harshlyとstarklyが比較的多いです。副詞ではなく形容詞の形にして、次のように訳しているものもあります。
...――with its hard, regular windows punched in the façade; ... (Underwood訳)
...――(本によっては[ダッシュではなくて]丸ガッコ) with its severe regular windows breaking up the facade. (Ian Johnston訳)
... with the austere and regular line of windows piercing its façade; ... (Wyllie訳)
...―with its severe windows regularly spaced across the front; ... (M. A. Roberts訳)
... , its grey-black façade pierced by rows of identical, stark windows. (Will Aaltonen訳)
...―with its severe evenly spaced windows cut into its front; ... (Daudert訳)
... , with its cold, featureless windows breaking through the exterior. (C. Wade Naney訳)
○Das Frühstücksgeschirr stand in überreicher Zahl auf dem Tisch, denn für den Vater war das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages, die er bei der Lektüre verschiedener Zeitungen stundenlang hinzog. Gerade an der gegenüberliegenden Wand hing eine Photographie Gregors aus seiner Militärzeit, die ihn als Leutnant darstellte, wie er, die Hand am Degen, sorglos lächelnd, Respekt für seine Haltung und Uniform verlangte.
テーブルの上には朝食用の食器がひどくたくさんのっていた。というのは、父親にとっては朝食は一日のいちばん大切な食事で、いろいろな新聞を読みながら何時間でも引き延ばすのだった。ちょうどまむかいの壁には、軍隊時代のグレゴールの写真がかかっている。中尉の服装をして、サーベルに手をかけ、のんきな微笑を浮かべながら、自分の姿勢と軍服とに対して見る者の敬意を要求しているようだ。
グレーゴルの写真についての描写は、訳によってかなり雰囲気が違っていますが、解釈が分かれる箇所ではありませんので、ここでは取り上げません。
ただ、「ちょうどまむかいの壁には」というのは、誰の向かい側なのでしょうか。実は私は最初、朝食のさいにすわっている父親の向かい側かなと思いました。グレーゴルやカフカの父親はとても強い人、という印象を強く持っていたためです。ですが、前後をよく読みますと、ここはやはり、グレーゴルの視点に立った描写が続いていますので、グレーゴルから見て向かい側と解するべきでしょうね。
邦訳では、誰の向かい側かを明記して訳したものは1つもありませんが、実は英訳では2つだけあり、これらの訳者はこのままではわかりにくいと判断したのではないかと、私は思います。
Right opposite Gregor on the wall ... (Willa & Edwin Muir訳)
On the wall in front of Gregorio ... (英語に問題が多いので『変身』の英訳リストには入れていませんが、某訳)
○Die Tür zum Vorzimmer war geöffnet, und man sah, da auch die Wohnungstür offen war, auf den Vorplatz der Wohnung hinaus und auf den Beginn der abwärts führenden Treppe.
玄関の間へ通じるドアは開いており、玄関のドアも開いているので、ドアの前のたたきと建物の下へ通じる階段の上のほうとが見えた。(原田訳)
玄関に通ずるドアが開いていて、玄関のドアもまた開いていたので、住居の前の踊り場や、下に通じている階段の降り口が見えた。(神品訳)
Vorzimmerの訳語に関しては、前回(第9回)の拙稿の、○»Haben Sie auch nur ein Wort verstanden?« 以下の文章を検討した箇所で、③として考察しています。グレーゴルの家の間取りに関する参考文献も、そこに記してあります。
「咬んだり刺したりするカフカの『変身』」9回目!月刊『みすず』4月号が刊行されました
まず、グレーゴルの家は、高層の集合住宅の上の階にあったことは確かであると思います。ここで階段という語が出てきていますし、もう少し先の方では、支配人がグレーゴルの姿を見て逃げ出すシーンがあり、支配人は階段を駆け下りています。また、第3部の終わりの方で、グレーゴルの家に下宿していた3人の男たちが家を退去するさいにも、階段を下りています。第3部の該当箇所では、
... ; an das Geländer gelehnt, sahen sie(グレーゴルの父母と妹) zu, wie die drei Herren zwar langsam, aber ständig die lange Treppe hinunterstiegen, in jedem Stockwerk in einer bestimmten Biegung des Treppenhauses verschwanden und nach ein paar Augenblicken wieder hervorkamen; ...
そして、三人がゆっくりとではあるが、しかししっかりとした足取りで長い階段を降りていき、一階ごとに階段部の一定の曲り角へくると姿が消え、そしてまたすぐに現われてくるのを、手すりにもたれてながめていた。(原田訳)
と書かれていますので、少なくとも4階以上ではないかと思われます。ちなみに、「グレーゴルの家=カフカ自身の家」というわけではありませんが、グレーゴルの家はカフカの家がモデルになっているようですし、カフカの家は5階にあったそうです(エルンスト・パーヴェル、伊藤勉訳『フランツ・カフカの生涯』、p.175)。
このことから、Vorplatzは、玄関のドアをあけてすぐの所にある、階段の降り口の前の少し広いスペースのことを言っているのではないかと、私は思います。邦訳では「踊り場」、英訳でもthe landingとしているものが非常に多いです。ただ、住居への入り口の前になるわけですから、純然たる意味(階段の途中に、方向転換・休息・危険防止のために設けた、やや広く平らな所〔大辞林〕)の踊り場と言ってよいのかなとも考えられないことはありませんが、ほかに適切な訳語は私も思いつきませんので、まあ妥当かなと思います。強いて言えば、「玄関の先のスペース」ということになるでしょうから、あっさり「玄関先」などとするのも1つの方法かもしれませんね。
なお、邦訳や英訳で、「前庭」とか「ポーチ」としているものもあります。ですが、この場合は庭があるはずはありませんし、「ポーチ」もちょっとと思います。ただ、この建物は今で言う高級マンションのような感じですから、玄関のドアの前に、ポーチに似たような装飾があった可能性も、ないとは言えないかもしれません。
また、原田訳のように「たたき」としている邦訳もありますが、たたきは玄関の中にありますから、玄関のドアもあいていたから見えたという記述とは、合わないのではないかと思います。
なお、Wohnungstürは、前に出ているdie Tür zum Vorzimmer([住まいの中から]玄関の間へ通じるドア)と同じ意味に使われることもあるようですが、ここでは前にこのように出ていますし、da auch(も) die Wohnungstür offen war と書かれていますので、ここではやはり、「玄関のドア」でよいと思います。
ドイツ語の体験話法に関しての補足:ドイツ語の体験話法における、接続法の時称の変化についてなど(「変身」の連載の第10回で取り扱われている範囲で)
岡上容士(おかのうえ・ひろし)
※ドイツ語の体験話法に関しては、次の題名の頭木さんのブログで詳しく説明しています。
「咬んだり刺したりするカフカの『変身』」6回目!月刊『みすず』8月号が刊行されました
※ドイツ語の接続法が使われている箇所を取り上げての説明になります。ですが、「ドイツ語の接続法とはどのようなものか」といったことから説明していますと非常に長くなりますし、ここのテーマからも外れてきます。ですから、ドイツ語の接続法に関してはご存知であることを前提とします。ご存知でない方でご興味がおありの方は、お手数ですが、ドイツ語の参考書などをご参照下さい。
※最初にドイツ語の原文をあげ、次に邦訳(青空文庫の原田義人〔よしと〕訳)をあげ、そのあとに必要に応じて原田訳以外の訳もあげ、さらにそのあとに説明を入れています。
※邦訳に出ている語の中で読みにくいと思われるものには、ルビを入れています。
※ご意見がおありでしたら、頭木さんを通じてご連絡いただけましたら幸いです。
第8回の「ドイツ語の体験話法に関しての補足」では、次のように記しました。ここにそのまま再録します。
上記のブログ(岡上注:今回のこの論述の冒頭にもリンク入りで記した、頭木さんのブログのことです)では、
接続法になっている動詞は、体験話法になっても変化しないのが普通です。
と2回ほど記しましたが、終わりの方の「○体験話法に関しての補足」では、
※既にお話ししたように、登場人物が思っている内容が接続法で言われている場合には、体験話法になってもそのままにされることが多いのですが、現在形の接続法が過去形の接続法に変えられることもあります。
とも記しました。
念のために、もう少し詳しく説明しておきますと、
地の文(小説の語り手の文章)が過去形で書かれていて、登場人物が思っている内容が現在形の接続法で言われている場合には、体験話法になっても地の文と合わせる形で過去形の接続法にはされずに、そのままにされることが多いのですが、中には過去形の接続法に変えられる場合もあります。
ということになろうかと思います。
また、現在形の接続法が、体験話法になったさいにそのままにされるか、過去形に変えられるかということに関しては、特に規則があるわけではありません。作者の好みによると言ってよいのではないかと思います。
今回の連載の第8回では、現在形の接続法が、体験話法になったことにより、過去形の接続法に変えられた例が出てきていますので、見てみることにしましょう。
以上のように記しましたが、少しだけ追記しておきますと、現在形の接続法が、体験話法になったさいにそのままにされるか、過去形に変えられるかということは、基本的には作者の好みによるのですが、中にはそれなりに理由があると考えられる場合もあります。
それで、今回の第10回でも、「現在形の接続法が、体験話法になったことにより、過去形の接続法に変えられた例」が(以下の(2)の方で)出てきていますので、第8回と同じように見てみることにしましょう。
(1)
Es schien leider, daß er keine eigentlichen Zähne hatte, –womit sollte er gleich den Schlüssel fassen? – aber dafür waren die Kiefer freilich sehr stark; ...
残念なことに、歯らしいものがないようだった――なんですぐ鍵をつかんだらいいのだろうか――。ところが、そのかわり顎(あご)はむろんひどく頑丈(がんじょう)で、...(原田義人〔よしと〕訳)
残念なことにはちゃんとした歯が彼にはないようであった。――では鍵を何ではさんだらよいのだろうか。無論歯の代りに顎が非常に強力であった。(神品〔こうしな〕友子訳)
残念ながら、本来の歯といえるようなものが彼にはないらしく――いったい何でもって鍵をつかめばよいというのか?――、しかしその代わりに、もちろん、顎が上下とも非常に頑丈だった。(浅井健二郎訳)
このwomit sollte er gleich den Schlüssel fassen? を、原田訳、神品訳、浅井訳などのように、体験話法とみなすか、地の文(小説の語り手の文章)とみなすかは、どちらでもよいと私は思います。特に、このように体験話法のような雰囲気を持った疑問文が、地の文の中に1つだけ入っている場合には、どちらと考えても、そのあたり全体の雰囲気に大きく影響するわけではありませんから。
ただ、この場合には、体験話法のような雰囲気が強いですから、どちらかと言えば、体験話法と解した方がよいかなとも思います。現に、邦訳の中でも、地の文のように訳しているものは2つしかありません。
それでも地の文とみなす場合には、このsollteは、ほかの地の文の時称(過去形)と同じですから、当然過去形になります。
体験話法とみなす場合には、グレーゴルが心の中で思ったこととして、直接話法で書いてみますと、
(a)womit soll ich gleich den Schlüssel fassen? …sollは現在形で、体験話法になったために地の文の時称に合わされて、過去形にされた。
(b)womit sollte ich gleich den Schlüssel fassen? …sollteは接続法第Ⅱ式で、体験話法になった場合、接続法では地の文が過去形であっても過去形にはされず、そのままにされることが多いので、ここでもそのままにされた。なお、この点に関しては、上記の「ドイツ語の体験話法に関しての補足」(第8回分)からの引用をご参照下さい。
これら(a)(b)のいずれとも考えられますが、グレーゴルが心の中でかなり深刻に思っているのでしたら、接続法にして疑いや迷いのニュアンスを出した方が雰囲気が出ますから、私は(b)を採りたいと思いますし、sollteが体験話法で出てくる場合には、一般的に接続法第Ⅱ式であることが多いようです。
付記:原田訳ではgleichを「すぐ」と訳していますが、このgleichはその意味ではなく、単に疑問文の意味を強める用法です。一部の辞書では、この用法ではdochを伴うように記されていますが、必ずしもその必要はなく、gleichだけでもこの用法は成り立ちます。
(2)
»Hören Sie nur«, sagte der Prokurist im Nebenzimmer, »er dreht den Schlüssel um.« Das war für Gregor eine große Aufmunterung; aber alle hätten ihm zurufen sollen, auch der Vater und die Mutter: ›Frisch, Gregor‹, hätten sie rufen sollen, ›immer nur heran, fest an das Schloß heran!‹
「さあ、あの音が聞こえませんか」と、隣室の支配人がいった。「鍵を廻(まわ)していますよ」
その言葉は、グレゴールにとっては大いに元気づけになった。だが、みんなが彼に声援してくれたっていいはずなのだ。父親も母親もそうだ。「グレゴール、しっかり。頑張って! 鍵にしっかりとつかまれよ」と、両親も叫んでくれたっていいはずだ。(原田訳)
「ほら、お聞きなさい」と隣室で支配人が言った、「鍵を回していますよ」 それはグレーゴルを大いに元気づける言葉だった。しかし、できるなら、みんながかれに声援を送ってほしかった。父と母にも「しっかり、グレーゴル、それ、こっちだ、鍵にしっかりつかまれ!」と大声で励ましてもらいたかった。(高本研一訳)
このaber alle hätten以下を、原田訳のように体験話法とみなして、現在のこととして訳している訳と、高本訳のように普通の文(地の文)とみなして、過去のこととして訳している訳とがあります。こちらでは(1)と違って、前者の訳と後者の訳が半々くらいになっています。私もかねがね言っていますように、体験話法らしい雰囲気の文が本当に体験話法か否かを判断する絶対的な決め手はありませんから、ここもどちらが正しいとは断定できません。しかしここの場合も、グレーゴルの現在の心の中の思いを言っていると考えた方が、生き生きとした感じが出るのではないかと私は思います。ですから、ここは体験話法であるとして、これからの話を進めて行きたいと思います。
それで、このaber alle hätten以下を、グレーゴルが心の中で思ったこととして、直接話法で書いてみますと、
aber alle sollten mir zurufen, auch der Vater und die Mutter: ›Frisch, Gregor‹, sollten sie rufen, ›immer nur heran, fest an das Schloß heran!
となりますね。sollenは過去形と接続法第Ⅱ式とが同形になりますから、表面的にはどちらか区別がつきませんが、やはりこれは過去のことではなく、現在の彼の心の中の思いを言っていると考えて、接続法第Ⅱ式と判断されうるのではないかと思います。
さてそれで、上記の直接話法を体験話法に直した場合、solltenは接続法第Ⅱ式ですから、過去形(hätten ... sollen)に変えたりせずにこのままにしておいても、グレーゴルの現在の心の中の思いを言っていると、読者には受け取ってもらえるのではないかとも思われます。
ですから、作者の好みで過去形に変えられたとも、言えないことはないかもしれません。ですが私は、次のように推測しました。
この文は、体験話法で多く登場する疑問文や感嘆文ではありませんし、体験話法と判断できるような明確な語句もなく、(1)の文などと比べると、体験話法とは判断しにくいですね――日本での話ではありますが、(1)と(2)の邦訳の状況を見ても、それは言えると思います――。従って、solltenのままにしておきますと、ネイティブであっても、普通の過去形と混同する可能性が、ゼロではないかもしれません。ですから、この原文のように接続法の過去形(hätten ... sollen)にして、「これは体験話法であり、グレーゴルのもともとの思いは接続法の現在形(sollten)で表現されている」ということを、明確にしたのではないでしょうか。
付記:動詞で過去形と接続法第Ⅱ式が同形の場合には、接続法第Ⅱ式を「würde(werdenの接続法第Ⅱ式)+不定詞(動詞の原形)」で代用して書くこともありますが、sollenなどの話法の助動詞をこのような形で書いた例は、私は見たことがなく、このようにはあまり書かれないのではないかと思います。ですが、もしもこのように書かれた例をご存知の方がおられましたら、ご教示いただけましたら幸いです。
———————————————————————
他に、このようなリストもアップしています。