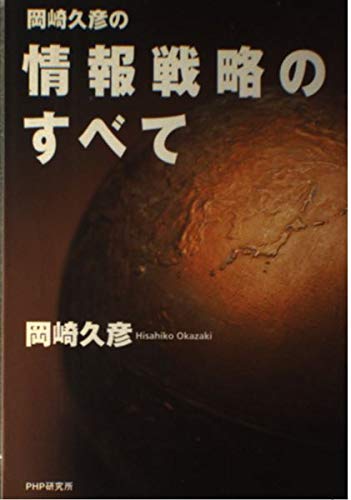◆村野将『米中戦争を阻止せよ』を読み解く
副題→「トランプの参謀たちの暗闘」
★要旨
・日米の戦略を論じるにあたり、岡崎久彦大使は、無視することができない存在である。
・筆者は、岡崎大使から直接教えを乞うことができた最後の世代であり、2014年に大使が亡くなるまでの8年間、ほぼ毎日のように情勢分析についてやりとりする機会に恵まれた。
・これは筆者にとってかけがえのない財産となっている。
・情報の分析や戦略を論じる上で岡崎大使から教わったことはたくさんある。
・情報分析の仕事を手伝うようになって最初に言われたのが、
「あなたは日々のストレートニュースは追わなくていい。
それはプロの記者やメディアの仕事だ。
僕らの仕事は、専門家が書いた論説や論文を読み込んで、それに対する自分の考えをまとめることだから」
ということだった。
・単なる情報ではなく、政策判断に資する情報であるためには、そこに何らかの思索が加わっていなければならない。
・そしてそれらの思索や論文に対して、その都度自分なりの肯定的意見や批判を加えていくことで、初めていざということきの判断に役立つ材料になる、
という趣旨だった。
・振り返れば、岡崎大使に促されて始めた思索の繰り返しが、筆者にとって米国の戦略コミュニティへの最初の入り口だったように思う。
・一方的な質疑応答と双方向の意見交換とでは、議論の深まり方に雲泥の差がある。
・こちらも当事者意識を持って自分の考えをぶつけると、彼らはまだ結論に辿り着いていない生煮えの問いを返してくれることがある。
これが、日米が直面している政策課題をどう解決していくかという共同作業の出発点となる。
★コメント
研ぎ澄まされた村野氏の文章に、学ぶ点が多すぎる。熟読したい。