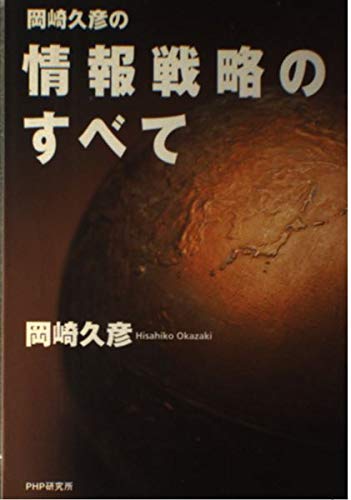◆岡崎久彦『情報戦略のすべて』を読み解く
★要旨
・私は戦略論を論じてきたが、煎じ詰めればそれは情報論である。
何か問題があって解決しようと思ったとき、問題点が全て見えて、
整理されていれば、それを解決する方策は、おのずから道筋が見えてくる。
それが私の戦略論だ。
・情報の処理は、まず収集、ついで整理分析、最後に伝達で終わる。
真っ先に申し上げたいことは、情報事務の基本は、
公開情報の分析能力にあるということ。
・情勢判断において、専門家の意見を尊重すべし。
専門家というのは、特定の地域なら地域について、土地勘もあり、
入手可能なあらゆる事実と過去の経緯を知っている人たちである。
・土地勘のある専門家というのは貴重なもの。
一つの国について入手できるあらゆる刊行物を読み、
過去数年の出来事の日誌が頭に入っていると、おのずから、
情勢の流れの中に目に見えない筋が見えてくるもの。
このことは専門家だけでなく、情報事務の管理者にとっても同じで、
部下の作った要領だけに頼ることなく、なるべく多くの原典を読んで、
その紙背に徹することが大切。
・文化革命を予言し、ソ連のチェコ侵入を予言したヴィクター・ゾルザは、
決して秘密の情報は読まず、共産圏の公開資料を1日9時間読んでいました。
ですから旅行すると失われた時間を取り戻すのが大変だと言って、
ほとんど旅行もせず、今までに本を1冊も書いていない。
・国際情勢は「一寸先は闇」ということを何時も忘れないこと。
・歴史的ビジョンを持て。
国際政治の原則には千古不易のものがあるという
しっかりとした歴史観を持っていることが必要だ。
「人間が人間であり、国家が国家である以上」孫子やマキャベリの言った真理は、
現在でも適用される。
・各情報機構のセクショナリズムに捉われない、
真に国家的な観点から取り上げられ、分析された情報こそが、
政策判断に必要な情報である。
要は情報の多様化を認める寛大さ、柔軟さと、
情報機関の間におけるフェア・プレイの精神を確立すること。
★コメント
大局観や歴史観は、情報マンにとって欠かせない。
現在におけるビジネスや社内外の関係において、歴史の教訓は応用できる。
ビジネスにおける根回し、調整、後方支援は、
偉人たちのうまいやり方を真似できる。
★