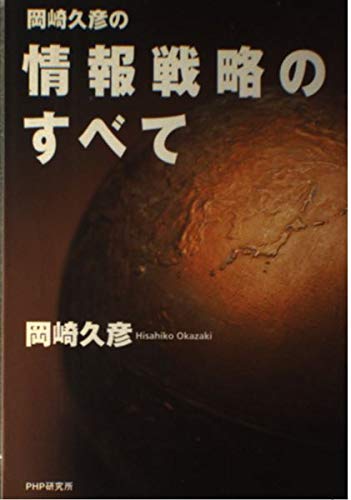◆宮崎伸治『50歳から8か国語を身につけた翻訳家の独学法』を読む
★要旨
・外国語が上達するコツは「長く続ける」がすべて。
・「やりたい」という気持ちが続けば、学習を続けられます。
・長続きできるか否かは自ら「やりたい」と
思えるよう自分を動機づけられるか否かにかかっているのです。
・上達するには「楽しい」だけでは乗り越えられない壁があるからです。
・行きづまったら助けを借りる。
「楽しいから」で長続きできれば一番理想的ですが、難易度の高いスキルが得られるまでの道のりは辛く長いものです。
・途中で投げ出したくなったら、英会話スクールなどの門を叩くのもいいでしょう。
自分に合った先生に巡り会えれば、学習意欲がかきたてられます。
・高齢になってから語学学習をゼロから始めて、中級レベルに達すれば、
頭が良くなる、新しいビジネスチャンスが開けてくるなど、素晴らしい可能性が開けてくる。
・40代の10年間で大学の学位を5つ取得したので、
相当な勉強家のように思われることもありますが、
中年ニートになることから逃れるために大学に籍を置いていたというのが実情でした。
・大学生活を送っていたある日、人生を変える出来事が起きました。
図書館に籠こもってロンドン大学の指定図書にのめり込んでいると、感電するかのような衝撃を受けたのです。
↓
「外国語の本が読めるってすごいことだ。
19世紀に地球の裏側に住んでいた人が書いた本でも、ダイレクトに理解できる。
つまり外国語が読めれば、時空を超えることができる」
・フランス語もイタリア語もスペイン語も中国語も韓国語もロシア語もまったくのゼロからスタートでした。
・その私を根底から支えた信念は、
「外国語の書籍は語彙力を徹底的に磨けば読めるようになる。
外国語が読めれば、過去に生きていた海外の偉人たちとも対話ができる」
でした。
・50歳から独学で学習を開始しても驚くほど可能性が開ける。
・自信をもって言えるのは、
「50歳から独学で学習を開始しても、中級レベルに到達できる」
ということです。
・そして中級レベルに達すれば、驚くほど素晴らしい可能性が開けてきます。
・学ぶ楽しさは「中級レベル」から急増する。
★コメント
やはり、学びにゴールはない。
今日から始めよう。