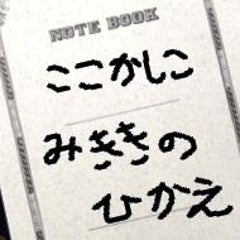さて、大阪の旅のお話も終盤でありますが、ここでまたひとつの(個人的)ハイライトなのでありますよ。
もとよりこの旅は、小説「金剛の塔」を読んで四天王寺五重塔を、
ドキュメンタリー映画「太陽の塔」を見て万博記念公園・太陽の塔を訪ねようと思い立ったことに始まったわけで。
ということでいよいよ太陽の塔と対面するために大阪メトロ谷町線から大阪モノレールを乗り継いで
万博記念公園駅に到着。すると、実に何とも唐突に立ち上がっている太陽の塔に直面してしまうのでありました。
なんとまあ、惜しげもなくといいますか…。
1970年、東京から大阪までは7時間半も掛かることはなくなっていて、
東海道新幹線0系電車で東京・新大阪間は3時間10分で結ばれていました。
それでも、今から思えば大阪は遠い遠い場所であって、
少年少女向け雑誌などの特集で取り上げられた万国博会場には
数々の個性的な建物が建ち並ぶさまが紹介され、それはそれは眩しく思えたものでありました。
それからおよそ50年の時を経て目の当たりにした太陽の塔は、
お祭り広場の大屋根を貫いて立つ姿ではなく、むしろ孤高といった雰囲気を醸している。
反って、岡本太郎が意識したかもしれない古代の祭祀のシンボルでもあるかと見えたものでありますよ。
ゆるやかな坂道を登り、塔の直下から見上げるとこんな感じでありますよ。
太陽の塔には四つの顔があると言われますが、そのうちで外側についている3つの顔の違いを見比べて
あれこれ思いを馳せるもの一興かと。
でもって、第4の顔というのが塔内地下空間にあったそうなのですが、万博閉幕後行方が知れないと。
こんなことでも神秘性を感じさせるといいますか。2018年3月から改めて塔内の公開が始まったときに、
復元された第4の顔も再登場したということなのですなあ。
ということで、予約をしてあった塔内見学へと歩を進めることにいたします。
入口は地下に設けらえておりますが、そこから上へ上へと向かう流れは万博での公開時からそうだったわけで、
やはりコンセプトはそのままにということでありましょう。受付を済ませて奥へ進むと、やおらこのような空間が。
いかにも岡本太郎好みの感じがするプリミティブアート的なるものがたくさん。
50年前はこれほどにライティングがシャープになされなかったでしょうから、
もしかすると、もそっと呪術っぽさが感じられたかもしれませんですねえ。
と、この並びの先に現れるのが、「地底の太陽」とか「太古の太陽」とか呼ばれる、復元された第四の顔でして。
この無表情に(些かとぼけたふうにも)見える第四の顔には、プロジェクションマッピングで表情に変化がありまして、
ときにこんな凶悪な一面も覗かせたりするという。冷静に考えるとヒトにもいろんな面があるのと同様に…?。
かような「第四の顔」のある空間を抜けますと、塔本体の底部に到着するのですね。
なにやら昔のSF映画に出てくる宇宙人の住まいとか、そんな印象がありますですねえ。
塔の内部を上へ上へと伸びる「生命の樹」の根っこにあたる部分ですので、
ここにいるのは原生的なる生き物ということでありましょう。「生命の樹」を見上げると、
生き物の進化(個人的にはこれを適応を呼びたい気がしているとは前にもいいましたですが)の過程が
表現されているということに。
ここでは低層階部分しか見えませんので、生き物はいまだ海の中から出ていない状態ですけれど、
外壁沿いに取り付けられた螺旋階段を上っていくにつれ、恐竜や哺乳類もやがて出現してきます。
が、高低差のある吹き抜け空間だけに、ものを落としたら一大事とということで、
階段の登り口でカメラをかばんにしまわないといけない規則になっておりましたよ。
途中に出てくる恐竜やゴリラは実物大とはいいませんが、それなりの大きさで樹上に取り付けられていますが、
(ゴリラは電動で動くようになっていたらしいですが、今は外皮が剥げてメカコングのようになってました…)
進化の果てにある人類がなんと小さな姿で置かれてあることか。
大きさがすべてならば恐竜はさぞかしエラいてなことになりますから、大きさばかりで云々はできませんが、
敢えて小さな姿で表されたことには思い至すべきところでありましょうねえ。
70年万博のテーマは「人類の進歩と調和」でしたけれど、
一定の達成をベースにこの先には明るい未来があるてな像はとても描きにくい時代でもあったのでは。
物事を良い方へ見たいということは誰しもあるにせよ、国が旗を振って皆に思い込ませようとする未来像の傍らで、
というより実際にはその真ん中で、岡本太郎はやはりアンチテーゼを込めたとしか思えませんですよね。
そう考えると「太陽の塔」は、1970年に万博という大きなイベントがありましたということのモニュメントではなくして、
そうしたことがあったことも歴史の部分としてもっともっと長い歴史の中で考えてみることを促す芸術作品として、
その存在意義があるてなふうにも思ったりしたものでありますよ。