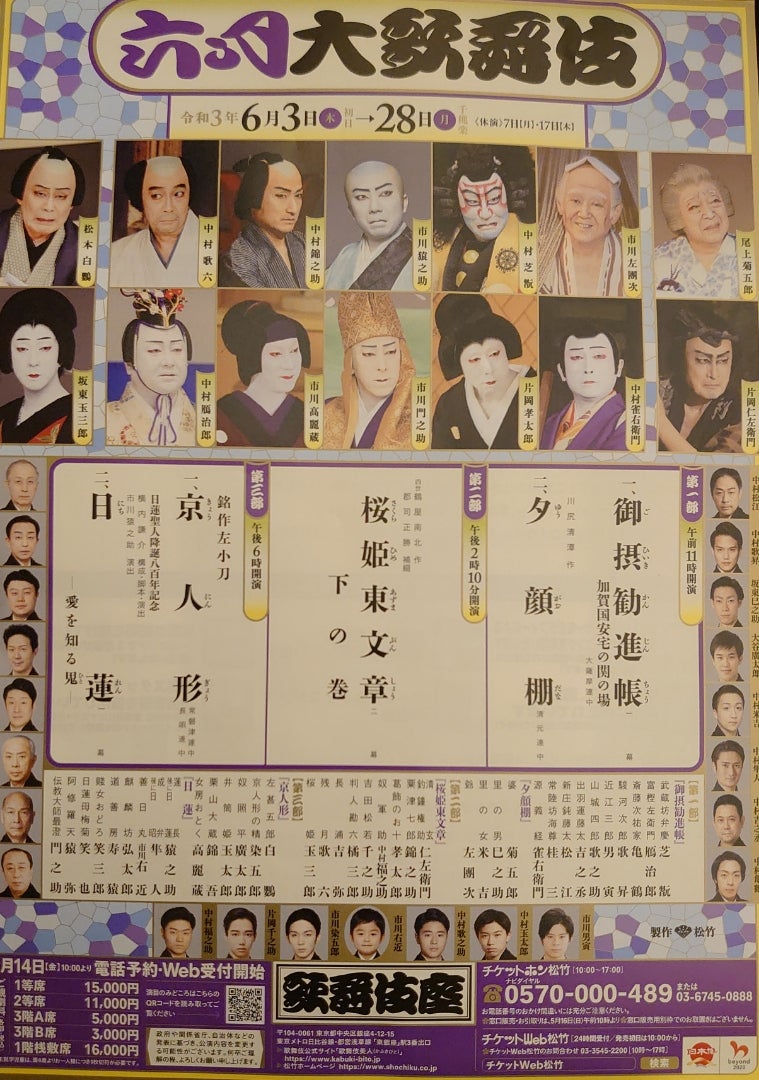今回は本来なら大正8年9月の帝国劇場の筋書を紹介する予定でしたが少し前に関連する珍しい筋書が手に入りましたので先にこちらを紹介したいと思います。
※注:今回の筋書に出て来る役者名は当時名乗っていた名跡で記しますのでご注意ください。
明治37年4月 歌舞伎座
演目:
一、桜の御所
二、日蓮聖人辻説法
三、艦隊誉夜襲
久しぶりとなる明治時代の歌舞伎座の筋書です。
今回紹介する明治37年と言うとずっと以前に紹介した九代目團十郎の最後の公演の直後であり、芝翫(歌右衛門)が座頭になるまでの過渡期に当たります。
参考までに前年の團十郎最後の公演の筋書
同じく明治37年6月の明治座の筋書
一番目の桜の御所は小説家の村井弦斎が明治27年に書いた小説を福地桜痴が手を入れて歌舞伎化した新作物となります。
数多ある歌舞伎の演目の中でも珍しい部類に入りますが、それもその筈で近世劇壇史 歌舞伎座編によると元々歌舞伎座は竹柴其水に脚本を依頼していました。しかし、其水は当時明治座専属の立作者であり明治座の座頭である初代左團次から
「明治座の立作者ともあらう者が他座の脚本を書くと云ふ法はない」
と許可が降りなかった為にボツとなり、困った福地が生前の九代目團十郎が村井弦斎について
「此の人の書いた物は、猥らな事がなく、而して筋立ても面白く、真面目な物だから、きっと芝居になる」
と言っていた事を思いだし当時売れていたこの作品に目を付けて劇化したそうです。
内容としては今放映中の大河ドラマの「鎌倉殿の13人」にも出てくる鎌倉時代に勢力を誇った相模の豪族三浦家の子孫である相模三浦氏が永正13年に伊勢宗瑞に攻め滅ぼされた時の事をテーマに羽左衛門演じる三浦義意と梅幸演じる小桜姫との絡みを入れて描いた物です。
今回は楽岩寺種久を八百蔵、三浦義意を羽左衛門、小桜姫を梅幸、三浦道寸を松助、初声行重を菊五郎、郎党團六を吉右衛門、郎党市橋雷太を八十助、北条早雲を市蔵、牧の方と大膳妻浅茅を源之助がそれぞれ務めています。
さて、劇評ではどうだったかと言うとまず演目そのものについては
「背景として使った宝蔵山尉ヶ島千段櫓などの地名が、已に当時の歴史を忍ばせる便宜を与へて居るし、三浦道寸が理由なき野心を起した為に隣国の楽岩寺と怨を結び、梟雄なる北条早雲に其隙を乗ぜられる顛末は史劇には格好の材料なのだ。原作者が楽岩寺の娘に小桜姫なるものを設けて、これが以上の衝突に依って、意中の人たる荒次郎と添うことならずに死する事したのも面白い」
と劇評でも歌舞伎演目の原作としては十分面白い物であると評価していますが、一方でいざ歌舞伎化してみたら
「只それを悲劇的に組立てる運びにタルミがあるのは、新聞の続物として書いた小説だからでもあらう。」
「総体に充分に作劇の力のある人が、此材料を使って新に仕組み直したら、初めて引締まった好いものが出来やうと思った。」
とも書いていて新聞小説故に展開が間伸びしてしまい今一つ面白くないという欠点を指摘しています。
続いて役者の方の出来はどうだったかと言うとまず東京座の芝翫との競演になり今回の役作りの為に薙刀の稽古までしたという小桜姫を演じた梅幸は
「梅幸の小桜姫、以前の緋の袿の裾を壷折、黒の塗笠を冠り長刀抱へての出は趣味のある筈ですが…笠を取ってからは花櫛がないので年増に成りました。(中略)夫柄(それから)稽古まで仕て居る長刀ですから見得の時の持方は法通りかも知れませんが、余り柄の下の方を持って居るの丈は損な格好でした。荒次郎との立廻りの時は車輪過ぎて白粉の附て居ない二の腕が現れるのは困り升。」
「長刀の使方は熱心に稽古した丈あって大出来。魔神と見て袿の右の肩を脱ぎ、荒次郎と聞いてこの肩を入れて跪く手順、「あれ御覧せう」と路を指示される時、長刀の石突で藪畳を割って向を見る科も好い。併し肝心の「何しに人に語らうぞ」と色気を含んでいふべき白廻しは何としても褒め兼た。」
と薙刀を使っての演技は高評価されている一方で羽左衛門との立廻りでは大車輪の余り思わぬミスをしたり、経験不足が祟ったのか演技部分での未熟さが露呈したらしく高評価であった芝翫に比べて功罪半々の評価となっています。
梅幸の小桜姫
それに対して小桜姫の恋の相手であり、物語の実質的な主人公でもある三浦荒次郎を演じた羽左衛門は
「羽左衛門の荒次郎、立廻りは姫に負けさうで危険でしたが、引抜いてからは、紺蒼濃の直垂が青電気との配合で一層引立って見受けられ、科白も落付が充分で好う御座いました。」
「「荒次郎義意で御座る」で面を取って上手へ眼使をした顔立、直垂に変って刀を杖いて腰を掛けた形、「御身の一命申し受けるぞ」で刀を脇挿んだ横向の形、姫の「楽き事候ぞや」の詞を受けて、首を僅に上手へ廻す思入れ、山へ上って刀を突いて奥を見込んだ形、幕切に別を惜しんで上手を向く思入など、角々の形や思入れで場を持って居る腕は豪いものだ。(中略)高麗蔵も團十郎を鵜呑みに市内で、この人の様に気組を飲込んだら好かったらうに。」
とこちらは同じ役を東京座で演じている高麗蔵とも雲泥の差で勝り、羽左衛門襲名からメキメキ腕を上げている様子が伺えます。
その一方で世話物にかけては右に出る人がいないと定評があり今回は三浦道寸を演じた松助はというと
「松助の三浦入道道寸、羽織が鼠色の質素な織物の為如何にも安っぽい上に、白廻しが空々しくその人に成って居ません。」
「坊主鬘に胡麻塩の頬髭を附けた押出は悪くはないが、白廻が世話物式なので活歴物に映らぬのが何よりの損荒次郎の諫を表面上容れる處で思入れ皆無なのは気なしといはれてもよんどころあるまい。」
と流石の松助も活歴物との相性は最悪だったらしく、かなりの不評で音羽屋の3人は明暗を分ける形となりました。
また5年ぶりに出演し牧の方と大膳妻浅茅をを演じた源之助もまた
「源之助の牧の方、綺の着付に白茶地織物の襠が不似合なのと白廻しが時代過ぎるのとも一つは栄えぬ損な役にも因りますが、好いとは思ひませんでした。幕切の「アゝ、我子は可愛い者ぢゃなあ」と脇息に凭れる處も、この座では些とお芝居過ぎる感じが致しました。」
とこれまでのんびり小芝居で得意な芸を堪能していたのに比べ團十郎の肚芸志向に染まった役者ばかりの歌舞伎座では浮いた存在になってしまっていたのと慣れない活歴物に苦戦したらしくこちらも不評で折角の歌舞伎座出演でも花を飾れず、大正3年末まで再び小芝居に戻り活動する事になります。
この様に羽左衛門の荒次郎を除いては何れも厳しい評価が目立ち今一つの結果に終わりました。
余談ですが、この演目は歌舞伎座が始まる1週間前に小芝居の宮戸座で初代澤村宗之助の小桜姫で上演され僅かながら歌舞伎座との競演になった他、上述の様に4月21日からはライバルの東京座でも芝翫の小桜姫で上演が始まりこちらも歌舞伎座との競演になりました。
宮戸座の方は残念ながら持っていませんが偶然にも東京座の方の筋書は持っていますので帝国劇場の筋書の後に紹介したいと思います。
艦隊誉夜襲は福地桜痴が新たに書いた活歴の新作で外題からも分かる様にこの年の2月に開戦したばかりの日露戦争に当て込んだ戦争芝居となります。尤も内容としては始まったばかりの日露戦争を直接描くわけには行かず幕末の文久元年2~4月に対馬で起こったロシア帝国海軍による不法占領事件を元ネタに島で被害に遭った島民の子孫が海軍佐官になり当時の船長と戦闘の末に撃沈させ仇討に成功するという強引な仇討物に仕立て上げました。
今回は松村剛毅を八百蔵、市橋海軍中尉を羽左衛門、寺口少尉候補生を菊五郎、浜田海軍大尉と後藤一等兵曹を吉右衛門、松本海軍大尉を八十助、荒郷司令長官を市蔵、松村夫人節子を源之助がそれぞれ務めています。
さて、この荒唐無稽な演目に対しては劇評も容赦がなく
「作者も作者なればそれをいふ役者も役者である」
「訳の分からぬ際物」
と既に日清戦争の戦争劇で新派に敗北し現代劇の限界を知ったにも関わらずまたもや同じ愚を犯した福地を含めて酷評されました。
この様に一番目は当時ライバルであった東京座との競演で話題こそ読んだもののそれ以上の物が無く、中幕は内容こそ優れているものの僅か一幕と余りに短すぎて呼び物には難しく、大切に至っては論外の際物呼ばわりされる愚作と全て新作で揃えた事が仇となり東京座に競り負けてしまい更には東京座の筋書でも触れた様に当時は日露戦争開始直後で呑気に芝居見物という悠長な状況でない世相も追い打ちを掛けてしまい不入りとなりました。
既に團菊の生前から入りに陰りが見えて来た所に井上の大胆な改革が裏目に出てのこの失敗はかなり大きかったらしく、歌舞伎座では出演する役者の給金を固定制では無く収入に応じた歩合制に変えざるを得なくなるなど早くも混乱の兆しが見えていました。
この混乱が暫く続いた事で以前紹介した芝翫の復帰へと話が繋がっていく事となります。