☆毎日更新中
昨日 は、
全く聞かされていなかった遭難者救助の仕事に、
急きょ行くことになった
というところまでお話ししました。
肩にはタンカを担ぎ、
救急道具が入った大型のウエストポーチを腰につけます。
そして、
登山者数を数える市のバイトのお兄さん4名に私を加えた、
5名の救助隊が出発。
僕の相方のN君はお留守番です。
現場は、下山道の緊急避難所(標高2900m)。
下山道は登るのには適していないので、
登山道から登って途中で下山道に移ることに。
最初から、猛烈なスピードで歩き始めます。
「ウソだろ・・・」
救助だから当然と言えば当然ですが、
本当に速いのです。
普通のバイトのお兄さん達かとばかり思っていたので、
「この人たちは一体何者なんだ?」
驚きを隠せませんでした。
肩に担いだ10キロ以上はありそうなタンカがずっしりと重く、
必死についていきます。
さすがにタンカを運ぶのは、
市のバイトのお兄さんが交代でやってくれましたが、
酸欠になりそうなくらいのペースで登り続けます。
そして、
あっという間に、
七合目(標高2700m)に到着。
ここまで、
六合目(標高2400m)からわずか20分ちょっと。
コースタイムだと1時間の区間です。
その後も登山者の間を縫うようにして登り続け、
まもなく標高2900m付近に到達。
ここから無理やり道なき道を通り、下山道に合流します。
あたりはもちろん真っ暗。
そこは道になっていない斜面で、
滑落や落石の危険をかなり感じました。
「救助に来たけど、むしろこっちの命の方が危ない」
という状態。
そして、
なんとか下山道に合流し、緊急避難所に到着。
緊急避難所といっても、
畳三畳ほどの広さの単なる板張りのスペースです。
(無人です。今はもう取り壊されていてありません。)
中には、
中年の女性が横たわっていました。
命に関わるケガではありませんが、
ひどいネンザをしている模様。
持ってきたタンカに女性を乗せ、
4人で肩に担ぎます。
本当に大変なのはここからでした。
真っ暗な下山道を、
足元のでっぱりなどに気をつけながら、
下らなければならないのです。
足元が非常に不安定なので、
5人のうち1人はライトで先頭の人の足元を照らし、
疲れた人が交代し、ライト役になります。
タンカで運ぶというのは、
思ってたよりずっとやっかいでした。
タンカの重さと女性の重さを合わせて60キロくらいだとすると、
4人で運べば1人にかかる重さはせいぜい15キロくらい。
普段の登山では30kg前後のザックを担ぐこともありますので、
それに比べれば大した重さではありません。
しかし、
ザックの場合は、
肩はもちろん背中や腰など上半身全体に重さを分散して担げるのですが、、
タンカというのは、
片方の肩だけに全ての重さがかかるのです。
背中や腰などに重さを分散できないのです。
感覚的には、
60キロくらいの重さに感じました。
もう、肩が痛くて、
5分くらいしか担いでいられないのです。
おまけに、
片方の肩だけに重さがかかるので、
バランスがすごく悪くなります。
ネンザの人を運んでいたわけですが、
「こっちはネンザどころか、骨を折ってもおかしくない」
というほど、全く気の抜けない状態。
5分担いでは降ろし、2・3分休んではまた担ぐ
ひたすらこれを繰り返し、
下へ下へと遭難者を運んでいきます。
ようやく六合目安全指導センターに着く頃には、
すでに出発から2時間以上が経過。
ここまでは車が来るので、
あとは車で病院まで連れていきます。
時刻は22時過ぎ。
朝5時過ぎに麓を車で出発して以来、
すでに17時間以上が経過。
もはや、
どうにもならないくらい疲れていました。
約2時間、全力を出しっぱなしです。
昼間の7時間の富士山巡回よりも、全然きつい
と思いました。
「もう、残った力はどこにもない」
という状態だった私に、
さらなる試練が待っていたのです。
続きは明日 です。
※これは13年前の話であり、現在の安全指導センターや富士山レンジャーとは運営主体も業務も異なり、何の関係もありません。
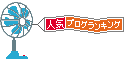
人気ブログランキングへ


