☆毎日更新中
それでは昨日 の続きです。
本八合目(標高3400m)からは登山道を外れ、
下山道に移ります (富士山は登山道と下山道が分かれています)。
この道を通れば、登山道の途中から下山道に移れます
下山道に入ると私の相方のN君のペースはさらに遅くなり、
前任のレンジャーG君が付き添って、
私と前任のレンジャーH君は、先に下ることに。
というのも、
下山道の7合目(標高2700m)付近には県が管理するトイレがあり、
ここの清掃と点検という重要な仕事があるからです。

現在の富士山吉田口下山道の七合目公衆トイレ(改修されてきれいになっています)
一足先に7合目のトイレに着いた私は、
H君に仕事を教わります。
まずは、トイレ内の清掃。
ご存知の方もいると思いますが、
富士山の五合目より上ではほとんど水が使えません。
川や湧き水がないからです。
そのため、
雨水を貯めて少しずつ使うしかないのです。
トイレの清掃をする時にも、貯めた雨水を使います。
すぐ近くに雨水を貯めるマンホールがあり、
このフタを空けて水をくむのですが、
このフタが恐ろしく重い。
「鉛でできてるのか?」
というくらい、ムダに重い。
しかも、
このマンホールがトイレの真ん前にあるので、
大勢の登山者が見ている前で、フタをこじ開けるわけです。
つまり、
できるだけ涼しい顔を保ちつつ、
フルパワーを発揮してマンホールのフタを横にずらす
という荒行をしなくてはならないのです。
これが、調子が悪いとなかなか持ち上がらない。
「フンッ![]() フンッ
フンッ![]() 」
」
と心の中で叫びつつ、
表面上はあくまで富士山レンジャーとして平静を装うわけなのですが、
持ち上がらないとものすごく恥ずかしい。
これから毎日、このトイレが近づくと、
「今日はマンホール持ち上がるかなあ・・・」
というムダな心配をすることになります。
いや、結局は持ち上がるまでやるしかないのですがw
ともかく、マンホールを持ち上げてずらしたら、
ヒモのついたバケツを下に落とす
という、原始時代のような手法で水をくみます。
これでようやく、トイレの掃除ができるわけです。
まず、
床に水を流して、ほうきで泥やゴミを掃きだします。
そして、
便器を一つ一つきれいに洗い、
使用済みトイレットペーパーを回収して持ち帰ります。
富士山では、トイレットペーパーは便器に流さず、
備え付けの箱か袋に入れるようになっています。
これで終わりではありません。
実は、ここのトイレは「乾燥トイレ」といって、
汚物を熱で処理する特殊なトイレ。
(今は、処理方法は違うかもしれません)
トイレの横に機械室があり、
発電機で動かしているのですが、
これが本当によく故障するのです。
機械が故障すると、
トイレに水が流れなくなります。
そうなると、
便器に汚物がたまり、
目を覆うばかりの惨状に。
高山なので、いちいち業者を呼ぶわけにはいきません。
ですので、
ちょっとした故障は自分で直さないといけないのです。
直すといっても、
機械を再起動させたりするくらいなのですが、
これがけっこう怖い。
不気味な音を立てるのです。
ビーッ、ビーッ、ビーッ
シュー・・・・・
「まさか爆発しないだろうな・・・」
機械室の中はとても暑く、
汗だくになりながらの作業になります。
無事直ったら、
あとは全く意味のわからない機械の数値を記録し、
それからトイレのチップを回収して、ようやく終わりです。
短くても30分、長ければ1時間以上かかります。
そして、
トイレの掃除が終わる頃、
N君が遅れて到着。
このパターンは最終日まで続くことになります。
ここまで、
六合目の安全指導センターを出発してから5時間以上が経過。
1日の富士山レンジャーの仕事は、
これでようやく折り返しといったところ。
夜には、想像もしていなかった恐ろしい仕事が待っていたのです。
続きは明日 です。
※これは13年前の話であり、現在の安全指導センターや富士山レンジャーとは運営主体も業務も異なり、何の関係もありません。
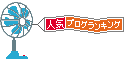
人気ブログランキングへ
