積読
最近はどうも「積読」が通じなくなりつつあるようで悲しいんですが。
最近行ってなかった古本屋に久々に行った。買い物ついでに。で、真っ先に行くのは当然100円コーナー。ついつい何冊も買ってしまうんですが、今回買ったもの(のうち、興味深いもの)はこれ。
・『右脳教育で子どもは変わる』七田眞
・『マイナスイオン療法の凄い効果を検証』師岡孝次
・『なぜそれは起こるのか』喰代栄一
七田はなんとかせなあかんと思って色々買い集めてるんですが、ざっと目を通す度に実にバカバカしくって逆になかなか読めない。いや、これが実際に行われてると想像すると、実に恐ろしいんですが、書いてあることは滅茶苦茶だし到底理論とは言えないレベルなので。典型的な議論の展開の仕方は、「AはBなのです。なぜならCだからです」というパターン。で、「AはB」というのがまず無茶苦茶で、例えば「イメージには予知力があります」とかイキナリ断言する。この本はずっとそういうのが書いてあるみたいで、後半になって「右脳は四次元的感覚を持ち、意識ではキャッチできない宇宙の全ての情報(波動情報)をキャッチする超高感度の受信機として働きます」なんて感じで「論証」しちゃう。
どの本もこんな感じみたいなんで苦痛なんですが、それでも如何にトンデモかというのをわかりやすく示せるような文章を探してまた買ってしまうんですよねえ。100円だし。
師岡さんという人は初めて見る名前なんですが、パラパラと見たら最初にどうも「マイナスイオン」批判が書いてあるようなので、ついつい買ってしまった。第一章のタイトルが「間違いだらけのマイナスイオン・ブーム」で、節を見ると「大流行のマイナスイオンはウソかマコトか」「マイナスイオン効果に異論続出」「空気マイナスイオンと活性マイナスイオンは違う」「マイナスイオン効果が一人歩きをしている」「空気マイナスイオン実験を実現する」「従来の交流式電位治療器にマイナスイオン効果はあるか」と来るわけです。しかもざっと眺めてみると、長年マイナスイオンの批判をされている安井至さんの発言を肯定的に引用したりもしている。
で、その上でですよ。第2章第1節のタイトルが、「宇宙医学から誕生したタカタイオン療法」で、最初のページを見ると、1938年に太陽に起源を持つ放射線、名づけて「太陽第四線」、というような記述が出てきて、これあ読まねば、とムラムラと来てしまったわけですね。
これ、2003年の本なので、もうマイナスイオンに対する差別化戦略が始まっていたってことですかね。そういう意味でもちょっと興味深い。
最後の喰代さんのやつなんですが、副題に「過去に共鳴する現在 シェルドレイクの仮説をめぐって」とあるとおり、そっち系(ってどっちだ^^;; 共鳴系というか100匹目の猿系というか)のシンクロニシティー本。サンマークで、帯に「船井幸雄氏も絶賛した驚愕の書」とあるとおり、この人の名前は船井の本には時々出てくるので知っていて、それで見つけて買ったわけです。
あ、巻頭にシェルドレイクの写真もデッカク載ってます。ってどうでもいいか。
この人とか、あとちょっと前に買ってこれもまた読んでないんですが飯田史彦(『生きがいの研究』とか)とか、現代資本主義をオカルト的に支える理論づくりをしている面があるように見えるので、一度きっちり見ておかないとな、とは思っているんですが、それだけに彼らの主張の本質を理解するのが一筋縄では行かなくて、ついつい後回しにしてしまうんですよねえ。
『シンクロニシティー』なんか読むのが実につらくて。物理用語がバンバン出てくるんですが、なまじ正しい意味を知っているだけに、著者がどういう意図で使っているのかがなかなか理解できなかったりする(ついつい正しい意味で解釈しようとしてしまうので)。
いや、限られた人生、こんなの読んだってなあ、と思いはするのですが、しかしこれも現代の病理を理解する一つの道かもしれん、と思うと、読むべきかなあ、などと思ってしまい、積み上げられたトンデモ本を前に悶々とするわけですが…。
トンデモ本の積読ほど哀しいものはないので、読むぞ、という決意を込めて書いてみました。(^^;;
最近行ってなかった古本屋に久々に行った。買い物ついでに。で、真っ先に行くのは当然100円コーナー。ついつい何冊も買ってしまうんですが、今回買ったもの(のうち、興味深いもの)はこれ。
・『右脳教育で子どもは変わる』七田眞
・『マイナスイオン療法の凄い効果を検証』師岡孝次
・『なぜそれは起こるのか』喰代栄一
七田はなんとかせなあかんと思って色々買い集めてるんですが、ざっと目を通す度に実にバカバカしくって逆になかなか読めない。いや、これが実際に行われてると想像すると、実に恐ろしいんですが、書いてあることは滅茶苦茶だし到底理論とは言えないレベルなので。典型的な議論の展開の仕方は、「AはBなのです。なぜならCだからです」というパターン。で、「AはB」というのがまず無茶苦茶で、例えば「イメージには予知力があります」とかイキナリ断言する。この本はずっとそういうのが書いてあるみたいで、後半になって「右脳は四次元的感覚を持ち、意識ではキャッチできない宇宙の全ての情報(波動情報)をキャッチする超高感度の受信機として働きます」なんて感じで「論証」しちゃう。
どの本もこんな感じみたいなんで苦痛なんですが、それでも如何にトンデモかというのをわかりやすく示せるような文章を探してまた買ってしまうんですよねえ。100円だし。
師岡さんという人は初めて見る名前なんですが、パラパラと見たら最初にどうも「マイナスイオン」批判が書いてあるようなので、ついつい買ってしまった。第一章のタイトルが「間違いだらけのマイナスイオン・ブーム」で、節を見ると「大流行のマイナスイオンはウソかマコトか」「マイナスイオン効果に異論続出」「空気マイナスイオンと活性マイナスイオンは違う」「マイナスイオン効果が一人歩きをしている」「空気マイナスイオン実験を実現する」「従来の交流式電位治療器にマイナスイオン効果はあるか」と来るわけです。しかもざっと眺めてみると、長年マイナスイオンの批判をされている安井至さんの発言を肯定的に引用したりもしている。
で、その上でですよ。第2章第1節のタイトルが、「宇宙医学から誕生したタカタイオン療法」で、最初のページを見ると、1938年に太陽に起源を持つ放射線、名づけて「太陽第四線」、というような記述が出てきて、これあ読まねば、とムラムラと来てしまったわけですね。
これ、2003年の本なので、もうマイナスイオンに対する差別化戦略が始まっていたってことですかね。そういう意味でもちょっと興味深い。
最後の喰代さんのやつなんですが、副題に「過去に共鳴する現在 シェルドレイクの仮説をめぐって」とあるとおり、そっち系(ってどっちだ^^;; 共鳴系というか100匹目の猿系というか)のシンクロニシティー本。サンマークで、帯に「船井幸雄氏も絶賛した驚愕の書」とあるとおり、この人の名前は船井の本には時々出てくるので知っていて、それで見つけて買ったわけです。
あ、巻頭にシェルドレイクの写真もデッカク載ってます。ってどうでもいいか。
この人とか、あとちょっと前に買ってこれもまた読んでないんですが飯田史彦(『生きがいの研究』とか)とか、現代資本主義をオカルト的に支える理論づくりをしている面があるように見えるので、一度きっちり見ておかないとな、とは思っているんですが、それだけに彼らの主張の本質を理解するのが一筋縄では行かなくて、ついつい後回しにしてしまうんですよねえ。
『シンクロニシティー』なんか読むのが実につらくて。物理用語がバンバン出てくるんですが、なまじ正しい意味を知っているだけに、著者がどういう意図で使っているのかがなかなか理解できなかったりする(ついつい正しい意味で解釈しようとしてしまうので)。
いや、限られた人生、こんなの読んだってなあ、と思いはするのですが、しかしこれも現代の病理を理解する一つの道かもしれん、と思うと、読むべきかなあ、などと思ってしまい、積み上げられたトンデモ本を前に悶々とするわけですが…。
トンデモ本の積読ほど哀しいものはないので、読むぞ、という決意を込めて書いてみました。(^^;;
血液型と性格に強い関係はないことがわかっています
 ブログネタ:星座・血液型の相性は気にする?
参加中
ブログネタ:星座・血液型の相性は気にする?
参加中本文はここから
Ameba×TBS アナCAN 連動ブログ
TBS アナCAN 公式HP

「血液型からその人の性格がわかる」
「その人の性格から血液型を当てられる」
こういうのを、「血液型性格判断」と言います。
血液型と性格の相関については長年心理学で研究され、こういう「強い相関」はない、ということが、既に明らかになっています。
よくよく調べれば、ごくわずかに関係があるかもしれません。しかし、それは「○型の人は~な性格」と言える様な強い関係ではありません。
なので、当然相性も無関係ということになります。
これはどう思うかとは関係なく、研究によって明らかにされた事実です。
このことについては、以下のエントリで私も取り上げています。
「真の血液型性格診断」って言われても…
血液型性格判断前史
なお、当然ながら、占星術にも科学的根拠はありません。
ところで、民放のアナウンサーであれば、当然民放連の放送基準 やBPO についてはご存知ですよね。
「放送基準」から一部を紹介します。
(53) 迷信は肯定的に取り扱わない。また、BPOからは、「血液型を扱う番組」に対する要望 が出ています。ぜひ御一読ください。下に、その一部を抜粋します。
(54) 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
放送局が血液型をテーマとした番組を作る背景には、血液型に対する一種の固定観念とでもいうべき考え方や見方が広く流布していることがあげられる。なお、この「要望」では、血液型に関する番組は、上の「放送基準」の(54)に抵触するおそれがある、と述べています。
しかし、血液型をめぐるこれらの「考え方や見方」を支える根拠は証明されておらず、本人の意思ではどうしようもない血液型で人を分類、価値づけするような考え方は社会的差別に通じる危険がある。血液型判断に対し、大人は“遊び”と一笑に付すこともできるが、判断能力に長けていない子どもたちの間では必ずしもそういうわけにはいかない。こうした番組に接した子どもたちが、血液型は性格を規定するという固定観念を持ってしまうおそれがある。
また、番組内で血液型実験と称して、児童が被験者として駆り出されるケースが多く、この種の“実験”には人道的に問題があると考えざるを得ない。
これらを踏まえた上で、アナウンサーという職業に伴う責任や倫理をいま一度深くお考えになり、発言なさることを希望するものです。血液型ハラスメントを起こさないためにも。
…ええ、野暮は承知の上ですとも。
でもね、事実は事実ですからね。
学問の自由
東中野修道・亜細亜大学教授が書いた本で南京事件の「ニセ被害者」と名指しされた夏淑琴さんに名誉毀損で訴えられていた控訴審で、東京高裁は一審判決を支持、東中野氏らに400万円の賠償を命じた。なにはともあれ、妙なことがおきなかったことは喜ばしい。
詳細は、
碧猫さん「南京事件に関する情報メモ・21日分と22日分」 (Gazing at the Celestial Blue )
ni0615さん「東中野教授、2審でも「減罰」なし」 (土俵をまちがえた方々 )
に詳しいのでご参照いただければと思います。
さて、一審判決が出たときから少し気になっていたのだが(このブログはまだ未開設だった)、一審判決で東中野氏はこう評価された。
しかし。
学問の自由を標榜し、言論の自由を謳歌することが求められる大学において、外部から「学問研究の成果というに値しない」と評価されることは、果たして大学にとっていいことなのだろうか?
本来、東中野のような言説については、アカデミズムの内部で徹底的に批判され、恥ずかしくてとても外部には出せないというぐらいになっていなければならないはずだ。厳しい相互批判があればこそ学問も進展するのであり、東中野が大学の教授ポストを占め、恥ずかしげもなく「学問研究」に値しないことを大声で主張する状況は、学問の自由を維持するという点からも決して歓迎されることではないのではないか。亜細亜大学法学部にどういう人々がいて、どういう立場に立っているのかは知らない。しかし、彼を採用した側として、このままでいいのか?という気はする。道義的な問題として。内部での学問的な批判がもっともっと求められると思うのだが(あるのかもしれないが、少なくとも私には見えない。内部的な努力があるのであれば、すみません)。
そう考えると、東中野を嗤ってばかりもいられない、という気がしてくる。学問の名を騙り人々に苦痛を与える「ニセ学者」は、言論において徹底的に批判されなければならない、と思う。
詳細は、
碧猫さん「南京事件に関する情報メモ・21日分と22日分」 (Gazing at the Celestial Blue )
ni0615さん「東中野教授、2審でも「減罰」なし」 (土俵をまちがえた方々 )
に詳しいのでご参照いただければと思います。
さて、一審判決が出たときから少し気になっていたのだが(このブログはまだ未開設だった)、一審判決で東中野氏はこう評価された。
被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く,学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない。(「15年戦争資料 @wiki 夏淑琴さん名誉毀損訴訟」 より抜粋)歴史修正主義者のボロが白日の下にさらけ出された瞬間であり、彼を持ち上げその著作を根拠に妄言を吐いていた人々に一撃を加える判決だった。今現在はどうかわからないが、いっときは彼の本は書店でいくつも平積みにされ、特設コーナーを置く書店も目にした。それを考えると、(通常なら)研究者生命を断つに等しいこの判決はまさに痛快とも言うべきものであった。
しかし。
学問の自由を標榜し、言論の自由を謳歌することが求められる大学において、外部から「学問研究の成果というに値しない」と評価されることは、果たして大学にとっていいことなのだろうか?
本来、東中野のような言説については、アカデミズムの内部で徹底的に批判され、恥ずかしくてとても外部には出せないというぐらいになっていなければならないはずだ。厳しい相互批判があればこそ学問も進展するのであり、東中野が大学の教授ポストを占め、恥ずかしげもなく「学問研究」に値しないことを大声で主張する状況は、学問の自由を維持するという点からも決して歓迎されることではないのではないか。亜細亜大学法学部にどういう人々がいて、どういう立場に立っているのかは知らない。しかし、彼を採用した側として、このままでいいのか?という気はする。道義的な問題として。内部での学問的な批判がもっともっと求められると思うのだが(あるのかもしれないが、少なくとも私には見えない。内部的な努力があるのであれば、すみません)。
そう考えると、東中野を嗤ってばかりもいられない、という気がしてくる。学問の名を騙り人々に苦痛を与える「ニセ学者」は、言論において徹底的に批判されなければならない、と思う。
「宇宙基本法案」通ってしまったけど…
残念ながら、5/21に可決、成立してしまいました。
が、これはあくまでも「基本法」。具体化はこれから。いままでの「平和目的に限る」という限定がなくなった、というのが今の状態なので、今後は平和目的ではない計画をいかにして止めるかというところに焦点が移ります(もちろん、この基本法を修正するという方向も必要だけど)。
もう一度、我が国による宇宙の軍事利用を解禁する「宇宙基本法案」 へのリンクをはっておきます。短時間でこれだけ(現在866件)の署名が集まったことは、今後に向けて貴重な財産となることでしょう(というか、そうしないといけない)。世話人の皆様、お疲れ様でした&ありがとうございました。
さて。
今回法が成立する運びとなったのは、自民・公明は当然だが民主党が賛成に転じたのが大きい。一部ではかなり衝撃だったようだけど(ととにかく「共闘」重視を主張する一部のブログを見るとそうだった。ってサンプル物凄い少ないですが)、所詮民主党は元・自民党、あるいは自民党竹下派を源流とするグループであるわけで、こうなるのはまったく不思議ではない。逆に民主党が大きくなれば日本が良くなると能天気に思えるのが不思議なくらい。
無論、個別法案への賛否について、民主党(だけでなく自民・公明に対してでさえも)に圧力をかけていくのは重要だけれども、それは現時点でそれだけの議席数を持っているから、と言う以上の意味はなく、民主党の議席をこれ以上増やしたところで自民党との馴れ合い(政策的な馴れ合い。大臣のポストとかの権力争いは激しいだろうけど、それは自民党一党支配体制のときでも同じであった)は全く変わらないだろう。むしろ政権交代による国民の不満のガス抜きによって、ますます世の中が悪い方向にズルズルと行くだけのように思える。
個別法案や個別課題について広く共闘するのは重要だろう(憲法9条なんかまさにそうだ)。しかし、無原則な共闘はかえって事態を悪化させる。どういう人を国会に送り込むかはよく考えたほうがいいだろう。自民党の議員が減れば問題が解決するほど物事は単純じゃない。また政権にいなくても世の中を多少なりとも変えることは可能である(ということをこの間の動きは示してきたといえよう。この法案についてじゃないけど)。無論、そういう人々の議席がもっともっと増えればさらに良い方向に変えていけるだろう。
今回の件は残念ではあったが、民主党への幻想を断ち切るという意味ではいい経験だったのではないか。というか、いい経験にして欲しいと思う。
が、これはあくまでも「基本法」。具体化はこれから。いままでの「平和目的に限る」という限定がなくなった、というのが今の状態なので、今後は平和目的ではない計画をいかにして止めるかというところに焦点が移ります(もちろん、この基本法を修正するという方向も必要だけど)。
もう一度、我が国による宇宙の軍事利用を解禁する「宇宙基本法案」 へのリンクをはっておきます。短時間でこれだけ(現在866件)の署名が集まったことは、今後に向けて貴重な財産となることでしょう(というか、そうしないといけない)。世話人の皆様、お疲れ様でした&ありがとうございました。
さて。
今回法が成立する運びとなったのは、自民・公明は当然だが民主党が賛成に転じたのが大きい。一部ではかなり衝撃だったようだけど(ととにかく「共闘」重視を主張する一部のブログを見るとそうだった。ってサンプル物凄い少ないですが)、所詮民主党は元・自民党、あるいは自民党竹下派を源流とするグループであるわけで、こうなるのはまったく不思議ではない。逆に民主党が大きくなれば日本が良くなると能天気に思えるのが不思議なくらい。
無論、個別法案への賛否について、民主党(だけでなく自民・公明に対してでさえも)に圧力をかけていくのは重要だけれども、それは現時点でそれだけの議席数を持っているから、と言う以上の意味はなく、民主党の議席をこれ以上増やしたところで自民党との馴れ合い(政策的な馴れ合い。大臣のポストとかの権力争いは激しいだろうけど、それは自民党一党支配体制のときでも同じであった)は全く変わらないだろう。むしろ政権交代による国民の不満のガス抜きによって、ますます世の中が悪い方向にズルズルと行くだけのように思える。
個別法案や個別課題について広く共闘するのは重要だろう(憲法9条なんかまさにそうだ)。しかし、無原則な共闘はかえって事態を悪化させる。どういう人を国会に送り込むかはよく考えたほうがいいだろう。自民党の議員が減れば問題が解決するほど物事は単純じゃない。また政権にいなくても世の中を多少なりとも変えることは可能である(ということをこの間の動きは示してきたといえよう。この法案についてじゃないけど)。無論、そういう人々の議席がもっともっと増えればさらに良い方向に変えていけるだろう。
今回の件は残念ではあったが、民主党への幻想を断ち切るという意味ではいい経験だったのではないか。というか、いい経験にして欲しいと思う。
大事なことは、みんな藤子不二雄に教わった。
というのはもちろん言いすぎですね。でも。
本を整理していたら、出てきたんですよね。藤子・F・不二雄のSF短編集。全8巻の、PERFECT版。あと、ドラえもんの自薦集(上下巻)。
子どものころ「ドラえもん」にドップリ漬かり、そこから派生して藤子作品をガンガン読んでまして。で、当時、判は文庫サイズだけどやたら分厚い「○○大百科」シリーズってのが沢山出てて、「藤子不二雄大百科」ってのがうちにあったんですよ。それにSF短編の一部がごくごく簡単に紹介されてて、読みたくてたまらなかった。
そのうち、短編集が発売されて(SF短編は全3巻で、紙は安っぽかったが分厚かった)、食い入るように読んだものです。
下に貼り付けてあるのは、大人になってから買ったもの(で、今回出てきたもの)。若干作者の手が入っていて、「差別表現」が「修正」されてあるのが残念なんですが、それでもまあ面白さの本質には変わりがない。
「ミノタウロスの皿」なんて、衝撃だったなあ。もう中学生になっていたか、まだ小学生だったか、定かではないけれど。漠然と感じていた「常識」というものへの不信感みたいなものの源泉の一つを、明快に表現してくれていた。
一応簡単に筋を言っておくと(ネタバレになるけど、バレても面白さは全然損なわれないと思います。何度読んでも面白いし^^;;)、宇宙船に事故が発生し、救援が届くまでにはとても食料がもたない。唯一生き残った主人公は、幸いにも人の住む星を見つけ、緊急着陸する。しかしそこは牛ににた「ウス」が支配する星で、人間は家畜であった(ちゃんと話もできる)…という話。要するに、文化相対主義を読者は目の当たりにするわけだ。最後のオチも凄くて、己の価値観を相対化できない者が、客観的にはいかに滑稽かを見せつけてくれる。
他にも「ウルトラ・スーパー・デラックスマン」とか。偏狭な正義感を持つ人がスーパーマン並みの力を持ってしまったらどうなるか、という。価値観の絶対化と、目的のためには手段を問わないということの恐ろしさが如実に示される(このモチーフはSF短編では他にも色々ありますね)。
「気楽に殺ろうよ」なんてもう文化相対主義に加えて食欲と性欲のどっちを恥じるべきかなんていう実に面白い展開で。自分の普段の価値観というものを問い直すとてもいいきっかけになる。
また「どことなくなんとなく」は独我論が実際成り立つかというのも関わっていて、色々考えさせてくれる。
タイムトラベルものも勿論あるし、親殺しに通じる話もあるし、たまらんのですわ。
いやまあ語りだすとキリがないんですが、(^^;;
堅い教科書読むよりよっぽど勉強になったと思う。というか、これ(短編集だけでなく、藤子不二雄の全作品)がなければ、いまの自分はなかっただろうなあ…と思うと罪作りなのかなんなのか。(^^;;
久々に読んで、誰かに言いたくてたまらくなったという次第。失礼しましたー。
本を整理していたら、出てきたんですよね。藤子・F・不二雄のSF短編集。全8巻の、PERFECT版。あと、ドラえもんの自薦集(上下巻)。
子どものころ「ドラえもん」にドップリ漬かり、そこから派生して藤子作品をガンガン読んでまして。で、当時、判は文庫サイズだけどやたら分厚い「○○大百科」シリーズってのが沢山出てて、「藤子不二雄大百科」ってのがうちにあったんですよ。それにSF短編の一部がごくごく簡単に紹介されてて、読みたくてたまらなかった。
そのうち、短編集が発売されて(SF短編は全3巻で、紙は安っぽかったが分厚かった)、食い入るように読んだものです。
下に貼り付けてあるのは、大人になってから買ったもの(で、今回出てきたもの)。若干作者の手が入っていて、「差別表現」が「修正」されてあるのが残念なんですが、それでもまあ面白さの本質には変わりがない。
「ミノタウロスの皿」なんて、衝撃だったなあ。もう中学生になっていたか、まだ小学生だったか、定かではないけれど。漠然と感じていた「常識」というものへの不信感みたいなものの源泉の一つを、明快に表現してくれていた。
一応簡単に筋を言っておくと(ネタバレになるけど、バレても面白さは全然損なわれないと思います。何度読んでも面白いし^^;;)、宇宙船に事故が発生し、救援が届くまでにはとても食料がもたない。唯一生き残った主人公は、幸いにも人の住む星を見つけ、緊急着陸する。しかしそこは牛ににた「ウス」が支配する星で、人間は家畜であった(ちゃんと話もできる)…という話。要するに、文化相対主義を読者は目の当たりにするわけだ。最後のオチも凄くて、己の価値観を相対化できない者が、客観的にはいかに滑稽かを見せつけてくれる。
他にも「ウルトラ・スーパー・デラックスマン」とか。偏狭な正義感を持つ人がスーパーマン並みの力を持ってしまったらどうなるか、という。価値観の絶対化と、目的のためには手段を問わないということの恐ろしさが如実に示される(このモチーフはSF短編では他にも色々ありますね)。
「気楽に殺ろうよ」なんてもう文化相対主義に加えて食欲と性欲のどっちを恥じるべきかなんていう実に面白い展開で。自分の普段の価値観というものを問い直すとてもいいきっかけになる。
また「どことなくなんとなく」は独我論が実際成り立つかというのも関わっていて、色々考えさせてくれる。
タイムトラベルものも勿論あるし、親殺しに通じる話もあるし、たまらんのですわ。
いやまあ語りだすとキリがないんですが、(^^;;
堅い教科書読むよりよっぽど勉強になったと思う。というか、これ(短編集だけでなく、藤子不二雄の全作品)がなければ、いまの自分はなかっただろうなあ…と思うと罪作りなのかなんなのか。(^^;;
久々に読んで、誰かに言いたくてたまらくなったという次第。失礼しましたー。
- 藤子・F・不二雄SF短編PERFECT版 (1) (SF短編PERFECT版 1)/藤子・F・不二雄
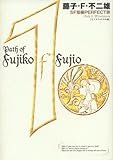
- ¥1,575
- Amazon.co.jp