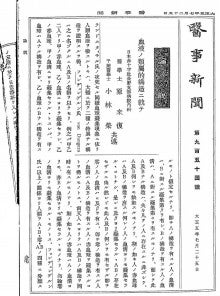『「血液型と性格」の社会史 血液型人類学の起源と展開』(松田薫、改訂第二版)(その3)
このシリーズも、当初の目的、即ちABO FAN氏がつけた難癖(私がエントリ中で血液型性格判断の歴史についての詳細を知りたい方は大村政男『血液型と性格』を見てくださいと書いたことに対し、大村本を引用するだけでも「アウト」だと言ったこと)に対する反論が一応前回前々回で終わったと思っているので、最後にこの本(『「血液型と性格」の社会史』)を理解する上で参考になる部分を紹介しておく。
まず、何度も繰り返すが、特に戦前の「血液型と性格」についての詳細を知りたい方は、是非この本を読むべきだ。少なくとも事実関係については実に詳細に書かれている。ただし、推測の部分については注意が必要だ。
で、どういう内容が書かれているか、いままで関連する部分しか紹介していなかったので、ここであらためて目次を出しておく(大見出しのみ)。改訂第二版であることに注意。
最初のほうで、血液型の発見や人類学への応用(血液型は遺伝するので、当然頻度分布が民族によって異なり、頻度の類似性などから民族の移動等の歴史を考察することができる)が語られており、単に「血液型と性格」にとどまらない範囲をカバーしている。また、1933年頃にアカデミズムの場では古川竹二の学説にほぼトドメを刺されたような格好になっているが(松田氏によれば、そこではまだ決着がついていないというのが正しいそうであるが、私は事実上ここで学問的には決着がついたとみて良いと思っている)、大衆的にはそれが広がらず、血液型性格判断の蔓延が深刻であったことがよくわかる。例えば、1937年に外務省嘱託医が「外交官はO型がよい」と述べ、「某課長」に至っては、自分がO型でないことが判明すると、もはや出世の望なしとして辞表を出したことがあったという。
そういうわけで、歴史の詳細を知りたいならば、この本を手にとることをおすすめする。
さて。
この本を読み解くには、松田氏独特の考え方を理解する必要がある。それが窺える部分をいくつか引用しておこう。
まず「はじめに」から。初版が絶版に至った経緯がこう述べられる(p.7)。
さらに、80年代のブームについて(p.8)。
80年代ブームについては、「補章」にも以下のような記述がある(p.321)。
最後に、「結び」の一番最後の文章を引用しておこう(p.370)。
以上、紹介した文章は、あくまでももっとも特徴的と思われる部分であって、全編この調子、というわけではないことに注意されたい。特に、本編の大半は、読んでもそう違和感を感じないと思う。
続いて、周辺での情報。
『現代のエスプリ』324巻は「血液型と性格」特集である。その中で、佐藤達哉氏がいくつか論文を書いているのだが、その一つ、「古川竹二-教育における相互作用的観点の先駆者」という論文の末尾では、松田氏から多くのことを教えてもらった旨感謝の言葉が述べられている。きっと、大変だったのではないかと思う。一方、松田氏はウェブサイトを開設している(「京都昨今」…あえてリンクは貼りません。お察し下さい)が、2007年夏~秋の文章で、佐藤達哉氏との出会いが語られている。松田氏が見た「世界」というものがどういうものかがよくわかる。…のだが、内容についてはここでは省略する。どうしても見たい方は検索して見られると良いと思う。
次に、ABO FAN氏との関係。松田氏は、ABO FAN氏にメールを送っている。それは、Mr. Matsuda というページに掲載されている。2001年ごろのようである。松田氏の文章は、見ていて正直痛々しい。そして、それを持て余しているABO FAN氏の姿も目に浮ぶ(もちろん、こちらの勝手な想像ですよ!)。
最後に、「その1」のエントリへいただいたB研さんのコメント が、実に的確であると思うので、勝手ながら引用させていただきたいと思う(空白行は削除した)。
というわけで、以上の3つのエントリの目的は、冒頭にも書いたように、大村本を引用したからと言って「アウト」などと言われてはたまったもんじゃない、ということを主張することにあった。その経緯については、このエントリ を参照していただきたい(特にコメント欄)。ABO FAN氏によれば、アウトであるという根拠は、「松田薫さんで尽きていると思います」だそうである。そうではないことを、エントリ3つも使って反論したのであるから、これを踏まえて、アウトである発言を撤回するか、再反論をしていただきたい。ちゃんと踏まえて、ね。
それから、今回コメントをいただいて気づいたが、不覚にもB研さんのウェブページを紹介したことがなかった。大変良いコンテンツなので、血液型性格判断に興味のある方は、是非、一度はご覧になられることをおすすめする。
→B型による B型のための B型の研究
ここから辿っていただきたい。特に「優生学 」の項は必見である。
まず、何度も繰り返すが、特に戦前の「血液型と性格」についての詳細を知りたい方は、是非この本を読むべきだ。少なくとも事実関係については実に詳細に書かれている。ただし、推測の部分については注意が必要だ。
で、どういう内容が書かれているか、いままで関連する部分しか紹介していなかったので、ここであらためて目次を出しておく(大見出しのみ)。改訂第二版であることに注意。
第一章 「血液型人類学」のはじまりなお資料として国や民族ごとの詳細な血液型頻度分布が掲載されている。
第二章 「血液型進化論」の展開
第三章 軍隊と心理学
第四章 古川竹二の血液型気質学説
第五章 「探偵趣味の会」と「日本民族衛生学会」
第六章 血液型大行進
第七章 血液型と病気
第八章 時代の流れの変わり目
第九章 長崎医科大事件
第一〇章 戦時下での血液型と性格
第一一章 血液型にこだわる古畑種基
第一二章 現在までの欧米の動向
補章 止むことのない社会病理
最初のほうで、血液型の発見や人類学への応用(血液型は遺伝するので、当然頻度分布が民族によって異なり、頻度の類似性などから民族の移動等の歴史を考察することができる)が語られており、単に「血液型と性格」にとどまらない範囲をカバーしている。また、1933年頃にアカデミズムの場では古川竹二の学説にほぼトドメを刺されたような格好になっているが(松田氏によれば、そこではまだ決着がついていないというのが正しいそうであるが、私は事実上ここで学問的には決着がついたとみて良いと思っている)、大衆的にはそれが広がらず、血液型性格判断の蔓延が深刻であったことがよくわかる。例えば、1937年に外務省嘱託医が「外交官はO型がよい」と述べ、「某課長」に至っては、自分がO型でないことが判明すると、もはや出世の望なしとして辞表を出したことがあったという。
そういうわけで、歴史の詳細を知りたいならば、この本を手にとることをおすすめする。
さて。
この本を読み解くには、松田氏独特の考え方を理解する必要がある。それが窺える部分をいくつか引用しておこう。
まず「はじめに」から。初版が絶版に至った経緯がこう述べられる(p.7)。
(…)刊行(引用者注:初版本のこと)して10日ほどしたら、(略)九月には古畑種基の門下生から便りをいただいた。能見正比古の著書を参考にしてとおもうが、古畑先生はB型ではなく、AB型だから訂正してほしいというものだった。わたしは改訂のときにと答え、出版社に初版の絶版をつたえた。本書の主旨と関係のない、実に些細なところでの違いで、絶版にしてしまうのである! この潔癖さは、一つの特徴であろう。
さらに、80年代のブームについて(p.8)。
1980年代のはじめ、(略)またもや血液型占いのブームが起きた。この原因は私にある。1980年の夏、私は白人種への抗議のための「エスニック」という聞きなれないことばをタイトルにいれた『ABO式(血液型)遺伝子による民族音楽(エスニック・ミュージック)の分析』という論文を印刷した。活字への指示は、とうじ科学史学会長をしていた神戸大の湯浅光朝だった。私に論文をかけといったのが、京大の湯川秀樹の一番弟子だったから、湯川たちがつくった学会で発表するようにともいった。どう言ったらいいのだろうか。さらに続けて、
この論文や発表をしったものたちが、私に私の著作を請求してきて、『朝日』を中心に故人の名誉を毀損し、私の人格権や著作権を侵害するデタラメの史実をつぎつぎかいていった。初版でこれらを抜いたのは、いずれまちがいに気づき、反省をするだろうとおもったからである。ところが、反省どころかデタラメがひどくなった。このような経過があったため、大きくかきなおすことにした。とのことである。客観的事実はともかく、松田氏にとって世界はこのように見えていたのだろうことはよくわかる。
80年代ブームについては、「補章」にも以下のような記述がある(p.321)。
私は、能見正比古も血液型占い批判の文章やテレビ番組をつくった側のひとも、面識があったり、私のかいたものから剽窃など著作権や人格権の侵害をしたので、非常にかきづらい。これは「補章」の最初の節の最後の文章で、なぜ改訂したか、なぜこの補章があるのかの理由になっている。このあと、松田氏の生い立ちが語られる。そして、なぜ松田氏が血液型に興味を持ったか(そして手掌紋に興味を持ったか)が述べられる。それは生い立ちとは切り離せない関係にある。さらに、松田氏が調べた戦前の歴史上の事実について、大村氏や溝口氏などが誤って文章化していた部分について、出版社や本人とどう議論したかが詳細に-松田氏の見た世界として-述べられる。前のエントリで紹介したのはその一例である。
ただ、80年代以降の血液型占いブームと批判の原因をつくり、血液型人類学の起源を解明したのは私ということもあり、私は義務として本書をかきすすめる。
最後に、「結び」の一番最後の文章を引用しておこう(p.370)。
また、今回の改訂版は、初版本にたいして私へ質問をあびせたマスコミ人にもこたえるようにかいたつもりである。大学生にもわかるようにと、できるかぎり、わかりやすい表現をつかったつもりだが、世界の第一線の科学者も知らない内容が多いため、理解には時間がかかるとおもう(1993年夏)。という自負(のようなもの)が披瀝されている。
以上、紹介した文章は、あくまでももっとも特徴的と思われる部分であって、全編この調子、というわけではないことに注意されたい。特に、本編の大半は、読んでもそう違和感を感じないと思う。
続いて、周辺での情報。
『現代のエスプリ』324巻は「血液型と性格」特集である。その中で、佐藤達哉氏がいくつか論文を書いているのだが、その一つ、「古川竹二-教育における相互作用的観点の先駆者」という論文の末尾では、松田氏から多くのことを教えてもらった旨感謝の言葉が述べられている。きっと、大変だったのではないかと思う。一方、松田氏はウェブサイトを開設している(「京都昨今」…あえてリンクは貼りません。お察し下さい)が、2007年夏~秋の文章で、佐藤達哉氏との出会いが語られている。松田氏が見た「世界」というものがどういうものかがよくわかる。…のだが、内容についてはここでは省略する。どうしても見たい方は検索して見られると良いと思う。
次に、ABO FAN氏との関係。松田氏は、ABO FAN氏にメールを送っている。それは、Mr. Matsuda というページに掲載されている。2001年ごろのようである。松田氏の文章は、見ていて正直痛々しい。そして、それを持て余しているABO FAN氏の姿も目に浮ぶ(もちろん、こちらの勝手な想像ですよ!)。
最後に、「その1」のエントリへいただいたB研さんのコメント が、実に的確であると思うので、勝手ながら引用させていただきたいと思う(空白行は削除した)。
松田本を一面的に評価するのは不可能であり、多面的評価が必要であると思います。まさに松田本人に対する理解を問うのがこの本であり、無条件で肯定するのでなく、批判的に吟味しようと思えば、松田氏自身を論じることを避けるわけにはいかなかった。その意味で、今回の3つのエントリは、書くのが非常に気が重かったことを告白しておく。
松田本を貫くテーゼは、松田本人に対する理解であり、血液型気質相関説は手段に過ぎません。
松田は独特な感性の持ち主であり、松田を理解できる人間は、松田本人以外に存在しません。
というわけで、以上の3つのエントリの目的は、冒頭にも書いたように、大村本を引用したからと言って「アウト」などと言われてはたまったもんじゃない、ということを主張することにあった。その経緯については、このエントリ を参照していただきたい(特にコメント欄)。ABO FAN氏によれば、アウトであるという根拠は、「松田薫さんで尽きていると思います」だそうである。そうではないことを、エントリ3つも使って反論したのであるから、これを踏まえて、アウトである発言を撤回するか、再反論をしていただきたい。ちゃんと踏まえて、ね。
それから、今回コメントをいただいて気づいたが、不覚にもB研さんのウェブページを紹介したことがなかった。大変良いコンテンツなので、血液型性格判断に興味のある方は、是非、一度はご覧になられることをおすすめする。
→B型による B型のための B型の研究
ここから辿っていただきたい。特に「優生学 」の項は必見である。
『「血液型と性格」の社会史 血液型人類学の起源と展開』(松田薫、改訂第二版)(その2)
前回からの続き。図書館で貸出の更新手続きしてきた。
【松田氏から見た大村評】(つづき)
p.352の最後の一行から引用する。
この部隊の詳細については、松田本には「補章」で上のように述べている程度であり、また大村本でも部隊名などはよくわからない。相補的なものが、『現代のエスプリ』324(1994/7)p.77からの「旧軍部における血液型と性格の研究」である。これも大村政男氏によるものである。これによると、井上日英は陸軍輜重兵第16大隊 *1の軍医(軍医大尉)で、1906年に創設、1936年に連隊に改称されているという(この時、他の輜重兵大隊も連隊となったようである)。なお、これはあくまでも井上のいた大隊の話であり、井上が創設した「血液型部隊」ではない。
井上は、134人を二個中隊に分け、それぞれをさらに4つの試験班に分割、計8班を編成した。そして、班長と班員の血液型について様々なパターンになるようにした。また、班員は初年兵ばかりにした。ところが、大隊編成の都合で古参兵が試験班に入るようになり、また大隊から満州に転属になる者も出、短期間でこの試みは崩れてしまったという。
さて、この「試験班」ないし「中隊」を、「戦闘チーム」と呼ぶことになにか問題があるだろうか。たとえ輜重兵といえども、軍隊は戦闘組織であって、戦闘組織における「班」を「戦闘チーム」と呼ぶのはむしろ当然ではないのだろうか。無論、班は班であるので、わざわざ「戦闘チーム」と言いかえる必要はないのかもしれない。実際、『現代のエスプリ』所収の論文では、大村は「戦闘チーム」という表現はしていない。これは、軍隊組織というものをよく知らない読者のために、わかりやすくしようとこういう表現になったのではないだろうか。いずれにしても、このことが取りたてて問題であるとは思えないし、捏造とはとても言えないし、「軍隊=悪」という前提があるともとても思えない。あとは「構成」図が井上日英のものと同じかどうかであるが、そんなものまでわざわざ作るとも思えず(各班の血液型別の構成人数が載っている)、「創作」とは言えないだろう(もちろんこれは井上論文を見てみないことにはなんとも言えないが)。
そのようなわけで、この一節については、完全に松田氏による「言いがかり」と判断して差し支えないように思われるのだがいかがだろうか。
次のトピックに移る前に、この直後の松田氏のコメントを見ておく。「大村も溝口も古川を利用した古畑種基を良い人物のようにかき、大村の本には古畑の息子(和孝)の門下生が血液型性格学説を否定している(238頁)とある。古畑親子の執拗さと、現在に権力をもつ相手をほめる大村と溝口に情けなくなる。」(p.353-354)古畑種基の問題はもちろんある。それは戦後の重大事件における血液鑑定である。ただ、それにしてはこの文章は攻撃的に過ぎるであろう。松田氏は第一章で古畑への不信を述べているのだが、古畑に対する個人的感情をベースに大村氏や溝口氏まで一緒くたにして非難しているように見えてしまう。
次はFBI効果だ。
しかし、松田氏の批判はそのようなものではなく、要するにわざわざ名付けるほどの意味はない、ということだ。しかしそれは違うだろう。名付けることによって、概念というのは明確になるものだ。それに、「言葉の意味の多義性、先入観に偏見、風俗や習慣」と言われて理解できる中学生はいったいどれくらいいるだろう?中学生に限らない。大人でもいい。先入観や偏見はわかるかもしれない。しかし、それで血液型性格判断を信じてしまう心理がわかるだろうか?私にはそうは思えない。
この後、約1ページにわたって、松田氏による意味のよくわからない批判が続く。どうも被害者意識が強すぎるようなのだが、どうにもこうにも論評しようがなく、ただ引用した文章を垂れ流すのもと思うので、途中、この部分は省略する。
大村との関係での最後の部分である。(p.355)
柴谷篤弘の名前を載せろというに至っては、もう理解不能である。「補章」のもう少し前のところで柴谷との関係が書かれているが、柴谷は単に松田氏に血液型に関するネイチャー論文の存在を教えたに過ぎない。それでなぜ柴谷の名前を載せろと言えるのか、訳がわからない。
このネイチャー論文の件については、もう少し先の部分で以下のようなことを述べている。(p.358)
それと、前エントリで書いた「文体」の問題、おわかりいただけただろうか。ちょっと尋常ではない。
他にも松田氏の書くものを理解するにあたって、松田氏がどういう発想でものを見ているかが伺える文章があるのだが、ここではこの程度にとどめておく。興味のある人は、本書を読んでもらいたい。
いずれにしても、(繰り返すが)本書が労作であることに間違いはない。「血液型と性格」の戦前の歴史について知りたい人は、是非御一読をおすすめする。
それから、これだけ見れば、少なくとも松田本で触れられている範囲での大村氏について「トンデモ」などというABO FAN氏の評はまったくおかしなものであることがわかっていただけると思う。大村氏へのネガティブな評価を持つ文献を持ってきて、大村氏を引用した私のエントリを「アウト」などと言う暇があったら、自分で書いたウェブページの中で、歴史についての大村氏の文章を引用している部分について、きっちり自己批判すべきではないだろうか。(この件については、こちらのエントリを御参照ください)
*1 陸軍第16師団に所属。この師団、1937年に華北に投入され、間もなく上海派遣軍の一員として南京攻略戦に参加、南京事件を引き起こす。もちろん、血液型とはなんの関係もないだろうし、南京事件の中で第16輜重兵連隊が果たす役割もよく知らないのですが。参考:wikipediaの説明
【松田氏から見た大村評】(つづき)
p.352の最後の一行から引用する。
大村は、軍医のかいた論文を、歪曲してよむ。「軍隊=悪」のイメージの強い日本では、軍隊に関しては、どんな捏造も許されるとおもっているのだろう。私のしるかぎり、日本の軍隊が戦場へ血液型別部隊を送ったという文書はでてこない。ところが、大村は、まず、事実関係については、私自身が井上日英の論文を読んでいないのでなんとも言えないのであるが、松田氏も事実関係そのものには特に異論がないように思われる。問題は、「戦闘チーム」という表現であろう。
「井上日英という軍医はそれを実行してみたのである」(170頁)
「井上日英は、血液型による最小の戦闘集団(班という)を構成したが、その構成の仕方は、医学的な血液型検査に拠っている」(171頁脚注2)
とかき、「図45井上日英の血液型による戦闘チームの構成」(173頁)まで創作する。
(中略、上官と部下の血液型が同じ班と違う班を作って4ヶ月日本で試したという事実の説明)
1932年の日本国内における四ヶ月間の、服や武器係の兵隊の成績くらべが、なぜ「戦闘チーム」になるのか。満州へ派遣された、輜重兵42人については、一年間、血液型と病気と進級を比較しただけとかいてあるのに、なぜ「戦闘チーム」になるのか。
この部隊の詳細については、松田本には「補章」で上のように述べている程度であり、また大村本でも部隊名などはよくわからない。相補的なものが、『現代のエスプリ』324(1994/7)p.77からの「旧軍部における血液型と性格の研究」である。これも大村政男氏によるものである。これによると、井上日英は陸軍輜重兵第16大隊 *1の軍医(軍医大尉)で、1906年に創設、1936年に連隊に改称されているという(この時、他の輜重兵大隊も連隊となったようである)。なお、これはあくまでも井上のいた大隊の話であり、井上が創設した「血液型部隊」ではない。
井上は、134人を二個中隊に分け、それぞれをさらに4つの試験班に分割、計8班を編成した。そして、班長と班員の血液型について様々なパターンになるようにした。また、班員は初年兵ばかりにした。ところが、大隊編成の都合で古参兵が試験班に入るようになり、また大隊から満州に転属になる者も出、短期間でこの試みは崩れてしまったという。
さて、この「試験班」ないし「中隊」を、「戦闘チーム」と呼ぶことになにか問題があるだろうか。たとえ輜重兵といえども、軍隊は戦闘組織であって、戦闘組織における「班」を「戦闘チーム」と呼ぶのはむしろ当然ではないのだろうか。無論、班は班であるので、わざわざ「戦闘チーム」と言いかえる必要はないのかもしれない。実際、『現代のエスプリ』所収の論文では、大村は「戦闘チーム」という表現はしていない。これは、軍隊組織というものをよく知らない読者のために、わかりやすくしようとこういう表現になったのではないだろうか。いずれにしても、このことが取りたてて問題であるとは思えないし、捏造とはとても言えないし、「軍隊=悪」という前提があるともとても思えない。あとは「構成」図が井上日英のものと同じかどうかであるが、そんなものまでわざわざ作るとも思えず(各班の血液型別の構成人数が載っている)、「創作」とは言えないだろう(もちろんこれは井上論文を見てみないことにはなんとも言えないが)。
そのようなわけで、この一節については、完全に松田氏による「言いがかり」と判断して差し支えないように思われるのだがいかがだろうか。
次のトピックに移る前に、この直後の松田氏のコメントを見ておく。「大村も溝口も古川を利用した古畑種基を良い人物のようにかき、大村の本には古畑の息子(和孝)の門下生が血液型性格学説を否定している(238頁)とある。古畑親子の執拗さと、現在に権力をもつ相手をほめる大村と溝口に情けなくなる。」(p.353-354)古畑種基の問題はもちろんある。それは戦後の重大事件における血液鑑定である。ただ、それにしてはこの文章は攻撃的に過ぎるであろう。松田氏は第一章で古畑への不信を述べているのだが、古畑に対する個人的感情をベースに大村氏や溝口氏まで一緒くたにして非難しているように見えてしまう。
次はFBI効果だ。
大村には、このほかに、テレビや雑誌で、大村の発見のように披露している「FBI効果」という訳のわからない代物がある。大村は血液型性格学が成り立っている原因を、まず用語の意味があいまいで、だれにでもあてはまるフリーサイズ効果(F)と、O型は大胆とかいわれると、その考え方で相手をみるラベリング効果(B)と、A型は神経質とかいわれると、そのまま信じてしまうインプリンティング効果(I)の三つにあるとする。じつに、おおげさだ。言葉の意味の多義性、先入観に偏見、風俗や習慣とでもいえば、中学生でも理解できるのに。FBI効果については、無論バーナム効果との違いについては議論すべき点があるのだと思うが、残念ながら私は心理学のプロではないので、そこのところはなんとも言えない。しかし、他の心理学者もFBI効果に言及していることは多く、またバーナム効果の中身の分類という意味でも意義のないこととは言えないと思う(単純にサブカテゴリーになっているとは思わないが)。
しかし、松田氏の批判はそのようなものではなく、要するにわざわざ名付けるほどの意味はない、ということだ。しかしそれは違うだろう。名付けることによって、概念というのは明確になるものだ。それに、「言葉の意味の多義性、先入観に偏見、風俗や習慣」と言われて理解できる中学生はいったいどれくらいいるだろう?中学生に限らない。大人でもいい。先入観や偏見はわかるかもしれない。しかし、それで血液型性格判断を信じてしまう心理がわかるだろうか?私にはそうは思えない。
この後、約1ページにわたって、松田氏による意味のよくわからない批判が続く。どうも被害者意識が強すぎるようなのだが、どうにもこうにも論評しようがなく、ただ引用した文章を垂れ流すのもと思うので、途中、この部分は省略する。
大村との関係での最後の部分である。(p.355)
大村や溝口の論文には私の名前はでてこない。このことを溝口にいうと、無名でしらべてもわからないからという。私が、『ネイチャー』の記事は柴谷篤弘に教えてもらったのだから、柴谷の名前は記入しろというと、…はっきり言って、意味がわからない。大村に限らず、松田氏の論文は他で引用されているのは見たことがない(って私がそれほど心理学の論文を見てないせいもあるだろうが)。なおこの『「血液型と性格」の社会史』は、よく引用されているようである。『現代のエスプリ』でも、多くの人に引用されている(大村氏を含めて)。大村の『新訂 血液型と性格』でも参考文献として挙げられている。要するにソレナリの仕事すれば引用してくれるし、そうでないマイナーなものや、各自の研究との関連性がごく薄いものは引用されない、それだけではないのだろうか。
「柴谷なんか、東京では無名だ、存在がない」
というので、私が、知人たちから東大の村上陽一郎は学者ではないとかを聞くのが嫌なんだ、そんな言い方はやめられないかといったら黙っている。そうなのか、村上をしらないのかとおもっていたら、ちがっていた。1992年神田の三省堂で、『ウィルヒョウの生涯』(E・H・アッカークネヒト著サイエンス社1984)をみつけた。溝口は村上といっしょに翻訳をしているのだ。
柴谷篤弘の名前を載せろというに至っては、もう理解不能である。「補章」のもう少し前のところで柴谷との関係が書かれているが、柴谷は単に松田氏に血液型に関するネイチャー論文の存在を教えたに過ぎない。それでなぜ柴谷の名前を載せろと言えるのか、訳がわからない。
このネイチャー論文の件については、もう少し先の部分で以下のようなことを述べている。(p.358)
(…)溝口元も寄稿(引用者注:『科学朝日』1991年11月号)して、…いや参るなあ、というのがこの文章を読んだときの感想である。なんで論文の存在を教えてもらったことまで書かないといけないのか?大事なのは論文の中身であって、どういう経緯で知ったかではないだろう。
「古川自身も自説を唱えることをやめてしまい」
など、いつもどおりの捏造文をかき、日本独自の血液型性格学説といいながら、なんのつながりもなく、いきなり『ネイチャー』で論争があったが否定されたとかく。もちろん、これはむかし私に手紙でおしえてもらったとか、私の本を参考にしたとかはかかない。
それと、前エントリで書いた「文体」の問題、おわかりいただけただろうか。ちょっと尋常ではない。
他にも松田氏の書くものを理解するにあたって、松田氏がどういう発想でものを見ているかが伺える文章があるのだが、ここではこの程度にとどめておく。興味のある人は、本書を読んでもらいたい。
いずれにしても、(繰り返すが)本書が労作であることに間違いはない。「血液型と性格」の戦前の歴史について知りたい人は、是非御一読をおすすめする。
それから、これだけ見れば、少なくとも松田本で触れられている範囲での大村氏について「トンデモ」などというABO FAN氏の評はまったくおかしなものであることがわかっていただけると思う。大村氏へのネガティブな評価を持つ文献を持ってきて、大村氏を引用した私のエントリを「アウト」などと言う暇があったら、自分で書いたウェブページの中で、歴史についての大村氏の文章を引用している部分について、きっちり自己批判すべきではないだろうか。(この件については、こちらのエントリを御参照ください)
*1 陸軍第16師団に所属。この師団、1937年に華北に投入され、間もなく上海派遣軍の一員として南京攻略戦に参加、南京事件を引き起こす。もちろん、血液型とはなんの関係もないだろうし、南京事件の中で第16輜重兵連隊が果たす役割もよく知らないのですが。参考:wikipediaの説明
『「血液型と性格」の社会史 血液型人類学の起源と展開』(松田薫、改訂第二版)(その1)(追記あり
評価に困る本である。
分厚くて大変とかじゃなくて、色々と判断が錯綜して、なんとも評価しづらいのである。
とりあえず、amazonにリンク をはっておく。改訂版も既に絶版のようであるが、古本では入手可能である。絶版に至った経緯も(初版については)書いてあるので、それも後で触れたい。
さて。
そもそも今回読んだ理由は、ABO FAN氏との「議論」の過程でABO FAN氏に読むことを薦められてしまったからである。当然、その議論の文脈で出てきた論点を中心に読んだわけで、普通にこの本に興味を持って読んだわけではない。なので、ここでもその論点を中心に紹介することになる。
が、まあそれではあんまりなので、とりあえず本書の内容をごくごく簡単に説明しておく。
これは、血液型と性格に関する心理学などの書物ではなく、「社会史」とタイトルについているように、「血液型と性格」がどのように着想され、概念が発展し、研究され、社会に受容されていったか、あるいはまたアカデミズムにおいてどのように否定されていったかを丹念に追ったルポルタージュ(あるいはノンフィクション)である。特に、戦前の動向が詳細に描かれており、血液型性格判断の歴史を知る上では貴重な文献と言えるだろう。労作である。
また、戦前の医学者はドイツに留学することが多かったが、彼らが何を学んできたかも描かれ、当時の海外の動向との関連もわかるようになっている。
というあたりに興味を持ち、深く知りたいと思う人は、以下に述べることを念頭に置いた上で是非読むべきだ。
まず一つ。著者による推測が随所に出てくるが、よくよく考えると根拠が不明なものがある。たとえば、前回のエントリで紹介した原来復の論文について、「A型とB型の兄弟のばあい、A型が良く、B型が不良という、まさにデュンゲルン博士がいっていた例にあたり驚き」と述べているのだが、デュンゲルンがどこでそう述べたのか明らかではない。松田氏のことであるから、デュンゲルンの論文を調べたのかもしれないが、この本からは明らかではない(無論私が見落としている可能性もあるし、当時の欧米でのB型が劣等という風潮のことを指しているのかもしれないが)。
次に、些細なことではあるのだが、あとで述べるようにそうとも言い切れない問題として、文体がある。どうにも読みにくいのだ。通常漢字にする単語が平仮名だったり(「当時」「思う」など)、文の構造が複雑で意味を取りにくかったり。これは、改訂第二版で追記されたらしい「補章」で特にひどくなる。
そして、その「補章」の問題であるが、これはこのエントリの主題ともなるので、これからゆっくり述べることにしよう。
いずれにしても、事実関係については相当資料を調べられたようで、そこのところは大変有用である。ただ、解釈が入るところは一筋縄ではいきそうにないのである。
ここではやや変則的だが、なるべくフェアに紹介をしたいと思うので、まずは「補章」の中の、大村政男氏について触れたところから見ていこう。その後、補章の他の話題、なぜ補章が書かれたのか、と進んでいきたい。
【松田氏から見た大村評】
ここでは主にp.352からの数ページの内容について見てみる。この前段に、溝口元氏(と『科学朝日』)に対する批判が述べられている。これは後で触れる。
まず、大村氏をこのように評する(漢数字は算用数字に改めた)。
最初に、原来復の論文が1916年に出版されたことについて、大村の言葉を引用している。どんな内容かというと、「すべて偉大な錯覚の歴史である」、「暗い年である」、原と小林の思いつきによって「血液型と性格」のベースが築かれたが、20世紀初頭に血液型が発見されてから1916年までに西欧ではなにも起きていないこと、それによって原と小林は最初のパイオニアになったこと、である。このような大村の言葉に対して、松田は「と、溝口どうよう血液型の歴史を消してしまう」と非難している。そして、原がデュンゲルンから血液型をならったことは原の論文にも書いてある、1916年は好景気なのに暗い年と解釈してしまう、と述べている。
この非難は正当だろうか。
私は大村の『血液型と性格』の新訂版しか持っていない。そのため、松田が上の文章を書くにあたって参照した文章とは異なっている可能性があることを考慮しつつ、大村の本を見てみたい。
まず「すべて偉大な錯覚の歴史である」は、血液型の歴史についてではない。「血液型と性格」の歴史について、大村流に述べたものである(大村『血液型と性格』p.174以降)。だから、原がデュンゲルンから血液型をならったことは関係ないだろう。そのことをもって「錯覚」と言っているのでないことは明白である。また、「暗い年である」というのも一種のレトリックで、大村はその前に、同年に夏目漱石が『明暗』の連載をはじめたこと、コレラが発生し流行したこと、そして漱石が死去し『明暗』が中絶したことを述べている。それを受けての「暗い年」である。だから、これは単なる表現の技法上の話であって、当時の社会の雰囲気について客観的に評したものでないことは明白である。
ついでに言えば、原の論文における「血液型と性格」の指摘は、前エントリで見たように、まさに思いつきの域を出ないものである。無論、それは論文の主旨がそこにはないからであり、そのことをもって原を批判するのは不適切だろう。むしろ、原を「血液型と性格」のパイオニアとして持ち上げてしまったために、原の本来の主旨とは異なる部分のみがクローズアップされたと言えるのではないか。原としても、それは不本意なのではないかと思う。
さて、次である。なるべくフェアにいきたいので、松田氏が指摘する点は、なるべく全て見ていこう。
旧日本軍における研究の紹介において、大村は、「平野と矢島の研究は、1925年7月、第7回日本医学会軍陣医学会で口頭発表されている」(p.76、前掲書)と書いている。これに対し松田は「平野たちの発表は、1926年4月2日灯台理学部で開かれた第7回日本医学会軍陣医学部会においてである。この年代の捏造は溝口もしている。どうも、大村と溝口は古川の研究開始より、平野たちの年代を早くしたい気持ちがあるようだ。」と批判する(「補章」だけでなく、本文の記述もその日付になっている)。
これについてはなんともわからないが、日本医学会のウェブページ を見ると、東京で医学会総会が開かれたのは大正15年(1926年)となっており、また大村と松田で一致している「第7回」を基準に取れば、これは大村の間違いの可能性が高い。ただ、「新訂」版でも修正されていないのだが、その事情はわからない。なにか理由があるのかもしれないし、単に修正し忘れただけなのかもしれない。
いずれにしても、これを「捏造」とは言わないのではないかと思うのだが。
次であるが、すぐ上で引用した松田の文章は、そのまま段落を変えずに次のように続いている。ちょっと長くなるが、全部引用した方が伝わると思うので、blockquoteで引用しよう。
最初の「自説の開始」については、たしかに『教育思潮研究』掲載の古川論文では「本年の初め頃から」と書いてあるし、また『血液型と気質』では「大正15年の秋から」と書いてある。つまり、古川の記述自体が矛盾している。また争点は古川がいつ実験を始めたかであり、論文の掲載日などと異なり、確認のしようがない。よほど状況証拠を調べあげない限りはなんとも言えない。そのような場合、よりメジャーな単行本の記述を信頼するのは当然ではないのだろうか。元が矛盾しているのであるから、それに従って述べたものを「捏造」と言われてはたまらないだろう。
また、その意図についてであるが、これも根拠が不明である。仮に「研究年代を早めた」のが事実であるとしても、それが平野らを意識したものかどうかはわからない。それに第一、早めたところで「大正15年の秋」では平野らよりも遅いことには変わりがなく、早める意味がわからない。なにをもって「実験」の最初とするのかで、古川の中でも混乱があったというあたりではないのだろうか。
さらに言えば、「気質検査表」であるが、まずp.39には載っていない。大村本ではp.84である。新訂版で位置が大幅に変わったのであろうか?また、これはそもそも古川の『血液型と気質』のp.74-75に載っているものである。「インストラクション」を除けば、『教育思潮研究』掲載の古川論文にも掲載されているものである。*1 大体、松田氏自身が、p.110で同様の表を掲載しているではないか。問題は、『血液型と気質』のほうでは、p.75に「大正15年の秋から」と書いてあることの是非であって、この表の存在自体は疑うべき点はない。それを「捏造」というのは「捏造」という言葉の定義があまりに松田氏独自のものと言わざるを得ないだろう。
次に血清の作成者であるが、これは松田氏が正しく(少なくとも古川を信じる限り)、北里伝染病研究所からの入手であると『教育思潮研究』掲載論文には書いてある。なぜ大村が古畑作成のものと思ったのかはわからない。ちなみに大村本では、松田による引用の直前に「古川が発明した試薬ではなく、」と入っている。なお、同じ段落で溝口元の『科学朝日』1987年7月号が引用されているのだが、この部分についての言及はなく、大村がどこかでそう思い込んだのかもしれない。
ついでに言えば、北里伝染病研究所の歴史(東大との様々な争いがあったことが本文で書かれている)とこの件についての関係がよくわからない。「歴史をしらず」ということに、どういう意味を込めたのであろうか。
最後に、「失脚」の原因であるが、先行研究無視がその要因なのであろうか?私はそのような主張は松田氏でしか見たことがない。本文のほうでもそのことは少し書いてはあるのだが、原や平野らの論文を引用しないことにカチンと来る人がいたとしても、それが原因で「失脚」などということはちょっと考えられない。これはむしろ、松田氏が「先行研究の引用」ということに極度の重きを置いていることの反映ではないか、と思う。なぜそう思えるかは、後に述べたいと思う(「補章」からそれが伺えるのである)。それから、前エントリのコメント欄でB研さんが指摘されたように、古川にとっては原の論文はあくまでも血液型についての論文であって、「血液型と性格(気質)」についての論文とは思っていなかったのではないか、と見る方が素直なようにも思える。軍の研究についてはどうなのかはよくわからないが…。
***
ええと、このペースでやっていては終わらんな。(^^;;
繰り返しますが、この松田氏の本は労作であり、戦前の「血液型と性格」に関する歴史を詳しく調べたい人は読むべきだと思います。
ただし、私の意図が、あくまでもABO FAN氏との「議論」の文脈の上にあるため、かなり批判的な紹介になってしまっていますが、価値のある貴重な文献であるというのが私の評価のベースですので、誤解なきようお願いします。
この先についてはまだ全然書いてないので、どう展開するかわかりませんが、(^^;;
少しづつ連載していきたいと思います。って明日が返却期限なんだよな。どうしよう。第二回はしばらく先になるかも(イキオイで明日やっちゃうかもしれませんが)。
(以下追記)
*1 このエントリをアップしたあとにちょっと気になってあらためて見てみたが、大村本に掲載されている検査表は『血液型と気質』から取ったもの、松田本に掲載されているのは1927年の古川の論文(2本とも表が掲載されている)である。微妙な差異がある。松田本掲載の表はA組(Active)P組(Passive)それぞれ9項目、それに対して大村本掲載の表は10項目づつで、最後の1項目が追加されている。また、9項目目も、松田本掲載の表で「主張」となっているところ(「自分ノ主張ヲ枉ゲナイ方」など)が、大村本掲載の表では「考ヘ」になっている。8項目目も、「他人ノ意見ニ」が「他人ニ」に変化している。いずれにしても、これは1927年の古川論文から1932年の『血液型と気質』の間に起きた変化であり、古川内部での矛盾である。大村に責任はない。
分厚くて大変とかじゃなくて、色々と判断が錯綜して、なんとも評価しづらいのである。
とりあえず、amazonにリンク をはっておく。改訂版も既に絶版のようであるが、古本では入手可能である。絶版に至った経緯も(初版については)書いてあるので、それも後で触れたい。
さて。
そもそも今回読んだ理由は、ABO FAN氏との「議論」の過程でABO FAN氏に読むことを薦められてしまったからである。当然、その議論の文脈で出てきた論点を中心に読んだわけで、普通にこの本に興味を持って読んだわけではない。なので、ここでもその論点を中心に紹介することになる。
が、まあそれではあんまりなので、とりあえず本書の内容をごくごく簡単に説明しておく。
これは、血液型と性格に関する心理学などの書物ではなく、「社会史」とタイトルについているように、「血液型と性格」がどのように着想され、概念が発展し、研究され、社会に受容されていったか、あるいはまたアカデミズムにおいてどのように否定されていったかを丹念に追ったルポルタージュ(あるいはノンフィクション)である。特に、戦前の動向が詳細に描かれており、血液型性格判断の歴史を知る上では貴重な文献と言えるだろう。労作である。
また、戦前の医学者はドイツに留学することが多かったが、彼らが何を学んできたかも描かれ、当時の海外の動向との関連もわかるようになっている。
というあたりに興味を持ち、深く知りたいと思う人は、以下に述べることを念頭に置いた上で是非読むべきだ。
まず一つ。著者による推測が随所に出てくるが、よくよく考えると根拠が不明なものがある。たとえば、前回のエントリで紹介した原来復の論文について、「A型とB型の兄弟のばあい、A型が良く、B型が不良という、まさにデュンゲルン博士がいっていた例にあたり驚き」と述べているのだが、デュンゲルンがどこでそう述べたのか明らかではない。松田氏のことであるから、デュンゲルンの論文を調べたのかもしれないが、この本からは明らかではない(無論私が見落としている可能性もあるし、当時の欧米でのB型が劣等という風潮のことを指しているのかもしれないが)。
次に、些細なことではあるのだが、あとで述べるようにそうとも言い切れない問題として、文体がある。どうにも読みにくいのだ。通常漢字にする単語が平仮名だったり(「当時」「思う」など)、文の構造が複雑で意味を取りにくかったり。これは、改訂第二版で追記されたらしい「補章」で特にひどくなる。
そして、その「補章」の問題であるが、これはこのエントリの主題ともなるので、これからゆっくり述べることにしよう。
いずれにしても、事実関係については相当資料を調べられたようで、そこのところは大変有用である。ただ、解釈が入るところは一筋縄ではいきそうにないのである。
ここではやや変則的だが、なるべくフェアに紹介をしたいと思うので、まずは「補章」の中の、大村政男氏について触れたところから見ていこう。その後、補章の他の話題、なぜ補章が書かれたのか、と進んでいきたい。
【松田氏から見た大村評】
ここでは主にp.352からの数ページの内容について見てみる。この前段に、溝口元氏(と『科学朝日』)に対する批判が述べられている。これは後で触れる。
まず、大村氏をこのように評する(漢数字は算用数字に改めた)。
1953年生まれの溝口の友人という、1925年生まれの大村の本(引用者注:『血液型と性格』のこと)の中身は、デタラメどころではない。絶句する。えらい言われようだ。以下、一つひとつ見ていこう。
原因は溝口どうよう、大村も資料をさがさず、原典は誤読し、故人への誹謗中傷どころか資料や年代までも捏造してしまっている。
最初に、原来復の論文が1916年に出版されたことについて、大村の言葉を引用している。どんな内容かというと、「すべて偉大な錯覚の歴史である」、「暗い年である」、原と小林の思いつきによって「血液型と性格」のベースが築かれたが、20世紀初頭に血液型が発見されてから1916年までに西欧ではなにも起きていないこと、それによって原と小林は最初のパイオニアになったこと、である。このような大村の言葉に対して、松田は「と、溝口どうよう血液型の歴史を消してしまう」と非難している。そして、原がデュンゲルンから血液型をならったことは原の論文にも書いてある、1916年は好景気なのに暗い年と解釈してしまう、と述べている。
この非難は正当だろうか。
私は大村の『血液型と性格』の新訂版しか持っていない。そのため、松田が上の文章を書くにあたって参照した文章とは異なっている可能性があることを考慮しつつ、大村の本を見てみたい。
まず「すべて偉大な錯覚の歴史である」は、血液型の歴史についてではない。「血液型と性格」の歴史について、大村流に述べたものである(大村『血液型と性格』p.174以降)。だから、原がデュンゲルンから血液型をならったことは関係ないだろう。そのことをもって「錯覚」と言っているのでないことは明白である。また、「暗い年である」というのも一種のレトリックで、大村はその前に、同年に夏目漱石が『明暗』の連載をはじめたこと、コレラが発生し流行したこと、そして漱石が死去し『明暗』が中絶したことを述べている。それを受けての「暗い年」である。だから、これは単なる表現の技法上の話であって、当時の社会の雰囲気について客観的に評したものでないことは明白である。
ついでに言えば、原の論文における「血液型と性格」の指摘は、前エントリで見たように、まさに思いつきの域を出ないものである。無論、それは論文の主旨がそこにはないからであり、そのことをもって原を批判するのは不適切だろう。むしろ、原を「血液型と性格」のパイオニアとして持ち上げてしまったために、原の本来の主旨とは異なる部分のみがクローズアップされたと言えるのではないか。原としても、それは不本意なのではないかと思う。
さて、次である。なるべくフェアにいきたいので、松田氏が指摘する点は、なるべく全て見ていこう。
旧日本軍における研究の紹介において、大村は、「平野と矢島の研究は、1925年7月、第7回日本医学会軍陣医学会で口頭発表されている」(p.76、前掲書)と書いている。これに対し松田は「平野たちの発表は、1926年4月2日灯台理学部で開かれた第7回日本医学会軍陣医学部会においてである。この年代の捏造は溝口もしている。どうも、大村と溝口は古川の研究開始より、平野たちの年代を早くしたい気持ちがあるようだ。」と批判する(「補章」だけでなく、本文の記述もその日付になっている)。
これについてはなんともわからないが、日本医学会のウェブページ を見ると、東京で医学会総会が開かれたのは大正15年(1926年)となっており、また大村と松田で一致している「第7回」を基準に取れば、これは大村の間違いの可能性が高い。ただ、「新訂」版でも修正されていないのだが、その事情はわからない。なにか理由があるのかもしれないし、単に修正し忘れただけなのかもしれない。
いずれにしても、これを「捏造」とは言わないのではないかと思うのだが。
次であるが、すぐ上で引用した松田の文章は、そのまま段落を変えずに次のように続いている。ちょっと長くなるが、全部引用した方が伝わると思うので、blockquoteで引用しよう。
古川学説はウソだといいながら、大村は古川の行為を見ぬけず、資料を捏造してしまう。古川は第二論文で、自説の開始について、なかなか激しい。一つひとつ見ていこう。
「この研究は私が本年の初め頃から学校の放課後少しづ々実験して居りました」(『教育思潮研究』一巻一輯1927年10月)
と、1927年からとかいた。が、著名になった1932年の単行本の『血液型と気質』では、「大正15年の秋から」(75頁)というぐあいに、1926年発表の平野論文を意識して、研究年代を早めたのだ。大村はこれに気づかず、単行本の文章を信じて、古川が1926年につくった気質検査表(39頁)という、存在しなかったものを捏造してしまっている。無いものをつくりあげる、大村の妄想グセは、古川の使った血清が北里伝染病研究所のものなのに、
「古畑種基(金沢医大教授)が作成した血清である」(91頁)
と、青山胤通の東大と対立した北里柴三郎の伝研の歴史をしらず、かってに捏造し、読者を混乱させる。さらに、
「不思議なことには、古川は、自分の前に三つの研究があったことを知らない。(略)軍隊内にあった大きな研究のことをその論文中に引用していないのは謎である」(78~9頁)
と、古川が先行論文無視で失脚したのに、なにもしらべず、「不思議」とか「謎」にしてしまう。全頁、こんな調子だ。
最初の「自説の開始」については、たしかに『教育思潮研究』掲載の古川論文では「本年の初め頃から」と書いてあるし、また『血液型と気質』では「大正15年の秋から」と書いてある。つまり、古川の記述自体が矛盾している。また争点は古川がいつ実験を始めたかであり、論文の掲載日などと異なり、確認のしようがない。よほど状況証拠を調べあげない限りはなんとも言えない。そのような場合、よりメジャーな単行本の記述を信頼するのは当然ではないのだろうか。元が矛盾しているのであるから、それに従って述べたものを「捏造」と言われてはたまらないだろう。
また、その意図についてであるが、これも根拠が不明である。仮に「研究年代を早めた」のが事実であるとしても、それが平野らを意識したものかどうかはわからない。それに第一、早めたところで「大正15年の秋」では平野らよりも遅いことには変わりがなく、早める意味がわからない。なにをもって「実験」の最初とするのかで、古川の中でも混乱があったというあたりではないのだろうか。
さらに言えば、「気質検査表」であるが、まずp.39には載っていない。大村本ではp.84である。新訂版で位置が大幅に変わったのであろうか?また、これはそもそも古川の『血液型と気質』のp.74-75に載っているものである。「インストラクション」を除けば、『教育思潮研究』掲載の古川論文にも掲載されているものである。*1 大体、松田氏自身が、p.110で同様の表を掲載しているではないか。問題は、『血液型と気質』のほうでは、p.75に「大正15年の秋から」と書いてあることの是非であって、この表の存在自体は疑うべき点はない。それを「捏造」というのは「捏造」という言葉の定義があまりに松田氏独自のものと言わざるを得ないだろう。
次に血清の作成者であるが、これは松田氏が正しく(少なくとも古川を信じる限り)、北里伝染病研究所からの入手であると『教育思潮研究』掲載論文には書いてある。なぜ大村が古畑作成のものと思ったのかはわからない。ちなみに大村本では、松田による引用の直前に「古川が発明した試薬ではなく、」と入っている。なお、同じ段落で溝口元の『科学朝日』1987年7月号が引用されているのだが、この部分についての言及はなく、大村がどこかでそう思い込んだのかもしれない。
ついでに言えば、北里伝染病研究所の歴史(東大との様々な争いがあったことが本文で書かれている)とこの件についての関係がよくわからない。「歴史をしらず」ということに、どういう意味を込めたのであろうか。
最後に、「失脚」の原因であるが、先行研究無視がその要因なのであろうか?私はそのような主張は松田氏でしか見たことがない。本文のほうでもそのことは少し書いてはあるのだが、原や平野らの論文を引用しないことにカチンと来る人がいたとしても、それが原因で「失脚」などということはちょっと考えられない。これはむしろ、松田氏が「先行研究の引用」ということに極度の重きを置いていることの反映ではないか、と思う。なぜそう思えるかは、後に述べたいと思う(「補章」からそれが伺えるのである)。それから、前エントリのコメント欄でB研さんが指摘されたように、古川にとっては原の論文はあくまでも血液型についての論文であって、「血液型と性格(気質)」についての論文とは思っていなかったのではないか、と見る方が素直なようにも思える。軍の研究についてはどうなのかはよくわからないが…。
***
ええと、このペースでやっていては終わらんな。(^^;;
繰り返しますが、この松田氏の本は労作であり、戦前の「血液型と性格」に関する歴史を詳しく調べたい人は読むべきだと思います。
ただし、私の意図が、あくまでもABO FAN氏との「議論」の文脈の上にあるため、かなり批判的な紹介になってしまっていますが、価値のある貴重な文献であるというのが私の評価のベースですので、誤解なきようお願いします。
この先についてはまだ全然書いてないので、どう展開するかわかりませんが、(^^;;
少しづつ連載していきたいと思います。って明日が返却期限なんだよな。どうしよう。第二回はしばらく先になるかも(イキオイで明日やっちゃうかもしれませんが)。
(以下追記)
*1 このエントリをアップしたあとにちょっと気になってあらためて見てみたが、大村本に掲載されている検査表は『血液型と気質』から取ったもの、松田本に掲載されているのは1927年の古川の論文(2本とも表が掲載されている)である。微妙な差異がある。松田本掲載の表はA組(Active)P組(Passive)それぞれ9項目、それに対して大村本掲載の表は10項目づつで、最後の1項目が追加されている。また、9項目目も、松田本掲載の表で「主張」となっているところ(「自分ノ主張ヲ枉ゲナイ方」など)が、大村本掲載の表では「考ヘ」になっている。8項目目も、「他人ノ意見ニ」が「他人ニ」に変化している。いずれにしても、これは1927年の古川論文から1932年の『血液型と気質』の間に起きた変化であり、古川内部での矛盾である。大村に責任はない。
『紋切型辞典』(フローベール、岩波文庫)
poohさん
が折りに触れ取り上げられる『紋切型辞典』。以前から気になっていたのだが、なかなか古本屋でお目にかかることもなく、読む機会がなかった。ところが、最近各種事情により(って血液型性格判断絡みですが)図書館に時々行くようになり、先日ふと「あ、図書館だったらあるんじゃないか?」と思って岩波文庫のコーナーにいったらちゃんとあったので借りてきた。図書館偉い。
内容については pooh さんのブログをお読みいただくのが一番だと思うので(「紋切型」タグを含むエントリを読むべし、ただし大量にある。とりあえず、平凡社版の『紋切型辞典』が載せられているエントリ「言葉の有効範囲 」にリンクをはらせていただきます)ここでは一言だけ。19世紀フランスに見られる紋切型の表現を、辞書風に集めて揶揄したもの。ただし、揶揄であると理解するのは結構難しい。実際、私にとっては理解できるものの方が圧倒的に少ない。まあ当時のフランスの文化を知らなければどうしようもない部分はあるのだが。
ただ、読み進めていくと、だんだん恐ろしくなる。笑える笑えないという話どころではない。文庫の解説にも書かれていたが、(ここに掲載されているかどうかは関係なく)自分の発言が紋切型ではないのかと思って何も言えなくなるのではないか、という恐怖である。それでも何かしらこうして書き連ねるわけではあるのだが、書きながら、気分は針のムシロである。
自分のことを棚にあげて(「心に棚をつくれッ!!」)世の中を見渡してみると、特にマスコミが気になる。何も言っていないのに、何か言った気になるのが「紋切型」なわけだが、そういう記事が実に多い。政治記事などはその典型だ(政局記事じゃなくてね)。形が決まっているだけに、その形に落とし込めれば何か言った気分になれる。これは本当に恐ろしい。
翻って己を眺めてみれば、やはりあちこちで使ってしまっているのだと思う。ニセ科学を批判するようなエントリだって、きっと「~では困ります」だの「~したほうがいいんじゃないだろうか」だの、誰でも言えるようなお決まりのセリフを使っているのだと思う。怖くて見返せないのだけど。
もっとも、紋切型の方がいい場合もおそらくある。典型的には挨拶だ。天気の話とか。内容のある話をお互いしたいわけじゃなくて、でもお互い相手のことを不快に思っているわけではないよ、というサインを送る必要がある場合はどうしたってある。フローベールは、書簡の中で、この紋切型辞典を「人前でこれさえ言えばよい、それだけで礼儀をわきまえた感じのよい人間になれる」(岩波文庫版p.305)と買いたそうだが、裏を返せばそれだけ「役に立つ」文例集であるとも言える。一種のマニュアル本、ハウツー本というわけだ。ただし、そういうものとして使っているという自覚が薄れるにつれ、その話の中身はおそらくどんどん空疎になっていく。
もう一つは、積極的な意味でである。読み終わってからボーッと考えていたのだが、ふと山田洋次の映画『学校』を思い出したのである。シリーズ第一作、夜間中学の物語だ。ラストシーンで仕事を終えて教師役の西田敏之らが学校の玄関から出てくる。時間は当然夜、あたりは真っ暗。そこに、雪が降ってくるのである。「あ、雪」。なんと白々しいセリフ、描写だろうか。しかし、これが、話の全体と妙にマッチするのだ。映画のパンフレットだったかどこかに書いてあった解説を読んで納得したのは、「このシーンで、山田洋次は、この映画を誰に観せたかったのかがわかる」ということ。つまり、紋切型を脱しようと「高尚」で「難解」な話をしても、それで話が伝わるとは限らない。というか、目的が全然違う。この映画は、紋切型を使いこなすことで、紋切型を紋切型でない展開に昇華させたとも言えるのだろう。
とまあ読むと何かと考えさせられる本である。なんだかエントリを書くのがますます遅くなりそうだ。いや、大事なのは表現形式ではなく思考の内容なのだとは思うけど、表現は内容に影響も与えるしねえ。怖い怖い。
なお、岩波版と平凡社版は、底本が異なるそうです。フローベールは若いころからこの「辞典」を作ることを考えていたが、まとまらないまま亡くなり(未完の『ブヴァールとペキュシェ』の第二巻となると晩年は構想されていたそう)、膨大な草稿が残され、それをどう解釈するか-一つの項目に対して草稿によって定義が異なる場合がある-で幾つか底本があるようです。時代とともに、その解釈も変わってきているらしいのだけど。
あと、オマケに一つ、引用しよう。
紋切型辞典 (岩波文庫)
紋切型辞典 (平凡社ライブラリー (268))
内容については pooh さんのブログをお読みいただくのが一番だと思うので(「紋切型」タグを含むエントリを読むべし、ただし大量にある。とりあえず、平凡社版の『紋切型辞典』が載せられているエントリ「言葉の有効範囲 」にリンクをはらせていただきます)ここでは一言だけ。19世紀フランスに見られる紋切型の表現を、辞書風に集めて揶揄したもの。ただし、揶揄であると理解するのは結構難しい。実際、私にとっては理解できるものの方が圧倒的に少ない。まあ当時のフランスの文化を知らなければどうしようもない部分はあるのだが。
ただ、読み進めていくと、だんだん恐ろしくなる。笑える笑えないという話どころではない。文庫の解説にも書かれていたが、(ここに掲載されているかどうかは関係なく)自分の発言が紋切型ではないのかと思って何も言えなくなるのではないか、という恐怖である。それでも何かしらこうして書き連ねるわけではあるのだが、書きながら、気分は針のムシロである。
自分のことを棚にあげて(「心に棚をつくれッ!!」)世の中を見渡してみると、特にマスコミが気になる。何も言っていないのに、何か言った気になるのが「紋切型」なわけだが、そういう記事が実に多い。政治記事などはその典型だ(政局記事じゃなくてね)。形が決まっているだけに、その形に落とし込めれば何か言った気分になれる。これは本当に恐ろしい。
翻って己を眺めてみれば、やはりあちこちで使ってしまっているのだと思う。ニセ科学を批判するようなエントリだって、きっと「~では困ります」だの「~したほうがいいんじゃないだろうか」だの、誰でも言えるようなお決まりのセリフを使っているのだと思う。怖くて見返せないのだけど。
もっとも、紋切型の方がいい場合もおそらくある。典型的には挨拶だ。天気の話とか。内容のある話をお互いしたいわけじゃなくて、でもお互い相手のことを不快に思っているわけではないよ、というサインを送る必要がある場合はどうしたってある。フローベールは、書簡の中で、この紋切型辞典を「人前でこれさえ言えばよい、それだけで礼儀をわきまえた感じのよい人間になれる」(岩波文庫版p.305)と買いたそうだが、裏を返せばそれだけ「役に立つ」文例集であるとも言える。一種のマニュアル本、ハウツー本というわけだ。ただし、そういうものとして使っているという自覚が薄れるにつれ、その話の中身はおそらくどんどん空疎になっていく。
もう一つは、積極的な意味でである。読み終わってからボーッと考えていたのだが、ふと山田洋次の映画『学校』を思い出したのである。シリーズ第一作、夜間中学の物語だ。ラストシーンで仕事を終えて教師役の西田敏之らが学校の玄関から出てくる。時間は当然夜、あたりは真っ暗。そこに、雪が降ってくるのである。「あ、雪」。なんと白々しいセリフ、描写だろうか。しかし、これが、話の全体と妙にマッチするのだ。映画のパンフレットだったかどこかに書いてあった解説を読んで納得したのは、「このシーンで、山田洋次は、この映画を誰に観せたかったのかがわかる」ということ。つまり、紋切型を脱しようと「高尚」で「難解」な話をしても、それで話が伝わるとは限らない。というか、目的が全然違う。この映画は、紋切型を使いこなすことで、紋切型を紋切型でない展開に昇華させたとも言えるのだろう。
とまあ読むと何かと考えさせられる本である。なんだかエントリを書くのがますます遅くなりそうだ。いや、大事なのは表現形式ではなく思考の内容なのだとは思うけど、表現は内容に影響も与えるしねえ。怖い怖い。
なお、岩波版と平凡社版は、底本が異なるそうです。フローベールは若いころからこの「辞典」を作ることを考えていたが、まとまらないまま亡くなり(未完の『ブヴァールとペキュシェ』の第二巻となると晩年は構想されていたそう)、膨大な草稿が残され、それをどう解釈するか-一つの項目に対して草稿によって定義が異なる場合がある-で幾つか底本があるようです。時代とともに、その解釈も変わってきているらしいのだけど。
あと、オマケに一つ、引用しよう。
無限小の [infinitésimal] 何だか分からないが、ホメオパシーと関係があるらしい。訳注もあるのだが、ハーネマンについてとフランスでも流行したということが書いてあるだけなので省略。これはもちろん分子一個すら残らないほど希釈することをもって「無限小」と言っているのだと思うが、無論当時は原子論が確立する前で、物質に構成単位があるとは思われていなかったため、「無限に薄い」状態があると考えられていたとしても不思議ではない。でもまあ無限に薄められているのがホメオパシーであるという共通認識は当時からあったということなのだろう。
紋切型辞典 (岩波文庫)
紋切型辞典 (平凡社ライブラリー (268))
- 学校 [DVD]

- ¥2,218
- Amazon.co.jp
「血液型と性格」の始祖、原來復
※ちょっとマニアックな血液型性格判断の歴史の話です。
日本で最初に「血液型と性格」を論じた論文は、原來復・小林榮の「血液ノ類屬的構造ニ就テ」(『醫事新聞』第954号、pp.937-941、1916年7月25日)であるとされる。そのコピーを某筋よりいただいたので、簡単に紹介してみよう。1ページ目のみ下に画像を出しておく。こんな感じで4ページ半の論文である(最後のページの下半分は別の論文になっている)。
この論文、血液型についての話がメインである。性格ではなくて、血液型とはどういうもので、調査した結果どういう血液型分布になったか、どのように遺伝するか、というものである。
もう少し詳しく言うと、血球と血清の型に違いがあって、凝集する/しない場合があること、デュンゲルンが348名の調査を行ったこと、親と子の血液型の関係(遺伝)、原らによる353名に対する血液型の調査の結果(A143名40.5%、B55名16.0%、O86名24.4%、AB69名20.0%)、どのように血液型を調査するか(何%のクエン酸ナトリウム(枸櫞酸ってクエン酸ですよね?)を用意して、とか)、の話が続く。
で、最後の方に、少しだけ性格との関係が議論されている。分量にして半ページちょい。引用してみよう。
文語体でわかりづらいと思うので、超意訳をしてみよう。
ま、雰囲気は伝わったと思う。で、「血液型と性格」(「性質」と言ってるけど)の関係について論じた部分はこれだけなのだ。
ちなみに「兄弟6人」ってのは、家族でどういう血液型になっているかを調べた例に出てくるもので、単に列挙してあるもののうちの一つである。具体的には、「父母共ニAニシテ子六人アリ、内五人Aニシテ一人零ナルモノアリ。」と言っているだけだ。
で、これをどう評価するか、が問題なわけだが…。
たしかに血液型と性格の関係について触れてはいる。触れてはいるが、「なんか関係ありそうだし、やってみたら面白いんじゃ?」と言ってるだけでもある。もちろん、B型はどうもこんな感じらしい、ということも言ってはいる。その意味では「最初」と言ってもいいのかもしれないが、調査してそう言ったわけではなく、血液型そのものを調べる過程のなかで、どうもそういう感じがする、ということを、ほとんど感想のような形で述べたにすぎないのだ。
だとすると、古川竹二が自分の論文で、この原・小林論文を引用していなくても、特に咎めたてられなければならないようなことではないのではないか、という気がする。古川の最初の論文は、血液型と性格(気質)の関係を調べる目的をもって行った実験の報告なのだから。
ついでに、日本人の血液型分布については、Bが多いということは既にデュンゲルンは知っていたらしい(アジア人というだけじゃなくて)。「我長野ニ於テハ他ノ處ニ比シ零ニ屬スルモノ少ナクシテ、Bニ屬スルモノ甚ダ多キコトナリ、日本人ニBヲ有スルモノ多キハ既ニ恩師フォンヂュンゲルン氏ノ唱ヘタル所ニシテ、氏ガ其教室ヲ訪問セル本邦人ニ就テ驗セル結果ニヨルモノナリ」と書いている。
さらについでに、今回のコピーで気になったことのもう一つなんですが。
下の画像を拡大してもらうとわかるのですが、左上に、後ろのほうのページのはしっこがハミ出て写ってます。この論文とは別のものなんだけど、その内容が…。「家庭ニ於テ日常番茶ヲ入レル操作」って。何が書いてあるのか、とっても気になる…。
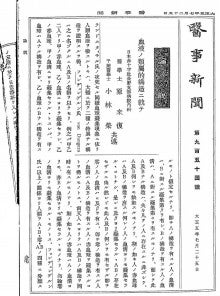
日本で最初に「血液型と性格」を論じた論文は、原來復・小林榮の「血液ノ類屬的構造ニ就テ」(『醫事新聞』第954号、pp.937-941、1916年7月25日)であるとされる。そのコピーを某筋よりいただいたので、簡単に紹介してみよう。1ページ目のみ下に画像を出しておく。こんな感じで4ページ半の論文である(最後のページの下半分は別の論文になっている)。
この論文、血液型についての話がメインである。性格ではなくて、血液型とはどういうもので、調査した結果どういう血液型分布になったか、どのように遺伝するか、というものである。
もう少し詳しく言うと、血球と血清の型に違いがあって、凝集する/しない場合があること、デュンゲルンが348名の調査を行ったこと、親と子の血液型の関係(遺伝)、原らによる353名に対する血液型の調査の結果(A143名40.5%、B55名16.0%、O86名24.4%、AB69名20.0%)、どのように血液型を調査するか(何%のクエン酸ナトリウム(枸櫞酸ってクエン酸ですよね?)を用意して、とか)、の話が続く。
で、最後の方に、少しだけ性格との関係が議論されている。分量にして半ページちょい。引用してみよう。
類屬ノ差異ニ依リ人ノ性質又其他ニ何カ特長ノ存在スルヤ否ヤニ就テハ未ダ全ク不明ナルモ、予等ガ實驗上聊カ奇異ニ感ジタル點ノミヲ左ニ擧グレバ、實驗中此人ハBニ非ズヤト思ハル丶人ハ多クハBナリキ、何如ナル人カト云ヘバ、身體ノ細ク優シサウナル人々ナリキ。曩キニ述ベタル兄弟六人アリテ内五人共ニA、一人ダケ零(引用者注:O型のこと)ナル家庭ニ於テAノ人々ハ同ジ様ナル性質ヲ有スルモ、零ナル一人ハ全ク異ナル性質ヲ有セリ。又或ル小學校ニテ兄弟一人ガAニテ一人ガBノモノアリテ、此二人ガ又甚シキ性質ノ相違ヲ有セリ、Aノ方ハ従順ニテ成績優等級ノ首席ヲ占ムルニ、Bノ方ハ粗暴ニシテ級ノ最下等ノ成績ヲ有セリ、以上ノ如キハ恐ク偶然ノ事柄ナランモ、然レドモ特ニ斯ノ如キ點ニ就テ調査セバ興味多キコトト信ズ。なお途中で改行を入れたが、直前「信ズ。」が丁度最下段に到達し、フォン~からが次の行になっていること、また段落が変更された場合に一文字下げが全体を通してなされていないことから、本来改行がない可能性もあるのだが、内容が若干変わるので、読みやすくするためもあり改行を入れた。なるべく原文ママに記載したが、一部旧字体になっていないところがあるかもしれない。そこはご容赦されたい。さらに、「フォンヂュンゲルン」については、フォンは左側に傍線、ヂュンゲルンは右側に傍線が引いてある(原文は縦書き)。ここではヂュンゲルンについて下線を引いた。
フォンヂュンゲルン氏ハ此人間ノ有スルABヲ直ニ動物ニ於テ實驗セルニ、Aナル構造ハ猿類ノ最高等ナル「シンパンゼン」(引用者注:チンパンジー)ニ發見セル外、他動物ニハ見ルコト能ハザリキ、然ルニBハ多クノ脊椎動物ニ於テ存在スルコトヲ發見セリ、尚同氏ハ人類ノ血球中多クノ猿ノ血淸ニ由リ凝集セラル丶モノアルコトヲ發見シ、之ニCナル名稱ヲ附セリ。勿論人類血液ノ生物學的構造ハ数種ニ止マラザルハ明ニシテ、若他ノ種々ナル動物ノ血淸ノ力ニ由リ檢セバ、尚多クノ類屬ニ分ツヲ得可ク、進化學上興味アル可キハフォンヂュンゲルン氏ノ既ニ唱フル所ナリトス。(完)
文語体でわかりづらいと思うので、超意訳をしてみよう。
血液型が違うと性格とかなんか違うかどうかってまだ全然わからんのやけど、みんなの血液型調べてたらさ、なんか妙なんだよね。「コイツBじゃね?」って思ったヤツって、たいがいB型なんだわ。で、なんか体が細くって優しそうなんだよね。さっき6人兄弟の話したじゃん?5人がAで1人だけOの。家ではAの5人はみんな似た感じなんだけど、Oのヤツだけ全然違うんだよね。それと某小学校にAとBの兄弟がいるんだけど、この二人がまた全然違うんだ。Aのほうは従順で成績優秀なんだけど、Bは粗暴でビリッケツ。まーだぶん偶然なんだろうけど、ちょっと調べてみたら面白そうじゃね?…失礼しました。
フォン・デュンゲルンてのが、動物の血液型を調べたんだけど、そしたら最も高等な猿であるチンパンジーだけがA型で、他はBだったんだって。あ、人の血の多くを凝集させちゃう猿の血清もあって、そいつをC型って名付けもしたんだ。ま、人の血液も数種類だけじゃないことは明らかだから、他の動物の血清使えばもっと色々分類できそうやし、進化を理解する上で重要そうだね、ってデュンゲルンは言ってるんだ。
ま、雰囲気は伝わったと思う。で、「血液型と性格」(「性質」と言ってるけど)の関係について論じた部分はこれだけなのだ。
ちなみに「兄弟6人」ってのは、家族でどういう血液型になっているかを調べた例に出てくるもので、単に列挙してあるもののうちの一つである。具体的には、「父母共ニAニシテ子六人アリ、内五人Aニシテ一人零ナルモノアリ。」と言っているだけだ。
で、これをどう評価するか、が問題なわけだが…。
たしかに血液型と性格の関係について触れてはいる。触れてはいるが、「なんか関係ありそうだし、やってみたら面白いんじゃ?」と言ってるだけでもある。もちろん、B型はどうもこんな感じらしい、ということも言ってはいる。その意味では「最初」と言ってもいいのかもしれないが、調査してそう言ったわけではなく、血液型そのものを調べる過程のなかで、どうもそういう感じがする、ということを、ほとんど感想のような形で述べたにすぎないのだ。
だとすると、古川竹二が自分の論文で、この原・小林論文を引用していなくても、特に咎めたてられなければならないようなことではないのではないか、という気がする。古川の最初の論文は、血液型と性格(気質)の関係を調べる目的をもって行った実験の報告なのだから。
ついでに、日本人の血液型分布については、Bが多いということは既にデュンゲルンは知っていたらしい(アジア人というだけじゃなくて)。「我長野ニ於テハ他ノ處ニ比シ零ニ屬スルモノ少ナクシテ、Bニ屬スルモノ甚ダ多キコトナリ、日本人ニBヲ有スルモノ多キハ既ニ恩師フォンヂュンゲルン氏ノ唱ヘタル所ニシテ、氏ガ其教室ヲ訪問セル本邦人ニ就テ驗セル結果ニヨルモノナリ」と書いている。
さらについでに、今回のコピーで気になったことのもう一つなんですが。
下の画像を拡大してもらうとわかるのですが、左上に、後ろのほうのページのはしっこがハミ出て写ってます。この論文とは別のものなんだけど、その内容が…。「家庭ニ於テ日常番茶ヲ入レル操作」って。何が書いてあるのか、とっても気になる…。