「人工宗教」でニセ(疑似)科学はなくせるか
ええと以前のエントリ「成果・効果・科学・思想(その1)
」「成果・効果・科学・思想(その2)
」の続き。主にコメント欄でのメカさんのコメントへの返事です。
メカさんの主張をまとめると、
(1)カルトや疑似科学をなくすのは不可能だから、人工宗教を作り、強制的に信じさせることで、社会問題を引き起こすようなカルトから人々を引き離すことができる(「無害化されたカルト」への信仰の強制)
(2)ニセ科学において、科学的事実を偽っていることは本質ではなく、またそのことを指摘することは無意味
(3)宗教は民主主義に反するものである
となるでしょうか。膨大なコメントは、いずれも上の二点から演繹されるもののようですので、ここに絞って論じます。
と言ってもまあ、私がモタモタしているうちに、zororiさんや黄金の口さんが論じてくださってしまったので、今更付け加えることもないのかもしれませんが、まあそれはそれとして。
先に(2)の方から。
「本質」の意味をどう捉えるかにもよるのですが、前半については同意するところ多、です。単に科学的に間違ったことを言うだけであればあれほど蔓延はしなかったでしょうし、また問題にもならなかったでしょう。一部の好事家のネタとなっていただけだと思います。
問題は後者です。何度も言っているのですが、実際問題として、私の周囲では、そのことを指摘することは大いに意味があります。またコメントいただいた他の方々からも、そのような声をいただきました。もちろん定量的に検証したわけではありませんので、グゥの音も出ないほど完璧に示すことなどできないわけで、メカさんが「いやオレは信じない」と言うのであれば、それ以上何かを言うことはありません。ただ私としては実際に効果があることを見ているし、明らかに逆効果であったこともないので、これからもこの路線で行くでしょう。メカさんの主張になんらかの説得力があれば参考にすると思いますが、観念的に「間違っている」と言われても、ねえ。
ですから、敢えてメカさんに好意的に言うなら、ここは理論が併存している状態であって、それぞれが検証する段階、ということになるでしょう。私のほうが間違っているかもしれません。もし間違っているとするなら、メカさんに徹底的に論破されるか、あるいは実践を積み重ねた結果、意味がないことを悟るかですが、現状では意味があるとしか思えませんので、メカさんがなにか私が忘れている重要なポイントを指摘するぐらいのことはしていただかないと、路線を変えることにはならないでしょう。
次に(1)について。
まあ色々言いたいことはあるのですが、そのあたりはきっとずっと昔から論考があるだろうし、コメント欄でも色々指摘していただいているし、詳細は私の能力を越えますので、簡単に少しだけ言うに留めます。
まず第一。人工宗教が必要だと言うのであれば、「水伝」でいいじゃん、というのがメカさんのコメント読んで最初に思ったこと。水伝、理想的じゃないですか?それ自体は完全に無害ですよ。ホメオパシーは人を殺すが水伝は人を傷つけません。まあ「御飯に声かけ実験」でクラスメイトの名前を書いて、クラスメイトを傷つけるぐらいのことはあるかもしれませんが。しかも、既に蔓延しています。メカさんがやるべきことは、水伝を教育指導要領に記載させ、すべての教科で水伝に基づいた授業をヤレ、ということなんじゃないですかね?違います?
第二。メカさんはこうコメントされています。
それから、当然、メカさんも私もその教育を受けることになるわけですよね。私は嫌です、そんな教育を受けるのは。メカさんはいいんですか?メカさんや、メカさんの子どもたちがそんな教育を受けることになって。
第三。日本はほんの60数年前まで、国家宗教を国民に強制してましたよ。その結果はどうだったでしょう(国家神道は宗教ではなかった、とかいうのはナシですよ)。
第四。水伝のようなニセ科学の問題は色々ありますが、他のニセ科学への耐性を低くしてしまうことも問題の一つとして挙げられるでしょう。水伝が入口になって、たとえばホメオパシーにはまったり。人工宗教だって、同じ機能を持つのではないかしらん。
第五。第二の最後の文章と絡みますが、いつ誰がどの時点で誰を人工宗教の信者にすべきかを判断するのでしょうか。あるいは信者でなくてもよいと判断するのでしょうか。確認しておきますが、そんな社会になったら、メカさんも私も、間違いなく人工宗教を信じなければ危険人物扱いですよ。
関連しますが、ある子どもが科学的思考に向かないかどうかは、いつ誰が判断するのでしょうか。おそらくは現場の教師がするしかないのだと思いますが。教育によって科学的思考ができるようになる子どもだって大勢いるでしょう。教育を放棄しておいて、向くだの向かないだの判断することが果たして人として正しいことなのでしょうか(価値観の問題です)。それに、そんな重大な判断ができるほど人を見る目のある教師が一体世の中どれだけいるというのでしょうか。
(3)について。
これはまあ蛇足です。蛇足ですが、メカさんの「議論」の姿勢が伺えるので、あえて独立した項目にしてみました。
私は宗教一般が民主主義に反するだとか、国民を騙すものだなどと言ってはいません。むしろ、そうではない、ということは言ったつもりなんですが。ところが、たとえばメカさんはこうおっしゃいます:
というわけで、(2)の論点については、メカさんは頑なに御自分の意見を変える気はないようですし、こちらとしても客観的に示せるようなものがあるわけではありませんので、これ以上は議論しても仕方がないでしょう。希望を一つ挙げるならば、ぜひ、御自分で、色々な方と-特にニセ科学をなんとなく信じてしまっているような人々と-直接話をしていただきたいと思います。ネット上じゃなくて、ね。ネット上だと、また少し話が変わると思うので。書いたものが残っちゃいますから、意固地にもなるだろうし(このことはpoohさんのところでも書きました)。
(1)の論点については、とりあえずざっと気付くだけでもこれぐらいの問題点があります。民主主義については、原理的に最善だと思っている人はあまりいないでしょうが、しかし知られているなかでは最善であろうというあたりが皆の合意するところではないでしょうか。そして、人工宗教がそれを解決するとは思えない、と。
あとは本当に蛇足ですが、返答が必要かなと思われるコメントについてだけ、レスしておきます。zororiさんや黄金の口さんのコメント内容とかぶる点が多々あると思いますが、ご容赦ください。
なんというかな、児童虐待の言い訳に「これはしつけだ」というのがよくあるわけですが、それに対して「それはしつけではない」と批判するのが意味がない、と言うのと同じに聞こえますね。
あなたは、
あなたが疑うのは自由ですよ。私が実感していることをメカさんに伝えられないのは残念ですが、しかし逆にメカさんの言葉に私は説得力を全く感じないので。
***
なんというのかな、そこまで我々が物を考えていない人間と思われているのかと思うと、悲しくなりますね。
メカさんの主張をまとめると、
(1)カルトや疑似科学をなくすのは不可能だから、人工宗教を作り、強制的に信じさせることで、社会問題を引き起こすようなカルトから人々を引き離すことができる(「無害化されたカルト」への信仰の強制)
(2)ニセ科学において、科学的事実を偽っていることは本質ではなく、またそのことを指摘することは無意味
(3)宗教は民主主義に反するものである
となるでしょうか。膨大なコメントは、いずれも上の二点から演繹されるもののようですので、ここに絞って論じます。
と言ってもまあ、私がモタモタしているうちに、zororiさんや黄金の口さんが論じてくださってしまったので、今更付け加えることもないのかもしれませんが、まあそれはそれとして。
先に(2)の方から。
「本質」の意味をどう捉えるかにもよるのですが、前半については同意するところ多、です。単に科学的に間違ったことを言うだけであればあれほど蔓延はしなかったでしょうし、また問題にもならなかったでしょう。一部の好事家のネタとなっていただけだと思います。
問題は後者です。何度も言っているのですが、実際問題として、私の周囲では、そのことを指摘することは大いに意味があります。またコメントいただいた他の方々からも、そのような声をいただきました。もちろん定量的に検証したわけではありませんので、グゥの音も出ないほど完璧に示すことなどできないわけで、メカさんが「いやオレは信じない」と言うのであれば、それ以上何かを言うことはありません。ただ私としては実際に効果があることを見ているし、明らかに逆効果であったこともないので、これからもこの路線で行くでしょう。メカさんの主張になんらかの説得力があれば参考にすると思いますが、観念的に「間違っている」と言われても、ねえ。
ですから、敢えてメカさんに好意的に言うなら、ここは理論が併存している状態であって、それぞれが検証する段階、ということになるでしょう。私のほうが間違っているかもしれません。もし間違っているとするなら、メカさんに徹底的に論破されるか、あるいは実践を積み重ねた結果、意味がないことを悟るかですが、現状では意味があるとしか思えませんので、メカさんがなにか私が忘れている重要なポイントを指摘するぐらいのことはしていただかないと、路線を変えることにはならないでしょう。
次に(1)について。
まあ色々言いたいことはあるのですが、そのあたりはきっとずっと昔から論考があるだろうし、コメント欄でも色々指摘していただいているし、詳細は私の能力を越えますので、簡単に少しだけ言うに留めます。
まず第一。人工宗教が必要だと言うのであれば、「水伝」でいいじゃん、というのがメカさんのコメント読んで最初に思ったこと。水伝、理想的じゃないですか?それ自体は完全に無害ですよ。ホメオパシーは人を殺すが水伝は人を傷つけません。まあ「御飯に声かけ実験」でクラスメイトの名前を書いて、クラスメイトを傷つけるぐらいのことはあるかもしれませんが。しかも、既に蔓延しています。メカさんがやるべきことは、水伝を教育指導要領に記載させ、すべての教科で水伝に基づいた授業をヤレ、ということなんじゃないですかね?違います?
第二。メカさんはこうコメントされています。
> その時に、無害な疑似カルトを用意しておいたからってそちらに行くとは限らないでしょう?それぞれの宗教に入信するのを認めるのであれば、危険なカルトに行く可能性はいくらでもあるでしょう。現状に比べてそんなに変わるとは思えませんが(むしろ増えたっておかしくない)。江原啓之にしろ、たしか麻原彰晃もだったと思いますが、いろいろな宗教を渡り歩いた挙句、自分で宗教開いてカルト化するパターンって結構ありますよね(江原をカルトと呼ぶかどうかはともかく)。だから、認めるのであれば、有効性はないと言ってもいいでしょう。
だから強制的に教育するのだ、といってるのだが。放っておくのが問題なんだよ。もちろん国家宗教の教育を受けた上で、それに上乗せする形でそれぞれの宗教に入信するのは認めざるを得ないけどね。
それから、当然、メカさんも私もその教育を受けることになるわけですよね。私は嫌です、そんな教育を受けるのは。メカさんはいいんですか?メカさんや、メカさんの子どもたちがそんな教育を受けることになって。
第三。日本はほんの60数年前まで、国家宗教を国民に強制してましたよ。その結果はどうだったでしょう(国家神道は宗教ではなかった、とかいうのはナシですよ)。
第四。水伝のようなニセ科学の問題は色々ありますが、他のニセ科学への耐性を低くしてしまうことも問題の一つとして挙げられるでしょう。水伝が入口になって、たとえばホメオパシーにはまったり。人工宗教だって、同じ機能を持つのではないかしらん。
第五。第二の最後の文章と絡みますが、いつ誰がどの時点で誰を人工宗教の信者にすべきかを判断するのでしょうか。あるいは信者でなくてもよいと判断するのでしょうか。確認しておきますが、そんな社会になったら、メカさんも私も、間違いなく人工宗教を信じなければ危険人物扱いですよ。
関連しますが、ある子どもが科学的思考に向かないかどうかは、いつ誰が判断するのでしょうか。おそらくは現場の教師がするしかないのだと思いますが。教育によって科学的思考ができるようになる子どもだって大勢いるでしょう。教育を放棄しておいて、向くだの向かないだの判断することが果たして人として正しいことなのでしょうか(価値観の問題です)。それに、そんな重大な判断ができるほど人を見る目のある教師が一体世の中どれだけいるというのでしょうか。
(3)について。
これはまあ蛇足です。蛇足ですが、メカさんの「議論」の姿勢が伺えるので、あえて独立した項目にしてみました。
私は宗教一般が民主主義に反するだとか、国民を騙すものだなどと言ってはいません。むしろ、そうではない、ということは言ったつもりなんですが。ところが、たとえばメカさんはこうおっしゃいます:
> ロジックとしてはとても似てますよね。一般大衆など幸せに騙してやればいいのだ、ということですから。メカさんの言う人工宗教が国民を騙すものだ、と言っているのであって、宗教一般について「騙す」ものだなどと勝手に広げないでくださいね。どうもメカさんには、私(FSM)という人間はこう考えているはずだ、というのが抜き難くあって、それに合う文言が表れると、一部を切り取ってそれが全体であるかのように言う癖があるようです。もちろん先入観なしに物事を見ることはできませんから、メカさんが、FSMというのはこういう人間だろう、と予想するのは別に問題ないのですが、せめて書かれたことぐらいは読み取って欲しいなあと思います。それともそんなに読み辛い文章ですかね?
宗教を「騙す」という概念でしか捉えられないところに、あなたの思考の限界というか偏りがあるように思うね。たとえば精神障害者に対して抗うつ剤など薬で解決するというのは、人によっては強引な手法と感じることもあるだろう。精神分析みたいな手法が正しいと信じられた時代もあったよね。心の問題なのだから心の中の悩みを時間をかけて解きほぐすのが正しいのだ、と。
というわけで、(2)の論点については、メカさんは頑なに御自分の意見を変える気はないようですし、こちらとしても客観的に示せるようなものがあるわけではありませんので、これ以上は議論しても仕方がないでしょう。希望を一つ挙げるならば、ぜひ、御自分で、色々な方と-特にニセ科学をなんとなく信じてしまっているような人々と-直接話をしていただきたいと思います。ネット上じゃなくて、ね。ネット上だと、また少し話が変わると思うので。書いたものが残っちゃいますから、意固地にもなるだろうし(このことはpoohさんのところでも書きました)。
(1)の論点については、とりあえずざっと気付くだけでもこれぐらいの問題点があります。民主主義については、原理的に最善だと思っている人はあまりいないでしょうが、しかし知られているなかでは最善であろうというあたりが皆の合意するところではないでしょうか。そして、人工宗教がそれを解決するとは思えない、と。
あとは本当に蛇足ですが、返答が必要かなと思われるコメントについてだけ、レスしておきます。zororiさんや黄金の口さんのコメント内容とかぶる点が多々あると思いますが、ご容赦ください。
> 受容者は、自覚的にある思想を持って何かを信じているわけではないですよね。ですから、自覚はしていないけど、「求めている」ことの根底を分析すると、おそらく共通するものがある、ということですよね?それは私も同意しています。
その点が俺と決定的に考え方が違う。自覚はしていなくても、人間が疑似科学やカルトや宗教に求めているものには一つの普遍的な存在があると俺は考える。ただこれまでその存在が人間には断片的にしか見えていないので、様々な形(キリスト教だったり、水伝だったり、オウム真理教だったり)をとっているだけだ。
人工宗教の構築という考えと疑似科学批判の接点として「疑似科学を信奉する人の心理」が見えるわけだ。俺はそういうとらえ方をしているので、そういう表現になる。だから疑似科学との接点だけに話を限定するならばあなたの定義でも問題ない。ただ、そこに限定する限り疑似科学の問題は解決できないというのが俺の考えなので、そういう話にはしたくない。
(中略)
> だから、直接的には受容者がどういう心理的メカニズムで信じるに至ったか/信じ続けるか、という問題の分析が必要だし、ええとよくわからない。「信じるモノ、本体」というのは、具体的には何をイメージしています?「水伝」だったら、江本の主張(あるいは思想)ということでしょうか?受容者側についてではなく。さっきまでは受容者側の話だと思っていたので、混乱しております。下を見ると、やっぱ受容者側のことを問題にしているようにも見えるけれど。
そのアプローチを続けたのに成果が上がらないのだから、アプローチを変えるべきで、信じるメカニズムではなく、信じるモノ、本体に焦点を当て、本体の全貌を描き出すことが、俺のいう「思想に切り込む」ということ。
> 後者については思想と言ってもいいのだとは思いますが(そして私が「恐るべきイデオロギー」などと言っているのはこちらに当たります)。ということであるならば、「信じるモノ、本体」というのは、受容者側に蔓延するものの見方のようなものになると思いますが…。いや「信じるモノ、本体」という言葉がよくわからないのですが、受容者側において、受容者が受容するに至る過程の本質のようなものを指しているのでしょうか?江本のような発信元の主張でもなく、個別の受容プロセスのことでもなく。
そういう分け方だと俺がいう思想の本質は「後者」になるだろうね。
何が「ちゃんとした世界観」なのかって話だよねぇ。あなたにはあなたなりの「ちゃんとした世界観」があるのだろうけど、それがどうしてそんな自信満々に唯一のものだと信じられるのか。なにをもって「ちゃんとした」かは深い問題だと思いますよ。ただ、自分で考え判断する力であるとか、そのためには世界をどう見るべきか、とかは自と定まってくるのではないでしょうか(漠然としてではあれ)。少なくとも、嘘であることがわかっているものを押しつけるのがいいことであるとは思えません。
宗教が民主主義に反するというのはおそらく、教義や教祖に盲従し個人の意見を持たない人間が増える事を危惧しているのだと思う。しかし現実的には大部分の人間は自分の意見を積極的には持っていない。他人や世論やメディアに盲従しているだけだ。だから大部分の人間が盲従することそれ自体は民主主義に致命的だとは俺は思わない。これも同意です。というか、そういう話をしていたつもりだったのだけど。
問題があるとすれば宗教やカルトは自己変革の要素を持たないか非常に乏しいことだ。その点自然科学は極めて優れているよね。だからあなたは民主主義と自然科学が好きなのだろう。俺も好きだ(笑)。しかしキリスト教だって長い年月がかかったがある程度自己変革を行ってきていると思う。自己変革の要素を持たないことが宗教の本質ではないと俺は考える。
宗教がカバーする範囲を法律できっちり制限し、その外側にはみ出さないようにすれば、危険性はかなり減るはず。ここが問題。既に法律的には宗教団体の定義はあるわけですが(税制上の問題として)、そういう話をしたいわけではないのですよね、きっと。とすると、個々人の思想に法律の網をかけようというわけで、それがメカさんの言う人工宗教のことなのかもしれませんが、そんな世の中私ゃゴメンですよ。
繰り返しになるけれど大部分の人間は論理的思考も科学的思考も客観的思考も出来ないし、望みもしない。そしてそういう状態で人類はここまで来たのだから、それでいいと思うよ、俺は。出来ないものを無理に「すべきだ」とやらせたところで、出来ないことには変わりないし、苦痛が残るだけだ。出来る人間だけがやればいいし、今までもそうだった。だから、出来る人が少しづつでも増えればいいのでは?それに、誰が出来る出来ないを判別するのですか?大体、そんな世の中になったら、メカさんが「できる」側にまわらせてもらえるとはとても思えないですよ(私も含めて、ね)。
フランス革命が起きたとき、それまで政治を引き受けてきた王様も、民衆に政治なんて出来るわけがない、危険すぎると思ったんじゃない?(笑)麻生太郎だってそう思ってたんじゃないかな。いや、いっそう強く思っているかも。
まあ実際に強制するとかしないとかの話の前段階として、そういうもの(人工的な宗教)がどういうものになるかどうか、それが本当に人の心の一定部分をカバーできるか、などを研究する価値はあると思うけどね。それとも遺伝子組み換えみたいに、研究すること自体が危険であり許し難い神への冒涜という考え?いや、研究すればいいのではないでしょうか。というか、ありそうな気がするけど。そういう発想に私は賛成はしかねますが、研究したい人は研究すれば?というだけです。
> 表れ方は多様ですから、メカさんの問題意識にある受容者の下半分の人々もいれば、なんとなく信じる人もいるし、普通の科学の結果と同列のものとして捉える人もいる。人工宗教がworkするとはとても思えませんが、まあその通りだと思いますよ。
カルトや疑似科学は人間の心を研究する良い材料だと思うよ。精神障害者を研究することで健常者の脳の働きも解明されてきた。極端なものの方が研究しやすいはず。人工宗教を作ってそれを国教とするにしても、長い時間がかかる。50年とか100年とかかかるんじゃなかろうか。とりあえずそのための研究は始めるべきだと思う。始めないことには永久に始まらない。その過程でやっぱダメだという結論になったなら、それはそれでいいわけだよ。
> > 疑似科学を信じる理由や状況は様々であり一筋縄で分析することは難しい「だけ」に注力しているつもりはなくて、問題意識としては持っているのだけれども、難しいからとりあえず放置、ときどき思い出したように論ずる、という感じかな。ある程度まとまった論考であれば、触れられているとは思いますけどね。それに、ニセ科学の文脈とは別に、そういう論考をされている方もいるようですし。やるべきだ、と思った方がやっていただくのが一番なんですよ。私も、私がやるべきだと思ったことをやっているわけで。
> ということと矛盾するとは思いません。たぶん、メカさんと私は、似たようなことを考えているのだと思います。
難しいからそこには触れないで差し迫ったことにだけ注力しようと考えるか、難しくてもいつか始めなければ始まらないと考えるかの違いかな。
> かなり誤解されていると思いますが、ニセ科学においては、カルト的主張は誤った科学的「事実」によって根拠づけられています。ですから、「こじつけ」ではなく、彼らの主張の重要な部分になっているのです。いやいやいや、彼らは同じ意味で使おうとしているのですよ。たとえば(「水伝」ばかりで申し訳ないけど)江本の本を読めば、波動の説明は音叉の共鳴から入るし、現代量子力学で説明可能だとか言っているし。もちろん彼らの科学の理解は決定的に間違っているので(書かれたものを読む限りは)、それをもって彼らが考えている「科学」が我々のものと違うと主張することはできる。でも、それに一体何の意味があるでしょう?
耳にたこができるほど聞いてるんだけど、なぜ疑似科学側がいう「科学的事実」が、自然科学でいう「科学的事実」と同じであり、自然科学の尺度で測れるものであると思うのだろう。
そういうと「彼ら(疑似科学支持者)自身が、科学だといってるじゃないか」という答えが返ってくると思うのだけど、なぜ彼らが考える「科学」と疑似科学批判者が考える「科学」が同じものでなければならないのか。
もちろん混同すると社会に多大な混乱を巻き起こす事柄はある。医師とか医薬品とかは重大な問題を引き起こすから、自称してはならないと法律で規制されているわけだ。しかし「科学」という言葉を自由な定義で使うことは、現在の法律では規制されていない。つまり社会にとってそこまで重大な事だとは考えられていないわけだ。むしろ規制してしまうことの問題の方が大きいと考えられているのだろう。
そういう現実を無視して、「科学」という言葉を自分たちの考える以外の意味で使うのはまかり成らんという主張は、神という言葉を自分たちがあがめ奉る神以外に使うのはけしからんと主張するのと同じだと思うよ。
なんというかな、児童虐待の言い訳に「これはしつけだ」というのがよくあるわけですが、それに対して「それはしつけではない」と批判するのが意味がない、と言うのと同じに聞こえますね。
> そして、こうやって水伝を批判することが、どうしてそう捉えられるのか不思議で仕方ありません。
> > それを争点にして世間にその是非を問い、審判を仰がなければならない
> のプロセスの一つであるわけです。
批判の仕方が正しくないといってるのだが。水伝の思想(水の結晶に善悪の判断を委ねること)が不健全と思うなら、その点を批判すべきで、科学という言葉を自分たちの専売特許というか既得権のごとく捉えて、水伝にその使用を禁じるのは、正攻法な批判ではない。宗教が同じような主張をやったらあなたはどうするのか。人類の誕生については我々の宗教しか語ってはならない、とか。
あなたは、
水伝が社会的に有害であると主張するなら、それを争点にして世間にその是非を問い、審判を仰がなければならない。自分が「水伝は有害だ」と考えるからと言って、何とかダメージを負わせる手段はないものかと本質的な問題点でない部分でスキャンダルを探して社会的に抹殺を画策するというのは、正当な手段ではない。自分の判断が間違っていたらとんだ独善ではないか。と言ったのであって、それに対して、(1)科学的に間違っているということは本質に含まれる、(2)科学的に間違っていることを流布させようとすること自体問題を孕んでいる(社会の周辺であれば問題視されなかったであろうが、教育現場などでの蔓延を放置するわけにはいかない)、(3)科学の部分だけではなく、道徳(水伝の場合であれば)その他においても問題が多い、ということを言ったつもりです。ですから、これがまさに「争点にして世間にその是非を問い、審判を仰」ごうという過程の一つなわけです。過程の一つですから、我々が間違っている可能性は当然折り込み済みです。あなたの視点からは我々の批判が間違っているということになるのでしょうが、それはあくまでもあなたの視点です。あなたの判断と違うことをもって独善のように言うのはおかしくありませんか。
> 水伝の主張自体が、既存の科学にダメージを与えるものです。科学が宗教にダメージを与える可能性はあります。宗教に限らず、いろいろなものにダメージを与え得ます。善意にだってダメージを与えます。だからこそ、客観的に検証されるというプロセスが必要なわけで、そこが科学とそれ以外を分ける分岐点でしょう。この社会において科学を進歩させることに合意するということは、人類の思惑とは異なる結果になることをも(検証されれば)受け入れざるを得ないということを含意しているのです。それにですね、科学は常に攻撃にさらされてきたのですよ。ガリレオを例に出すまでもなく。それを、客観的な検証という強力な武器をもってはね返してきたわけです。
そんなこと言い出したら、科学が宗教にダメージを与えることも配慮しなければならなくなる。つくづく思うんだよね。疑似科学批判者というのは逆の立場に立たされて、自分たちが今使っている同じ武器で自分が立ちが攻撃されたらどうするかを考えていない。
疑似科学番組を減らすようにメディアに圧力をかける話についても、どこかの宗教が数にものをいわせてテレビ局に逆のことをやった場合、あなたはそれを国民の意見の反映だと肯定するのだろうか。誰にだって抗議する権利はあります。だから、有限の資源である電波については法律で規制がかかるわけだし、なるべく公権力の介入を招かないようBPOのような自主的な団体によって自制させることも重要なわけです。科学に反することを実行する権利は誰にだってあるのですよ。そういう人が多数になれば、国家としてそうすることだって実際問題できるわけですよ。肯定するとかしないとかじゃなくて、それが現実でしょう?
> 繰り返しますが、科学的に誤っている部分も、彼らの主張の重要な一部です(図の右側)。そこを指摘することは、奇手で妙手でもないし、邪道でもありません。ええ、江本の本をいくらかでも読めば、科学的な説明は彼らの根本を成していることはすぐわかりますし、またいままで話しをしてきた人々の反応からも、ゆるく受容している(そして多くはこういう層)人々は、科学的に根拠があるから受容してきたということが実感としてあります。
どうしてそう考えるのか俺には理解できない。少なくともあんたの一連の文章には説得力を感じない。強弁しているだけに見える。あなた自身、自分の説明に説得力を感じているの?
あなたが疑うのは自由ですよ。私が実感していることをメカさんに伝えられないのは残念ですが、しかし逆にメカさんの言葉に私は説得力を全く感じないので。
> その疑問はもっともで、その影響についても論文中では指摘されています。実際にどれくらい影響があるかの分析は、残念ながら書かれていませんけれども。私じゃないですよ(と言ったはずだけどなあ)。心理学者の論文です。それに、そこは論文の趣旨の本質じゃないし、詳しい紹介はいずれしたいとも述べたはずです。
ん?あなたが統計をとったんじゃないの?まあ、どうでもいいけど、そういう自分にとって不都合な面を(俺から突っ込まれるまで)言わないという姿勢はあまり感心できないな。疑似科学支持者が不都合な実験データを隠して、都合の良いデータだけを並べるのと変わらない。
***
なんというのかな、そこまで我々が物を考えていない人間と思われているのかと思うと、悲しくなりますね。
『藤子・F・不二雄大全集 エスパー魔美 1』(藤子・F・不二雄)
今週はとにかくメチャメチャに忙しくて(間に出張も挟まった)更新もままならなかったのですが。コメントいただいた皆様、ありがとうございます。ちょっと考える気力がまだ起きないので、明日以降、御返事したいと思います。特にメカさんのコメント群については、新しいエントリを作ろうと思っています。しばらくお待ちください。すいません。
で、だいぶ時間がたっちゃいましたが、藤子・F・不二雄大全集の8月分配本に含まれている『エスパー魔美』について、ちょっとご紹介。
エスパー魔美、小学生のころだったかな、たぶん高学年だったと思いますが、初めて読みまして。色々と学ぶところが多かったのです。主人公の魔美と高畑くんが中学生という設定も大きかったのだと思いますが、自我に目覚める年頃だけに、作者としては、まるで自分の娘に語るように、世の中というものを語りたかったのだと思います。
そういうわけで、当時の私にとっては「ちょっと大人」の中学生が展開するお話に、「ああ、大人って、色々ややこしくて大変だな」と、心の奥深くに染み込んでいったのです。
今回、その中でも特に心に残っている作品が掲載されていました。ちょっとだけ引用します。筋がわかってしまうとアレなので、私が感銘を受けたところを抜き書きするような感じで(その分面白さは伝わらないと思いますが、まあそれは実物を読んでもらうということで)。
p.140 (「くたばれ評論家」)より。カッコ書きは引用者による。
この後、魔美は剣に抗議しようとして剣の家に入り込む。p.150から。
家に戻り、家族との会話。
また、ネット上に限りませんが、批判というものをどう考えるか、という意味でも、重要な視点を提供してくれていると思います。公権力の介在を排除しようとすれば、私的自治のなかで、たとえどれだけ精神的につらい思いをしようとも(程度問題はあるわけですが)、そのこと自体はあり得るものとして受けとめなければならない。もちろんそれは反論する自由もあるからこそ、なわけですが。ニセ科学への批判やそれへの批判についても同様でしょう。
さて、次。これ、話としてはポジティブな物言いになっていますが、「信じる」ということの本質を言い当てていると思います。そして、そのネガティブな面が、ニセ科学やオカルトを信じる心性と実は同じである、ということも。
p.322(「魔女・魔美?」)より。
島本和彦にも同種の言葉があって、たとえば「わかってはいるが、わかるわけにはいかん!!」とか、「正義より友情だ」みたいな(後者はうろ覚え。友情じゃなかったかな。すいません)感じなんですが、生きる上では確かに理屈より大事なものはあるんですよね。それが、いい方向に向かうのであればいいんですが…。
さて、ついでにもう一つ。エスパーであるということが、世の中にとってどういう意味を持つか。
p.81 (「勉強もあるのダ」)より
『ドラえもん』に限らず、藤子作品は大人になってから読み返すとまた深い理解に到達することが多いのですが、『エスパー魔美』はもともと中学生が対象で、しかも各話のページ数も結構あり、丁寧に書かれていることが多いのですよね。そういうわけで、今読んでも、なにかと勉強になるのです。それ以上に面白いわけですが。ついでにこれが「単純所持」あたるか、という論点もあるのですが、それはまたそれとして。
で、だいぶ時間がたっちゃいましたが、藤子・F・不二雄大全集の8月分配本に含まれている『エスパー魔美』について、ちょっとご紹介。
エスパー魔美、小学生のころだったかな、たぶん高学年だったと思いますが、初めて読みまして。色々と学ぶところが多かったのです。主人公の魔美と高畑くんが中学生という設定も大きかったのだと思いますが、自我に目覚める年頃だけに、作者としては、まるで自分の娘に語るように、世の中というものを語りたかったのだと思います。
そういうわけで、当時の私にとっては「ちょっと大人」の中学生が展開するお話に、「ああ、大人って、色々ややこしくて大変だな」と、心の奥深くに染み込んでいったのです。
今回、その中でも特に心に残っている作品が掲載されていました。ちょっとだけ引用します。筋がわかってしまうとアレなので、私が感銘を受けたところを抜き書きするような感じで(その分面白さは伝わらないと思いますが、まあそれは実物を読んでもらうということで)。
p.140 (「くたばれ評論家」)より。カッコ書きは引用者による。
パパ: くたばれ!!(以下、剣による酷評が続く)
魔美: パパの声だわ。
パパ: だいたいな、おまえなんかにだな、絵がわかってたまるかってんだ!!
パパ: ヘッポコ評論家め!!
パパ: 大ばか者め!!
パパ: こうしてやる!! (本をたたきつけながら)
パパ: えいっ!
パパ: えいっ! (ジャンプしながら本を踏みつける)
魔美: どうしたの?
魔美: そんなにあれくるって、パパらしくないわ。
パパ: 読んでみろ!
パパ: 月評欄! ぼくの個展の批評がでてる! 剣鋭介という評論家だ。
この後、魔美は剣に抗議しようとして剣の家に入り込む。p.150から。
魔美: (…)だからパパがあの作品にどんなに情熱をそそいだか、よく知ってるんです。学校勤めのかたわら、ねる間もおしんで……。そして魔美は腹いせに、剣の書きかけの原稿を、テレキネシスで庭にばらまき、復讐をとげる。
魔美: それを……、
魔美: それをあなたは!
魔美: 情け容赦もなく……。
剣: お答えしよう。
剣: その一! 情けとか容赦とか、批評とは無関係のものです。
剣: その二! 芸術は結果だけが問題なのだ。
剣: たとえ、飲んだくれて鼻唄まじりにかいた絵でも、傑作は傑作。
剣: どんなに心血をそそいでかいても駄作は駄作。
魔美: 父の絵が駄作だと!?
剣: 残念だが……。
家に戻り、家族との会話。
魔美: わるい人には天罰が下るって、ほんとだよね、パパ。最後。落ちはまあ書かないでおくが、パパの一言。
パパ: だれだい、そのわるい人って?
魔美: きまってるでしょ。剣鋭介氏よ。
パパ: ハハハ わるい人ってのはかわいそうだよ。
魔美: だって!! あんなひどい批評をかいたじゃない!
パパ: マミくんそれはちがうぞ。
パパ: 公表された作品については、見る人全部が自由に批評する権利をもつ。
パパ: どんなにこきおろされても、さまたげることはできないんだ。
パパ: それがいやなら、だれにも見せないことだ。
魔美: でも、さっきはカンカンにおこってたくせに。
パパ: 剣鋭介に批評の権利があれば、
パパ: ぼくにだっておこる権利がある!!
パパ: あいつはけなした! ぼくはおこった! それでこの一件はおしまい!!
パパ: つまらんことにいつまでもこだわってないで、さっさと忘れなさい。
パパ: ばかいえ! そのうち、あいつにもけなしようのないすばらしい絵をかいてみせるさ。ああ、大人だ。オトナの世界ですよ。公の場に何かを晒すというのは、こういうことなのですよね。ネット上に簡単に自分の言説を公開できてしまう昨今、このオトナの世界の厳しさを理解している人が一体どれだけいるのだろうか。無防備な言葉を晒し、簡単な批判すら予想だにしないブログが氾濫するこの状況、もの凄く怖いと常々感じているのですが…。「物を言う」ということについて、未だに私の頭をかすめるのがこの話なのです。
また、ネット上に限りませんが、批判というものをどう考えるか、という意味でも、重要な視点を提供してくれていると思います。公権力の介在を排除しようとすれば、私的自治のなかで、たとえどれだけ精神的につらい思いをしようとも(程度問題はあるわけですが)、そのこと自体はあり得るものとして受けとめなければならない。もちろんそれは反論する自由もあるからこそ、なわけですが。ニセ科学への批判やそれへの批判についても同様でしょう。
さて、次。これ、話としてはポジティブな物言いになっていますが、「信じる」ということの本質を言い当てていると思います。そして、そのネガティブな面が、ニセ科学やオカルトを信じる心性と実は同じである、ということも。
p.322(「魔女・魔美?」)より。
魔美: あたしに関するうわさを信じる?信じない?そう、理屈じゃないんですよね。信じるってことは。そして、ここにこそ、ニセ科学やオカルトを批判することの難しさがあると思うわけです。
魔美: ねえ どっち?
高畑: ふしぎとしかいいようがないね。
高畑: 密室の会話を、
高畑: 聞きとるなんてことは……、
高畑: エスパーででもなけりゃ、できることじゃない!
魔美: やはり……、
魔美: そう思われてもしかたないわね。
高畑: おい、まてよ!
高畑: 一つ考えたことがあるんだ。
高畑: 真犯人をさぐる方法について。
魔美: じゃ、高畑さんは、
魔美: 犯人はあたしじゃないと?
高畑: あたりまえだろ!
魔美: あらゆる証拠が不利なのに?それでもあたしを信じてくれるの!?
高畑: 理屈じゃないんだよ、人を信じるってことは。
島本和彦にも同種の言葉があって、たとえば「わかってはいるが、わかるわけにはいかん!!」とか、「正義より友情だ」みたいな(後者はうろ覚え。友情じゃなかったかな。すいません)感じなんですが、生きる上では確かに理屈より大事なものはあるんですよね。それが、いい方向に向かうのであればいいんですが…。
さて、ついでにもう一つ。エスパーであるということが、世の中にとってどういう意味を持つか。
p.81 (「勉強もあるのダ」)より
魔美: ね、ね、ママ!(以下、魔美のパパとの会話。下線は原文では傍点)
ママ: なあに、マミちゃん。
魔美: これは「もしも」のことなんだけど、
魔美: もしも………
魔美: もしもよ。
魔美: もしも家族にエスパーがいたら……
魔美: すてきだと思わない?
ママ: なによ、そのエスパーって?
魔美: 超能力者よ。手をふれずに物をうごかしたり、
魔美: 人の心を読んだり、そのほかいろいろと……。
ママ: 気味がわるいわね、
ママ: そんな人が身近にいたら。
ママ: いつ心を読まれてるかと落ちつけないし、へたにおこらせるとなにされるかわからないし。
魔美: これはもしもの話なんだけどさ。先天的かどうかはおいといて。まあ、この手の特殊能力を持つ人が迫害されたり秘密組織に追われたり、というのは昔からあるテーマではあるのですが、子ども心に「そういうものなのか…」と、大人の世界を垣間見たような気がしたものです。
魔美: もしも、
魔美: パパがエスパーだったら、どんなことする?
パパ: ぼくが?
パパ: そうね…………
パパ: 自分がエスパーだってことをひたかくしにかくすだろうね。
魔美: かくす!?どうしてよ。
パパ: 平和にくらしたいからね。
パパ: 人間には先天的に自分とは毛色のちがうものをきらう性質がある。
パパ: エスパーもけっして歓迎されないだろう。
魔美: だって! ユリ・ゲラーとか、スプーンまげとか、
魔美: みんなテレビにでて、英雄みたいになったじゃない!!
パパ: 彼らはよく失敗した。インチキという声も高かった。
パパ: だから、ほんのごあいきょうですんだ。
パパ: だがもし……ほんとのエスパーなんてものがこの世にいたとしたら……、
パパ: はじめはものめずらしさでチヤホヤされるだろうが、
パパ: やがて、その力へのねたみとかおそれとかで、迫害がはじまるよ。
パパ: 一つの例がヨーロッパの魔女狩りだ。
パパ: あやしげな魔法を使ったという罪で、大ぜいの人が処刑された。
パパ: うちのフランスのご先祖には火あぶりになった人がいたそうだ。
魔美: 火あぶり!?
『ドラえもん』に限らず、藤子作品は大人になってから読み返すとまた深い理解に到達することが多いのですが、『エスパー魔美』はもともと中学生が対象で、しかも各話のページ数も結構あり、丁寧に書かれていることが多いのですよね。そういうわけで、今読んでも、なにかと勉強になるのです。それ以上に面白いわけですが。ついでにこれが「単純所持」あたるか、という論点もあるのですが、それはまたそれとして。
成果・効果・科学・思想(その2)
前のエントリ
をふまえた上で、poohさんのところでのメカさんのコメント
への御返事を書きたいと思いますが、やたら長いので(失礼)、まとめます。前のエントリにメカさんからのコメントがついていますが、とりあえずこのエントリは、そのコメントを読む前にまとめていますことをご承知おきください。
一度はメカさんのコメントに対して逐次的にレスをつけたのですが、ただでさえ長いメカさんのコメント以上にレスをつけることになってしまい(笑)、しかし重複する内容がそこかしこに出てきてしまったので、バッサリ削ることにしました。私だって人の子ですから(^^)、自分の書いた物には愛着も湧きますし辛かったのですが、他人が読めないエントリにしても意味がないので、泣く泣く削除しました。まあこれはどうでもいいことなのですが。
さて、メカさんの主張は、以下のようにまとめられるでしょうか。
(1) ニセ科学の科学の部分を批判することに意味(効果)はない。
(2) 思想の部分を批判しなければならない。
(3) 科学の名で根拠づけていることを批判しておいて、なぜ宗教を批判しないのか。
(4) ニセ科学を検閲のようなことまでして排除するのはけしからん。
(5) メカさんが「事実」と言うものは、客観的事実ではなくてメカさんが「こうだろう」と思った推測。
(6) 「社会のため」「正義のため」と思い込んでやっているのは危険だ。
順番に考えていきます。
【(1)について】
まず前エントリでも書きましたが、「効果」と言った場合に、なにをもって「効果」あるいは「成果」とするかということをある程度は見極めておく必要があります。それは、「受容者」にもスペクトルがあるからです。メカさんは「信者」という言葉をお使いになりますが、長い文章を眺めていると、どうもかなりコアなビリーバーと俗に呼ばれるような人々を想定しておられるようです。そのような人々に対して、この界隈でニセ科学を批判している人々のやり方が、直接的になんらかの効果を発揮するとは思いません。たとえばあちこちで告発して江本の活動を周辺化していくことぐらいでしょうか。それ自体は科学の営みではなく、ある意味政治ですね。社会における勢力争いです。この社会において、ちゃんとした科学がそれなりの意義を保ち続けるのか、オカルトと同列に扱われるのか、の。
しかし、大方の批判している人々の目的はそこにはないでしょう。ABO FANさんやSSFSさんみたいな方々と「対話」している私だって、彼らを説得できるとは毛頭思っていません。対話をする目的は別にあります。
私もそうですが、主要な目的は、ゆるく、なんとなく信じてしまった人々に気付いてもらうこと、またそもそもニセ科学などにはまらないで済むようになること、です。また教育やメディア(特にテレビ)のあり方とも深く関わるでしょう。血液型性格判断を垂れ流す番組に対して「BPOの勧告を守れ」と言うのはそれとも関係します(メカさんはこれも検閲とか排除だとか見做すのでしょうか?)。
目的をそう設定した場合、ニセ科学がどう科学を騙っているかを示すこと、どう科学的に間違っているかを示すことは、なんとなく信じてしまっている人々に対して一旦冷静に考えてもらうきっかけを作ることになります。前エントリで示した図の受容者の上半分に位置する人々にとっては、これはとても効くという感触があります。もちろんその効果を客観的に検証したわけではありませんが、私の個人的な経験としてはそうです。それを一般化したいのではなく、私はこうだった、あなたは?という経験交流を通じて、より良い方法を探っていきたいのですね。
そして、さらに期待することは、一旦信じたことを(きっかけは外部だとしても)自ら整理して信じなくなるという経験をすることで、ニセ科学に対する耐性を構築できるのではないか、ということです。もちろん、どう指摘したら耐性を作りやすいかは研究する価値があります。直接的には心理学の課題だろうと思いますし、血液型性格判断を中心に、それなりに豊富な経験が蓄積されています。このあたりは、『不思議現象 なぜ信じるのか こころの科学入門』(菊池聡、谷口高士、宮元博章編著)に詳しいです。メカさんの問題意識ととても良く噛み合う本だと思いますので、御一読を強く進めます。きっと、面白く読めると思います。「水伝」などに対しても応用していけるといいのですが、それはこれからの課題ですね。
「土俵」問題ですが、まずニセ科学提唱者の土俵とは何か、なんですが、ニセ科学と我々が呼んでいるものは、その一部に客観的に検証可能なものが含まれていますから、科学の土俵の上だって彼らの土俵の一部です。それから科学の部分を強調するのは、まさに戦いやすいからですよ(少なくとも私の場合は)。客観的に検証できるんですから。間違いだとか間違いじゃないとか容易に言えないような価値観に属するようなことについての議論は重要なんですが、問題があるものに対してどう切り込むかは戦略をたてて臨むべきです。もちろん、どう切り込むかは個人の自由なので、メカさんが思想に切り込んでいただけるなら、それは見てみたいと思います。参考にできるところはしたいですから。
私なりにまとめると、(a)コアなビリーバーはほぼ洗脳に近い状態であると思われ、別種の対応が必要だろう、(b)個別のニセ科学について、なんとなく信じている層を引き離すのには科学の部分を批判することに意味がありそうである、(c)信念を自ら否定する経験によって、ニセ科学に頼らなくて済むようになることを期待する、(d)cの期待があるため、bを実行することは長期的に見ても受容者の「思想」(先取りですがメカさんが思想と言っているものはこれを指すことが多いようなので)を突き崩すことに貢献できる、となりましょうか。たぶん、c, d の部分がメカさんと私とで意見の対立があるところだと思います。
【(2)について】
実はメカさんは「思想」という言葉に幾つもの異なる意味を持たせているためメカさんの言いたいことを読み取るのが難しいのですが、多くの場合、受容者が受容してしまう心理を「思想」と呼んでいるようなので、ここではそれを指すとします。とはいえ、そのまま「思想」と呼ぶと色々と混乱するので、以下では「受容者の心理」と言うことにします。その方がより限定的で、混乱も少ないでしょう。
受容者の心理を分析することは極めて重要です。それはまったくその通り。そして、人々がついニセ科学を信じてしまうのも、もはや人間の「性」と言えるでしょう。それは人間にとってごく自然なことなのだと思います。科学のほうがずっと特殊です。特殊な方法を人類が発見し、共通の知として蓄積していくことで、ここまで発展してきたのですね。
こういったことは、それこそ pooh さんがしばしば考察されていることです。ホメオパシーに関する新しいエントリ でも興味深い考察がなされていますので、読まれてみてはいかがでしょう。ホメオパシーはまさに受容者がなぜ受容してしまうのかが大きな関心となっています。kikulogの関連エントリでも活発に議論が行われていますね。
きくちさん(菊池誠氏)などは、しばしば「折り合いをつける」と言ったりします。まあ結論としてはそういうことになるんでしょうが、じゃあどうやって折り合いをつけりゃいいんだ、ってのが問題なわけで、そこはもっと考える必要があります。
さて、ではメカさんの「思想に切り込む」というのは、具体的にはどういうイメージをされているのでしょう?実は「切り込む」というのもよくわからないのですよね。受容者に対して、信じなくなるための対処のことを言っているのか、それとも対受容者ということではなくて、受容者の心理をもっと分析しろ、と言っているのか。両方かもしれませんし、もっと他の意味も込めているのかもしれませんが、ちょっと曖昧すぎて、どうしたらいいのやら、というところです。
もう一つ、メカさんが「思想」に込めているっぽいことは、科学とニセ科学を対等のものとする、ということです。これは、一つには、前の図で言うところの受容者の下半分について当てはまります。科学的な間違いを指摘しても、科学自体を相対化してしまって、どっちもどっちという対応をとりつつ、心はしっかりニセ科学の方に向いている、そういう状態をどうするか、と。これは極端な相対主義にもつながる思想でもあります。
これは論理的には哲学や科学論の問題になってしまうのですが、学問的に深めることも重要ですが、実践的にはそういう心性に対してどのように対処すべきかが重要でしょう。心理学的にはおそらく「サブタイピング」という概念が重要になると思われます。これは血液型性格判断を信じる心を分析する際にしばしば登場します。批判されてもそれを例外扱いすることで、自分が信じている本体に影響がないように自分の心を整理してしまうということです。このあたりは、個別のニセ科学に即してもっと分析する必要があります。
もう一つは、「科学」と「神」の位置関係です。メカさんは、しきりに科学を騙っていることをもって批判しているのに、なぜ神の名で行われる宗教は批判しないのだ、とおっしゃいます。これも、科学の意義を相対化することから出てくるものです。これについては次の3で。
【(3) について】
まず、なぜニセ科学が批判されているのかということろから考えないといけません。水伝にしてもなんにしても、科学的でないから(=非科学だから)批判しているというわけではありません。科学的知見と矛盾することが、いかにも科学で証明されたかのように言うから批判しているんですよ(ちなみにマイナスイオンなどの場合は、科学的に決着のついていないことを、さも決着がついたかのように言うところが批判のポイントです)。
私は無神論者だからいくらでも宗教批判したって構わないんですが、科学の名で批判するものとは違います。キリスト教に関係するものだったら、たとえば 創造説なんてのは強い批判にさらされてますよ。キリスト教全体が聖書の記述を絶対のものとみなすのであれば、キリスト教自体の批判へと向かうでしょうが、 実際はそうではないので、キリスト教への批判ではなく、創造説への批判、となっているわけですが。
それから、メカさんのお尋ねでもありますが、害がないからってのは(私個人としては)ありますね。キリスト教を名乗って社会問題を引き起こせば、当然その団体は(キリスト教自体ではなく)批判されるでしょう。
むしろ私がお聞きしたいのは、どうして「キリスト教も水伝も同じように有害」と言ってしまえるのか、です。どう同じように有害なのでしょう?
宗教が抱える思想自体についても、私自身は批判的な部分はあります。それはもちろん宗教との付き合い方、ということになるので、まあ難しいところもあるのですが、なんにせよ依存してしまうのは良くないし、「神」にすべてを還元してしまうのも良くない。物事の原因を追求することに対し、ブレーキをかけ思考停止に貢献してきた部分はやはりあると思うわけです。個人の人生においても、社会においても。それこそ「宗教は悩めるもののアヘンである」というのは、宗教の持つ一面を指摘するものであろうと思います。もちろんそういった面を自覚してうまく付き合っている人も多いでしょうし、そもそも宗教に限らず、なにかに精神的に頼るのは人間どうやっても避けられませんから(頼ったもののうち検証不可能なものを「神」や「霊」などと呼ぶ、ぐらいの方がいいのかもしれませんが)、これも難しい問題であろうと思います。
ついでに言えば、「解放の神学」みたいなキリスト教もあるわけで(今日の中南米の状況も、それが底流にあるのでは-70年代だけではなく-と思っているのですが、どうでしょうか)、逆にブッシュのような福音派もキリスト教なわけで、まあ「宗教」と十把一絡げにしても意味がないことを端的に示していると思います。
いずれにしても、ポイントは「客観的検証」が重要であるか否か、です。まず信じよ、というのは、私はそれに与するものではありませんが、それを否定するつもりもありません。それは生き方の問題ですから、それこそ「カレーパンかヤキソバパンか」という問題と同じなわけです(まあ重大さは全然違いますが)。「好み」でしょう。
もう一つついでに言えば、科学の研究だって、場合によっちゃ批判しますよ私は。低コストで大量殺人を可能にする兵器の開発だとかね。核兵器の開発研究だってね。科学者の社会的責任をどう考えるのか、ってことになるんですが。話が拡散するのでこれだけにしておきますが、ニセ科学と宗教の類似点と相違点を考えるにあたって、科学内部にも研究自体に対する批判があるのだということは押えておきたいところです。
【(4) について】
これがサッパリわからない。なぜ排除しているように見えるのか?
まず大前提は、我々も彼ら(ニセ科学の提唱者)も、言論出版の自由を保障されているということです。保障されているし、それを侵害してはならない。
そして、言論の自由があるということは、批判する自由もあるということです。言論の中には批判も含まれますから。ですから、公になされた出版や発言に対して、権力から離れたところで批判するのは完全に自由でしょう。たとえば、明らかに科学的に間違ったことに対して、ほとんどの科学者が「それは間違いだ」「そんな間違いを学校で教えるな」と言ったとします。それは言論弾圧ですか?違うでしょう。
個々の人間にはもちろん間違える自由だってあります。でも、それを公にするのであれば、批判にさらされるのは仕方ないでしょう。公になった状態で放置されれば、あちこちで問題が引き起こされかねないのですから。それを排除だの検閲だの言ってしまっては、批判なんてできませんよ。というか、メカさんの発言自体が、ニセ科学批判に対する言論弾圧である、ということも言えてしまうわけですよ(もちろん私はまったくそうは思っていませんが)。
ニセ科学をテレビ番組で放映することに対してテレビ局に抗議することだって、民主主義社会における正当な行いですよ(電話やファックス攻勢などはもちろん程度の問題はありますが)。これはもちろんニセ科学の側がテレビ局や新聞社に対して抗議する権利をも認めた上で言っています。テレビ局は、それに対して反論する権利がある。そして、ニセ科学に対立する側が、「そんな抗議はおかしい」と批判する権利もあるわけです(逆もまた同様)。
むしろ、思想弾圧も場合によっては許されるとも読めるようなメカさんの発想の方が、私には恐しいです。
【(5) について】
これはまあそうなのか、と(ちょっと脱力しつつですが)了解しました。
あちこちこの界隈のブログ等を読まれたのであれば大体見えてきたのではないかと思いますが、おそらくメカさんが思っているよりは、様々な考察がなされています。もちろん、私としては、そこにメカさんがなにがしかの有益な知見を加えてほしいと思っています。
【(6) について】
それの何が悪いのかがわかりません。もちろん、謙虚でないのであれば、それは問題を引き起こす可能性が多分にあります。でも、ニセ科学を批判している人々は、たいてい自分が間違っている可能性を考慮した上で発言しているのではないでしょうかね?2chみたいなとこだとどうか知りませんが。
環境問題との比較をメカさんはされました。それは実は重要で、実際困っているのですよね。EM関連の記事を見てもらえるとわかりますが、環境問題(水伝でもそうですが)に絡むニセ科学において常につきまというのが「善意」の存在です。「善意でやっているのだからいいじゃないか」というやつですね。以前、『環境問題 善意の落とし穴』という本を紹介するエントリ を書いたこともあります。
これは常に自戒しておかないといけません。ニセ科学問題というのは社会問題でもあるわけで、社会との関わりを抜きには語れませんから、どうしても「善意」というのは絡んできます。知らず知らずのうちにそれを免罪符にしている可能性は誰にもあるわけで、気をつけないといけないですね。
もう一つ、ニセ科学を批判する理由として「自分のため」と「社会のため」は相反するものではありませんよね。自分がやりたいからやってるという大前提があるわけで(金ももらわず自分の時間を使ってやってるわけですから)、純粋に社会のためなわけじゃないことは自明でしょう。
【その他の点について】
ちょっとだけ言うと、ある女子大で、100人ほどの授業で血液型性格判断を批判する講義を行った。講義前は信じている人が7割だったのが、講義直後は3割まで減り、3ヶ月後も維持された、というものです。3割の人は信念を捨てなかったし、また同じ授業に出席していたわけで、信じている友人はそばにいると考えてもおかしくありません(もちろん、信じている者・信じていない者同士で友人グループを作っていた可能性もありますが)。それから、娯楽としての血液型性格判断を容認することが自身の血液型ステレオタイプを強化する方向づけを与えることや、ステレオタイプが強い者ほど受講しても信念が変わらなかった、といったことが報告されています。
ただし1992年の論文(『現代のエスプリ』No.324, p.146)なので、その後の蓄積もきっとあるだろうとは思うのですが、そのあたりはわかりません。
もう一つ、おそらく重要な点。
ただ、科学が宗教的なものを排除した、というのは一面的かな、と思います。実際に宗教的なものが科学に入り込んでくると困るわけですが(個別の科学者の 内的動機は別にして)、一方で、信じようが信じまいが、誰もが同じ条件で同じことをやったら同じ結果になることの集大成が科学であるとも言えるわけです (もちろん、これも科学の一面を述べているに過ぎませんが)。宗教的なものに依存せず、客観的に検証可能なものに頼るという方針で進んだら、恐しいまでに 発展してしまったのが現代の科学(と技術)、そして我々は日々その恩恵を受けている-こうしてブログを書くことでさえ(笑)。
しかしその道筋が一旦忘れ去られ、科学の恩恵を「あるもの」としてしか受け止められなくなると、宗教的なものが感じられないことに寂しさのようなものを感じる人々はきっと多いのでしょうね。本末転倒ですが、そこにニセ科学がつけ入る隙があるのでしょう。
***
というわけで、いかがでしょうか。たぶん一通りメカさんの疑問には答えたと思うのですが、答えていない問があったら言ってください。
メカさんの問題意識はわかるのですよね。わかるのですが、一部は既に多くの人が考えているし、また一部は難しくて手に負えなかったり、手薄な分野であったり、みなさん忙しくて手が回らなかったりで十分に深められていないのです。
だからこそ、皮肉でもなんでもなくて、メカさんなりのやり方というものを具体的に見せてほしいのですよね。実践的に批判してくれれば一番いいですけど、そこまでいかなくても、例えば水伝だったら具体的にこの点をこのように批判すべきである、とか。それが一番参考になるので。
一度はメカさんのコメントに対して逐次的にレスをつけたのですが、ただでさえ長いメカさんのコメント以上にレスをつけることになってしまい(笑)、しかし重複する内容がそこかしこに出てきてしまったので、バッサリ削ることにしました。私だって人の子ですから(^^)、自分の書いた物には愛着も湧きますし辛かったのですが、他人が読めないエントリにしても意味がないので、泣く泣く削除しました。まあこれはどうでもいいことなのですが。
さて、メカさんの主張は、以下のようにまとめられるでしょうか。
(1) ニセ科学の科学の部分を批判することに意味(効果)はない。
(2) 思想の部分を批判しなければならない。
(3) 科学の名で根拠づけていることを批判しておいて、なぜ宗教を批判しないのか。
(4) ニセ科学を検閲のようなことまでして排除するのはけしからん。
(5) メカさんが「事実」と言うものは、客観的事実ではなくてメカさんが「こうだろう」と思った推測。
(6) 「社会のため」「正義のため」と思い込んでやっているのは危険だ。
順番に考えていきます。
【(1)について】
まず前エントリでも書きましたが、「効果」と言った場合に、なにをもって「効果」あるいは「成果」とするかということをある程度は見極めておく必要があります。それは、「受容者」にもスペクトルがあるからです。メカさんは「信者」という言葉をお使いになりますが、長い文章を眺めていると、どうもかなりコアなビリーバーと俗に呼ばれるような人々を想定しておられるようです。そのような人々に対して、この界隈でニセ科学を批判している人々のやり方が、直接的になんらかの効果を発揮するとは思いません。たとえばあちこちで告発して江本の活動を周辺化していくことぐらいでしょうか。それ自体は科学の営みではなく、ある意味政治ですね。社会における勢力争いです。この社会において、ちゃんとした科学がそれなりの意義を保ち続けるのか、オカルトと同列に扱われるのか、の。
しかし、大方の批判している人々の目的はそこにはないでしょう。ABO FANさんやSSFSさんみたいな方々と「対話」している私だって、彼らを説得できるとは毛頭思っていません。対話をする目的は別にあります。
私もそうですが、主要な目的は、ゆるく、なんとなく信じてしまった人々に気付いてもらうこと、またそもそもニセ科学などにはまらないで済むようになること、です。また教育やメディア(特にテレビ)のあり方とも深く関わるでしょう。血液型性格判断を垂れ流す番組に対して「BPOの勧告を守れ」と言うのはそれとも関係します(メカさんはこれも検閲とか排除だとか見做すのでしょうか?)。
目的をそう設定した場合、ニセ科学がどう科学を騙っているかを示すこと、どう科学的に間違っているかを示すことは、なんとなく信じてしまっている人々に対して一旦冷静に考えてもらうきっかけを作ることになります。前エントリで示した図の受容者の上半分に位置する人々にとっては、これはとても効くという感触があります。もちろんその効果を客観的に検証したわけではありませんが、私の個人的な経験としてはそうです。それを一般化したいのではなく、私はこうだった、あなたは?という経験交流を通じて、より良い方法を探っていきたいのですね。
そして、さらに期待することは、一旦信じたことを(きっかけは外部だとしても)自ら整理して信じなくなるという経験をすることで、ニセ科学に対する耐性を構築できるのではないか、ということです。もちろん、どう指摘したら耐性を作りやすいかは研究する価値があります。直接的には心理学の課題だろうと思いますし、血液型性格判断を中心に、それなりに豊富な経験が蓄積されています。このあたりは、『不思議現象 なぜ信じるのか こころの科学入門』(菊池聡、谷口高士、宮元博章編著)に詳しいです。メカさんの問題意識ととても良く噛み合う本だと思いますので、御一読を強く進めます。きっと、面白く読めると思います。「水伝」などに対しても応用していけるといいのですが、それはこれからの課題ですね。
「土俵」問題ですが、まずニセ科学提唱者の土俵とは何か、なんですが、ニセ科学と我々が呼んでいるものは、その一部に客観的に検証可能なものが含まれていますから、科学の土俵の上だって彼らの土俵の一部です。それから科学の部分を強調するのは、まさに戦いやすいからですよ(少なくとも私の場合は)。客観的に検証できるんですから。間違いだとか間違いじゃないとか容易に言えないような価値観に属するようなことについての議論は重要なんですが、問題があるものに対してどう切り込むかは戦略をたてて臨むべきです。もちろん、どう切り込むかは個人の自由なので、メカさんが思想に切り込んでいただけるなら、それは見てみたいと思います。参考にできるところはしたいですから。
私なりにまとめると、(a)コアなビリーバーはほぼ洗脳に近い状態であると思われ、別種の対応が必要だろう、(b)個別のニセ科学について、なんとなく信じている層を引き離すのには科学の部分を批判することに意味がありそうである、(c)信念を自ら否定する経験によって、ニセ科学に頼らなくて済むようになることを期待する、(d)cの期待があるため、bを実行することは長期的に見ても受容者の「思想」(先取りですがメカさんが思想と言っているものはこれを指すことが多いようなので)を突き崩すことに貢献できる、となりましょうか。たぶん、c, d の部分がメカさんと私とで意見の対立があるところだと思います。
【(2)について】
実はメカさんは「思想」という言葉に幾つもの異なる意味を持たせているためメカさんの言いたいことを読み取るのが難しいのですが、多くの場合、受容者が受容してしまう心理を「思想」と呼んでいるようなので、ここではそれを指すとします。とはいえ、そのまま「思想」と呼ぶと色々と混乱するので、以下では「受容者の心理」と言うことにします。その方がより限定的で、混乱も少ないでしょう。
受容者の心理を分析することは極めて重要です。それはまったくその通り。そして、人々がついニセ科学を信じてしまうのも、もはや人間の「性」と言えるでしょう。それは人間にとってごく自然なことなのだと思います。科学のほうがずっと特殊です。特殊な方法を人類が発見し、共通の知として蓄積していくことで、ここまで発展してきたのですね。
こういったことは、それこそ pooh さんがしばしば考察されていることです。ホメオパシーに関する新しいエントリ でも興味深い考察がなされていますので、読まれてみてはいかがでしょう。ホメオパシーはまさに受容者がなぜ受容してしまうのかが大きな関心となっています。kikulogの関連エントリでも活発に議論が行われていますね。
きくちさん(菊池誠氏)などは、しばしば「折り合いをつける」と言ったりします。まあ結論としてはそういうことになるんでしょうが、じゃあどうやって折り合いをつけりゃいいんだ、ってのが問題なわけで、そこはもっと考える必要があります。
さて、ではメカさんの「思想に切り込む」というのは、具体的にはどういうイメージをされているのでしょう?実は「切り込む」というのもよくわからないのですよね。受容者に対して、信じなくなるための対処のことを言っているのか、それとも対受容者ということではなくて、受容者の心理をもっと分析しろ、と言っているのか。両方かもしれませんし、もっと他の意味も込めているのかもしれませんが、ちょっと曖昧すぎて、どうしたらいいのやら、というところです。
もう一つ、メカさんが「思想」に込めているっぽいことは、科学とニセ科学を対等のものとする、ということです。これは、一つには、前の図で言うところの受容者の下半分について当てはまります。科学的な間違いを指摘しても、科学自体を相対化してしまって、どっちもどっちという対応をとりつつ、心はしっかりニセ科学の方に向いている、そういう状態をどうするか、と。これは極端な相対主義にもつながる思想でもあります。
これは論理的には哲学や科学論の問題になってしまうのですが、学問的に深めることも重要ですが、実践的にはそういう心性に対してどのように対処すべきかが重要でしょう。心理学的にはおそらく「サブタイピング」という概念が重要になると思われます。これは血液型性格判断を信じる心を分析する際にしばしば登場します。批判されてもそれを例外扱いすることで、自分が信じている本体に影響がないように自分の心を整理してしまうということです。このあたりは、個別のニセ科学に即してもっと分析する必要があります。
もう一つは、「科学」と「神」の位置関係です。メカさんは、しきりに科学を騙っていることをもって批判しているのに、なぜ神の名で行われる宗教は批判しないのだ、とおっしゃいます。これも、科学の意義を相対化することから出てくるものです。これについては次の3で。
【(3) について】
まず、なぜニセ科学が批判されているのかということろから考えないといけません。水伝にしてもなんにしても、科学的でないから(=非科学だから)批判しているというわけではありません。科学的知見と矛盾することが、いかにも科学で証明されたかのように言うから批判しているんですよ(ちなみにマイナスイオンなどの場合は、科学的に決着のついていないことを、さも決着がついたかのように言うところが批判のポイントです)。
私は無神論者だからいくらでも宗教批判したって構わないんですが、科学の名で批判するものとは違います。キリスト教に関係するものだったら、たとえば 創造説なんてのは強い批判にさらされてますよ。キリスト教全体が聖書の記述を絶対のものとみなすのであれば、キリスト教自体の批判へと向かうでしょうが、 実際はそうではないので、キリスト教への批判ではなく、創造説への批判、となっているわけですが。
それから、メカさんのお尋ねでもありますが、害がないからってのは(私個人としては)ありますね。キリスト教を名乗って社会問題を引き起こせば、当然その団体は(キリスト教自体ではなく)批判されるでしょう。
むしろ私がお聞きしたいのは、どうして「キリスト教も水伝も同じように有害」と言ってしまえるのか、です。どう同じように有害なのでしょう?
宗教が抱える思想自体についても、私自身は批判的な部分はあります。それはもちろん宗教との付き合い方、ということになるので、まあ難しいところもあるのですが、なんにせよ依存してしまうのは良くないし、「神」にすべてを還元してしまうのも良くない。物事の原因を追求することに対し、ブレーキをかけ思考停止に貢献してきた部分はやはりあると思うわけです。個人の人生においても、社会においても。それこそ「宗教は悩めるもののアヘンである」というのは、宗教の持つ一面を指摘するものであろうと思います。もちろんそういった面を自覚してうまく付き合っている人も多いでしょうし、そもそも宗教に限らず、なにかに精神的に頼るのは人間どうやっても避けられませんから(頼ったもののうち検証不可能なものを「神」や「霊」などと呼ぶ、ぐらいの方がいいのかもしれませんが)、これも難しい問題であろうと思います。
ついでに言えば、「解放の神学」みたいなキリスト教もあるわけで(今日の中南米の状況も、それが底流にあるのでは-70年代だけではなく-と思っているのですが、どうでしょうか)、逆にブッシュのような福音派もキリスト教なわけで、まあ「宗教」と十把一絡げにしても意味がないことを端的に示していると思います。
いずれにしても、ポイントは「客観的検証」が重要であるか否か、です。まず信じよ、というのは、私はそれに与するものではありませんが、それを否定するつもりもありません。それは生き方の問題ですから、それこそ「カレーパンかヤキソバパンか」という問題と同じなわけです(まあ重大さは全然違いますが)。「好み」でしょう。
もう一つついでに言えば、科学の研究だって、場合によっちゃ批判しますよ私は。低コストで大量殺人を可能にする兵器の開発だとかね。核兵器の開発研究だってね。科学者の社会的責任をどう考えるのか、ってことになるんですが。話が拡散するのでこれだけにしておきますが、ニセ科学と宗教の類似点と相違点を考えるにあたって、科学内部にも研究自体に対する批判があるのだということは押えておきたいところです。
【(4) について】
これがサッパリわからない。なぜ排除しているように見えるのか?
まず大前提は、我々も彼ら(ニセ科学の提唱者)も、言論出版の自由を保障されているということです。保障されているし、それを侵害してはならない。
そして、言論の自由があるということは、批判する自由もあるということです。言論の中には批判も含まれますから。ですから、公になされた出版や発言に対して、権力から離れたところで批判するのは完全に自由でしょう。たとえば、明らかに科学的に間違ったことに対して、ほとんどの科学者が「それは間違いだ」「そんな間違いを学校で教えるな」と言ったとします。それは言論弾圧ですか?違うでしょう。
個々の人間にはもちろん間違える自由だってあります。でも、それを公にするのであれば、批判にさらされるのは仕方ないでしょう。公になった状態で放置されれば、あちこちで問題が引き起こされかねないのですから。それを排除だの検閲だの言ってしまっては、批判なんてできませんよ。というか、メカさんの発言自体が、ニセ科学批判に対する言論弾圧である、ということも言えてしまうわけですよ(もちろん私はまったくそうは思っていませんが)。
ニセ科学をテレビ番組で放映することに対してテレビ局に抗議することだって、民主主義社会における正当な行いですよ(電話やファックス攻勢などはもちろん程度の問題はありますが)。これはもちろんニセ科学の側がテレビ局や新聞社に対して抗議する権利をも認めた上で言っています。テレビ局は、それに対して反論する権利がある。そして、ニセ科学に対立する側が、「そんな抗議はおかしい」と批判する権利もあるわけです(逆もまた同様)。
むしろ、思想弾圧も場合によっては許されるとも読めるようなメカさんの発想の方が、私には恐しいです。
【(5) について】
これはまあそうなのか、と(ちょっと脱力しつつですが)了解しました。
あちこちこの界隈のブログ等を読まれたのであれば大体見えてきたのではないかと思いますが、おそらくメカさんが思っているよりは、様々な考察がなされています。もちろん、私としては、そこにメカさんがなにがしかの有益な知見を加えてほしいと思っています。
【(6) について】
それの何が悪いのかがわかりません。もちろん、謙虚でないのであれば、それは問題を引き起こす可能性が多分にあります。でも、ニセ科学を批判している人々は、たいてい自分が間違っている可能性を考慮した上で発言しているのではないでしょうかね?2chみたいなとこだとどうか知りませんが。
環境問題との比較をメカさんはされました。それは実は重要で、実際困っているのですよね。EM関連の記事を見てもらえるとわかりますが、環境問題(水伝でもそうですが)に絡むニセ科学において常につきまというのが「善意」の存在です。「善意でやっているのだからいいじゃないか」というやつですね。以前、『環境問題 善意の落とし穴』という本を紹介するエントリ を書いたこともあります。
これは常に自戒しておかないといけません。ニセ科学問題というのは社会問題でもあるわけで、社会との関わりを抜きには語れませんから、どうしても「善意」というのは絡んできます。知らず知らずのうちにそれを免罪符にしている可能性は誰にもあるわけで、気をつけないといけないですね。
もう一つ、ニセ科学を批判する理由として「自分のため」と「社会のため」は相反するものではありませんよね。自分がやりたいからやってるという大前提があるわけで(金ももらわず自分の時間を使ってやってるわけですから)、純粋に社会のためなわけじゃないことは自明でしょう。
【その他の点について】
> ちなみに血液型性格判断については、どういうレクチャーをやったらどれくらい受講者の認識が変わるか、またそれが維持されるかどうか、といった効果についてそうですね。その研究については、いずれ改めて紹介エントリを作りたいと思います。このブログでは血液型性格判断についての論文を紹介するシリーズをやってるんですが(左のサイドバーに載せています)、その一環でやってみたいと思います。私も深めてみたいし。ちょっと先になるとは思いますが…。
その「維持」という部分が興味深いんだけど、どういう検査をしたのかな。たとえば受講直後には血液型と性格との関連に否定的な認識をもった人でも、信じている友人がそばにいるかいないかで、その認識を保ち続けられるかは大きく変わると思うんだよね。
で、そもそも疑似科学を信じる人は周囲にもそういう人たちが多いはずで、再び疑似科学にはまる率は非常に高いと思うんだけどね。まあ何にせよそういう研究は今後もやるべきではある。
ちょっとだけ言うと、ある女子大で、100人ほどの授業で血液型性格判断を批判する講義を行った。講義前は信じている人が7割だったのが、講義直後は3割まで減り、3ヶ月後も維持された、というものです。3割の人は信念を捨てなかったし、また同じ授業に出席していたわけで、信じている友人はそばにいると考えてもおかしくありません(もちろん、信じている者・信じていない者同士で友人グループを作っていた可能性もありますが)。それから、娯楽としての血液型性格判断を容認することが自身の血液型ステレオタイプを強化する方向づけを与えることや、ステレオタイプが強い者ほど受講しても信念が変わらなかった、といったことが報告されています。
ただし1992年の論文(『現代のエスプリ』No.324, p.146)なので、その後の蓄積もきっとあるだろうとは思うのですが、そのあたりはわかりません。
もう一つ、おそらく重要な点。
まあ簡単にいえば科学が宗教的なものをあまりにも排除してしまったからだろうね。科学が非科学的なものと一緒に宗教が 担っていた人の心の支えという役割まで否定してしまった。しかたないから今度は科学を宿主にしてそういうものが芽生えたわけだ。ある意味すごい生存競争だ よね。天敵に寄生して生き残りを図ろうとしてるんだから。そうですね。まあ指摘されればウソがわかってしまうような主張を内包せざるを得ない宿命を負ってしまったわけですから。
ただ、科学が宗教的なものを排除した、というのは一面的かな、と思います。実際に宗教的なものが科学に入り込んでくると困るわけですが(個別の科学者の 内的動機は別にして)、一方で、信じようが信じまいが、誰もが同じ条件で同じことをやったら同じ結果になることの集大成が科学であるとも言えるわけです (もちろん、これも科学の一面を述べているに過ぎませんが)。宗教的なものに依存せず、客観的に検証可能なものに頼るという方針で進んだら、恐しいまでに 発展してしまったのが現代の科学(と技術)、そして我々は日々その恩恵を受けている-こうしてブログを書くことでさえ(笑)。
しかしその道筋が一旦忘れ去られ、科学の恩恵を「あるもの」としてしか受け止められなくなると、宗教的なものが感じられないことに寂しさのようなものを感じる人々はきっと多いのでしょうね。本末転倒ですが、そこにニセ科学がつけ入る隙があるのでしょう。
***
というわけで、いかがでしょうか。たぶん一通りメカさんの疑問には答えたと思うのですが、答えていない問があったら言ってください。
メカさんの問題意識はわかるのですよね。わかるのですが、一部は既に多くの人が考えているし、また一部は難しくて手に負えなかったり、手薄な分野であったり、みなさん忙しくて手が回らなかったりで十分に深められていないのです。
だからこそ、皮肉でもなんでもなくて、メカさんなりのやり方というものを具体的に見せてほしいのですよね。実践的に批判してくれれば一番いいですけど、そこまでいかなくても、例えば水伝だったら具体的にこの点をこのように批判すべきである、とか。それが一番参考になるので。
- 不思議現象 なぜ信じるのか―こころの科学入門/菊池 聡

- ¥1,995
- Amazon.co.jp
- 環境教育 善意の落とし穴 (クレスコファイル)/田中 優
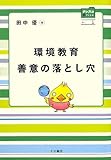
- ¥1,050
- Amazon.co.jp
成果・効果・科学・思想(その1)
【はじめにおことわり】途中まで書いて下書きを保存しようとしたら、半角40000字を越えてて保存できない、などと抜かしよった。なので、エントリを二つにわけます。それはつまり、こういうことです。「長いよ」。すみませんすみません。メカさんのコメントへの返事は、次のエントリです。
【おことわりその2】メカさんへの返事、ざっと書いたんですが、これが長いのなんの。(^^;; ちょっと長過ぎなので、重複する部分を削り、もう少しコンパクトにしたいと思います。ので、とりあえずこのエントリだけ先に公開します。
先日、poohさんのエントリ がメカさん(メカAGさん)の記事をとりあげ、そこにメカさん御本人がコメントを寄せていました。私はその展開にちょっと興味を持ち、反論とかそういうことではなく、議論を深めようという立場から、少しばかりコメントをいたしました。
だいぶ長くなりますが、まずは私がコメントした文章を紹介します。ここまでの経緯は、poohさんの当該エントリのコメント欄をお読みください(そこまでは、そう長くはありません)。
さて、上のようなコメントをした背景には、以下のような、私なりのニセ科学問題の分析があります。一般論はたいていの場合無力なので、具体例で話を進めましょう。
下の図は、「水からの伝言」(以下「水伝」)をとりまく構造を、ある側面から切り取ったものです。もちろん私なりのまとめであり、異論のある方もいるでしょう。特に一番下の部分は違和感を覚える人も少なくないかもしれません。メカさんのおっしゃる「思想」は、おそらくこの図の左側「受容者」に関わるものだとは思いますが、まずは一般的な話をしたいと思います。
ここでは、まず大きく左右二つに分類しています。右側が江本勝をはじめとする「提唱者」(コアなビリーバーも含むでしょう)、左側がそれを信じる「受容者」です。受容者の上のほうが、水伝を授業で使っちゃった教師の典型でしょう。
さて、まず右側。こちらは江本らの主張がそもそもどういう構造をしているか、です。これについては多くの分析があり、特に hietaro さんの「『水からの伝言』の2つの側面」 に端的にまとめられています。ここでは、hietaroさん言うところの「現象篇」を「根拠」、「解釈篇」を「結論」「応用」と言っていますが、まあそれは視点をどこに置くかという話なので、違うことを主張するために違う言葉を使っているわけではないです(通常の科学だって、現象が根拠ですしね)。ここではさらに、その「説明原理」として「理論」-つまり、彼らが言うところの「波動」(もちろん物理学で出てくる波動とはなんの関係もない)も載せています。
なお誤解のないように言っておくと、「根拠」から上下に伸びる矢印の向きは、彼らの動機の順番とは関係ありません。あくまでも、彼らの議論の展開を元にしているだけです。彼らの発想としては、「応用」側の結論が先にあり、一方江本らが持ち込んだ波動測定器を使いたいという思惑がそれに結びついて、「根拠」「応用」のセットが出来たのでしょう。
この「理論」(「波動」)は一般化されており、「水伝」だけではなく、多くのニセ科学に持ち込まれています。「EM」の説明原理も「波動」です。ホメオパシーも、原子論が確立したあとはレメディの中に分子が一つも残っていないということがわかっちゃいましたから(ということだと思いますが)、「波動」を持ち出して効能を説明しようとしますね。そして、ニセ科学というよりもっとストレートにオカルトなものにも「波動」は登場します。さらにさらに、「波動」で生き方を決める発想まであるわけですね。
提唱者の部分に限って見ると、科学っぽい「実験」の部分、科学っぽい「理論」の部分、もろに「道徳」の部分、といくつかのパーツに分けられます。「道徳」の部分をもって「思想」と言ってもいいのかもしれません。また、「理論」の部分も科学的な言辞は使っていますが(量子力学など)、まあ客観的に見れば「思想」ということになるだろうと思います。
次に左側。こちらは受容する側の(ごく簡単な)分析です。分析と言っても、受容者に典型的な例をいくつか述べているに過ぎませんが、まあこんな感じだろう、と(コアなビリーバーは除きます)。彼らにとっての心の支えは、やはり客観的に検証されたと思い込める「根拠」の部分(つまり「実験」)でしょう。それがあるから、「道徳」的な結論を活かして授業に使おうなんて思っちゃうわけです。このあたりの人々(つまりこの図で言うところの受容者の上半分に位置する人々)は、「根拠」を崩せばたいがい「え?そうだったの?」となって、「水伝」からは離れていきます。少なくとも、私のそう多くはないが少なくもない経験ではそうです。心の整理をつけるのに時間がかかる人もいますが。もちろん統計データを取っているわけではありませんから、それをそのまま信じろと言うつもりは毛頭ありませんが、経験交流は大事だと思っていますので、まあそういうヤツがおる、ぐらいに思って聞いてもらえればいいかなと思います。
問題は下半分、つまり「波動」側に心魅かれてしまっている人々でしょう。ここはばっちりニューエイジ系の思想と重なります。軸足がこちらに来てしまうと、「根拠」の間違いを言ってもなかなか受け入れなくなります。どう受け入れないかは様々でしょう。単に聞く耳を持たなくなる場合もあるでしょうし、悪しき相対主義を持ち込んで、ちゃんとした実験結果を認めない場合もあるでしょう。もっと中途半端に「科学でもわかっていないことはいっぱいある」で思考停止してしまう場合も多いでしょう。
ここから先はニセ科学を批判する人々の間でもコンセンサスがあるわけではないと思いますが、ここは私のブログですので私の主張を書いておきます。このような「思想」には問題点が大変多く含まれています。その第一歩は、「百匹目の猿」に代表される思想でしょう。簡単に言えば、みんなで祈れば願いは実現する、ってやつです。世界平和も願えば実現する、と。これは色々な意味で問題ですが、平和への地道な努力をまったく見ないという点で有害ですらあります。
「みんなで」というのが一つのキーワードですね。ここにゆるやかな連帯を感じ、心地良く感ずる人も多いと思います。しかし、これが曲者。「個」を相対化し、しかも相対化したままにする。独立した「個」の連帯ではなく、相対化されたままの「個」の連帯は、融合した「全体」に向かわざるを得ないと思います。そうなった時、自分が何かうまくいかないことがある、失敗してしまった、つらい、ということに直面したら、どうなるでしょうか。祈りが足りない、となりますね。「祈り」じゃなくてもいいんですが、要するに、例えば生活がつらいのは自分が怠けてる場合もあるだろうけど派遣切りだのなんだの自分ではどうしょうもない社会的な問題に起因するものだっていくらでもあるわけです。そこを捨象してしまい、すべて「自分」に還元していまう。「連帯」の幻想は、すべてを「自己責任」へと転化させる危険を孕んでいます。これは「空気を読む」ということに(私などから見たら)異常なまでにこだわる最近の風潮と似たようなものなのかもしれませんね。
ついでに余談ですが、最近都市部の大学では「トイレで食事をしないでください」と張り紙がしてあるとか。これは、学食で一人で食べているところを友人に見られたくないからだそうなんですが、別に一人で食べてたっていいじゃんねえ。トイレで食べるほどに空気読まないかんのかねえ。息苦しいだろうねえ。
このような「思想」は、まさに大衆支配のおそるべきイデオロギーでしょう。実際、そうやって社員に「生きがい」を持たせ、どんな長時間の過酷な労働も喜びに感じさせてしまうという社員教育をやっている企業もあると聞きます(ちょっと古いけど『カルト資本主義』でだいぶ取り上げられていますね。稲盛和夫の「アメーバ経営」なんてまさにその例らしいのですが、まだチェックできていません)。
別の面から言うと、本当は、受容者が受容してしまう心理をもっと分析しないといけません。そこはニセ科学の「蔓延問題」への対策としては極めて重要でしょう。心理学者の皆様におかれましては、ぜひ、そこを取り組んでいただければと思います。血液型性格判断対策の蓄積が活かせる場ではないでしょうか。というのが、とりあえずのメカさんへの噛み合った形での返答、ということになるでしょうか。
というわけで、長々と書いてきましたが、ここでようやくメカさんへの質問となります。メカさん言うところの「思想」とは、この図でいうとどのあたりをイメージされているのでしょうか?もちろん分析は人によって違うし、メカさんとしては現状は大雑把な枠組みを提出する段階のようですから、「ここ」と言っていただかなくてもいいのですが、大体どのあたりをイメージしているのかを言っていただくと、わかりやすくなると思います。受容者が受容する心理、というあたりでいいのでしょうか?(このあたりは次のエントリで)
ちなみに今まで(このエントリだけではなくて)「水伝」の「思想」と言った場合何を指すかというと、文脈によって異なります。「道徳」の部分を指す場合もあるだろうし、「波動」の部分かもしれない。あるいは「水伝」を受け容れる思想のことかもしれない。要するに「実験」の部分以外はしばしば「思想」と呼ばれることがあるわけで、私としては「思想」が何を指すのかがよくわからないのですよね。
さて、最後にもう一つ。オカルトや社会的に問題のある新興宗教などへの批判は昔からありましたよね。私はそれに一定の効果(あるいは意義と言ってもいいのですが)はあったと思っているのですが、そうは言ってもその類のものはなくならないですよね。江原啓之の人気、各種占い師の人気、いまでも色々ありますよね。では、どうしてなくならないのでしょう?
ニセ科学批判が(ネット上のごく一部とはいえ)それなりに注目され、まさにメカさんのような方がなんらかのコメントをしていくという状況は、それだけ今までの「思想」そのものに切り込むやり方に比べて斬新な面があった、ということなのではないでしょうか。ニセ科学批判が直接対峙できるものは限られます。「根拠」が客観的に検証できるもの、つまり「科学」の土俵で勝負できるもの、だけなんですよね。しかし、多くの(歴史の浅い)オカルトは、うっかり客観的に検証できる部分を内包してしまっています。だったら、そこを叩くというのは、戦略としてはもっとも(一番かどうかは別にして)有効ではないでしょうか。
私が自分が実際に人と話した事例を挙げたのは、効果があるということを感じながらやっていることを紹介するためでした。しかし、もちろんまだまだうまく行かない部分も多々あります。
たとえば最近も、「たしかに問題はいっぱいあるけど、世の中から排除するのは良くないよね」と心配そうに言われたことがあります。この人は、ニセ科学は問題だと思っている人なんです。私は排除するつもりなんて毛頭なくて、むしろなんとかせめて周辺化できないかと思っているだけなんですが、しかしメカさんが書かれた文章にも同様のことはあったし、ネット上でも似たような言説は時折見かけます。どうしてそういう意見が出てくるのかは真剣に知りたいんですよね。
もちろん、「思想」に直接切り込み、それが効果を挙げるなら、そうしたいんです。ハッキリ言って、「水伝」そのものはそう大きな問題ではない。それよりもむしろ、上の図での一番下のラインを私は最も危惧しているのです(教育に持ち込まれれば影響は長年続くだけに問題は問題なんですが)。しかし、どう切り込んだらいいのかわからない。そして、おそらく、思想への問題提起は昔からされている。そしてそして、私の得意分野はそちらというよりは(自然)科学の部分なのであって、だったら自分の得意なことを活かすのが合理的だと思うわけです。一人でなんでもやらなきゃいけないわけじゃないのだから、得意なこと・問題だと思っていることをそれぞれが取り組むことによって、いわば集合知として進んでいけば良い。
というわけで、メカさんには思想に直接切り込むことにぜひ取り組んでほしいし、どう切り込めば効果的なのかを教えてほしいのですよね。
(その2に続く)
【おことわりその2】メカさんへの返事、ざっと書いたんですが、これが長いのなんの。(^^;; ちょっと長過ぎなので、重複する部分を削り、もう少しコンパクトにしたいと思います。ので、とりあえずこのエントリだけ先に公開します。
先日、poohさんのエントリ がメカさん(メカAGさん)の記事をとりあげ、そこにメカさん御本人がコメントを寄せていました。私はその展開にちょっと興味を持ち、反論とかそういうことではなく、議論を深めようという立場から、少しばかりコメントをいたしました。
メカさんの議論は、いわゆる「ニセ(疑似)科学批判批判」と呼ばれるものの典型を含むように見えましたが、一方で、ありがちな「批判批判」にとどまらない展開も期待できるのではないか、と思っておりました。メカさんのおっしゃることは、ざっくりまとめると、ニセ科学批判者がやってきたことは無意味(あるいは間違い)であり、思想に切り込まなければならない、となるでしょう(まとめすぎかな)。
だいぶ長くなりますが、まずは私がコメントした文章を紹介します。ここまでの経緯は、poohさんの当該エントリのコメント欄をお読みください(そこまでは、そう長くはありません)。
こんばんは。最初に「別の角度から」と断っている通り、このコメントは、それまでの流れとは違う視点を持ち込むものでした。メカさんの問題意識に正面からぶつかったわけではありません。もちろん、それが有益な議論につながると思ったからなんですが。それから、私自身が最近色々と感ずるところがあって、メカさんとの議論を通じて何か見えるものがあるのではないか、と期待したからでもあります。
別の角度から一言だけコメントさせてください。
狭い範囲とはいえそれなりに大勢の人々と顔を合わせて話をしてきた経験をふまえて言えば、信じていた人の大半は、事実関係での間違いを指摘されれば信じなくなります。たとえば「水伝」の場合なら、中谷ダイアグラムを引き合いに出して、言葉や意識や「波動」の介在する余地はない、ということを説明すれば、今まで信じてきたことに大してショックを受けたり動揺したりすることもありますが、まず信じなくなります。
逆に、事実関係抜きに道徳の問題の話から入ると、なかなか納得はされない場合が多いようです。
事実関係の指摘で納得されず、さらに深みにはまる人もネットを見ているといらっしゃるようですが、ネット上ではなくリアルでの実感で言えば、そういう人はごく少数です。そういう人々はネット上ではエキセントリックな主張をされるので目立ちますが。
血液型性格判断のように、日常的に誤った情報にさらされている問題の場合はなかなか納得しきられない場合も多いのですが、それでもある程度は懐疑的に見るようにはなってくれるようです。
ネット上での議論の場合は、信奉者が自分の信念を強化するようなサイトのみを見てまわるという行動がありますのでまた難しいのだと思いますが、一応、両手両足の指では足りないくらいの人々に「今までは信じてたんですが…」と言ってもらった経験をふまえると、客観的事実を把握してもらうのがもっとも効率的な道であるように思います。
> いや、やっぱり「どういんちきなのか」を示すのは必要で。そこは起点になるわけだし。
本当にそうだと思います。そして、信じちゃってる多くの人は、その起点のところで引っかかってるのだと思います。
by FSM (2009-08-24 01:51)
さて、上のようなコメントをした背景には、以下のような、私なりのニセ科学問題の分析があります。一般論はたいていの場合無力なので、具体例で話を進めましょう。
下の図は、「水からの伝言」(以下「水伝」)をとりまく構造を、ある側面から切り取ったものです。もちろん私なりのまとめであり、異論のある方もいるでしょう。特に一番下の部分は違和感を覚える人も少なくないかもしれません。メカさんのおっしゃる「思想」は、おそらくこの図の左側「受容者」に関わるものだとは思いますが、まずは一般的な話をしたいと思います。
ここでは、まず大きく左右二つに分類しています。右側が江本勝をはじめとする「提唱者」(コアなビリーバーも含むでしょう)、左側がそれを信じる「受容者」です。受容者の上のほうが、水伝を授業で使っちゃった教師の典型でしょう。
さて、まず右側。こちらは江本らの主張がそもそもどういう構造をしているか、です。これについては多くの分析があり、特に hietaro さんの「『水からの伝言』の2つの側面」 に端的にまとめられています。ここでは、hietaroさん言うところの「現象篇」を「根拠」、「解釈篇」を「結論」「応用」と言っていますが、まあそれは視点をどこに置くかという話なので、違うことを主張するために違う言葉を使っているわけではないです(通常の科学だって、現象が根拠ですしね)。ここではさらに、その「説明原理」として「理論」-つまり、彼らが言うところの「波動」(もちろん物理学で出てくる波動とはなんの関係もない)も載せています。
なお誤解のないように言っておくと、「根拠」から上下に伸びる矢印の向きは、彼らの動機の順番とは関係ありません。あくまでも、彼らの議論の展開を元にしているだけです。彼らの発想としては、「応用」側の結論が先にあり、一方江本らが持ち込んだ波動測定器を使いたいという思惑がそれに結びついて、「根拠」「応用」のセットが出来たのでしょう。
この「理論」(「波動」)は一般化されており、「水伝」だけではなく、多くのニセ科学に持ち込まれています。「EM」の説明原理も「波動」です。ホメオパシーも、原子論が確立したあとはレメディの中に分子が一つも残っていないということがわかっちゃいましたから(ということだと思いますが)、「波動」を持ち出して効能を説明しようとしますね。そして、ニセ科学というよりもっとストレートにオカルトなものにも「波動」は登場します。さらにさらに、「波動」で生き方を決める発想まであるわけですね。
提唱者の部分に限って見ると、科学っぽい「実験」の部分、科学っぽい「理論」の部分、もろに「道徳」の部分、といくつかのパーツに分けられます。「道徳」の部分をもって「思想」と言ってもいいのかもしれません。また、「理論」の部分も科学的な言辞は使っていますが(量子力学など)、まあ客観的に見れば「思想」ということになるだろうと思います。
次に左側。こちらは受容する側の(ごく簡単な)分析です。分析と言っても、受容者に典型的な例をいくつか述べているに過ぎませんが、まあこんな感じだろう、と(コアなビリーバーは除きます)。彼らにとっての心の支えは、やはり客観的に検証されたと思い込める「根拠」の部分(つまり「実験」)でしょう。それがあるから、「道徳」的な結論を活かして授業に使おうなんて思っちゃうわけです。このあたりの人々(つまりこの図で言うところの受容者の上半分に位置する人々)は、「根拠」を崩せばたいがい「え?そうだったの?」となって、「水伝」からは離れていきます。少なくとも、私のそう多くはないが少なくもない経験ではそうです。心の整理をつけるのに時間がかかる人もいますが。もちろん統計データを取っているわけではありませんから、それをそのまま信じろと言うつもりは毛頭ありませんが、経験交流は大事だと思っていますので、まあそういうヤツがおる、ぐらいに思って聞いてもらえればいいかなと思います。
問題は下半分、つまり「波動」側に心魅かれてしまっている人々でしょう。ここはばっちりニューエイジ系の思想と重なります。軸足がこちらに来てしまうと、「根拠」の間違いを言ってもなかなか受け入れなくなります。どう受け入れないかは様々でしょう。単に聞く耳を持たなくなる場合もあるでしょうし、悪しき相対主義を持ち込んで、ちゃんとした実験結果を認めない場合もあるでしょう。もっと中途半端に「科学でもわかっていないことはいっぱいある」で思考停止してしまう場合も多いでしょう。
ここから先はニセ科学を批判する人々の間でもコンセンサスがあるわけではないと思いますが、ここは私のブログですので私の主張を書いておきます。このような「思想」には問題点が大変多く含まれています。その第一歩は、「百匹目の猿」に代表される思想でしょう。簡単に言えば、みんなで祈れば願いは実現する、ってやつです。世界平和も願えば実現する、と。これは色々な意味で問題ですが、平和への地道な努力をまったく見ないという点で有害ですらあります。
「みんなで」というのが一つのキーワードですね。ここにゆるやかな連帯を感じ、心地良く感ずる人も多いと思います。しかし、これが曲者。「個」を相対化し、しかも相対化したままにする。独立した「個」の連帯ではなく、相対化されたままの「個」の連帯は、融合した「全体」に向かわざるを得ないと思います。そうなった時、自分が何かうまくいかないことがある、失敗してしまった、つらい、ということに直面したら、どうなるでしょうか。祈りが足りない、となりますね。「祈り」じゃなくてもいいんですが、要するに、例えば生活がつらいのは自分が怠けてる場合もあるだろうけど派遣切りだのなんだの自分ではどうしょうもない社会的な問題に起因するものだっていくらでもあるわけです。そこを捨象してしまい、すべて「自分」に還元していまう。「連帯」の幻想は、すべてを「自己責任」へと転化させる危険を孕んでいます。これは「空気を読む」ということに(私などから見たら)異常なまでにこだわる最近の風潮と似たようなものなのかもしれませんね。
ついでに余談ですが、最近都市部の大学では「トイレで食事をしないでください」と張り紙がしてあるとか。これは、学食で一人で食べているところを友人に見られたくないからだそうなんですが、別に一人で食べてたっていいじゃんねえ。トイレで食べるほどに空気読まないかんのかねえ。息苦しいだろうねえ。
このような「思想」は、まさに大衆支配のおそるべきイデオロギーでしょう。実際、そうやって社員に「生きがい」を持たせ、どんな長時間の過酷な労働も喜びに感じさせてしまうという社員教育をやっている企業もあると聞きます(ちょっと古いけど『カルト資本主義』でだいぶ取り上げられていますね。稲盛和夫の「アメーバ経営」なんてまさにその例らしいのですが、まだチェックできていません)。
別の面から言うと、本当は、受容者が受容してしまう心理をもっと分析しないといけません。そこはニセ科学の「蔓延問題」への対策としては極めて重要でしょう。心理学者の皆様におかれましては、ぜひ、そこを取り組んでいただければと思います。血液型性格判断対策の蓄積が活かせる場ではないでしょうか。というのが、とりあえずのメカさんへの噛み合った形での返答、ということになるでしょうか。
というわけで、長々と書いてきましたが、ここでようやくメカさんへの質問となります。メカさん言うところの「思想」とは、この図でいうとどのあたりをイメージされているのでしょうか?もちろん分析は人によって違うし、メカさんとしては現状は大雑把な枠組みを提出する段階のようですから、「ここ」と言っていただかなくてもいいのですが、大体どのあたりをイメージしているのかを言っていただくと、わかりやすくなると思います。受容者が受容する心理、というあたりでいいのでしょうか?(このあたりは次のエントリで)
ちなみに今まで(このエントリだけではなくて)「水伝」の「思想」と言った場合何を指すかというと、文脈によって異なります。「道徳」の部分を指す場合もあるだろうし、「波動」の部分かもしれない。あるいは「水伝」を受け容れる思想のことかもしれない。要するに「実験」の部分以外はしばしば「思想」と呼ばれることがあるわけで、私としては「思想」が何を指すのかがよくわからないのですよね。
さて、最後にもう一つ。オカルトや社会的に問題のある新興宗教などへの批判は昔からありましたよね。私はそれに一定の効果(あるいは意義と言ってもいいのですが)はあったと思っているのですが、そうは言ってもその類のものはなくならないですよね。江原啓之の人気、各種占い師の人気、いまでも色々ありますよね。では、どうしてなくならないのでしょう?
ニセ科学批判が(ネット上のごく一部とはいえ)それなりに注目され、まさにメカさんのような方がなんらかのコメントをしていくという状況は、それだけ今までの「思想」そのものに切り込むやり方に比べて斬新な面があった、ということなのではないでしょうか。ニセ科学批判が直接対峙できるものは限られます。「根拠」が客観的に検証できるもの、つまり「科学」の土俵で勝負できるもの、だけなんですよね。しかし、多くの(歴史の浅い)オカルトは、うっかり客観的に検証できる部分を内包してしまっています。だったら、そこを叩くというのは、戦略としてはもっとも(一番かどうかは別にして)有効ではないでしょうか。
私が自分が実際に人と話した事例を挙げたのは、効果があるということを感じながらやっていることを紹介するためでした。しかし、もちろんまだまだうまく行かない部分も多々あります。
たとえば最近も、「たしかに問題はいっぱいあるけど、世の中から排除するのは良くないよね」と心配そうに言われたことがあります。この人は、ニセ科学は問題だと思っている人なんです。私は排除するつもりなんて毛頭なくて、むしろなんとかせめて周辺化できないかと思っているだけなんですが、しかしメカさんが書かれた文章にも同様のことはあったし、ネット上でも似たような言説は時折見かけます。どうしてそういう意見が出てくるのかは真剣に知りたいんですよね。
もちろん、「思想」に直接切り込み、それが効果を挙げるなら、そうしたいんです。ハッキリ言って、「水伝」そのものはそう大きな問題ではない。それよりもむしろ、上の図での一番下のラインを私は最も危惧しているのです(教育に持ち込まれれば影響は長年続くだけに問題は問題なんですが)。しかし、どう切り込んだらいいのかわからない。そして、おそらく、思想への問題提起は昔からされている。そしてそして、私の得意分野はそちらというよりは(自然)科学の部分なのであって、だったら自分の得意なことを活かすのが合理的だと思うわけです。一人でなんでもやらなきゃいけないわけじゃないのだから、得意なこと・問題だと思っていることをそれぞれが取り組むことによって、いわば集合知として進んでいけば良い。
というわけで、メカさんには思想に直接切り込むことにぜひ取り組んでほしいし、どう切り込めば効果的なのかを教えてほしいのですよね。
(その2に続く)
最近の江本勝ブログ(9/8)
ちょっと気になる文言を見かけたので報告だけ。8/9のエントリ
。
(1) 横浜開港150周年記念イベントで江本勝の講演会 が行われたらしい。絵本の配布も行われた模様。
(2) 「メキキの会13周年記念祝賀会」に出席、村上和雄の講演があったそうな。懇親会では江本が乾杯の音頭。
(3) 「平和道場勉強会」なる会で講演。一緒に話をしたのは、なんとあの藤岡信勝・拓殖大教授。
「新しい教科書を作られている、拓殖大学の藤岡信勝教授」ってザックリしたまとめがステキ。
他にもツッコみたいところはあるが省略。
ちなみに7/24のエントリ では、こんな記述もある。
来年4月は高野山の婦人会で講演だそうですよ。誰か注意する人はおらんのか。講演聞いてた僧侶はどんなことを考えただろう。
(1) 横浜開港150周年記念イベントで江本勝の講演会 が行われたらしい。絵本の配布も行われた模様。
(2) 「メキキの会13周年記念祝賀会」に出席、村上和雄の講演があったそうな。懇親会では江本が乾杯の音頭。
(3) 「平和道場勉強会」なる会で講演。一緒に話をしたのは、なんとあの藤岡信勝・拓殖大教授。
8月23日は幣立神宮の5色人祭ですが、その前日は宿坊である平和道場で勉強会が行われることになっています。題して人徳研鑽会です。映画「WATER」の上演の後私がその解説を行いました。いやあ、ついに歴史トンデモと一体化、かな。太田竜から藤岡信勝か。
春木宮司も講師の一人です。
新しい教科書を作られている、拓殖大学の藤岡 信勝教授もご講義をされました。
幣立神宮五色人祭当日
お社までの参道を行く私たち。
10時過ぎにはもう沢山の参拝客が見えていました。
映画ストーンエイジの白鳥哲監督も来ておられました。
この方が、平和道場の佐藤昭二さんです。いつ見ても良い顔です。
波動カウンセラーの増田さんもいらっしゃいました。
(以下略)
「新しい教科書を作られている、拓殖大学の藤岡信勝教授」ってザックリしたまとめがステキ。
他にもツッコみたいところはあるが省略。
ちなみに7/24のエントリ では、こんな記述もある。
(…)高野山の金剛峰寺教学部から安居会(あんごえ)という僧侶たちの勉強会の講師としての招聘を受けたのでした。だだだ大丈夫か高野山!!
(中略)
私は2時間半ある自分の持ち時間を1部2部に分け、1部では映画「WATER」のうち、宗教と水に関する部分を抽出して50分ほど見てもらいました。そして2部は新刊の「水と宇宙からのメッセージ」と言うテーマで一生懸命お話をさせていただきました。
高野山の開祖である空海・弘法大師さまの言葉の中に次のような言葉があります。
「声字実相義」(ショウジジッソウギ)
・あらゆるものを構成する要素には、みな音がある。また、その音によって、さまざまな世界にそれぞれの言葉がある。また、その言葉が伝えるさまざまな情報は、ことごとく文字である。そしてそれらは同時に仏そのものに他ならないのである。
この言葉は最近発見したもので、これを見つけた時は
本当に興奮しました。私が水や研究を研究してきて得た、言葉に対しての仮説が、そこに見事に表現されていたからです。
ですから、今日の講義はいわゆる釈迦に説法のようなものでしたが、私なりのユニークな見解も付加してどうどうとお話しすることが出来たかと思います。
その証拠に私は来年の4月に、今度は高野山の婦人会での講演を、帰りがけに依頼されたからです。
来年4月は高野山の婦人会で講演だそうですよ。誰か注意する人はおらんのか。講演聞いてた僧侶はどんなことを考えただろう。
