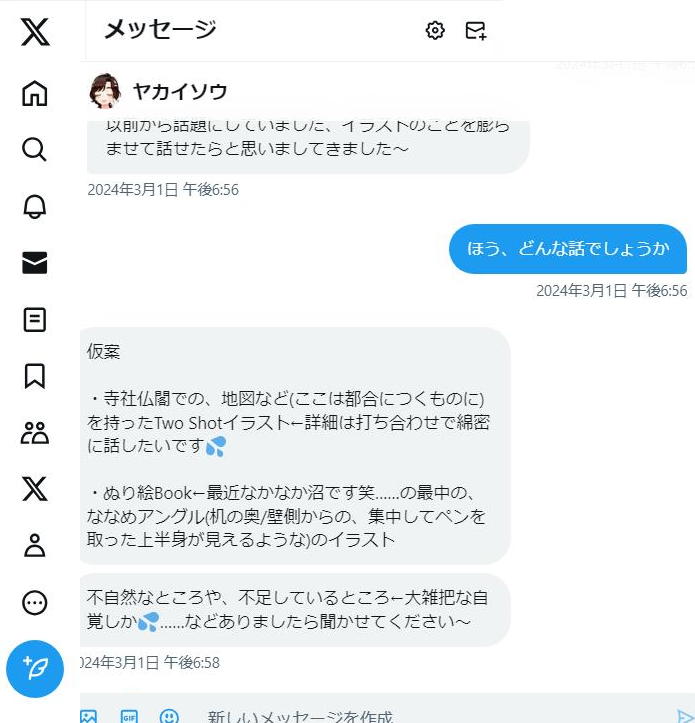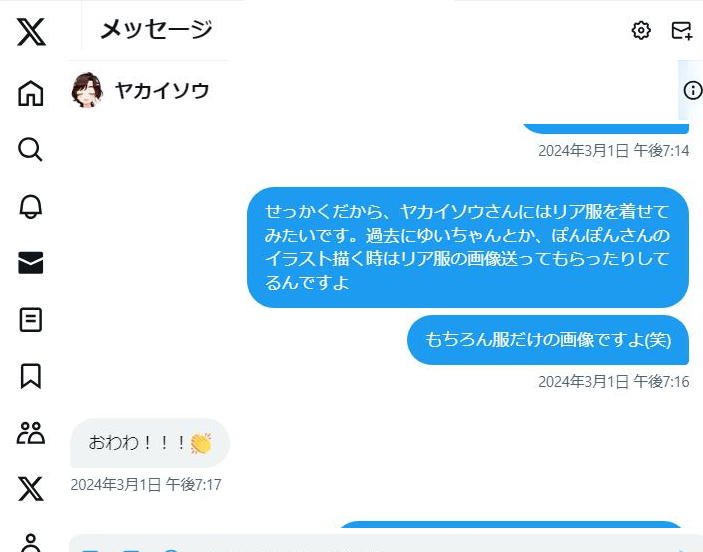今年もやって来ました、東大寺二月堂お水取りの季節が。小生も修二会のハイライトである3月12日、このブログでは毎年恒例のお松明と、平成27年以来8年ぶりの香水汲み上げの撮影に夜の東大寺へ行きました…が、
色々とありました、正直これまででもかなり気力体力を使う奈良レポになったと思います。
この日のスケジュールは、12日午後7時半からお松明の撮影、日付変わって13日午前1時半から香水汲み上げの撮影。機材はレンタルなので昼間に機材レンタル店に回りました。機材を運ぶために自家用車での奈良入り、翌日朝にはレンタルの機材を返却しなくてはならないので、駐車場で車中泊をしました。
この日のまず難関は雨。毎年お松明の撮影の時には気がかりになるのが天候で、6年前の平成27年、2年前の令和4年の撮影の時には雨が降られ、大変に苦労をしました。そして、今年の12日の天気予報は…
夜からはやや降水確率が下がっているとは言え、しっかり傘のマークが。機材は1ヶ月前からレンタル予約をするので、レンタル時には当日の天候は予想できず。雨でも予定は変えられず、天候で言えばお松明の撮影はギャンブルなのです。
そんな懸念がいっぱいの中12日を迎え、機材を借りに車を出しました。ちなみに家を出たときはかなり強い雨が降っていました。
機材をレンタル店で借りた後、奈良市内の撮影場所へ。新たな撮影スポットを見つけることが出来ず、今年も去年と同じ不退寺に近い法蓮町の住宅地の高台からを撮影場所としました。到着した時は今にも降り出しそうなどんよりとした空模様でしたが、何とか雨は止んでいて、天気予報の回復傾向を信じて撮影準備を開始しました。
昨年は理由不明のブレで撮影に失敗。年はそのリベンジという気構えでの撮影となりました。
昨年のお松明 撮影:2023年3月7日
昨年の技術的なミスを受けて、今年は原点に戻ろうと過去に作ったお松明撮影のチェック項目一覧を見直すことにしました。4年前のお松明撮影の記事 で自分で作ったチェック項目。ここに再掲しますと…
① まず、もう少し時間に余裕を。遅くとも午後5時半には平城宮跡に到着し、撮影のセットを始められるように段取りする。
② レンタルの望遠レンズであることを気にしてテープ固定などを省き、撮影に失敗してしまっては元も子もない。傷つけたり汚したりしないように気を付けながら、慎重にピントやズームリングをテープで固定する。
③ レンタルの時は超望遠レンズと合わせて、大型望遠レンズの重さに対応した大型の三脚も同時に借りる。
④ ニッコール200-500mmズームレンズには“VR”(手ブレ補正)機構ががあります。このVRを活かす。
⑤ 以前に二月堂近くから撮影した時はISO100の絞りf8~11くらいで撮影していましたが、今回の超望遠での撮影では露光時間が長くなるため、f16まで絞りを絞る。
⑥ 今回の撮影では双眼鏡が非常に役に立ちましたが、手持ちだったので見辛かった。カメラとは別に双眼鏡用ににスタンドを用意し、双眼鏡も固定をする。
今年はこの一覧から特に、事前チェックが必要と思った4つの項目を紙に印刷し現地に持って行きました。そして現地でこのチェック項目を一つ一つ確かめながらセッティングをしました。
まず、①遅くとも5時半には到着するということで、現地到着は5時20分過ぎくらいに到着、チェックの意味も込めて現地で時計の写真を撮りました。
そして、②レンズのピントやズームリングをテープで固定する は現地に仮止め紙テープを持ち込みしっかりと、そして④カメラのVR(手ブレ補正)機能を活かすということで。レンズの操作リングに貼った紙テープと、VRのスイッチがオンになっているのも写真に撮ってチェック。
そうして撮影セットをして、お松明の上堂を待ちました。下の画像を説明しますと、左の大きな三脚が愛機のニコンD7000にレンタルしたAF-S ニッコール 200-500mm f/5.6 ED VR、テレコンバーターTC17IIで850mm超望遠効果での撮影です。カメラを乗せた三脚はハスキー4段(HT-1040)でこれもレンタルした大型三脚。これで③の条件をクリア。
真ん中は愛用のパソコンで、hdmiケーブルでデジカメに繋ぎビデオキャプチャー画面を表示。精密なピント合わせをしました。そして右の小さい三脚には双眼鏡。⑥の条件でもある三脚セットの双眼鏡は、撮影中はキャプチャー画面が見れなくなるので双眼鏡でお松明の動きを見るためのものです。さらにカメラを入れてきたアルミカメラケースを椅子にしようと座布団まで用意とセッティングはバッチリ。お松明が上堂する午後7時半を待ちます。
ところが、お松明が上堂する午後7時半直前になって、急に雨がパラパラと降り出してきたのです。「ここまで何とか持ってたのに、よりによって何でこのタイミングで降り出すの」と、少々腹立つ気持ちで、借り物の望遠レンズが濡れて故障でもしたら大変と、用意したポリ袋を慌ててかぶせ、寒い中雨に濡れ、過酷な状況での雨に煙る2.7km先の二月堂お松明を撮影をしました。
露光はチェック項目では絞りf16と書きましたが、f11とf9.5と少し絞りを開けて撮りました。まず、下の画像がf11と絞りを絞ってのお松明。
上の画像をレタッチソフトで、露光と色補正したのが下の画像です。
そして明るくお松明を写るように、f9.5に絞りを開けて撮ったのが下の画像。
上の画像をレタッチソフトで明るさと色補正をしたのが下の画像です。
絞りf9.5の方は火がハレーションのように白く飛んでしまってますが、自分的には火の粉が光条のように写っていて、f11の方よりアクティブな出来でいいなと思いました。
出来た写真を自己評価すると、かなり厳密にピント合わせはしたつもりでしたが、画像にシャープさがやや欠けているという気がします。雨の影響か、それとも超望遠撮影の限界なのか検証するべきとは思いますが、とりあえずは過去の自身のミスは防げた撮影となりました。来年こそは天候に恵まれて欲しい、雨さえ降らなければ、おそらく来年がこの撮影方法の最終トライになるのではと思われます。
時々強くもなった雨に濡れながらのお松明撮影を終えて、食事を済ませると籠松明が夜空を焦がした東大寺二月堂へ。同じ夜に行われる香水汲み上げを撮影へと場所を移動です。香水汲み上げとは修二会の通り名でもある『お水取り』の別称。東大寺HPの修二会についてのサイト から説明を引用しますと…
「お水取り」は、12日後夜の五体の途中で勤行を中断してはじまる。「お水取り」の行列は灑水器と散杖を携えた咒師が先頭となり、その後に牛玉杖と法螺貝を手にした北二以下五人の練行衆が続く。13日の午前1時過ぎ、南出仕口を出ると咒師童子が抱える咒師松明が行列を先導し、篝火(かがりび)と奏楽の中、堂童子、御幣を捧げ持つ警護役の講社の人たちや、汲んだ水を入れる閼伽桶を運ぶ庄駈士(しょうのくし)も同道して、「お水取り」の行列はしずしずと石段を下り、途中興成神社で祈りを捧げ、閼伽井屋(若狭井)に至る。
「お水取り」の井戸は閼伽井屋という建物の中にあり、当役の者以外は誰も入ることもうかがうことも出来ない。行列が閼伽井屋に到着すると咒師、堂童子等が中に入り水を汲む。これが二荷ずつ、閼伽井屋と二月堂の間を三往復して、お香水が内陣に納められる。「お水取り」が終わると閼伽井屋に下っていた練行衆等は再び行列を組んで二月堂へ戻り、中断していた後夜の「時」が再開される。
お水取りの由緒と言われるのは、修二会を始めたと伝えられる実忠和尚が全国一万七千余の名を読み上げ参集したが、若狭の遠敷明神だけが川で魚釣りをして遅刻をされた。若狭の神はそのお詫びとして二月堂の前で祈ると、二月堂下から白と黒の鵜と共に霊水が湧き出たのです。
実忠はその霊水を二月堂の十一面観音に供えた。それが修二会がお水取りと呼ばれる由緒として今の伝えられ、若狭井は今も二月堂下の閼伽井屋の中にあり、修二会の13日の深夜に汲み上げられ、十一面観音に供えられるのです。我々はついお松明 = お水取りと言ってしまってますが、本当の意味でのお水取りとは、この香水汲み上げのことを指すのです。
香水汲み上げのことは、8年前に見学した時のことを2015年4月6日のブログ記事 で、その時に撮影した写真と合わせて紹介をしています。
2015年の香水汲み上げ 撮影:2015年3月13日
電灯の光の無い、ストロボも使えない夜間での望遠撮影という極めて難しい条件での撮影、8年前にこのような望遠撮影に使っていたレンズはAFニッコール35-135mm f/3.5-4.5という望遠効果も低くF値も暗く夜間撮影に適しているとは言えないレンズで、納得のいく撮影をするのにかなり難儀しました。
その後愛用の望遠ズームレンズがAF-Sニッコール70-200mm f/2.8 ED VRIIになったことを3年前の2020年9月22日の記事 で紹介しています。望遠効果もF値の明るさも格段にアップした新しいレンズで、購入したことを書いた3年前の記事では2015年の香水汲み上げの撮影を引き合いに出してるくらいに、買った当初から再度の香水汲み上げの撮影を意識していました。
そして、今年は8年ぶりに香水汲み上げの撮影をするチャンスを迎え、深夜の二月堂に行ったのです。香水汲み上げが行われるのは大体13日の午前1時半、8年前に二月堂を訪れた時間は午前0時半でしたが、この夜は日付の変わる前の午前0時前。
にも、かかわらず、既に大勢の見学者がいたではありませんか。
大勢の見学者がここに集まっていたのは8年前も同じでしたが、小生の印象では8年前よりもさらに見学者が増えていた、おそらく倍くらいになっていたのでは無いかと思われました。そして、既に大勢の見学者が集まった現場での撮影に適した場所取りを行わなくてはなりませんでした。
…何とか場所取りは出来たのですが、香水汲み上げが始まる一時間弱前になる午前0時半に事件が起きたのです…
直前になって場内整理の係の人が、徳前に集まった見学者全員に場所の移動を求めて来たのです。行事に影響のある場所にも見学者が大勢入っていたので、詰めろということを会場全体の見学者に伝えて来たのです。見学者はベストポイントを維持しようと係の人の指示にもなかなか動かずにらみ合いのような時間がしばらく続き、やがて渋々という感じで人が動き出したのですが、この後がさらにとんでもない事に。
当初は高齢の人などが前の列に座り、大きなカメラを持ったカメラマンは後列という整然とした状態だったのですが、この場内整理の後は、ベストポジションの前列をカメラマンがちゃっかり占拠。しかも立ったままで後ろの人のことを考えもしない場所取りに出てしまったのです。小生は前の人は姿勢を低くするだろう(自分が前ならそう振る舞うつもりでした)と思い少し後ろに下がったのですが、小生の前を体格の良い男性二人が前を覆い塞ぐように位置取りをして来たのです。
これでは写真が撮れないと、二人の隙間に割り込むようにカメラを差し込んだのですが、何とその二人から「撮影の邪魔をするな」と苦情を言われる始末。そこで小生は察しました…
「この場での撮影は、強い者勝ち。他の人に気遣いをした者は損をする」
そう察して、何か気持ちの糸が切れたのです。いくら苦情を言われても「前に立ち塞がるな!」と言い返し、構わず撮影を行いました。それまでの、出来る限りまわりの状況を見て撮影をして来たこれまでの自分はそこにはありませんでした。
そうしてかなり殺伐とした状況の中、またも香水汲み上げのタイミングでも小降りの雨が降り出す徹底的な悪条件。そのような状況の中で撮ったのが、以下の写真です。行事の解説は8年前のこちらの記事 に譲ります。まず、堂童子か抱え持つ咒師松明に続いて練行衆咒師が下堂。
咒 師松明に続き、『閼伽井棚』と呼ばれる香水を汲み上げる桶を吊るした、天秤棒を担ぐ庄駈士が石段を降ります。
二月堂下の興成社詣に入った練行衆および童子を、咒師松明を立てて石段脇で待つ堂童子。
そして、咒師と庄駈士が閼伽井屋に入り、若狭井の香水を汲み閼伽桶に入れます。その前で童子が待機し、運び出されます。
汲み上げられた香水は閼伽桶に入れられ、庄駈士が担いで二月堂へと石段を登り運ばれて行くのです。香水汲み上げではこれが3回繰り返されます。
8年前には3回の汲み上げが終わるまで撮影を行いましたが、今年の香水汲み上げは始まったのが例年の午前1時半より少し遅れて、午前2時半時点ではまだ2回目の汲み上げが終わったところでした。翌朝にはレンタルした撮影機材をレンタル店に返却するスケジュールもありましたし、とにかくハードな1日で疲れたので、この夜の小生は3回目の汲み上げを前に二月堂を後にしました。
今回は8年前の補足という意図も大きかったこともあったので、今回はこれだけの写真が撮れて及第点と思ったというのもありました。すべて70-200mmの望遠レンズで撮影、すべてf/2.8の開放絞りで、感度設定はISO6400を使ったので、ここに貼った写真はレタッチソフトで補正はしているものの、シャッタスピード1/30~1/100秒という高速シャッターが使え、粒子の荒れも耐えられないほどの酷さにはなりませんでした。写真の出来は課題はいっぱいですが、とりあえず愛機のニコンD7000、AF-Sニッコール70-200mm f/2.8 ED VRIIの性能の高さは立証出来たとは思います。
大阪在住の小生ですが、この夜は家に帰らず、東大寺から近い駐車場で車中泊。3時間半ほど眠るための時間を取りましたが、眠れたのは結局1時間ほどでした。計画を伝えた奥さんからは「車中泊では寒いのでは?」と心配されましたが、車に毛布を2枚積んで行ったこともあり、寒さはそれほどでも。ただ、深夜までの撮影で気持ちが昂ぶったことが眠れなかった理由では無いかと思います。
過去10年以上も奈良の行事を追ってブログ記事を書くために取材を行いましたが、今回は過去最悪レベルの状況での撮影でありました。家に帰ってただただ「とにかく疲れました」というのが率直な感想です。
家に帰った13日の昼にTVを観ていたら、奈良の空模様がライブ映像で出まして、天候が回復し、日差し一杯の快晴の奈良市街の映像が映っているのを見て疲れが倍増したような気がします。