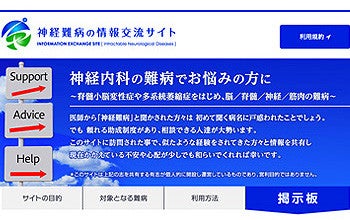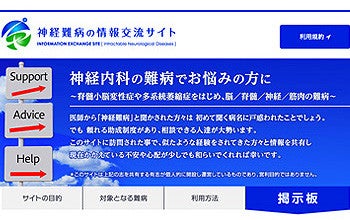西 智弘 医師の著書、『だから、もう眠らせてほしい~安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語』を読んだ。
(一部は https://note.com/tnishi1/m/m554cc2c3a5b2 で無料で読める)
著者は、 川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター 腫瘍内科/緩和ケア内科医長。
プロローグにあった以下の文章が、この本を読んでみようと思わせた。
『日本には安心して死ねる場所がない――だからこの患者はスイスに行こうとしているのか……。僕は日本の緩和ケア医として、どうすれば患者たちがこの国で、安心して生きて、そして死んでいけるのかということを、ずっと考えて実践してきたつもりだ。10年前と比べれば、この国はずっと良くなったと思う。それでもこの吉田ユカという患者(※)は「ここには安心して死ねる場所がない、スイスで安楽死したい」と言っている……。』
『きっと、話せばわかることがある。僕だって伊達に、緩和ケアの専門家を10年もやってきたわけじゃない。緩和ケアは体の痛みだけではなく、心も、社会的な苦痛も緩和できる方法だ。安楽死なんてことを考える前に、まだ、できることがあるはずだ。きっと、何とかできるんだ。
そう期待して、僕は外来の日を迎えた。ドアを開けるまで、僕は自信満々だったのだ。
――そう、ドアを開けるまでは……。』
(※)吉田ユカさんは、膵臓癌で抗がん剤治療を続けていたが、同時に実親からの虐待によって「複雑性PTSD(Post-traumatic Stress Disorder)」の診断も受けていて、一昨年小島ミナ(紺美)さんが安楽死された、スイスの自死幇助支援団体であるライフサークル、からの承認が降り次第、渡航予定だった。
筆者は、「安楽死制度は否定しないが、仮に安楽死制度があったとしても、それを使いたいと思う人をゼロにするための、一つの方策として早期に外来で開始する緩和ケアという方法もある」と言う立ち位置である。
彼女は、想定外に待たされた挙げ句に、最終的には望んでいた「持続的な深い鎮静」と言う名の間接的安楽死を施してもらうのだが、別の患者に施した「持続的な深い鎮静」の過程も含めて、筆者は苦悩することになる。
その苦悩については後段に譲る。
ちなみに、筆者の関心は癌患者のみであり、その他の病の緩和ケアは一切考えていない。
故に、神経難病患者の我々には、本書はあまり参考にならない。
だからと言って、筆者を責められない。癌以外の病気の患者の緩和ケアは診療報酬外なのだから。
多少の期待を持って筆者本人ともメールを交わしたが、やはり神経難病患者は対象外との返事をもらっただけに終わった。(私は癌患者でもあることを伝えたにも関わらず)
本書の登場人物である二人の癌患者は、死ぬ直前まで普段通りに会話を交わしたり、トイレにも自分で歩いて行けたりする。
もう一人の患者は、末期にも関わらず緩和ケアのお陰で痛みも無く元気に過ごせるからと、希望していた安楽死を断ったそうである。
以前、癌 or 神経難病 どちらがマシ?にも書いた通り、神経難病との比較で言うと、癌はマシな部類の病である(何事にも例外はあるが)。
神経難病の場合は例外無く死に向かって身体機能が奪われていくため、死ぬ直前まで普通に会話ができるとか、トイレに歩いて行けるなんてことは想像も出来ない(私は現時点で両方とも出来ない)ことに加えて、神経難病には緩和ケアという概念が存在しないこともその一因である。
本書に登場する二人の癌患者を見ていると、「緩和ケア」が必要なのは彼らではなく、今も日々身体機能喪失の恐怖と戦って苦しんでいる神経難病の仲間だろう、との思いが募る。
結局、本書を読んで感じたのは、癌患者と言うだけで向き合う医師が存在することが心底羨ましい、と言う思いだ。
緩和ケア対象の病気であるかどうか、即ち、診療報酬の有無でこれだけの違いが出るのだ。
本書が神経難病患者の参考にならないことは前述の通りだが、幡野広志氏(癌患者で安楽死肯定派の写真家。自らもスイスでの安楽死を望んでいる)との対談の中に、興味を惹かれた記述があった。
それは、前述の筆者の苦悩にもつながる。
幡野氏は、
『患者の「持続的な深い鎮静」の希望を阻むのは家族と医者』
『患者は医者の死生観の犠牲になる』
『患者は一番弱い立場』
『要件の「耐え難い苦痛」は医師の主観に基づく我慢大会』
『だから自分の生死を医者や家族には任せられない』
『医者に判断を委ねるのは偏るから、むしろ裁判所などが判断を下すべき』
と言う。
実際、「持続的な深い鎮静」の実施率は20%程度と言われているようで、望んだ5人の内わずか1人しか処置してもらえない。
中には、しない方針であることを自慢する医師まで居て、そんな医師が主治医になってしまったら、患者がどんな状況に置かれていても(客観的に見れば、十分「持続的な深い鎮静」の要件に適合した状態だったとしても)、「持続的な深い鎮静」は施されずに苦痛の中で死んでいくしか無いのだ。
実際に、他の例でも吉田ユカさんのケースでも、患者とその家族が強くそれを望んでいて、筆者も主治医として「持続的な深い鎮静」を施すべき、と判断しているにも関わらず、病院のたった一人の医師の反対によって、それまで賛成だった医師までもが保守に回ったことで孤立し、患者との板挟みになり苦悩する様子が克明に描かれている。
緩和ケアの終着駅とでも言うべき「持続的な深い鎮静」、にもこんな曖昧さが残っていることは頭に留めておくべきだ。
と共に、神経難病患者の早期緩和ケアにおいては、癌とは違って、将来必ず必要になる介助・介護・看護などをカバーする医療・福祉制度や、生活を支える補助金・年金制度などの専門的な知識を持った人のアドバイスが必須だ。
それらの情報の有無が、闘病生活における精神的安心感を大きく左右する。