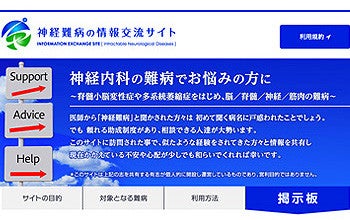「尊厳死」の定義について、ここまでは混乱を避けるために日本尊厳死協会のそれに甘んじてきたが、この定義にはかねてより違和感がある。
『充分な緩和ケアを施されて』などと、どうにでも取れる言い方もさることながら、ふたさんが、https://ameblo.jp/ookawas/entry-12618984226.html で指摘されている通り、「尊厳死」=「延命治療拒否」、逆に言うと「延命治療受入」=「尊厳の喪失」かのような捉えられ方をされかねないからである。
『治療法の選択一つで、尊厳が左右されるものではない、あらゆる選択はその人にとって尊厳を守る行動であるはず』
ふたさんの仰る通りだ。
個人的には、定義をもっと適したものに変えるべきだと思っている。散々考えたが適当な言葉が浮かばないので、ここではCategory別けをするに留める。
Category 1:
幇助された自殺による死
Category 2:
患者本人の意思によって延命治療を選択しない自然死、及び、装着済みの延命装置の撤去による死。
緩和ケアの一環として、苦痛緩和の薬剤使用も可能とする。
Category 3:
患者の希望を尊重することを条件とした、積極的安楽死(自然の死期に先だって直接短縮)、と間接的安楽死(苦痛緩和の薬剤使用で死期を早める)を複合させた形。
私は、上記のCategory 1は論外として、Category 2とCategory 3は、勿論推奨するわけではないが、厳しい条件をつけた上で認めることで、神経難病患者により多くの選択肢を与えるべきであると考える。(条件については後段参照)
「安楽死」について、1991年4月の「東海大安楽死事件」に際して、意図的に死を早める「積極的安楽死」が許容される要件として、横浜地裁が示した以下の判例はよく知られている。
(https://square.umin.ac.jp/endoflife/shiryo/pdf/shiryo03/04/312.pdf)
とは言っても、これは法律でもなければ最高裁判決でもないので、いつ覆ってもおかしくないことが前提となる。
1.患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
2.患者の死が避けられず、その死期が迫っていること
3.患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、ほかに代替手段がないこと
4.生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること
多くの方々が、過去に様々な角度からコメントしているので細かくは触れないが、これは多分に神経難病以外の患者を念頭に置いたものなので、神経難病患者に適用する際に問題となり得る点を挙げてみた。
① 「肉体的苦痛」には言及しているが、「精神的苦痛」が判決文中で明白に除外されていること。
⇒ Part 3で述べた通り、『神経難病特有の肉体的苦痛は知られていない』上に、身体機能を日に日に削られていき、最終的には体のどの部位も他人に動かしてもらわなければ動かせなくなるという、神経難病特有の「精神的苦痛」や「精神的恐怖感」が含まれていない。
② 「肉体的苦痛」に対しても、「耐えがたい」や「除去・緩和するために方法を尽くし、ほかに代替手段がないこと」と言う極めて恣意性の高い条件がついていること。
⇒ Part 3で述べた通り、『除去・緩和するために方法を尽くす』ための、緩和ケアの対象に神経難病が含まれていないと思われるので、明白に含める。
⇒ 誰が、どう言う状況証拠を持ってこれらを証明することが求められるのか、を明らかにする。曖昧な恣意性を排除し、実現可能な手続きにしなければ意味が無い。
⇒ 主治医の主観のみによって患者の生死が決められてしまうことは避けなければならない。
③ 「死期が迫っていること」と書かれているが、余命判断の不確実性をどう考えるのか?
⇒ これもPart 3で述べた通り、神経難病の場合は余命予測が難しい。神経難病の場合は、「治療方法が無く、死が避けられない」だけで十分。
これらを考え合わせた上で、冒頭の勝手な定義(Category別け)に基づく私の提案は、以下の通りである。
1. Category 1
単なる自殺の幇助は、明白な罪である。
2. Category 2
「人工呼吸器装着の有無」と言う選択肢は、神経難病患者にも既に与えられている様に思われるが、これ以外の延命治療に当たる処方に対する選択権、それによって生じる苦痛の除去、及び「装着済みの延命装置の撤去」については、Part 3で述べた通りハードルが高い。
これらのハードルを明白に取り除く必要がある。
3. Category 3
上記①~③の問題点をクリアーした上で、認めるべき。
上記2.と3.については、以下が大前提。
ア) その時点で治療方法のない神経難病であること。
イ) 医師が、代替治療の有無や内容、治療中止後の余命などを患者本人とその家族にきちんと説明する、所謂インフォームド・コンセントの義務を遂行し、理解したことを書面に残すこと。
(1998年の『川崎協同病院事件』と同じ轍を踏まないように)
ウ) 患者本人の書面による明確な意思表示(口述筆記や視線入力などの場合は、医師を含む複数の立ち会いと、立会人の署名入り議事録を残す)があること。
エ) 患者の意思は常に揺れ動くことが十分に考えられるため、イ)の意思の撤回については医師を含む家族等、複数の立会人による、患者本人の意思の確認で足りるものとすること。
オ) エ)の後、再度患者本人が、イ)の意思表示をすることも可能とすること。
カ) 明らかな認知症状が認められる場合はこの限りではない。
まとめとして、神経難病患者が希望に従って「緩和ケア」を受けられるように制度を明確にし、神経難病患者も終末期医療のガイドライン(Category 2 が含まれる)に従って選択ができることによって、患者は十分に考える時間を与えられるとともに、その途中、もしくはその先に、Category 3 の選択肢を残すことが、最善の方法ではないかと思う。
様々なご意見は有ろうかと思うが、あくまでこれは一個人の私見であることをお断りしておく。
神経難病患者が、林優里さんや小島ミナさんの様な、苦渋の決断はしなくても良い法律や制度になって欲しい、と心から祈ると共に、決してお二人の死を無駄にしてはならない、と思う。
”京都 ALS 安楽死” シリーズ =完=